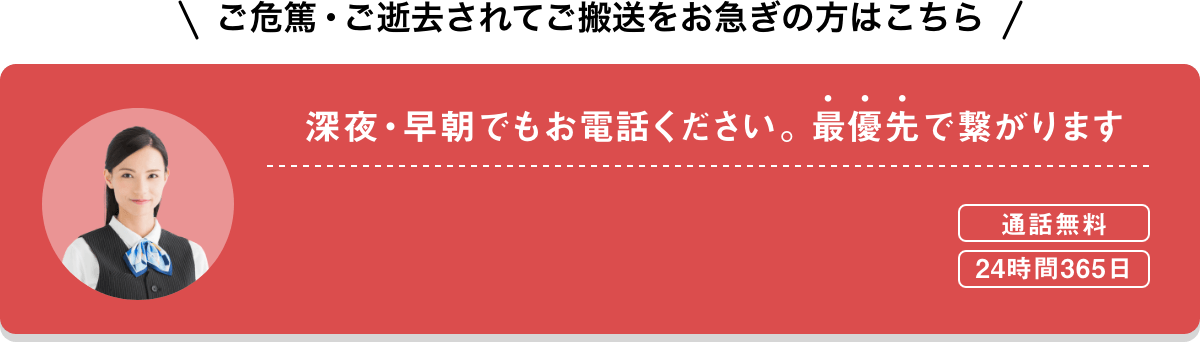親の葬儀を終えたあとで「遺骨を引き取りたくない」「遺骨の管理ができない」といった悩みを抱えている方はいませんか?経済的な負担や関係性の問題から、遺骨の引き取りを躊躇してしまうケースが増えています。
本記事では、親の遺骨がいらない場合の対処法や正しい処理方法について詳しく解説します。「遺骨の引き取りは拒否できるの?」「法律に違反しない処理方法は?」といった疑問にもお答えするので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を要約すると
- 親の遺骨は法律上必ずしも引き取る義務はないものの、地域や火葬場によっては引き取りが求められる場合があります。引き取りを希望しない場合は、事前に葬儀社や自治体に相談し、対応方法を確認することが重要です。
- 遺骨の管理ができない場合は、合祀墓への納骨や散骨・樹木葬・永代供養墓の利用などの選択肢があります。費用は、3~80万円程度と幅があり、経済状況や遺族の希望に応じて最適な方法をえらびましょう。
- 遺骨をゴミとして捨てることは、死体遺棄罪となり違法行為です。遺骨の扱いに困った場合は、自治体の福祉課や葬儀社に相談しましょう。
親の遺骨がいらない場合は拒否できる場合がある
遺骨を必ず引き取らなければならないという法律上の義務はありません。しかし、地域や火葬場によっては引き取りを求められる場合があります。
遺骨の引き取りを希望しない場合は、事前に葬儀社や自治体に相談し、対応方法を確認する必要があるでしょう。
葬儀社に相談すれば、合葬墓や永代供養墓への納骨を手配してもらえます。重要な点は、遺骨の処理方法を火葬前に決めておくことです。
葬儀社や自治体の福祉課に早めに相談すれば、状況に応じた解決策を提案してもらえます。遺骨の引き取り拒否は遺族側の権利ではあるものの、故人の尊厳を保ちながら手続きを進めることが大切です。
親の遺骨がいらないときの対処法
親の遺骨の処理について困った際の対処法を4つ紹介します。
- 合祀墓(合葬墓)に納骨する
- 散骨をする
- 樹木葬を利用する
- 永代供養墓・納骨堂を利用する
それぞれの方法について、詳しく見ていきましょう。
合祀墓(合葬墓)に納骨する
親の遺骨を自宅で管理できない場合、合祀墓へ納骨することが費用を抑えるための選択肢のひとつです。
合祀墓とは、複数の遺骨をひとつの墓に共同で埋葬する施設です。寺院や霊園が運営しており、個別の墓石を建てる必要がないため初期費用は3~30万円程度と低く抑えられます。年間管理費も不要な場合が多く、経済的負担が軽くなるでしょう。
納骨の手続きは、まず希望する寺院や霊園に問い合わせて見学します。契約時には、埋葬許可証・印鑑・戸籍謄本などの書類が必要です。
納骨式は、ほかの家族と合同で行われることもありますが、個別で実施することも可能です。ただし、一度納骨すると遺骨を取り出せないため、親族間で十分に話し合うことが大切です。
宗教や宗派を問わない施設も増えており、無宗教の人でも利用できます。都市部では、公営の合祀墓も整備されており、より安価に利用可能な場合もあります。
遺骨の供養方法に悩む人にとって、合祀墓は現実的で心の負担も少ない選択肢といえるでしょう。お墓を建てずに供養する方法については、以下の記事を参考にしてみてください 。
散骨をする
散骨は、遺骨を粉末状にして海や山などの自然に撒く方法で、墓地管理の負担がなく費用も抑えられる選択肢です。遺骨を2mm以下の粉末状に砕く「粉骨」という作業が必要で、専門業者に依頼すると1~3万円程度かかります。
海洋散骨の場合、個別散骨なら15~40万円、複数の遺族が合同で行う場合は10~20万円、委託型は3.5~10万円程度とされています。
船をチャーターして沖合まで出て、花びらとともに遺骨を撒くのが一般的な方法です。散骨後は、手元に遺骨が残らないため、一部を手元供養用に残しておく方もいます。
樹木葬を利用する
樹木葬は、遺骨を樹木の根元に埋葬する葬送方法です。墓石を建てずに、桜や紅葉などの樹木を墓標とする供養のあり方です。
都市部の霊園や寺院でも、樹木葬専用区画を設けているところが増えています。一般的な墓地と比べて管理費が安く、年間1万円程度です。
個別型では、1人1本の樹木の下に埋葬し、合祀型では複数の遺骨を一本の大きな樹木の周りに埋葬します。宗教や宗派を問わず利用できる施設が多く、無宗教の人でも申し込めるのが魅力的です。
永代供養付きのプランなら、後継者がいなくても霊園側が供養を続けてくれます。費用は、20~80万円程度で、立地や樹木の種類によって異なります。
申し込み時には、埋葬許可証や印鑑・身分証明書が必要です。樹木葬は、遺族の負担を軽減する現代的な供養のあり方として注目されています。
永代供養墓・納骨堂を利用する
親の遺骨を自宅で管理できない場合は、永代供養墓や納骨堂を利用することで、寺院や霊園に遺骨の管理を任せられます。
永代供養墓の費用目安は、以下のとおりです。
| タイプ | 永代供養料 |
|---|---|
| 単独墓 | 40万円 |
| 集合墓 | 20万円 |
| 合祀墓 | 10万円 |
※あくまで目安
納骨堂は、建物内に遺骨を安置する施設で、ロッカー式や仏壇式などさまざまな形式があります。都市部に多く立地しており、天候に左右されずに参拝できるのが利点です。
契約期間は、33回忌までなど期限付きであることが多く、期限後は合同墓に移されます。どちらも宗派を問わない施設が増えており、無宗教の人でも利用可能です。
親の遺骨はいらないとなる理由
親の遺骨を引き取りたくない理由として、以下の4つの要因が挙げられます。
- 関係性が薄い・交流がなかった
- 経済的な負担が大きい
- お墓や納骨スペースがない
- 墓じまいを予定・実施している
それぞれの背景について詳しく見ていきましょう。
関係性が薄い・交流がなかった
親の遺骨を引き取りたくないと感じる最大の理由は、生前の関係性が希薄だったり長期間交流がなかったことです。
幼少期から親と離れて暮らしていた場合、親子としての実感が持てないまま大人になることがあります。また、虐待や育児放棄などで親から十分な愛情を受けられなかった人は、親に愛着がないのも無理はありません。
経済的な援助もなく、精神的な支えにもならなかった親に対しては責任を感じない人もいるでしょう。このような背景から、遺骨の引き取りを拒否したいと考える人は一定数存在します。
経済的な負担が大きい
遺骨の管理や供養にかかる経済的負担の重さが、親の遺骨を引き取らない選択をする大きな理由といえるでしょう。
一般墓を建てる場合、155.7万円かかるというデータもあります。(参考:【第16回】お墓の消費者全国実態調査(2025年)霊園・墓地・墓石選びの最新動向)
毎年の管理費も5,000~2万5,000円程度必要で、長期的な負担は軽視できません。
また、納骨堂を利用する場合でも、初期費用として79.3万円程度かかります。(参考:【第16回】お墓の消費者全国実態調査(2025年)霊園・墓地・墓石選びの最新動向)
子供の教育費や住宅ローンを抱える現役世代にとって、法要などの費用を捻出するのは厳しいという家庭も多いでしょう。
なお、葬儀の費用を抑える方法として、葬儀形式を見直しがあります。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、必要なものを含んだ分かりやすいセットプランで、相場よりも抑えた価格の様々なプランをご用意しています。
お墓や納骨スペースがない
お墓や納骨スペースがないことも、親の遺骨を引き取れない大きな理由のひとつです。
現代では核家族化が進み、先祖代々の墓を持たない家庭が増加しています。賃貸住宅に住む人々にとって、自宅に仏壇を置くスペースを確保することも困難です。
経済的な負担に加えて、将来的な墓の管理や維持費用への不安も重なります。とくに、子どもがいない夫婦や独身者の場合、自分の死後に墓を継承する人がいないという問題もあります。
このような現実的な制約が、散骨や樹木葬など墓を持たない供養方法を選ぶ人が増えている理由です。
遺骨の行き先に悩む遺族にとって、従来の埋葬方法にとらわれない新しい選択肢を検討する必要があるでしょう。
墓じまいを予定・実施している
墓じまいを予定または実施している場合、親の遺骨を引き取らないケースが増えています。
墓じまいとは、今あるお墓を撤去して更地に戻し、墓地の使用権を管理者に返還することです。少子高齢化や核家族化により、お墓を継承する人がいなくなることが墓じまいをする主な理由です。
墓じまいをする際は、まず墓地に埋葬されている遺骨を取り出す必要があります。取り出した遺骨は、永代供養墓や納骨堂・樹木葬など、管理の負担が少ない場所に改葬することが多いでしょう。
しかし、すでに墓じまいを決めている場合、新たに親の遺骨を受け取ってもすぐに改葬先を探さなければなりません。そのため、永代供養を選択する人もいます。
遺骨がいらないからといってゴミに捨てるのは違法
遺骨を一般ゴミとして捨てることは、刑法190条の死体遺棄罪にあたり、3年以下の懲役刑となる違法行為です。
遺骨の処分に困った場合でも、自宅の庭や公園・山林などに勝手に埋めることも違法です。墓地埋葬法により、遺骨は都道府県知事の許可を受けた墓地にのみ埋葬できると定められています。
どうしても遺骨を手元に置けない事情がある場合は、永代供養墓への納骨や散骨業者へ依頼するのが正しい対応方法です。遺骨の扱いに困ったときは、葬儀社や寺院・自治体の窓口に相談しましょう。
引き取り手がない遺骨に関するよくある質問
最後に、引き取り手がない遺骨についてよくある疑問を4つ紹介します。
- 相続放棄した場合の遺骨の所有権は?
- 遺骨の引き取り義務は本来誰にある?
- 引き取りを拒否した場合、費用負担はどうなる?
- 法律に違反せずに遺骨を処理するにはどうすればいい?
それぞれ詳しく見ていきましょう。
相続放棄した場合の遺骨の所有権は?
相続放棄をしても、遺骨の引き取り義務を放棄したことにはなりません。
民法では、相続放棄により財産の相続権は失いますが、遺骨は財産ではなく祭祀財産として扱われるためです。相続放棄しても、祭祀財産は承継される点に留意しましょう。
祭祀財産には、遺骨や仏壇・位牌・墓地などが含まれ、相続財産とは別に承継されます。
遺骨の引き取りを拒否した場合、市区町村が火葬場で一定期間保管したあと、無縁仏として合祀されます。保管期間は自治体により異なりますが、1~5年程度の自治体がほとんどです。
引き取り手がない遺骨は、最終的に自治体の無縁墓地に埋葬されます。相続放棄を検討する際は、遺骨の供養方法についても親族間で事前に話し合っておくことが大切です。
遺骨の引き取り義務は本来誰にある?
遺骨の引き取り義務は、原則として祭祀承継者にあります。
祭祀承継者とは故人の祭祀を主宰する者のことを指し、遺言で指定されていればその人が、指定がなければ慣習により決まります。多くの場合、配偶者や長男・長女など故人と最も近い関係にある親族が祭祀承継者となるのが一般的です。
相続人は、民法で定められた順位に従い、配偶者は常に相続人で、子→直系尊属→兄弟姉妹の順となります。身寄りがない場合や全員が引き取りを拒否した場合は、最終的に市区町村が引き取ることになるでしょう。
遺骨の引き取りは、故人を弔う大切な行為でもあるため、親族間で十分に話し合うことが重要です。
引き取りを拒否した場合、費用負担はどうなる?
遺骨の引き取りを拒否しても、法的には火葬費用の支払い義務から逃れられません。民法第897条により、祭祀承継者には遺骨を引き取る義務があり、これは相続放棄をしても消滅しない点に留意しましょう。
火葬費用は故人の財産から優先的に支払われますが、不足する場合は相続人や扶養義務者が負担するのが一般的です。
相続放棄をした場合でも、生前に扶養義務があった親族は火葬費用の負担を求められる恐れがあります。遺骨の引き取りは故人への最後の責任であるため、費用負担も含めて慎重に判断しましょう。
法律に違反せずに遺骨を処理するにはどうすればいい?
引き取り手がない遺骨を法律に違反せずに処理するには、まず自治体の福祉課や市民課に相談することが重要です。
身寄りのない遺骨は、墓地埋葬法に基づいて処理する必要があります。自治体では無縁仏として合葬墓や納骨堂への埋葬を行っており、費用は生活保護法による葬祭扶助や自治体の予算で賄われます。
寺院や霊園によっては、無縁仏を受け入れている施設もあるため、問い合わせてみてもよいでしょう。
遺骨の処理には、死亡届の提出から火葬許可証の取得まで、正式な手続きが必要です。また、費用面で困難な場合は生活保護の葬祭扶助制度を利用できる可能性があるため、福祉事務所へ相談することも検討しましょう。
なお、葬祭扶助の対象向けの葬儀にも「1日葬・家族葬のこれから」は対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。
葬祭扶助について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください
親の遺骨がいらない場合は自治体や葬儀社に相談しましょう
親の遺骨の処理に困った場合は、ひとりで悩まずに専門機関に相談することが大切です。
市区町村の福祉課や市民課では、引き取り手がない遺骨の処理について法的な手続きを案内してくれます。経済的に困難な場合は、生活保護の葬祭扶助制度を利用できる可能性があるため、福祉事務所へ相談するとよいでしょう。
葬儀社では、合祀墓や永代供養墓への納骨手配も対応しており、費用や手続きについて詳しい説明を受けられます。
なお「1日葬・家族葬のこれから」では価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を執り行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。