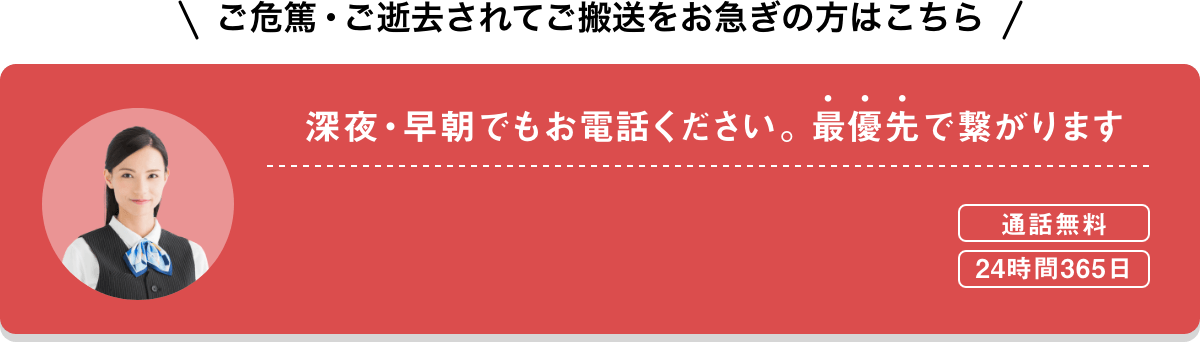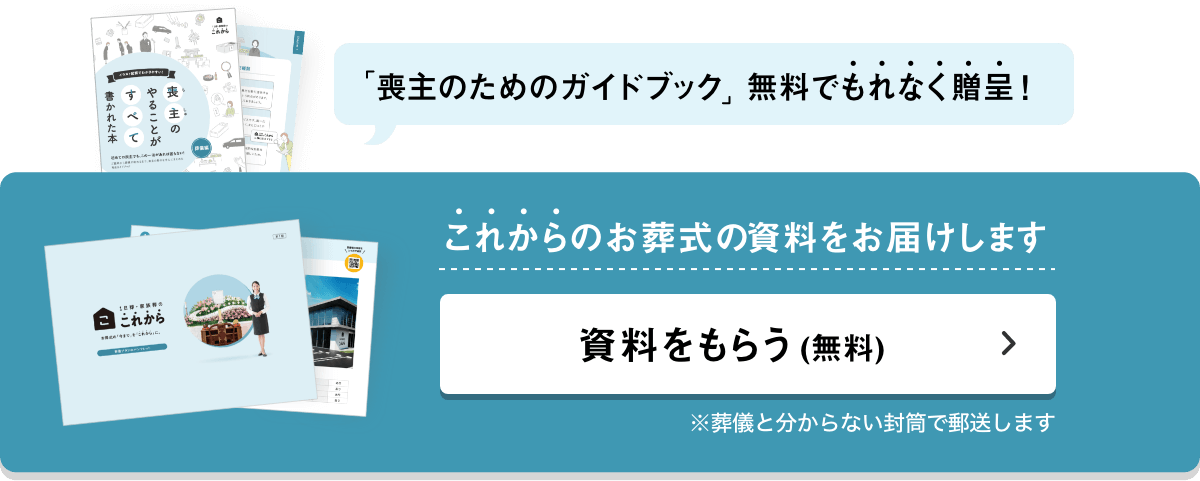親族のみのアットホームな空間で故人とお別れする家族葬は、近年人気を集めている葬儀形式です。ただし、参列者の限られる家族葬を選択した場合、生前関わりのあった方に対して参列をお断りする連絡を入れなければなりません。
今回は、家族葬への参列をお断りする方法を知りたい方向けに、連絡を入れる適切なタイミングから連絡方法・具体的な例文までわかりやすく解説します。お断りの連絡の際は、相手に対して失礼のないよう、丁寧に対応することが大切です。
この記事を要約すると
- 家族葬は遺族や親しかった人のみが集まって小規模な葬儀を行う形式です。参列できる人数に限りがあるため、複数の関係者に対して参列をお断りする連絡を入れなければなりません。
- 参列のお断り連絡は、葬儀前に訃報と合わせて伝えるか、葬儀を執り行った後に事後報告するかの2パターンに分かれます。どちらにせよ、相手に誤解を与えないよう、丁寧に事情を説明する必要があります。
- 参列をお断りする場合は、香典や後日弔問も辞退するのが一般的です。「恐縮ですが、ご弔問は謹んで辞退申し上げます」などと添えて辞退の意向を伝えましょう。
家族葬とは?
家族葬とは、親族やごく近しい人のみで執り行う小規模な葬儀形式です。一般葬と比べて参列者が少なく、葬儀費用を安く抑えられるうえ、故人との最期の時間を静かに過ごすことができます。近年は感染症の影響や高齢化によって、家族葬を選択する方が増えています。
なお、家族葬は参列できる人数が限られているため、生前に関わりのあった場合でも、葬儀に参列できないケースが珍しくありません。参列をお断りする場合は、丁寧に事情を説明することが求められます。
家族葬を選択する理由
近年は、さまざまな事情から家族葬を選ぶ遺族が増えています。
親族だけで静かに執り行いたい
家族葬を選ぶ1番の理由は、故人との最後の時間を親族だけで静かに過ごしたいという意向です。大勢の参列客や弔問客に対応する一般葬では、遺族が故人とのお別れに集中できず、心身ともに大きな負担がかかることが考えられます。家族葬は気心の知れた身内のみが集まるため、落ち着いて葬儀を執り行えるといえるでしょう。
遺族の負担を減らしたい
家族葬は遺族の精神的・物理的な負担を軽減できる点も魅力のひとつです。参列者が少ないと、当日の受付・香典対応のほか、葬儀後の香典返しの用意も負担が少なく済みます。葬儀前後の一連の準備をスムーズに進めたい方には、規模の小さい家族葬が適しています。
葬儀費用を安く抑えたい
家族葬は一般葬に比べて会場規模が小さく、参列者の人数も少ないため、式場利用料・料理・返礼品などの葬儀費用一式を安く抑えられます。
近年は高齢化による医療費の出費増加や長期入院によって葬儀をできるだけ安く執り行いたいと考える方が増えており、家族葬のニーズが高まっています。
参列できる人が少ない
遠方に住む親族や高齢の親族が多い場合、葬儀に参列するのに大きな負担がかかることが考えられます。また、生前の付き合いが限られていた故人や、すでに親しい親族が少ない家庭では、大規模な葬儀を開く必要がないと判断されることもあります。
初めから参列者が集まりにくいことが予想できているケースでは、小規模な家族葬を選択するのが一般的になっています。
参列を断るタイミング
家族葬への参列をお断りする場合は、トラブルを回避するためにも、適切なタイミングで連絡を入れることが重要です。
葬儀前に訃報と合わせて伝える
参列の辞退を伝えるタイミングとして最も丁寧なのは、訃報を知らせる際にあわせて伝える方法です。
故人の訃報とともに「家族葬のため、近親者のみで執り行います」と明確に伝えることで、参列の可否についての混乱を避けられるでしょう。とくに故人が生前関係性の深かった相手には、電話やメールなどで丁寧に知らせると誠意が伝わります。
葬儀後に挨拶状を送る
葬儀前の負担を少なくしたい方や、バタバタしていて連絡が遅くなりそうなときは、葬儀を終えてから挨拶状を送るのもひとつの方法です。報告が遅くなったことをお詫びしたうえで、すでに葬儀を終えていることを丁寧に伝えましょう。故人が生前お世話になったことへの感謝も綴ると、相手によい印象を与えられます。
参列を断る相手への案内文の例
参列をお断りする相手へ訃報を伝える際は、近親者のみで家族葬を執り行うことを丁寧に伝えましょう。
電話
電話での連絡は、相手の反応に応じて柔軟に事情を説明できるのがメリットです。
葬儀前の場合
突然のご連絡となり恐れ入ります。
〇〇の息子の〇〇でございます。昨日、父の〇〇が亡くなりました。葬儀は本人の生前の希望を尊重し、家族葬にて執り行います。大変恐縮ですが、葬儀へのご参列やご厚意は、固くご辞退申し上げます。なお、ほかの皆様には葬儀後にお知らせいたしますので、どうぞご内聞にお願い申し上げます。ご不便をおかけいたしますが、何卒ご容赦ください。
葬儀後の場合
突然のご連絡となり恐れ入ります。
〇〇の息子の〇〇でございます。昨日、父の〇〇が亡くなりました。葬儀は本人の生前の希望を尊重し、家族葬にて執り行います。大変恐縮ですが、葬儀へのご参列やご厚意は、固くご辞退申し上げます。ご報告が遅くなり恐縮ですが、生前のご厚誼を賜り深く感謝申し上げます。
メール・手紙・ハガキ
書面で参列をお断りする旨を伝える場合は、文中で句読点を用いないのがマナーです。
葬儀前の場合
謹啓
◯月◯日 父の◯◯が逝去いたしました
葬儀は本人の遺志を尊重し 家族葬にて近親者のみで執り行います
誠に勝手ではございますが ご厚志 ご弔問の儀は 固くご辞退申し上げます
ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げ 略儀ながらご報告申し上げます
謹白
葬儀後の場合
謹啓
◯月◯日 父の◯◯が逝去いたしました
葬儀はすでに近親者のみで滞りなく執り行いました
誠に勝手ではございますが ご厚志 ご弔問の儀は 固くご辞退申し上げます
ここに生前賜りましたご厚情に深く感謝申し上げ 略儀ながらご報告申し上げます
今後とも変わらぬお付き合いのほど よろしくお願い申し上げます
謹白
参列を断るときの注意点
参列をお断りする際は、相手に対して誠意を持った振る舞いをすることでよい印象を与えられます。
訃報はどこかのタイミングで必ず伝える
参列をお断りする相手や、故人との関係性があまり深くなかった相手に対しても、必ずどこかのタイミングで訃報を伝えるのが常識です。もし訃報を伝えなかった場合、相手に不信感や誤解を与えてしまう可能性があります。
葬儀前後の多忙な時期を避けたい方は、葬儀の一連の流れがすべて終わった後の落ち着いたタイミングで、訃報と葬儀を無事に終えたことを報告する挨拶状を用意するのがスマートです。家族葬を選んだ背景を丁寧に説明し、連絡が遅くなったことへのお詫びを添えることで、相手に対して丁寧な印象を与えられます。
お断りしたことへのお詫びを伝える
参列をお断りするときは、ただ「参列はご遠慮ください」と伝えるのではなく、必ず一言お詫びの言葉を入れるのがマナーです。相手に配慮する姿勢を見せることで、今後の円満な関係性の維持にもつながります。「大変恐縮ですが」や「謹んで辞退申し上げます」などの文言を用い、丁寧に対応しましょう。
香典や供物の辞退も伝える
参列をお断りする場合は、香典や供花も辞退するのが一般的です。相手に気を遣わせないよう、香典や供花の辞退も合わせて伝えましょう。
曖昧な表現では誤解を招く可能性があるため、「ご厚志につきましては、固く辞退させていただきたく存じます」などと明確に伝えるのがポイントです。
断る相手には葬儀情報を伝えない
参列をお断りする場合は、葬儀の日時・場所などの詳細を伝える必要はありません。葬儀の情報を共有すると、かえって混乱を招いてしまう可能性があるため注意しましょう。「葬儀は故人の遺志により、近親者のみで執り行います」とだけ伝えるのが一般的です。
葬儀社に事前に共有する
参列や香典をお断りする意向は、事前に葬儀社へも共有しておきましょう。万が一当日に招いていない方が訪れた場合でも、葬儀社が丁寧に対応してくれる場合があります。
また、香典や供物の受け取りについても、葬儀社が代行してくれるケースがあるため、事前に対応状況を伝えておくとスムーズです。
職場にも訃報と断りの連絡を入れる
故人や遺族が会社に勤めていた場合は、職場にも訃報と参列をお断りする連絡を入れるのがマナーです。とくに社内で故人に縁があった人が多いときは、あらかじめ「家族葬につきご参列はご遠慮いただいております」と一言添えると丁寧です。
会社によっては香典や弔電を用意する制度が整っているケースもあるため、事前に対応状況を伝えることで担当者が準備しやすくなります。
弔問の断り方
弔問とは、葬儀会場や遺族の自宅に訪れ、線香をあげて弔意を伝えることを指します。参列をお断りする場合は、葬儀前後の弔問を受け付けるかどうかもあらかじめ決めておきましょう。弔問を受け付ける場合は、葬儀前や葬儀後に遺族が対応する手間が増えるため、注意が必要です。
弔問もお断りする場合は、訃報を伝える際に、「恐縮ですが、ご弔問は謹んで辞退申し上げます」といった文言を添えてください。
参列を断った後の対応方法
参列をお断りした相手に対しても、今後の円満な関係を維持するために、必要に応じてさまざまな対応をする必要があります。
葬儀後にお礼状を送る
家族葬に招かなかった相手や訃報を伝えた際に参列をお断りした相手には、葬儀後に無事に葬儀を終えたことを伝えるお礼状を送ると親切です。
お礼状には故人の訃報と近親者のみで葬儀を執り行ったことを簡潔にまとめ、生前の故人とのお付き合いへの感謝の言葉も記しましょう。しっかりとした文書に残すことで、相手に対する誠意が伝わります。
近隣住民には挨拶回りをする
町内会の関係者や顔見知りの住民には、葬儀後に直接挨拶に伺いましょう。とくに故人が地域住民のつながりが深い地区に住んでいた場合は、今後の円満なご近所付き合いのためにも、遺族から挨拶しておくと好印象を与えられます。
挨拶の際は、参列をお断りしたお詫びとともに、「今後も変わらぬお付き合いをお願いします」といった一言を添えると丁寧です。
後日弔問にはできるだけ対応する
葬儀に参列しなかった人のなかには、後日の弔問を申し出る人がいるかもしれません。弔問を辞退している場合はその旨を伝えたうえでお断りしてかまいませんが、一度お断りしても相手が引き下がらなかった場合は可能な範囲で対応するのがベターです。弔問客が遺族の自宅に訪れた際は、手短にお線香をあげてもらいましょう。
香典を受け取ったら香典返しをする
葬儀に参列しなかった相手から香典を受け取った場合、葬儀で香典を辞退していたとしても、香典返しを用意するのがマナーです。
お返しは受け取った金額の三分の一〜半額を目安として用意し、四十九日を終えた忌明けに送りましょう。品物はタオル・飲料・カタログギフトなどの消え物を選ぶのが一般的です。
会社からの弔慰金は受け取って問題ない
故人や遺族が勤めている会社によっては、会社からの弔慰金や見舞金を受け取れる場合があります。このお金は福利厚生の一環として受け取れるもので、香典とは異なります。そのため、香典を辞退していても受け取って問題なく、お返しの必要もありません。ただし、受け取った際は会社の担当者宛に一言お礼を伝えるのがマナーです。
辞退したのに参列されたら
参列をお断りしていた方が葬儀当日に斎場へ訪れた場合は、事情を説明したうえで、参列をお断りしてかまいません。
わざわざ足を運んだ相手に申し訳ないと感じたり、相手がなかなか引き下がらなかったりしたら、式が始まる前にお線香だけあげてもらいましょう。後々のトラブルにつながらないよう、できるだけ丁寧に対応することが重要です。
参列を断るときは誠意をもって対応しましょう
参列者の限られる家族葬では、参列や弔問をお断りするケースが多く発生します。参列をお断りするときは、相手に対して誠意を持って丁寧に対応することが大切です。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。