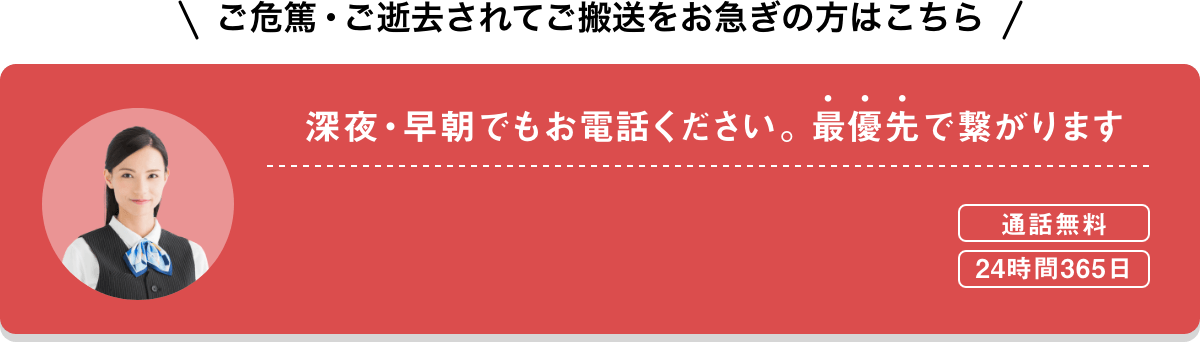「身内が亡くなったと警察から突然連絡が…」というショッキングな状況に直面したとき、多くの方が動揺し、何をすべきかわからなくなるでしょう。
事故や突然死など予期せぬ形で大切な人を失った場合、警察の介入があり、通常の葬儀とは異なる手続きが必要です。
そこで本記事では、警察から死亡の連絡を受けた際の対応方法や葬儀までの手順をわかりやすく解説します。
混乱しやすい状況を少しでも落ち着いて乗り切るための情報をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を要約すると
- 警察から身内の死亡連絡を受けた際は、警察署名・担当者名・連絡先をメモし、必要書類(身分証明書・印鑑・故人との関係を証明する書類)を準備することが重要です。現場検証中は、遺族で会っても現場に立ち入りできません。
- 早い段階で葬儀社へ相談することで、警察とのやり取りや遺体の処置・搬送など専門的サポートを受けられます。葬儀社に依頼したことを警察に伝え、両者が直接連絡を取れるようにすると手続きがスムーズになるでしょう。
- 検視終了後、警察署で死体検案書を受け取り、遺体の引き渡し手続きを行います。葬儀社による遺体の処置・搬送後、枕飾りの準備や葬儀の打ち合わせへと進みます。
身内が死亡したと警察から連絡が入るケース
身内の死亡通知が警察から来るケースは複数あります。ここでは、警察から連絡が入る代表的な3つのケースについて説明します。
- 事故によって死亡した場合
- 自宅で孤独死していた場合
- 事件性が疑われる場合
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 事故によって死亡した場合
交通事故や水難事故などで身内が亡くなった場合、警察から電話で連絡が入ります。
連絡を受けた遺族は、警察署や病院に向かい、霊安室でご遺体と対面し本人確認を行います。事故死の場合は、死因や事件性の有無を確認するため、警察による検視が行われる流れです。
検視の結果、事件性が疑われる場合には司法解剖が実施されます。
検視や司法解剖が完了すると警察からご遺体引き渡しの連絡が入るので、自身の身分証明書や印鑑・故人の身分証明書などを持参して警察署に出向きましょう。
ご遺体の引き渡しと同時に「死体検案書」が交付されます。死体検案書は、死亡届を提出する際に必要な書類なので大切に保管しましょう。
身内が事故死した場合の葬式については、以下の記事を参考にしてみてください。
2. 自宅で孤独死していた場合
身内が自宅で孤独死した場合、近隣住民や新聞配達員などが異変に気づき警察に通報されます。警察は現場に立ち入り、遺体を発見すると現場検証を行います。
現場では、事件性の有無や死亡原因・死亡日時が特定され、このときに故人の身分証明書などから身元を確認し、親族へ連絡が入るでしょう。
連絡を受けた親族は、まず警察署へ向かい身元を確認する必要があります。現場検証中は、警察の許可なく部屋に立ち入れません。
事件性がないと判断されると、死体検案書とともに遺体が引き渡されます。その後、死亡届の提出や葬儀の準備・特殊清掃の手配などを進めていく流れです。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、お客様の要望に沿った様々なプランを、相場より安く抑えた価格でご提供しております。葬儀に必要なものを含んだ、わかりやすいセットプラン料金でご用意しておりますので、お気軽にご相談ください。
なお、身内が孤独死した場合の葬儀については、以下の記事を参考にしてみてください。
3. 事件性が疑われる場合
火事や事故・事件など警察が最初から介入している状況では、事件性の有無を徹底的に調査します。
事件性が疑われると、遺族の意向に関わらず捜査機関の判断で司法解剖が実施されます。検視・検案のみの場合は半日程度ですが、解剖が必要な場合は1日以上かかり、事件性が強い場合は1か月以上かかることもあります。
この間、葬儀の日程を事前に決めることは難しいでしょう。そのため、捜査が終了して死体検案書とともに遺体が引き渡されたら、ようやく葬儀の準備に移れます。
警察から死亡の連絡が入ってから葬儀に移るまでの流れ
遺体引き渡しまでの流れを知っておけば、イレギュラーな状況下でもスムーズに乗り切れるでしょう。ここでは、警察からの連絡から葬儀準備に至るまでの一連の流れを6つのステップに分けて解説します。
- 警察からの連絡を受ける
- 葬儀社に連絡する
- 警察で検死が行われる
- 遺族へ終了の連絡が入る
- 葬儀社がご遺体の処置と搬送する
- 安置・枕飾り後、葬儀の打ち合わせを進める
参考にしてみてください。
1. 警察からの連絡を受ける
事故死や突然死・自殺など医師の診断を受けていない場合、警察が介入します。警察は、現場で発見された公的書類や契約書から遺族を特定し、血縁関係の近い順に連絡を取ります。
連絡を受けたら、まず警察署へ向かい身元確認を行いましょう。この際、自分の身分証明書や故人との関係性がわかる戸籍謄本や住民票・印鑑を持参する必要があります。
また、警察から連絡を受けた時点では、警察署名・担当者名・電話番号をメモしておくことが重要です。
事件性がないと判断されると、死体検案書とともに遺体が引き渡され、葬儀の準備に移れます。
なお、現場検証中は遺族であっても警察の許可なく現場に立ち入れません。
2. 葬儀社に連絡する
警察から連絡を受けたら、早い段階で葬儀社に相談することが重要です。葬儀社は、警察案件に精通しており、遺体の状況や今後の流れについて警察と専門的な話ができます。
そのため、混乱している遺族の強い味方となり、精神的な負担を軽減してくれるでしょう。また、葬儀社に依頼しておけば、警察からの遺体引き渡し時に必要な寝台車の手配や遺体の処置・搬送などをまかせられます。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」は、警察案件の対応実績が豊富で、スムーズな進行をお約束します。警察への対応を熟知しているからこそ、ご遺族の不安を最小限に抑えながらサポートいたします。
お電話をいただければ、直ちに手配し、30分〜1時間でお迎えにあがります。突然の事態でお困りの際は、事前にお問い合わせいただいていなくても問題ありませんので、どうぞ安心してご相談ください。
3. 警察で検死が行われる
病院以外の場所で死亡した場合、警察による検死が必ず行われます。
検死とは「検視」「検案」「解剖」の一連の流れを指し、死因の究明と事件性の有無を確認する重要な手続きです。
期間は、事件性がなければ半日程度で終わりますが、事件性が疑われる場合は数日から1ヶ月以上かかることもあります。検死は、刑事訴訟法に基づいており、遺族は拒否できません。
なお、検視については以下の記事を参考にしてみてください。
4. 遺族へ終了の連絡が入る
警察による検視・検案や解剖が完了すると、遺族へ終了の連絡が入ります。この連絡は、検視や解剖の結果、事件性がないと判断された場合に行われます。
警察から検視終了の連絡を受けたら、警察署に出向き、死体検案書を受け取り遺体の引き渡し手続きを進めましょう。その際、身分証明書や印鑑・故人との関係性を証明する書類が必要です。
死体検案書は、A3サイズで右側が死体検案書、左側が死亡届という様式で、火葬許可証の取得に必要となる重要な書類です。死体検案書は一度役所に提出すると戻ってこないため、提出前に5〜10枚程度コピーを取っておきましょう。
コピーは、保険金請求や預金口座の名義変更など、後々の手続きで必要です。
警察署では、死亡状況についての説明を受け、故人の貴重品や部屋の鍵なども返却されます。遺体の引き渡しが完了したら、葬儀社によるご遺体の処置と搬送が行われ、ようやく葬儀の準備に移れます。
なお、死体検案書については、以下の記事も参考にしてみてください。
5. 葬儀社がご遺体の処置と搬送する
警察からの検視・検案が終了し、遺体引き渡しの連絡を受けたら、葬儀社に連絡して搬送の準備を依頼します。葬儀社は、警察署から遺体を引き取り、必要な処置を行います。
警察は、病院と異なりエンゼルケアを行わないため、葬儀社による遺体の清拭や着替えなどの処置が必要です。この処置には、通常の葬儀プランとは別に「処置代」が発生するケースがほとんどです。
6. 安置・枕飾り後、葬儀の打ち合わせを進める
警察から遺体が引き渡されると、葬儀社によって自宅や斎場など指定の場所へ安置されます。安置場所が決まったら、故人の枕元に枕飾りと呼ばれる小さな祭壇を設けるのが一般的な流れです。
枕飾りには、宗教や宗派によって違いがあり、仏教では三具足(香炉・燭台・花瓶)や枕飯などを用意します。枕飾りの準備後、僧侶に枕経を上げてもらい、故人の魂が成仏することを祈ります。
その後、葬儀社と葬儀の打ち合わせに入り、葬儀の場所と日時・プランや葬祭用品・料理や返礼品などを決めましょう。打ち合わせでは、葬儀のプランや金額をしっかり確認し、自分たちの要望を伝えることが重要です。
可能であれば複数人で打ち合わせに参加し、後々のすれ違いを防ぐのが望ましいでしょう。
警察から死亡の連絡がきたときによく使われる専門用語
警察から連絡が入ったときに、専門的な用語がわからないと事態を正しく把握できません。
ここでは、死亡の連絡においてよく使われる専門的な用語を8つまとめました。参考にしてみてください。
| 用語 | 詳細 |
|---|---|
| 検案 | ・自宅など病院以外で亡くなった方の死因・死亡時刻・異常死ではないかの確認を医師が行う。 ・医師が死亡を確認して死因がわからない「異常死」かを総合的に判断する行為を指す。 |
| 検視 | ・死体の状況を見て刑事捜査によって犯罪性の有無を明らかにし、疑いのある場合は司法解剖を行う。 ・身元の確認をして遺体や周囲の状況を調べて、犯罪の疑いがあるかを判断する刑事手続きで、主に検察官や司法警察員(認定された警察職員)によって行われる。 |
| 検死 | ・「検視」「検案」「解剖」の3つの手続きをまとめて呼ぶ際に用いる言葉。 ・死因や死亡状況を医学の観点から判断するための一連の手続き。 |
| 異状死 | ・病気による診療を受けながら、診断されている病気で死亡した場合以外のすべての死。 |
| 変死者 | ・病死や自然死が不明の場合、犯罪の疑いがある場合の死亡者を指す。 |
| 行政解剖 | ・行政によって設置された監察医が行う解剖。 ・犯罪性の疑いがある場合は、司法解剖に移される。 ・事件性はないと判断された遺体に対して死因を究明するために行われる解剖で、死体解剖保存法8条に基づいて実施される。 |
| 司法解剖 | ・犯罪の有無を判定するために行われる解剖。 ・事件性が疑われる遺体に対して死因を究明するために行われる。 ・警察が捜査上死因究明のため裁判所に要請し、裁判所が「鑑定処分許可状」を発行することによって解剖できる。 |
| 死体検案書 | ・死亡診断書と同じ書式を使用するが、病院で亡くなった方ではなく、検案を受けた方に発行される書類。 ・警察での検視が終わると発行され、これを受け取ることで遺体を引き取れる。 |
警察からの連絡でよくわからない言葉があっても、以上の意味を確認することで連絡内容をより正確に理解できるでしょう。
身内が死亡したと警察から連絡が入ることに関するよくある質問
最後に、警察から身内の死亡連絡を受けた際によくある3つの質問とその回答を紹介します。
- 警察からどのようなことを聞かれる?
- 遺体の引き取りは拒否できる?
- 孤独死の場合、検視の期間はどれくらい?
ここで紹介する情報を知っておけば、いざというときの対応に役立つでしょう。
1. 警察からどのようなことを聞かれる?
警察から身内の死亡連絡を受けると、事件性の有無を確認するための事情聴取が行われます。第一発見者や家族に対して、故人の健康状態や亡くなる間際の状況について質問されるでしょう。
具体的には、亡くなる前最後に会った時期や状況・普段のやり取りの頻度について尋ねられます。また、持病や通院歴・日常的に服用していた薬についても確認されるでしょう。
遺体発見時の状況や部屋の様子など、死亡時の状況に関する詳細な質問もあります。事情聴取は決して疑われているわけではなく、死因究明のための必要な手続きであるため、誤解しないことが大切です。
わからないことは「わからない」と正直に答えましょう。
2. 遺体の引き取りは拒否できる?
警察から遺体の引き取り依頼があった場合でも、引き取りは強制ではなく遺族の意向が尊重されるため、法的には拒否できます。
引き取りを拒否された遺体は、自治体によって火葬され、無縁仏として供養されます。
ただし、遺体の引き取り拒否と相続放棄は別の手続きが必要です。遺体の引き取りを拒否したからといって、相続を放棄したことにはならない点に留意しましょう。
また、自身が扶養義務者(配偶者や直系血族など)である場合は、火葬費用などを請求される可能性があります。
引き取り拒否の決断は、後悔しないよう慎重に検討しましょう。
遺体の引き取りを拒否する場合については、以下の記事で詳しく解説しています。
3. 孤独死の場合、検視の期間はどれくらい?
孤独死の場合の検視期間は、事件性の有無によって大きく異なります。事件性がないと判断できる場合は、半日程度で検視が終了するケースがほとんどです。
しかし、死因が不明確な場合や事件性が疑われる場合は、詳細な調査が必要です。このような場合、検視期間は数日から1ヶ月程度かかることもあります。
とくに、遺体の状態が悪い場合や身元確認に時間を要する場合は、最大2ヶ月ほどかかるかもしれません。死亡後の経過時間によっても、検視期間は変わります。
検視が終わるまでは死亡後の手続きを進められないため、警察からの連絡を待つ必要があるでしょう。
身内が死亡したと警察から連絡が入ったら落ち着いて対応しましょう
突然の警察からの連絡は大きなショックですが、冷静に対応することが大切です。まずは、警察署名や担当者名・電話番号をメモし、身分証明書や印鑑など必要書類を準備しましょう。
また、早い段階で葬儀社に連絡しておけば、専門的なサポートを受けられるため精神的負担を軽減できます。この困難な時期を乗り越えるためには、親族や葬儀社の力を借りながらひとつひとつ手続きを進めていきましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。