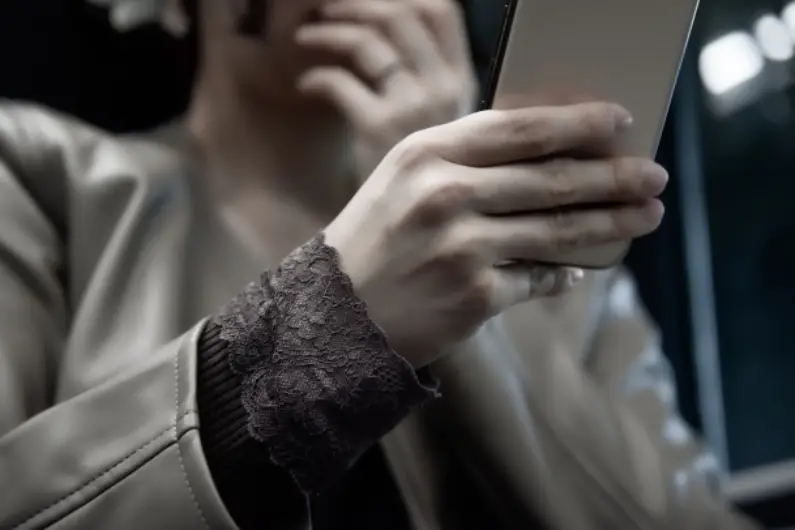近年では、家族葬での葬儀が増えています。しかし実際に知人から家族の訃報を聞き、家族葬で葬儀を行うと言われた場合、葬儀に行くべきか行かないべきか、マナーに悩むこともあるでしょう。
本記事では、家族葬へ参列するかどうかの基準について紹介します。家族葬に参列する際のマナーや、参列しない場合の弔意の伝え方についてもあわせて紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事を要約すると
- 家族葬は近親者を中心に行う葬儀です。遺族と2親等までの親族が家族葬に参列し、友人や会社関係の人は一般的に参列しません。
- ただし、遺族から直接訃報を受けたり、葬儀に参列してほしい趣旨の連絡があった場合は、他人でも参列することがあります。家族葬では香典を辞退しているケースもあるため、事前に確認しておくと安心です。
- 家族葬に呼ばれなかった場合でも弔意は伝えられます。香典や弔問、お悔やみの連絡など、相手の都合にあわせて弔意を伝えるのが大切です。
家族葬とはどんな葬儀?
家族葬とは、亡くなった方の近親者を中心に執り行う葬儀です。ご近所付き合いが希薄になった近年では、選ばれることが増えてきた葬儀形式です。
一般葬より参列者が少なく、葬儀が小規模で済むため、家族葬では遺族の負担を抑えられる傾向にあります。身内が中心のため、他人への気遣いも不要です。しめやかに葬儀を執り行いながら、故人との最後のお別れに集中しやすい特徴があります。
家族葬は身内メインで行うのが基本ですが、実は明確な定義がなく、友人関係などを含めて家族葬を行う場合もあります。
家族葬について詳しく知っておきたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。
家族葬に参列する人・しない人
家族葬に参列する人・しない人は、一般的には以下のとおりです。
| 家族葬に参列する人 | 家族葬に参列しない人 |
|---|---|
| ● 遺族 ●2親等までの親戚 | ●3親等以降の親戚 ●友人 ●知人 ●会社の同僚や上司 ●近所の人 |
家族葬には、故人と生計を共にしていた遺族のほか、一般的には2親等までの親戚が参列します。3親等以降の親戚や友人・知人、会社関係の人間、近所の人は参列しないのが基本です。
ただし遺族の意向により、同居していた家族のみの2~3人で家族葬を実施するケースや、親しい友人を呼んで家族葬を行う場合もあります。
家族葬に参列すべきかどうかは、自分の立場や状況によって異なるため、その都度注意して判断することが大切です。
家族葬の参列基準
家族葬への参列基準となるのは、以下のポイントです。
- 親戚などの身内であるかどうか
- 喪主や遺族から直接訃報をもらったかどうか
- 訃報に葬儀日程・参列を依頼する文面が記載されているかどうか
詳しく解説していきます。
親戚などの身内であるかどうか
家族葬の参列基準の1つめは、親戚などの身内であるかどうかです。
同居家族だけで葬儀を行うといった趣旨の説明を喪主や遺族から受けていない場合、一般的には故人の2親等までに該当する親族が家族葬に参列します。2親等までの親族には、以下の人が該当します。
- 父母
- 祖父母
- 子
- 孫
- 兄弟姉妹
遠方に住んでいたり、日頃やり取りがなかったりした場合でも、2親等以内の親族は家族葬に参列して問題ないとされます。ただし、あまりに疎遠などで迷うケースでは、念のため喪主や遺族に意向を確認しておいた方が無難です。
喪主や遺族から直接訃報をもらったかどうか
家族葬の参列基準の2つめは、喪主や遺族から直接訃報をもらったかどうかです。
故人の家族から直接訃報を伝えられたり、参列をお願いされた場合は、親族でなくても参列して差し支えありません。こうした場合は、故人との関係性を大切にし、遺族もぜひ参列してほしいと考えていると受け止められます。できる限り予定を調整し、参列するようにしましょう。
一方で、人づてに訃報を知った場合には、葬儀の規模を抑えたいといった理由から、遺族があえて参列を望んでいない可能性があります。故人と親しく、最後のお別れをしたい気持ちがあっても、お通夜や告別式への参列は控えるのが望ましいでしょう。
訃報に葬儀日程・参列を拒否する文面が記載されているかどうか
家族葬の参列基準の3つめは、訃報に葬儀日程の詳細や、参列を依頼または拒否する文面が記載されているかどうかです。
訃報を受け取っていても、葬儀の日程や会場といった詳細が記載されていない場合は、単に故人が亡くなった事実だけを知らせたい意図である可能性が高いでしょう。さらに、訃報に「参列はご遠慮ください」といった文言があれば、身内だけで静かに見送りたいという遺族の思いが込められていると考えられます。
このような場合には、家族葬への参列は控えるのが適切です。告別式だけでなく、お通夜についても同様に参列は控えましょう。
訃報に葬儀の日程や会場などの詳細が記されていたり、参列を辞退してほしい旨の記載がなかったりする場合は、家族葬でも参列して差し支えありません。判断に迷うときは、あらかじめ遺族に直接確認しておくと安心です。
家族葬の参列マナー
家族葬に参列することになった際には、特に以下の3つのマナーに注意が必要です。
- 参列時の服装
- 香典
- 挨拶
それぞれの注意点は次のとおりです。
参列時の服装
家族葬に参列する際の服装は、基本的には一般葬と同じく、以下のような準喪服や略喪服(略礼服)を着用します。身内中心で打ち解けた雰囲気の家族葬だからといって、過剰に服装を簡略化しないよう注意しましょう。
| 準喪服 | 略喪服(略礼服) | |
|---|---|---|
| 男性 | ・ブラックスーツ ・白ワイシャツ ・黒ネクタイ ・黒靴下 ・黒革靴 | ・ダークスーツ |
| 女性 | ・黒アンサンブル、黒ワンピース、ブラックスーツ ・黒ストッキング ・黒パンプス | ・ダークスーツ ・地味な色味のワンピース |
準喪服とは、いわゆるブラックフォーマルのことで、一般的に「喪服」と呼ばれる装いを指します。近年では葬儀の簡略化が進んでおり、喪主であってもモーニングなどの正喪服ではなく、準喪服を着用するケースが多く見られます。
また、略喪服は主にお通夜や弔問時に着用し、告別式では準喪服を着用するのが一般的です。お通夜に準喪服を着ても問題はありません。さらに、「平服でお越しください」と案内があった場合には、告別式に略喪服を着用しても差し支えないとされています。
葬儀に参列する際の服装などのマナー全般については、以下の記事で詳しく解説しています。
香典
家族葬の場合、香典を辞退しているケースがある点には注意が必要です。家族葬は内輪だけで執り行うことが多いため、返礼品の準備や余計な気遣いを避ける目的から、香典を辞退するケースも少なくありません。
遺族の意向に反して無理に香典を渡すのはマナー違反とされます。厚意であっても、かえって遺族の負担になってしまう可能性があるため注意しましょう。
香典を辞退している場合、訃報に明記されているのが一般的です。供花や供物についても、「御厚志辞退」の旨が記載されていれば用意しないよう注意しましょう。
香典を辞退していない葬儀であれば、香典を渡しても問題ありません。香典辞退の有無がはっきりしない場合には事前に確認するか、念のため用意しておき、会場で遺族の意向を伺うのもひとつの方法です。
香典を渡す際のマナーは一般葬と同様で、ほどよく使い古された紙幣を、宗教に合った香典袋に入れて渡します。友人・知人、会社の同僚であれば5,000円〜1万円が香典の相場です。
香典のマナーについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてください。
挨拶
家族葬では、挨拶のマナーに関しても一般葬と異なることがあるため注意が必要です。
一般葬では、受付でお悔やみの言葉を添えて香典を渡すのが一般的です。ところが家族葬では、そもそも外部からの参列を想定していないため、受付自体を設けないことも少なくありません。
葬儀会場に受付が見当たらない場合は、喪主やご遺族に直接お悔やみを伝えるとよいでしょう。香典を受け付けている家族葬で受付が設けられていない場合は、喪主に直接お渡ししても差し支えありません。
お悔やみの言葉は「この度はご愁傷様です」「お悔やみ申し上げます」といった簡潔な表現で伝えましょう。その際には忌み言葉を使わないよう注意が必要です。
家族葬に参列しない場合の弔意の伝え方
家族葬に参列しない場合には、弔意の伝え方に迷うこともあるものです。その場合には、以下の点に配慮しながら弔意を伝えましょう。
- 香典・供花・弔電
- 弔問
- お悔やみの連絡
具体的に解説していきます。
香典・供花・弔電
家族葬に参列しない場合の弔意の示し方としては、香典や供花、弔電を送る方法があります。訃報に「香典辞退」「御厚志辞退」といった記載がなければ、基本的には送っても問題ありません。
ただし、家族葬はあえて参列者を限定して行うものです。そのため、お返しが必要となる行為は遺族の負担になる可能性がある点に十分配慮しましょう。香典や供花を渡す場合には、「お返し不要」と添えて伝えるのもひとつの方法です。
弔電はお返しが不要で比較的負担になりにくいものですが、葬儀を大げさにしたくないという理由から辞退しているケースもあります。判断に迷うときは、事前に確認してから送ると安心です。
弔問
弔問によって弔意を伝える方法もあります。遺族が落ち着いた頃合いを見計らい、事前に連絡を入れてから訪問するのが基本的なマナーです。一般的には、葬儀から数日後から四十九日までの間に弔問するのが適切とされています。
その際は、なるべく遺族の負担にならないよう、相手の都合に合わせて訪問し、長居を避ける配慮が必要です。会社関係で弔問する場合は、個別に訪問するのではなく、代表者のみが伺うほうが遺族の負担を抑えられます。
弔問時に香典や供花を持参しても問題ありませんが、辞退の意向が示されている場合には、それに従うよう注意しましょう。
お悔やみの連絡
弔問が遺族の負担になりそうな場合や、遠方で訪問が難しい場合には、お悔やみの連絡によって弔意を伝えるのがよいでしょう。
お悔やみの伝え方としては、忌中の期間である四十九日までに、電話・手紙・メールなどで気持ちを伝えるのが一般的です。電話の場合は直接思いを伝えられる反面、失意の中にある遺族の時間を割くことになるため、手短に済ませる配慮が必要です。
手紙やメールでの弔意表明も問題ありません。相手の状況に合わせ、適切な方法を選ぶよう心がけましょう。
家族葬と言われた場合のよくある質問
ここからは、家族葬で葬儀を行うと言われた場合のよくある質問を紹介します。
身内の葬儀を家族葬でやると社員から言われたら?
社員から「身内の葬儀を家族葬で行う」と伝えられた場合、基本的には参列を控えるのが望ましい対応です。
代表者すら参列しないのは失礼ではないかと心配される方もいるかもしれませんが、無理に参列するほうがかえって遺族の負担となります。代表者のみ参列を依頼される場合でも、会場の入口などで挨拶をする程度にとどめるのが無難です。
ただし、家族葬であっても参列者を身内に限定していないケースでは、参列しても差し支えありません。
香典・供花・弔電については、遺族が辞退していない場合に限り、送っても問題ありません。社員一同の名義でまとめることで、遺族の負担を軽減できます。辞退の有無が不明な場合は、事前に確認しておくと安心です。
また、就業規則で定められた弔事休暇や弔慰金については、身内のみの家族葬であっても速やかに対応する必要があります。
以下の記事では、会社側の立場で、社員から家族葬を行うと言われた場合の対応方法についても解説していますので、併せてお読みください。
身内から家族葬で葬儀をやりたいと言われた場合、親しくない親戚は呼ばなくてよい?
身内から「家族葬で葬儀を行いたい」と伝えられた場合、親しくない親戚を無理に招く必要はありません。
家族葬には明確な参列者の決まりはなく、2親等までの親族で執り行うこともあれば、同居家族のみで行うこともあります。大切なのは、故人の遺志や遺族の意向に沿い、納得できる形で葬儀を行うことです。
ただし、葬儀に招かないからといって一切連絡をしないのはトラブルの原因になりかねません。訃報や葬儀が事後報告となると、不満や誤解を招く恐れがあるため、招かない理由を事前にしっかり説明しておくことが大切です。
また、呼ばない理由を明確に説明できない場合や、格式を重んじる地域・家柄では、2親等以内の親族には声をかけておくほうが無難といえるでしょう。
ご心配な方は、家族葬に親戚を呼ばない場合の注意点と対策を以下の記事で解説しておりますので、併せてチェックしてみてください。
家族葬と言われたら、親しい身内で葬儀を行えるよう配慮しよう
家族葬は、基本的に近親者のみで執り行う葬儀です。友人や会社の同僚が家族葬で葬儀を行うと聞いた場合、参列しないと失礼にあたるのではと不安になることもあるかもしれません。しかし、あえて家族だけの葬儀を選択したことには何らかの意味があるため、遺族の意向は尊重すべきです。
葬儀に参列しなくても、弔意は伝えられます。香典・供花・弔電や、弔問、お悔やみの連絡など、相手の状況に合わせて選択するのが大切です。家族葬の趣旨を理解し、遺族の思いに配慮しましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国にご提供しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。