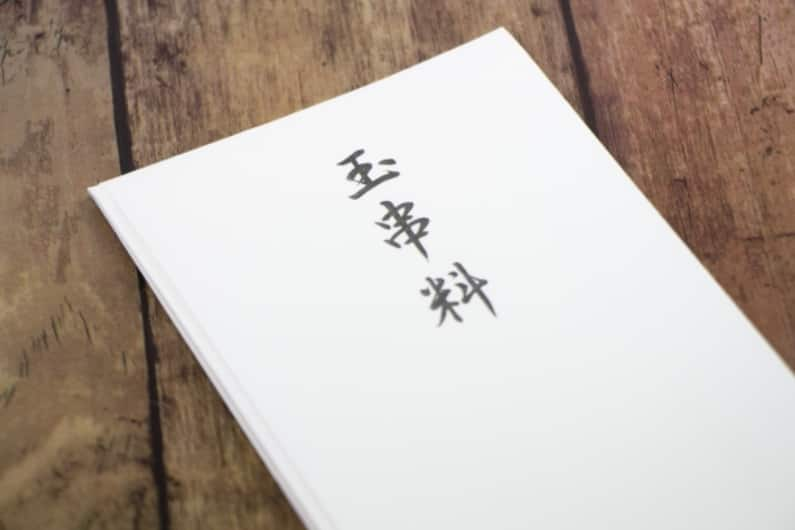神式で執り行われる神葬祭は、仏教式とは異なる独自の流れや作法があります。「玉串料(たまぐしりょう)」は、参列時に知っておきたい大切な習わしのひとつです。
名前は聞いたことがあるものの「渡すタイミングやのし袋の書き方など詳細までわからない」という方がほとんどでしょう。
この記事では、神葬祭における玉串料の基礎知識や相場、のし袋のマナーなどについて分かりやすく解説していきます。
この記事を要約すると
- 玉串料とは、神式の葬儀で神前に捧げるもので、仏式の香典にあたるもの。
- 玉串料には金額の相場や表書きの書き方、のし袋選びなど細かなマナーがある。
- 玉串料のお返しには時期や金額の目安があり、神式にふさわしい挨拶状やのし袋が必要。
玉串料は神道におけるお葬式「神葬祭」で必要
日本では葬儀といえば仏教式のイメージを持つ方が多く「香典」を包む習慣が一般的です。一方、神道に基づく「神葬祭(しんそうさい)」では、香典ではなく「玉串料(たまぐしりょう)」を用意するのが習わしです。
神葬祭は、神職が司る神道の儀式で、仏式とは葬儀の進行や用語も異なります。特に玉串料は、神葬祭に参列するうえで欠かせないもののひとつであり、意味やマナーを知らずに参列すると戸惑う場面も出てくるかもしれません。
また、香典とは見た目が似ていても、表書きや金額の目安、渡し方などに違いがあります。正しく対応するためには、事前に神葬祭における基本的な流れと、玉串料の位置づけを理解しておくことが大切です。
玉串料とは神葬祭で神前にお供えするお金のこと
玉串料とは、神葬祭で神前に捧げるための金銭のことです。前述のとおり、香典に似た役割を持ちますが、宗教の違いによって意味や使い方に違いがあります。
言葉だけではイメージが湧きにくいという方もいるでしょう。ここでは、玉串料の成り立ちや似たような場面で使われる「初穂料」との違いについて解説します。
玉串料の読み方と由来・意味
玉串料は神前へ思いを捧げるための金銭を表す言葉です。もともと神道では榊の枝に紙垂(しで)を結んだ「玉串」を神前に供える習わしがありました。玉串は神様への敬意や感謝の気持ちを形にしたものです。
しかし現在では、一般の参列者が玉串を用意することは少なく、代わりに金銭を包んで渡す形式が一般的になっています。それが「玉串料」です。
なお、玉串料という名称は弔事だけでなく、七五三や鎮魂祭など神道の慶事でも使われることがあり、幅広い場面で登場します。
玉串料と初穂料の違い
玉串料は、神式の儀式で使われる金銭の名目です。「御玉串料(おたまぐしりょう・おんたまぐしりょう」と表記されることもあり、のし袋の表書きでは「御玉串料」と書くのが一般的です。
一方で、神道の儀式では「初穂料(はつほりょう)」という表現も使われます。これはもともとその年に収穫された最初の穀物を神式に捧げていたことに由来しており、今では金銭に置き換えた形で納められています。
ただし、初穂料は本来、七五三や結婚式、安産祈願などの慶事の場で使うものです。葬儀や告別式のような弔事では用いらずに、玉串料を選ぶのが正式なマナーとされています。どちらも神前に気持ちを捧げるものですが、場面に応じて適切な表記を選ぶようにしましょう。
玉串料の相場
玉串料では、包む金額に明確な決まりはありません。香典と同じく、立場や関係性、地域の習慣によって相場が異なります。
高すぎると気を遣わせてしまい、少なすぎると配慮が足りない印象を与えることもあるため、一般的な相場を把握しておくのが安心です。ここでは、神職にお渡しする場合と、参列者が遺族に渡す場合の金額の目安について解説します。
神職(神主)にお渡しする玉串料の相場
神職へお渡しする玉串料の相場は、一般的に20〜50万円とされています。
葬儀の内容や神社の規模、地域の慣習によって異なるため、全国一律ではありません。神社によっては、祭祀の種類ごとに玉串料の金額をあらかじめ設定していることもあります。
金額の指定がないときは「お気持ちで」と言われることもありますが、その際は相場を参考にすると安心です。不安がある場合は、神社に「神葬祭の玉串料について伺いたいのですが」と尋ねてみるとよいでしょう。
また、地域差があるため、近隣で神式葬儀を経験した方や葬儀社のスタッフに相談して目安を知るのもひとつの手です。
参列者が遺族に渡す玉串料の相場
参列者が遺族に渡す玉串料は、故人との関係性や地域、また自分の年齢や立場によって包む金額が異なります。金額の幅はありますが、以下の表を目安として確認しておくと安心です。
| 故人との関係性 | 玉串料の目安 |
|---|---|
| 両親(義理含む) | 5〜10万円程度 |
| 兄弟姉妹(義理含む) | 3〜5万円程度 |
| 祖父母(義理含む) | 1〜3万円程度 |
| 叔父・叔母(義理含む) | 1〜3万円程度 |
| 友人・知人・その家族 | 5,000〜1万円程度 |
| 会社の同僚・ご近所の方 | 3,000〜5,000円程度 |
金額はあくまで一般的な目安ですが、20代であれば少なめでも失礼にあたらないことが多く、社会的な立場や年齢が上がるほど、相場の上限に近づけたほうがよいとされています。
また、玉串料は香典と同じく「偶数は避ける」という考えもあるため5千円・1万円・3万円といった数字が選ばれやすい傾向があります。
友人や会社の同僚など、複数人で参列する場合は、金額に大きな差がでないようあらかじめ包む額を統一しておくとよいでしょう。
玉串料に関するマナー
玉串料を準備する際は、相場の金額だけでなくのし袋の選び方や表書き、お札の入れ方などにも細かい決まりがあります。一見すると香典と似ていますが、神式ならではの作法や注意点があるため、仏式と同じ感覚で対応しないようにしましょう。
ここでは、神職に渡す場合と参列者として遺族に渡す場合、それぞれに必要なマナーについてわかりやすく解説していきます。
のし袋のマナー
玉串料を包む際には、必ず不祝儀袋(弔事用ののし袋)を使用します。のし袋にはお祝いごと用の紅白と、弔事用の白黒・双銀などがありますが、神式の葬儀では後者を選びましょう。
選ぶ際には、蓮の花や百合の花が印刷されたものを避けることも重要です。蓮は仏教、百合はキリスト教の象徴となるため、神道の儀式では不適切とされています。金額に応じた不祝儀袋の使い分けもマナーのひとつです。
- 1万円未満の場合:印刷の黒白水引つきのもの
- 1万円以上の場合:実際の黒白水引が付いた袋
- 5万円以上の場合:大判の袋に双銀や双白の水引が付いたもの
水引の結び方は「結び切り」が基本です。これは「不幸を繰り返さない」という意味を持つ、固くほどけない結び方です。
同じ意味で、左右を強く結び合う「あわじ結び」も使用可能です。一方「蝶結び」は何度も結べるため、葬儀では使用しないようにしましょう。
表書きのマナー
のし袋の表書きは、水引の上部に「御玉串料」と記載するのが基本です。神葬祭ではほかに「御神前」「御榊料」「御神饌料」「御霊前」なども使われますが、地域や神社によって使い分けが異なるため、事前に確認しておくと安心です。
水引の下には、玉串料を納める方の氏名をフルネームで記載します。2〜3名までであれば連名でも構いませんが、それ以上の場合は、代表者の氏名の下に「他一同」などと添えるのが一般的です。
弔事では、墨の濃さを抑えた「薄墨」で表書きと名入れを行うのが礼儀とされています。これは、突然の訃報に準備が整わなかった心情を表現する意味が込められています。
中包み書き方のマナー
中包みはのし袋の内側に入れる封筒で、金額・氏名・住所を記入する重要なパーツです。表面と裏面で書く内容が異なります。中包みの表面には、中央上部に包んだ金額を記載します。
基本的に縦書きで「弌・弐・参・伍・拾・阡(仟)・萬」などの旧字体を使って書きましょう。たとえば3万円を包む場合は「金参萬円」と表記します。
最近では、あらかじめ横書きの記入欄が設けられた中包みもあり、その場合は「30,000円」と記載しても問題ありません。
中包みの裏面には、送り主の氏名と住所を記入します。住所は縦書きで記載し、数字部分は「五丁目七番地」など、漢数字を使うのが丁寧な印象を与えます。複数名で贈る場合は、代表者の氏名と住所のみを記載しましょう。
筆記具は、黒のサインペンやボールペンで、見た目が乱れないよう丁寧に記載することが大切です。
お札の入れ方と向きのマナー
玉串料を包む際、お札の向きにも決まりがあります。お札は、人物が書かれた面(表面)を裏にして、肖像画下側にくる向きで中包に入れるのが基本です。これは中袋を裏から開けた時に、お札の表が自然に上を向いて見えるようにするためです。
中袋がない場合は、外袋に対して同じように封入すれば問題ありません。どちらの場合も、複数枚あるときは上下と向きを揃えてきれいに重ねると丁寧です。また、玉串料には使用済みの紙幣を用いるのが一般的とされています。
新札は「準備していた」印象を与えるため、避けたほうがよいでしょう。やむを得ず新札を使う場合は、折り目を一度入れてから封入すると配慮が伝わります。細かな所作ですが、こうしたひと手間に心遣いが表れます。
不祝儀袋の出し方
神職への玉串料は、儀式の開始前に直接手渡すのが一般的です。この際、袱紗(ふくさ)に包んで持参し、袱紗から取り出して渡します。渡す際には、のし袋の表書きが相手から読める向きにし、両手で丁寧に差し出しましょう。
神職が多忙な場合や、直接手渡しが難しい場合は受付などに預けるケースもあります。事前に神社や葬儀社に確認しておくと安心です。
参列者として玉串料を納める場合は、葬儀会場の受付でお悔やみの言葉とともに渡すのが一般的です。受付が設けられていない時には、ご遺族に直接手渡す形となります。その際も袱紗に包んで持参し、渡す直前に袱紗から取り出して、表書きが相手から読める向きに揃えて両手で渡します。
どちらの場合でも、渡す際の所作や言葉遣いに気を配ることで、相手に対する敬意が伝わります。
玉串料のお返しをする際のマナー
仏式の葬儀と同じように、神葬祭で玉串料を受け取った場合も、感謝の気持ちを込めた返礼品を送るのが一般的です。
ただし、神式ならではのマナーや用語の違いがあり、仏式と同じ感覚で対応してしまうと失礼にあたることもあります。ここでは、神式における玉串料のお返しについて、解説します。
神式における玉串料のお返しの基本マナー
神道においても、葬儀で玉串料や御霊前をいただいた場合は、感謝の気持ちを表す返礼を行うのが一般的です。仏式では四十九日が一区切りとされますが、神式では「五十日祭」がそれにあたります。
そのため、返礼品は五十日祭が過ぎたタイミングで贈るのが通例です。ただし、最近では仏式同様に葬儀当日に「即日返し」として品物を渡すケースも増えてきました。地域や家ごとの習慣により対応はさまざまです。
五十日祭後に返礼を行う場合は、一ヶ月以内を目安に「偲び草」などの表書きを付け、挨拶状を添えて送るのが丁寧です。
返礼品の金額と選び方のポイント
ると相手に気を遣わせてしまうため、控えめな金額で問題ありません。
返礼品は使ってなくなる「消えもの」が好まれます。お茶やお菓子、海苔、調味料などの食品のほか、石けんやタオルなど日用品も人気です。最近ではカタログギフトを選ぶ方も増えており、受け取る側が好きなものを選べます。
地域や家庭によって風習が異なることもあるため、形式にとらわれすぎず、感謝の気持ちを大切に選びましょう。
のし紙と表書きのマナー
返礼品には、神式にふさわしいのし紙を用いることが大切です。水引は黒白または黄白の「結び切り」が基本で、仏式でよく見かける蓮の花の柄は避けましょう。のしの表書きには「志」や「偲び草」と書くのが一般的です。
地域によっては「茶の子」などの表記が使われることもありますが、広く使える「偲び草」のほうが無難です。名義は、喪主の姓だけでも構いませんが、より丁寧に伝えたい場合はフルネームで記載します。
神式で用いる挨拶状の書き方と文例
香典返しに添える挨拶状は、形式だけでなく言葉遣いにも注意が必要です。神式では「供養」や「冥福」など仏教由来の表現は避け「帰幽」「五十日祭」など、神道に即した用語を使用します。
【挨拶状の例文】
謹啓
このたび(続柄)(故人名)帰幽に際しましてはご多用中にもかかわらずご会葬を賜り
また御玉串料のご厚志をいただき誠にありがとうございました
おかげをもちまして去る○月○日に五十日祭を滞りなく執り行いました
つきましては偲び草のしるしまでに心ばかりの品をお届けいたしますので何卒ご受納賜りますようお願い申し上げます
本来であれば拝眉の上ご挨拶申し上げるべきところ略儀ながら書中にて失礼いたします
奉書紙を使用した格式ある挨拶状やカード型の簡易タイプなど、送り先との関係性や地域の習慣に合わせて選びましょう。
玉串料に関するよくある質問
神葬祭における玉串料のマナーについて解説してきましたが、まだまだ気になることがあるという方もいるでしょう。
ここでは、玉串料のマナーに関する4つのよくある質問に答えていきます。内容を理解したうえで正しく対処しましょう。
通夜と葬儀、玉串料を両方渡すべきか?
玉串料は、通夜と葬儀のどちらか一方でお渡しすれば問題ありません。両方に参列する場合は、通夜で渡したら葬儀では記帳のみとし、重ねて渡すのは控えましょう。
通夜と告別式のどちらかだけに参列する場合は、その場で玉串料を渡しましょう。
玉串料に「御」はつける?
玉串料の表書きには「御玉串料」と「御」を付けて記載するのが一般的です。これは、神職や遺族への敬意を示すための丁寧な表現とされており、仏式で「御香典」と書くのと同じような意味合いがあります。
玉串料とだけ記載しても間違いではありませんが、格式ある場では「御」を付けるのが無難です。なお、地域や神社によっては「御榊料」「御神饌料」などの表記が使われる場合もあります。
葬儀後に玉串料を渡すタイミングやマナーは?
仕事の都合や距離の関係などで葬儀に出席できず、玉串料を渡す機会を逃した場合は、後日ご遺族のもとを訪ねる「弔問」のタイミングで渡しましょう。弔問とは、故人の家を訪れてご遺族にお悔やみの言葉を伝える行為を指します。
弔問の際には、あらかじめ都合を確認したうえで伺うようにし、玉串料を袱紗に包んで持参します。「ご仏前」など仏教用語を避け「御玉串料」と書きましょう。
どうしても弔問が難しい場合は、現金書留を用いて送付することも可能ですが、できるだけ直接渡すほうが丁寧です。
玉串料に関するマナーを理解して神式の葬儀に備えよう
玉串料とは、神葬祭で故人に祈りを捧げる際に用いられる大切なものです。金額の相場は立場や関係性によって異なり、のし袋の種類や表書き、お札の入れ方などにも細かなマナーがあります。
また、葬儀後に返礼品を送る際には、神道のしきたりに沿ったのし紙や挨拶状の用意も欠かせません。慣れない神式でも、基本的な作法を知っておけば、落ち着いて対応できます。事前にしっかり備えて、誠実な気持ちを丁寧に伝えましょう。
なお、弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。