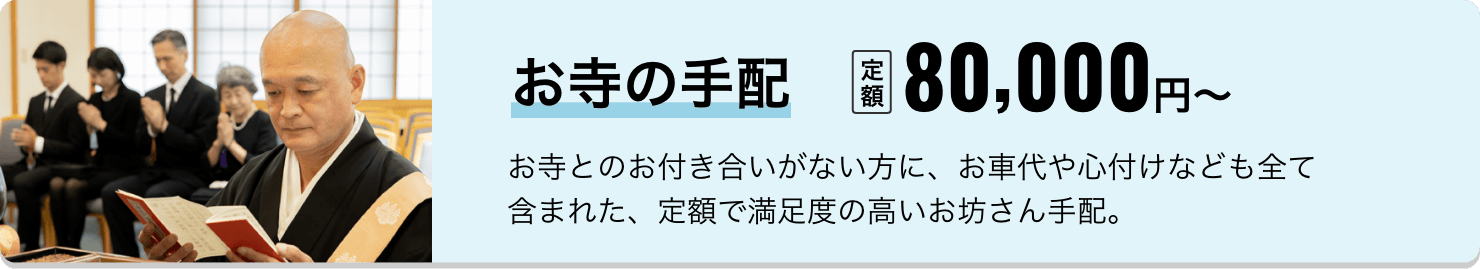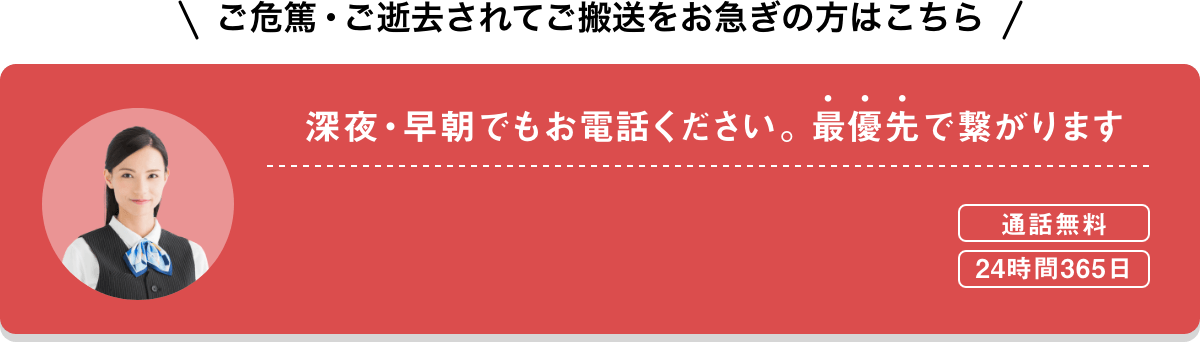大切な家族が重篤と告げられたとき、家族は数多くの対応をこなす必要があります。しかし、突然の出来事に対して動揺や不安を抱え、何をすべきか迷う方は多いのではないでしょうか。
今回は、家族が重篤になった際の基本的な対応やもしものときのための準備、周りの人の家族が重篤と診断された際の対応方法などをわかりやすく解説します。万が一のときに備えて、一通りの流れややるべきことを押さえておきましょう。
この記事を要約すると
- 「重篤」は、病気や怪我によって命の危険が迫っている状態を指す医療用語です。「危篤」よりは軽度ですが、「重体」や「重症」よりも重い状態で、場合によっては回復せずに亡くなる可能性もあります。
- 家族が重篤と診断されたら、すぐに病院に駆けつけて医師の説明を仰ぎましょう。また、本人への声かけやほかの家族・職場・学校などへの連絡も欠かさずに行う必要があります。
- 親しい人や職場の関係者から家族が重篤状態であると告げられた場合、お見舞いの言葉を伝えて本人へ最大限の配慮を行いましょう。なお、家族以外は直接お見舞いに伺うのを控えるのがマナーです。
「重篤」とは?
「重篤(じゅうとく)」は、病気や怪我が進行し、命に関わるほどの深刻な状態に陥っていることを指す医療用語です。緊急搬送をする際にも用いられ、死亡の次に症状が重いことを示します。重篤状態は症状が急変する可能性が高く、病院での集中治療が必要です。
<重篤な症状の例>
- 病院外での心停止
- 重症の大動脈疾患
- 重症の脳血管障害
- 重症の外傷・熱傷
- 重症の敗血症・特殊感染症
- 重症の呼吸不全
- 重症の急性心不全
- 重症の出血性ショック
また、「重篤」と似たような言葉に、「危篤」・「重体」・「重症」などの言葉があります。それぞれの意味合いを知り、適切に状態を判断できるようになりましょう。
| 用語 | 意味 | 回復の見込み |
|---|---|---|
| 重篤 | 命に関わる深刻な状態 | やや低い |
| 危篤 | 死が差し迫っている状態 | 極めて低い |
| 重体 | 症状が重いが、死に至るほど深刻ではない。報道でよく用いられる | 比較的高い |
| 重症 | 3週間以上の入院と治療が必要な怪我と病気 | 高い |
「危篤」との違い
「危篤」は、死が目前に差し迫っており、今後数時間から数日の間に亡くなる可能性が高い状態を指します。医師から危篤を告げられた場合、すぐに家族や親族に連絡を取り、最期に立ち会う準備を進めるのが一般的です。
危篤は重篤と同様に命に関わる状態を表す言葉ですが、重篤よりもさらに危険な状態を表すため、きわめて緊急度が高いといえます。
「重体」との違い
「重体」は、意識がない・脳や内臓に重度の外傷や障害があるなど、容体がきわめて重い状態を指す言葉です。報道用語でもあり、「意識不明の重体」といった表現がよく用いられています。
重体は重篤や危篤と比べるとやや軽い状態であり、必ずしも死が差し迫っているとは限りません。重体と診断されてから回復する可能性も十分にあるといえます。
「重症」との違い
「重症」は、厚生労働省によって「3週間以上の入院加療を必要とするもの」と定められています。こちらも同様に深刻な症状を指しますが、必ずしも命の危険に晒されているわけではなく、重篤や重体と比べて軽度な状態です。たとえば骨折や感染症による高熱などで入院をする場合、重症とみなされます。
重篤から回復する見込みはある?
「重篤」は状態がきわめて重いことを指す言葉ですが、必ずしも死を意味するわけではありません。適切な治療や早期の対応によって、重篤状態から回復に向かうケースもあります。
ただし、重篤とされる状態にもさまざまあり、年齢・基礎疾患の有無・症状の程度などによって回復率は大きく異なります。「危篤」よりもやや軽度な状態ではありますが、場合によっては回復せずに亡くなってしまう可能性も考えられます。
身内が重篤になったときに行うべきこと
身内が重篤状態になったという連絡を受けたら、すぐに適切な行動を取る必要があります。できるだけ落ち着いた状態で、今できることを尽くしましょう。
落ち着いて行動する
急に重篤の知らせを受けたとき、驚きや不安から気が動転してしまう方は珍しくありません。しかし、必要な対応を的確に進めるには、まず自分の心を落ち着かせることが大切です。
焦ったりパニックになったりするとかえって忘れ物や連絡漏れなどのミスにつながる可能性があるため、できるだけ冷静に、今何を優先すべきかを考えながら行動しましょう。
病院に駆けつける
病院から重篤の連絡を受けたら、できるだけすぐに病院へ向かいましょう。病状によっては、延命治療の可否などの重大な判断が求められることもあります。病院に到着したら医師の説明をしっかりと聞き、現在の状態や今後の治療の見通しについて理解することが大切です。不明な点はその場で確認し、家族間で情報を共有してください。
また、場合によっては病院に宿泊したり、そのまま亡くなることも考えられます。宿泊の荷物・貴重品・ある程度の現金などを持っておくと安心です。
本人に声かけをする
本人の意識がある場合、家族から声をかけることが大きな励ましになります。また、たとえ意識がないように見えても、聴覚が機能しているケースは珍しくありません。枕元でやさしい言葉や励ましの言葉をかけ、本人が安心できる空間を作りましょう。
家族や親戚に連絡する
身内が重篤状態になった場合、家族や親族へ連絡する必要があります。連絡範囲の目安は三親等までが一般的で、本人の両親や子ども、兄弟姉妹、祖父母などがこれにあたります。
とくに、もし亡くなった場合に葬儀へ参列してもらいたい相手や、本人との関わりが深い相手には早めに連絡するのがマナーです。連絡を入れる際は、本人の状態とともに、入院先の病院の情報や家族の代表者の続柄と連絡先なども共有しましょう。
<例文>
突然のご連絡失礼いたします。⚪︎⚪︎の息子の⚪︎⚪︎です。父の⚪︎⚪︎が、本日重篤の状態であると診断されました。入院先は⚪︎⚪︎病院の⚪︎⚪︎号室で、面会は⚪︎時から⚪︎時まで受け付けております。もしお時間が許す場合は、お越しいただけますと幸いです。なお、何かご不明点がございましたら、私の携帯電話までご連絡くださいませ。
病院の住所・電話番号
自身の連絡先
職場や学校に事情を伝える
身内が重篤と診断された場合、お見舞いやその後の容体急変・葬儀によって仕事や学校を休む可能性があります。そのため、職場や学校などの関係先にもすみやかに連絡を入れる必要があります。連絡する際は、直属の上司や担任などの関係の深い相手に対して事情を簡潔に伝えるだけでもかまいません。
「身内が重篤のため、本日より数日間お休みをいただきたいです。急なことでご迷惑をおかけいたしますが、ご理解いただけますと幸いです」などと伝えれば、事情を汲んで対応してもらえるでしょう。
宗教者へ連絡する
仏教では亡くなる直前に枕経を行うケースがあるほか、キリスト教では臨終時に宗教者を招いて儀式を行うしきたりがあります。このような宗教的儀礼を行いたい場合は、重篤の診断が下された時点で僧侶や神父に連絡を入れておくと相手に失礼がなく、容体が急変した際にもスムーズに対応してもらえます。お世話になっている宗教者に事情を説明し、亡くなる前に必要な儀式を行えるように準備しておきましょう。
なお、お世話になっている宗教者がいない場合、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では全国でのご手配を承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。
葬儀社選びを始める
重篤と判断された時点で、万が一に備えて逝去後の準備を始めることも大切な行動のひとつです。もし容体が悪化した際に慌てないよう、あらかじめ信頼できる葬儀社を見つけておくと安心です。
すでに終活やエンディングノートなどによって本人が希望する葬儀を定めている場合は、それに沿って準備を進めましょう。すでに葬儀社が決まっている方は、担当者の連絡先を確認したり、あらかじめ葬儀社に事情を説明したりしておくと、いざというときにスムーズに動けます。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では全国一律価格で、必要なものに厳選したセットプランでの葬儀をご提供しております。さらに、事前にお問い合わせいただいた方には、特別価格でご案内しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。
身内以外が重篤になったときの対応
ここからは、仲の良い友人や職場・学校での関係者から「身内が重篤になった」と連絡を受けた際の適切な対応方法を解説します。
お見舞いの言葉を伝える
相手の家族が重篤な状況と知ったら、まずは相手にお見舞いの言葉を伝えましょう。このとき、本人との関係性の深さを問わず、メールやSNSを用いて間接的にメッセージを送るのがマナーです。
たとえば、「お母様のご容体を伺い、大変驚いております。一日も早いご快復をお祈りしています」などといった文面を送ります。相手の心情を思いやり、簡潔かつ温かい言葉を選ぶことで、相手が看病に専念しやすくなるでしょう。
自分がお見舞いに行くのは控える
自分と関わりのある相手や顔見知りの相手だったとしても、家族ではない以上、直接お見舞いに行くのは控えましょう。重篤時は容体が急変することが多く、家族や医療関係者が対応に追われているため、訪問はかえって負担になってしまいます。
お見舞いの気持ちはメールやSNSで伝え、症状が落ち着いたタイミングや回復時に改めてお見舞いの機会を設けるのが賢明です。
容体が回復せず亡くなった場合の流れ
重篤状態は場合によっては回復の見込みがありますが、容体が悪化し、回復せずに亡くなることも考えられます。ここからは、残念ながら危篤や臨終を迎えた場合の葬儀までの流れを紹介します。
臨終
入院先の病院で容体が急変し、医師による死亡確認が行われると、正式に死亡が確定します。家族がそばにいる場合は、看取りに立ち会ってお別れをすることも可能です。死亡の確認後、医師は死亡診断書を作成します。この診断書は遺族が退院の際に受け取り、今後の死亡届の提出の際に使用します。
末期の水を取る
臨終を迎えた後、仏教では「末期の水(まつごのみず)」とよばれる儀式を行います。これは故人の唇を湿らせる儀式で、無事にあの世へと旅立てるように寄り添う意味合いが込められています。末期の水を行う際は、本人と関わりの深い遺族から順番に、水を含ませたガーゼや脱脂綿などを故人の口元に静かに当てましょう。
霊安室へ移動・搬送先の手配
病院で死亡が確認されたら、入院していた病室から霊安室にご遺体を移動させます。霊安室はご遺体の安置先が決まるまでの一時的な安置場所で、長くても半日程度しか利用できません。
そのため、遺族はすみやかにご遺体の搬送先を手配することが求められます。なお、この時点で依頼する葬儀社が決まっている場合は、ご遺体の搬送から葬儀社に依頼することも可能です。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、24時間365日・葬儀の専門スタッフが受け付けておりますので、お電話いただければすぐにご搬送の手配をいたします。
また、ご安置の場所にお困りの場合、「これからの家族葬プラン」であれば、会館でのご安置を4日までプラン料金内に含んでおりますのでご安心ください。
葬儀社へ連絡
ご遺体の安置先が決まったら、すみやかに葬儀社へ連絡しましょう。事前に相談している葬儀社があれば、昼夜を問わずにすぐに対応してもらえます。もし葬儀社が決まっていない場合は病院から紹介されることもありますが、割高な葬儀社を紹介されることが多いため、自力で比較・検討のうえで葬儀社選びをする方が賢明です。
なお、弊社は事前にご連絡いただいていなくても、もしものことがあってからのお電話でもすぐにご手配いたしますので、ご安心ください。
家族や親戚に訃報を伝える
身内が亡くなったら、家族・親戚・親しい友人らに訃報を伝える必要があります。連絡順は葬儀への参列を依頼する相手を優先し、電話やメールですみやかに連絡を入れましょう。なお、訃報は有事のため、昼夜を問わずに連絡してかまいません。
また、故人や遺族の通っている学校や職場にも事情を伝える必要があります。以下の記事を参考にしながら、適切に内容を伝えてください。
死亡診断書の受け取り
死亡診断書は死亡が確認された後に医師が作成し、遺族が退院の際に受け取ります。この書類は死亡届の提出や火葬許可証の取得に必要な重要書類のため、必ず大切に保管してください。
なお、発行には数万円程度の手数料がかかるため、あらかじめまとまった現金を用意しておくと安心です。診断書を受け取ったら、何通かコピーを取っておくとその後の準備で役立ちます。
ご遺体搬送
ご遺体の搬送準備が整ったら、霊安室から自宅や葬儀会場などの安置所へご遺体の搬送を行います。搬送は寝台車やストレッチャーを用い、専門業者が特殊な処置を施しながら進めるのが一般的です。なお、搬送先によって搬送費用が変動するため、自宅や葬儀場との位置関係を鑑みながら安置所を選ぶことが重要です。
ご遺体安置
ご遺体が搬送先に到着したら、ご遺体に必要な処置を施したうえで安置します。自宅で安置する場合は布団の用意が必要ですが、ご遺体の処置や枕飾りの準備は葬儀社に一任できるため、遺族は葬儀社の指示に従っていれば問題ありません。ご遺体を適切に安置できたら、お香を絶やさずにあげながら納棺までの間を過ごしましょう。
葬儀の準備
ご遺体を適切に安置できたら、葬儀の準備に本格的に移ります。葬儀日程・葬儀形式・葬儀会場などの基本事項を決定したら、遺族と葬儀社で打ち合わせを行いながら詳しい葬儀内容を詰めていきます。また、僧侶の手配・料理の手配・参列案内などもこのタイミングで行う必要があります。
葬儀の内容は故人の宗派や地域の風習によって異なるため、事前に遺族間で希望や予算感をすり合わせておくことが重要です。 なお、以下の記事では葬儀準備の流れや葬儀前に準備することのチェックリストをより詳しくまとめているので、ぜひ参考にしてください。
身内が重篤になったら、落ち着いて対応しましょう
身近な家族が重篤と診断されたら、冷静に適切な行動を取る必要があります。病院での対応・親族への連絡・葬儀の準備などの数多くのやるべきことがありますが、あらかじめ理解しておけばいざというときにスムーズに対応できるでしょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。