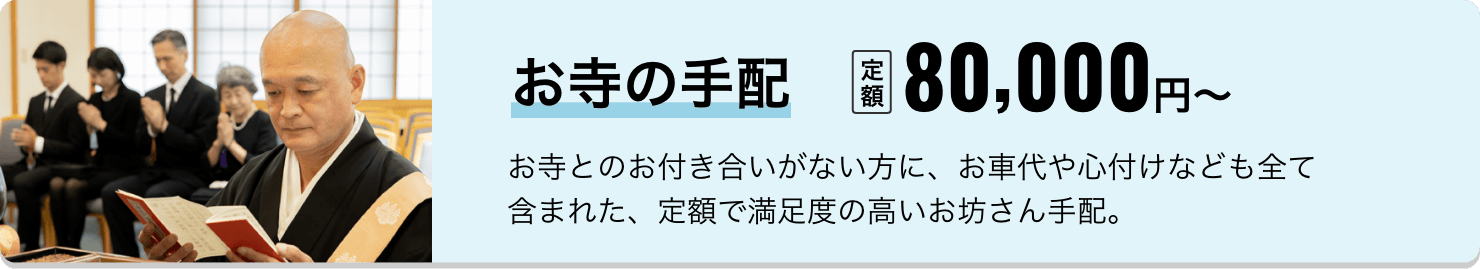浄土真宗の最大宗派である浄土真宗本願寺派は、京都の龍谷寺本願寺に本山を構え、「お西さん」という名で親しまれています。真宗本願寺派の葬儀は、「絶対他力」や「往生即身仏」の教義に基づき、故人を極楽浄土へと導いた阿弥陀如来を讃える場として執り行われます。
本記事は、浄土真宗本願寺派の葬儀について詳しく知りたい方やこれから参列を予定している方向けに、浄土真宗本願寺派の葬儀の流れや特有の風習について詳しく解説します。葬儀に参列する際に知っておきたいマナーも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事を要約すると
- 浄土真宗本願寺派は、全国に約10,000もの寺院を持つ浄土真宗の最大宗派です。京都の龍谷寺本願寺(西本願寺)を本山とし、「絶対他力」や「往生促進仏」という考え方を持ちます。
- 真宗本願寺派の葬儀・告別式は、読経を中心としたシンプルな儀式です。阿弥陀如来への感謝を伝え、信仰を新たにする「聞法の場」という意味合いがあります。
- 真宗本願寺派の焼香の回数は1回で、撚り房が付いた数珠を使用します。故人はすでに成仏しているととらえるため、香典の表書きは「御仏前」や「御香典」とするのがマナーです。
浄土真宗とは?
浄土真宗は、浄土宗の開祖・法然の弟子である親鸞によって鎌倉時代に開かれた仏教の一派です。
浄土宗では「現世で阿弥陀仏を信じ念仏を唱えれば、誰でも極楽浄土に成仏できる」という「他力本願」の教えを説きますが、浄土真宗はその教えをさらに発展させた「絶対他力」の教えを持ちます。これは、「念仏を唱えていなくても、阿弥陀如来を信じていれば誰もが救われる」という考え方です。
また、死者は亡くなってすぐに成仏するという「往生即身仏」の思想を持ち、極楽浄土へ往生した後、この世に戻って人々を救済するという教えも説かれています。
浄土真宗本願寺派とは?
浄土真宗本願寺派は、全国に約10,000もの寺院を持つ浄土真宗の最大宗派です。本山は京都府にある龍谷山本願寺で、西本願寺とも呼ばれることから「お西」や「お西さん」という名で親しまれています。
本願寺派はほかの宗派に比べて戒律を重んじず、僧侶の妻帯や肉食も認められている点が特徴的です。経典には、釈迦如来が説いた「浄土三部経」や、親鸞聖人が記した「正信念仏偈」などが用いられています。
浄土真宗本願寺派の歴史
もともと大きな宗派として全国に広がっていた浄土真宗ですが、戦国時代から江戸時代初期にかけて真宗大谷派と分かれた歴史を持ちます。これは戦国時代に起こった信者による対立問題と後継問題がきっかけになったもので、最終的には徳川家康の政策によって東西に分けられました。
浄土真宗大谷派との違い
浄土真宗本願寺派と大谷派は、「絶対他力」や「往生促進仏」の考え方を持つ点は同じですが、葬儀の形式やさまざまな作法に違いがあります。真宗本願寺派の葬儀に参列する際は、事前に両者の違いを知っておくことが大切です。
| 真宗本願寺派 | 真宗大谷派 | |
|---|---|---|
| 本山 | 龍谷寺本願寺(西本願寺) | 真宗本廟(東本願寺) |
| 葬儀の特徴 | 簡素な形式 | 葬儀式が2部構成 |
| 数珠の房の形 | 撚り房 | 飾り編み |
| 焼香の回数 | 1回 | 2回 |
浄土真宗本願寺派の葬儀の特徴
真宗本願寺派では、往生即身仏の考えのもと、葬儀を前に故人が成仏しているという前提で葬儀が執り行われます。そのため、葬儀は故人の冥福を祈る場ではなく、阿弥陀仏の教えを学ぶ「聞法の場」と位置付けられます。
<浄土真宗本願寺派の葬儀の特徴>
- 引導・授戒の儀式がない
往生即身仏の考えに基づき、引導・授戒・末期の水などの儀式が行われない - お清めの塩を用意しない
死者のことを「穢れ」とみなさないため、お清めを行わない - 死装束を着せない
死装束は極楽浄土への旅立ちの服装を意味するため、代わりに白衣を着用させる - 戒名ではなく法名と呼ぶ
法名にはランクがなく、自然に授かるものと考える - 位牌を安置しない
位牌の代わりに過去帳に法名が記される - 枕飾りを設置しない
死後の供養を行わないため、枕団子・枕飯・水等のお供えは不要
浄土真宗本願寺派の葬儀の流れ
浄土真宗本願寺派では、納棺勤行という儀式の後に葬儀が執り行われます。合掌や礼拝を行なう対象は故人ではなく、故人を極楽浄土へと導いた阿弥陀如来という点に留意しましょう。
お通夜
真宗本願寺派のお通夜は、「臨終勤行」と呼ばれる儀式から始まります。これは他宗派における枕経に相当する儀式で、僧侶が故人の代わりに阿弥陀如来への最後のお勤めを行います。故人が法名をまだ授かっていない場合は、式の中で僧侶から授かります。
臨終勤行を終えたら、その後の式の内容は一般的な仏式のお通夜とほとんど変わりません。式の後は僧侶や遺族・親族が集い、故人の思い出を偲び語らう通夜振る舞いの席が開かれます。
納棺式
真宗本願寺派の納棺式は「納棺勤行」ともよばれ、故人が安置されている自宅の仏壇前やご遺体安置所で行われます。はじめに故人の身体を清め、清潔な白衣を身につけさせます。手には木製の数珠をかけ、胸の前で合掌させた姿で納棺します。
最後に胸元に「南無阿弥陀仏」と記された「納棺尊号」という紙をのせるのが真宗本願寺派特有の風習です。これは「誤って故人に手を合わせたとしても、結果的に阿弥陀如来に礼拝する形になるように」という意味が込められています。
棺を閉じたら、浄土真宗の七条袈裟を掛けて斎場へと搬送されます。一連の儀式の最中には、僧侶による読経も行われます。
葬儀・告別式
真宗本願寺派の葬儀・告別式は「葬場勤行」とも呼ばれ、阿弥陀如来や仏・菩薩の名を唱えて導きを願う「三奉請(さんぶしょう)」という儀式から始まります。続いて僧侶が故人の死を仏に報告する「表白(びょうびゃく)」を行い、正信偈(しょうしんげ)や和讃(わさん)などの浄土真宗ならではの読経に移ります。
真宗本願寺派における葬儀は故人を供養する目的ではなく、参列者が仏の教えを学び、阿弥陀如来への信仰を新たにする「聞法の場」としての意味合いを強く持つのが特色です。以下は、一般的な真宗大谷派の葬儀の流れです。
<真宗本願寺派の葬儀の流れ>
- 導師入場
導師が斎場に入場する - 開式
開式が宣言される - 三奉請(さんぶしょう)
阿弥陀如来・釈迦如来・十方如来を招く - 導師焼香
導師による焼香が行われる - 表白(びょうびゃく)
仏や参列者に葬儀を行う意義を伝える - 正信偈(しょうしんげ)
親鸞聖人の記した「教行信証」の偈文を読経する - 念仏
短い念仏を唱える - 和讃(わさん)
阿弥陀如来を褒め称える讃歌を唱える - 回向
回向文を唱え、読経の功徳を説く - 導師退場
導師が斎場から退場する - 閉式
閉式が宣言される - 喪主の挨拶
喪主による挨拶と御礼が行われる - 出棺
故人が火葬場に向けて出棺される
火葬・初七日法要
出棺後、火葬の直前には「火屋勤行(ひおくごんぎょう)」という儀式が行われます。これは焼香と読経によって故人と最後のお別れをするための勤行で、これを終えると火葬が始まります。
火葬を終えた後は火葬場や自宅などで「還骨勤行(かんこつごんぎょう)」を行い、遺骨を迎え入れます。初七日法要を繰り上げて行う場合は、還骨勤行に続いて初七日法要を執り行います。初七日法要では、僧侶による読経や法話があげられます。
四十九日法要
仏教では、亡くなった日を1日目として49日目にあたる日を忌明けの区切りの日として重要視します。真宗本願寺派は「往生即身仏」の考え方を持つため、49日を待たずに故人の魂が成仏すると考えますが、阿弥陀如来の導きへの感謝を伝える場として四十九日法要を大切にしています。
法要では僧侶による読経や法話が行われ、遺族や参列者が念仏を唱えて感謝の心を表します。真宗本願寺派の四十九日法要は、生きている人々が仏の教えを聞く機会という意味合いも持ち合わせています。
浄土真宗本願寺派の葬儀に参列するときのマナー
真宗本願寺派の葬儀は他の仏教宗派と異なる儀礼が多いため、参列する前に正しいマナーを把握しておくことが大切です。
焼香の回数は1回
真宗本願寺派の焼香の回数は1回です。焼香をあげる際は、香を額に押し上げる仕草を行わないのがマナーとされています。香を香炉にくべて合掌する際は、「南無阿弥陀仏」と念仏を唱えて阿弥陀如来に感謝を捧げます。
焼香の順番は、喪主を先頭に、遺族・そのほかの参列者と続いていきます。自分の番が回ってきたら、静かに席を立って祭壇の前に移動しましょう。なお、真宗本願寺の焼香回数は2回と宗派によって異なるため、回数を間違えないように注意が必要です。
撚り房の付いた数珠を用いる
真宗本願寺派では、撚り房の付いた数珠を使用します。僧侶は本式数珠を用いますが、参列者は略式数珠でも問題ありません。数珠は108個の主玉と2個の親玉・4個の天珠によって構成されていますが、数を数えるうえで目標となるものはなく、念仏の数が数えられない作りになっているのが特徴です。
合掌する際は右手に通して手を合わせ、房は下に垂らします。合掌をするとき以外の時間は、左手に掛けておきましょう。女性用・子供用の数珠を用いる場合は、二重のままでもかまいません。
香典の表書きは「御仏前」や「御香典」
浄土真宗本願寺派では、「亡くなった方はすでに仏となっている」という教えに基づき、香典の表書きには「御仏前」や「御香典」と記します。仏式で広く用いられる「御霊前」は浄土真宗では使用しない表現のため、注意が必要です。
金額の相場は、故人との関係性や参列者の年齢層によって異なります。故人が両親の場合は3〜10万円、祖父母の場合は1〜5万円程度を包むのが一般的です。お金を入れた香典袋はふくさに包み、受付で手渡しましょう。
香典の包み方や書き方はこのほかにもさまざまなマナーがあります。詳しく知りたい方は、ぜひ以下の記事もチェックしてみてください。
喪服を着用して参列する
真宗本願寺の葬儀に参列する際は、一般的な喪服を着用すれば問題ありません。男性はブラックスーツと黒のネクタイ、女性は黒のワンピースやアンサンブルなどの露出の少ない服装を選びましょう。本願寺派の信徒の方は、「門徒式章(もんとしきしょう)」や「門徒肩衣(もんとかたぎぬ)」を肩に掛けて参列する風習があります。
以下の記事では葬儀に参列する際の服装のマナーを詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
線香は寝かせた形で供える
真宗本願寺派の葬儀で線香をお供えする際は、線香を立てずに横向きに寝かせるのがマナーです。線香を手に取ったら香炉の大きさに合わせて2〜3つに折り分け、火を点けた先端が左側になるように寝かせましょう。
線香を寝かせるのは浄土真宗特有の風習で、古くにお香を常香盤という香炉を用いて焚いていた名残とされています。
念仏の発音の違いに気を付ける
浄土真宗では、勤行や焼香などで「南無阿弥陀仏」の念仏を度々用いますが、宗派によって読み方が異なります。本願寺派では、「なもあみだぶつ」と発音します。なお、大谷派では「なむあみだぶつ」と発音するため、両者を混同しないように注意してください。
冥福を祈るお悔やみの言葉を用いない
真宗本願寺派では、亡くなった方はすでに極楽浄土に成仏していると考えられています。そのため、故人の成仏を願う意味合いのある「御冥福をお祈りします」や「安らかにお眠りください」といった表現は葬儀の場で不適切です。
代わりに「このたびはご愁傷さまです」や「安らかにお浄土へ向かわれたことと存じます」といった言葉が用いられます。弔辞や弔電を送る際も、浄土真宗の考え方に配慮した文言を選びましょう。
浄土真宗本願寺派のお布施の相場
真宗本願寺派の葬儀では、10〜30万円程度のお布施を包むのが一般的です。この金額は、ほかの宗派に比べてやや安いといえるでしょう。また、真宗本願寺派では、法名を授かったことに対する法名料がかかりません。これは、「法名は葬儀のなかで自然に授けられるもの」という考え方に基づいています。
なお、僧侶の送迎を行わなかった場合や僧侶が会食を辞退した場合は、「御車料」や「御膳料」をそれぞれ5千〜1万円程度包むのがマナーです。
| 宗派 | 金額相場 |
|---|---|
| 浄土真宗 | 10〜30万円 |
| 浄土宗 | 15〜50万円 |
| 真言宗 | 30〜70万円 |
| 曹洞宗 | 30〜100万円 |
| 天台宗 | 40〜70万円 |
| 臨済宗 | 30〜50万円 |
| 日蓮宗 | 30〜60万円 |
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、菩提寺などお寺とのお付き合いがない方に、全国一律価格で僧侶を手配いたします。読経、戒名、お車代や心付けなども全て含まれた定額の手配料金ですので、安心してご依頼ください。
また、以下の記事ではお布施について詳細に解説しているので、併せてチェックしてみてください。
浄土真宗本願寺派の葬儀費用の相場
真宗本願寺派の葬儀費用の相場は、ほかの仏式の宗派と大きく変わりません。近年人気を集めている家族葬なら30万〜100万円程度、それよりも簡素な一日葬や直葬の場合は50万円以下で執り行えるケースもあります。多くの参列者を招く一般葬を選んだ場合は、100〜200万円とやや高額な費用がかかります。
| 葬儀形式 | 費用相場 |
|---|---|
| 一般葬 | 100~200万円程度 |
| 家族葬 | 30~100万円程度 |
| 一日葬 | 30~50万円程度 |
| 直葬・火葬式 | 20~50万円程度 |
実際の費用は地域や寺院によっても異なるため、事前に予算を決めておくと良いでしょう。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、不要なものを省き、相場よりも価格を抑えたセットプランでの葬儀を全国一律価格で提供しています。さらに、事前にご相談いただいた方には、特別価格でご案内しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
また、葬儀費用の相場について詳しく知りたい方は以下の記事も併せてお読みください。
本願寺派の葬儀の特徴を知り、マナーを守って参列しましょう
本願寺派の葬儀は、浄土真宗の教えに基づき「故人を仏にする儀式」ではなく、「すでに仏となられた方を偲ぶ場」として行われます。焼香は一回が基本で、数珠の持参や静かな服装など、宗派ならではのマナーもあります。参列前に特徴を知っておくことで、心を込めて見送ることができるでしょう。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。