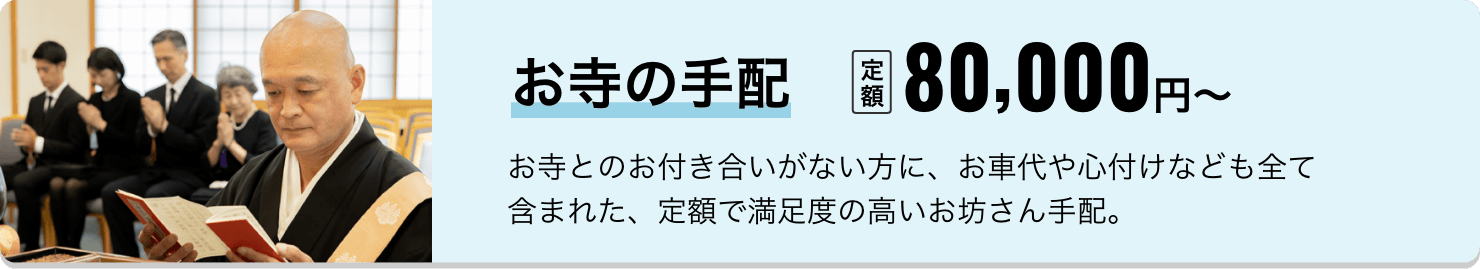浄土真宗の葬儀を検討するなかで「浄土真宗の戒名ってほかの宗派と何が違うの?」「費用はどれくらいかかるの?」といった疑問を抱えている方は多いのではないでしょうか。
実は、浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」と呼ばれ、他宗派とは大きく異なる特徴があります。
本記事では、浄土真宗の法名の基本知識から費用相場・つけ方のルールまで詳しく解説します。浄土真宗の葬儀を予定している方はぜひ参考にしてみてください。
この記事を要約すると
- 浄土真宗では「戒名」ではなく「法名」と呼び、基本的に「釈〇〇」という3文字構成が基本です。
- 基本的な法名「釈〇〇」は無料で授けられますが、実際には3~10万円程度を包むのが一般的です。
- 法名は生前に帰敬式で授かるか、葬儀の際に授けられます。生前に受ける場合の費用は、5,000~1万円程度です。
浄土真宗では亡くなった方に「戒名」ではなく「法名」をつける
法名とは、阿弥陀如来に帰依し、浄土真宗の教えを拠り所として生きる仏弟子の証として授けられる名前です。
他宗派では「戒律を守る」という意味で戒名と呼びますが、浄土真宗では戒律より阿弥陀如来の本願を重視する教えから法名と称します。
法名は基本的に「釈〇〇」という形式で、特別な貢献をした方には院号がついて「〇〇院釈〇〇」となります。前半部分が院号で、後半部分は法名です。
法名には、仏弟子としての名前という意味があります。院号は、宗門や本願寺の護持発展に貢献された方に授与されるものです。
基本的な法名「釈〇〇」は、お布施の金額によって長さや内容が変わることはなく、宗派の教えに基づいて授けられます。葬儀の際には、菩提寺の住職に法名の授与について相談するとよいでしょう。
浄土真宗における戒名の相場
浄土真宗では、法名は基本無料です。とはいえ、実際には3〜10万円程度を包む人も多い傾向があります。
ここでは、浄土真宗の葬儀におけるさまざまなパターンのお布施の相場について紹介します。
- 生前に帰敬式(ききょうしき)で法名を授かる場合
- 葬儀の際に法名を授かる場合
- 院号など特別な称号を希望する場合
- 宗派別の違い
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 生前に帰敬式で法名を授かる場合
浄土真宗では、生前に帰敬式を受けることで法名を授かれます。多くの寺院では、帰敬式の受付料として5,000〜1万円程度を設定しています。
帰敬式とは、阿弥陀如来の教えに帰依する儀式であり、真宗門徒としての自覚を新たにする機会のことです。この式を受けると「釈〇〇」という形の法名が授与され、生前に自分の法名がわかるという精神的な安心感も得られます。
帰敬式で授かった法名は、亡くなった後もそのまま使われるため、葬儀時に新たな戒名料は不要です。浄土真宗の特徴として、他宗派のような戒名の位号(大姉、居士など)による格付がないことも覚えておきましょう。
2. 葬儀の際に法名を授かる場合
浄土真宗の葬儀では、亡くなった方に「法名(ほうみょう)」が授けられますが、法名として特別な料金は発生しません。ただし、実際には3〜10万円程度を包むのが一般的といわれています。
葬儀をあげる際は、事前に菩提寺や葬儀社を通じて僧侶に連絡し、法名の授与を依頼する流れです。
とくに、由緒ある寺院や知名度の高い寺院では、葬儀全体のお布施の値段として30万円以上になるケースもあります。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、菩提寺などお寺とのお付き合いがない方に、全国一律価格で僧侶を手配いたします。戒名だけでなく、読経、お車代や心付けなども全て含まれた定額の手配料金ですので、安心してご依頼ください。
浄土真宗の葬儀におけるお布施については、以下の記事を参考にしてみてください。
3. 院号など特別な称号を希望する場合
浄土真宗では、院号などの特別な称号を希望する場合、通常の法名より高額な費用が必要です。
院号とは「〇〇院」という形で法名の前につける尊称であり、浄土真宗本願寺派では20万円以上、真宗大谷派では8万円以上をお布施の金額とは別に本山に納めます。
院号は本山で料金が定められているため、菩提寺を通じて本山に納める必要があることを留意しておきましょう。なお、浄土真宗の本来の教えでは、阿弥陀仏の救いは平等であり、称号の有無で救済に差はないとされています。
4. 宗派別の違い
浄土真宗の戒名は、他宗派と比較して相場が低い傾向があります。
浄土真宗では「釈〇〇」という形式で、他宗派のような「居士」「大姉」などの位号は付けません。ただし、院号が付く場合は「〇〇院釈〇〇」という形式になります。
浄土真宗本願寺派では、生前の帰敬式での法名授与は1万円程度、葬儀全体のお布施は20万円程度が相場です。
真宗大谷派(東本願寺)も同様の相場ですが、地域や寺院によって若干の差があります。天台宗や真言宗では、位牌に記される階位によって料金が変わり、上位の階位ほど高額になります。
宗派によって戒名の形式や相場が異なるため、菩提寺がある場合は事前に相談しておくとよいでしょう。葬儀社に依頼する場合も、故人の宗派を確認したうえで適切な寺院を紹介してもらうことが大切です。
浄土真宗における戒名のつけ方
浄土真宗の法名は、他宗派と比べてシンプルで「釈〇〇」という3文字構成が基本です。
法名は、経典にある文字や仏教に関する文字のなかから音の響きや意味などで選ばれ、俗名から一字を取る場合もあります。他宗派でよく見られる「居士」「大姉」といった位号は浄土真宗では使用されません。
法名は、亡くなってから授かるものではなく、生前に仏教の教えを受けた際に授かる場合もあります。浄土真宗の法名は、阿弥陀如来の教えのもとに仏弟子として授かる名前であり、お釈迦様の弟子であることを表しています。
宗祖親鸞聖人の教えに基づいており、平等の精神を反映したシンプルな形式になっているのが特徴です。
浄土真宗の戒名に関するよくある質問
浄土真宗の法名について理解を深めるために、以下の5つのよくある質問にお答えします。
- 釈はどういう意味?
- 法名はいつ、どのように授かる?
- 他宗派の戒名との違いは?
- 生前に法名をもらうメリットは?
- 法名にランクってあるの?
それぞれ解説するので、ぜひ参考にしてみてください。
Q. 釈はどういう意味?
「釈」は、浄土真宗の法名の最初につく言葉で、仏教の開祖である釈迦牟尼仏の弟子であることを表しています。
浄土真宗では、亡くなった方は阿弥陀如来の救いによって極楽浄土に往生し、そこで悟りを開いて仏になると考えられています。
ほかの仏教宗派では「院」「居士」「大姉」などの位号が戒名に含まれることが多いですが、浄土真宗では、基本的に「釈〇〇」という3文字の形式です。
このような習わしは、親鸞聖人の教えに基づき、すべての人が平等に救われるという思想を反映しています。
Q. 法名はいつ、どのように授かる?
浄土真宗において、法名は生前に「帰敬式」で授かるのが本来のありかたです。ただし、生前に法名を受けなかった場合は、葬儀の際に授けられます。
浄土真宗の法名は、戒名と異なり戒律を守る誓いではなく、阿弥陀仏の救済を表すものです。浄土真宗の法名は死後の成仏を願うものではなく、生前に仏弟子として生きることの証として授けられるという意味があります。
浄土真宗における葬儀の流れについては、以下の記事を参考にしてみてください。
Q. 他宗派の戒名との違いは?
浄土真宗の戒名は「法名」と呼ばれ、他宗派の戒名とは形式や意味が異なります。浄土真宗では、基本的に「釈〇〇」という形式が一般的です。
このような形式をとるのは、親鸞聖人が仏弟子としての自覚を示すため「釈」の字を名乗ったことに由来しているといわれています。
他宗派では『〇〇院△△▲▲居士・大姉』のように、院号・道号・戒名・位号が含まれる複雑な形式が多い傾向があります。
また、阿弥陀仏の救いは平等であるという浄土真宗の教えを反映し、浄土真宗では「位」による格付けがないのも特徴です。
Q. 生前に法名をもらうメリットは?
浄土真宗では、生前に法名をいただくことで、阿弥陀如来との縁を深めるきっかけになるとされています。
法名は、亡くなってからつける「戒名」とは異なり、生きているうちに仏法の弟子として歩む証となるものです。また、生前に法名をいただいておくことで、葬儀時における遺族の負担を軽減できます。
とくに、急な不幸の際、遺族はさまざまな手続きに追われるため、法名が決まっていればひとつの心配事が減ります。また、日々の生活で自身の法名に触れることで、仏教への理解を深めるきっかけとなるでしょう。
浄土真宗の教えでは、阿弥陀如来の本願を信じる心が大切とされており、法名はその象徴といえます。
Q. 法名にランクってあるの?
浄土真宗では、基本的に法名にランクはありません。法名にランクがない理由は、阿弥陀如来の救いは平等であるという教えに基づいているためです。
基本的な法名「釈〇〇」は、お布施の金額によって長さや内容が変わることはなく、宗派の教えに基づいて授けられます。他宗派のような「居士」「大姉」といった位号による格付けは、浄土真宗では行われません。
ただし、宗門や本願寺の護持発展に特別な貢献をした方には、院号「〇〇院釈〇〇」が授与される場合があります。院号は、階級というより宗門への貢献に対する感謝の表れという意味合いが強いといえるでしょう。
浄土真宗の戒名については菩提寺に相談してみましょう
浄土真宗の法名は、宗派の教えに基づいて無料で授けられますが、基本的には3〜10万円程度を包むのが一般的です。生前に帰敬式を受けることで法名を授かれば、葬儀時の負担を軽減できるメリットがあります。
法名の授与や葬儀の進め方について不明な点がある場合は、葬儀社や菩提寺の住職に相談することが最も確実で安心です。
菩提寺との良好な関係を築きながら、故人にふさわしい供養を行うためにも、早めの相談と準備を心がけましょう。
なお「1日葬・家族葬のこれから」では価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。