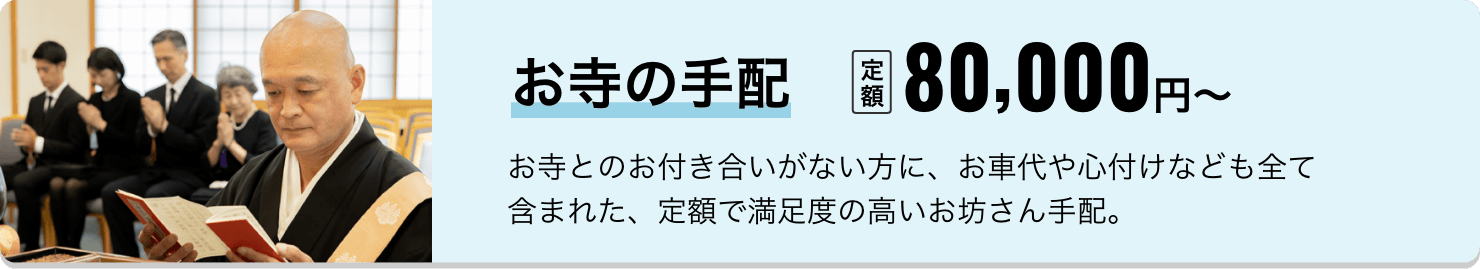日本の葬儀は仏教式が主流であり、故人を弔ううえで僧侶は欠かせない存在です。しかし、菩提寺とのつながりが薄れつつある現代では、僧侶の手配方法が分からないという方もいるでしょう。
また、葬儀での僧侶の呼び方(敬称)やお布施の金額、渡し方などのマナーに不安を感じる方もいるのではないでしょうか。
この記事では、僧侶の役割や手配の方法、お布施の相場などについて分かりやすく解説します。僧侶を呼ばない場合の選択肢についても紹介していますので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を要約すると
- 葬儀において僧侶は、読経による供養や故人の成仏への導きを担い、仏教葬儀に欠かせない存在である。
- 葬儀で僧侶を呼ぶ際は、菩提寺へ早めに連絡し、日程や人数を調整する。お布施の相場やお車代、御膳料も確認が必要。
- 無宗教葬や直葬を選択し僧侶を呼ばない人も増えてきている。この場合、事前に親族などと話し合い、法要や納骨についても準備しておくことが大切。
葬儀における僧侶の必要性と役割
日本で行われる葬儀の多くは仏式であり、僧侶が読経を行い参列者が焼香する形が一般的です。もともとの仏教葬は、修行中に亡くなった僧侶を弔う儀式がもとになっているとされ、故人を仏弟子として送りだす意味を持ちます。
そのため、仏弟子の証として戒名が授けられます。また、僧侶は故人と遺族の橋渡し役も担っており、遺族の思いを故人に伝え、安心して成仏できるように導く存在です。
一方で、葬儀の形式は多様化しており、キリスト教や神道の葬儀、無宗教の形式も増えてきています。
葬儀における僧侶の手配方法
葬儀を執り行う際、僧侶の手配方法は菩提寺の有無によって異なります。菩提寺とは、先祖代々の供養をお願いしているお寺のことで、法要や供養をお願いしている寺院を指します。
しかし、最近では特定のお寺と関係を持たない家庭も増えてきました。ここでは、菩提寺がある場合とない場合の僧侶の手配方法について解説します。
菩提寺がある場合
日頃から付き合いのある菩提寺がある場合は、まず菩提寺に連絡し、通夜や葬儀の依頼をします。連絡する際は、故人の名前や生年月日、亡くなった日時、享年、遺族の連絡先を伝えましょう。
菩提寺の住職が都合により対応できない場合、他の僧侶を紹介されることもあります。また、菩提寺が遠方にある場合でも、事前に連絡を入れることで、近隣のお寺を紹介してもらえる可能性があります。
普段から関係があるお寺に依頼することで、葬儀の流れやお布施についても相談しやすくなります。
菩提寺がない場合
菩提寺がない場合や、遠方にあって依頼が難しい場合は、僧侶の手配方法を考える必要があります。まず、遠方に菩提寺がある場合は、故人が逝去したことを伝え、近隣で関係の深い同じ宗派の寺院を紹介してもらえるか確認してみましょう。
菩提寺がない場合は、葬儀社に僧侶を手配してもらう方法もあります。その際、希望する宗派や戒名の有無などを伝えておくことが大切です。インターネットを利用して僧侶を呼ぶ方法もありますが、運営会社や実績、評判を事前に確認する必要があります。
なお、弊社では、全国一律価格で僧侶を手配いたします。お車代や心付けなどもすべて含まれた定額の手配料金ですので、安心してご依頼ください。
僧侶を手配するタイミング
葬儀を執り行う際、僧侶の手配はできるだけ早めに行う必要があります。葬儀の日程は、遺族の希望だけでなく、僧侶の予定や式場、火葬場の空き状況などを考慮して決定されます。
たとえ式場や火葬場に空きがあっても、僧侶の都合が合わなければ、その日に葬儀を行えません。菩提寺がある場合は、故人が逝去したらすぐに連絡を入れ、葬儀社との打ち合わせの際に日程を調整しましょう。
菩提寺がない場合や僧侶を別途手配する場合も、早めに依頼し、希望の日程で対応してもらえるか確認することが大切です。
葬儀に呼ぶ僧侶の人数
葬儀に招く僧侶の人数は、1人が一般的です。ただし、僧侶の人数に明確な決まりはなく、宗派や葬儀の形式によって異なります。
たとえば、曹洞宗では3人、浄土真宗では3人以上が基本とされる場合があり、補助の僧侶や雅楽を演奏する僧侶を含めると、7人ほどになることもあります。
また、葬儀の規模や内容によっても呼ぶ僧侶の人数は変わります。大規模な葬儀では複数の僧侶が役割を分担することがあり、故人が生前に関係を持っていた複数の寺院の僧侶が参列するケースも珍しくありません。
僧侶の人数によって必要なお布施の金額も変わるため、事前に確認しておくと安心です。
葬儀で僧侶を呼ぶ際の敬称について
葬儀に僧侶を招いた際、実際に目の前にするとなんと呼べばよいのか困ってしまうものです。僧侶を呼ぶ際の敬称には「お坊さん」「住職」「和尚」などがあります。
お坊さんは僧侶全般を指し、一般的な表現ですが、直接呼びかける際には、ややカジュアルな印象となります。住職はお寺の代表者を表す役職名であり、全ての僧侶に使えるわけではありません。
和尚は、宗派によって読み方が異なり、使わない宗派もあるため注意が必要です。失礼のない言い方としては「〇〇寺様」や、「僧侶様」本名が分かる場合は「名字+様」などが適切です。葬儀の場では、敬意をこめた呼び方を心掛けることが大切です。
葬儀で僧侶に渡すお布施の相場
葬儀に僧侶を呼んだ場合、お布施を用意する必要があります。お布施は読経をしていただいたことへの謝礼として渡すもので、決まった金額はないものの、地域や宗派、葬儀の規模によって相場があります。
また、戒名を授かる際には「戒名料」僧侶が移動する際の「お車代」通夜や葬儀後の食事にかかる「御膳料」など、別途必要です。ここでは、それぞれのお布施の相場について解説します。
戒名代の相場
戒名を授かる際には「戒名授与の費用」としてお布施を納めます。相場は30〜50万円程度です。また、戒名の位によっても異なり、詳細は、以下の通りです。
- 信士・信女:10~50万円
- 居士・大姉:50~80万円
- 院信士・院信女:50~100万円
- 院居士・院大姉:100万円以上
もともと戒名は、故人の信仰や功績に応じて授けられるものでしたが、近年では戒名の位にこだわらず、比較的費用を抑えられる「信士・信女」を選ぶ人も増えています。
また、寺院によっては戒名料が不要な場合や、定額制を導入しているところもあるため、事前に確認しておくことが大切です。
お車代・御膳料の相場
お布施とは別に、僧侶へ渡す費用として「お車代」と「御膳料」があります。お車代の相場は5,000円〜1万円で、僧侶の移動にかかる費用として渡します。ただし、お迎えの車を手配した場合は不要です。
御膳料の相場も同じく、5,000円〜1万円で、僧侶が会食を辞退した際に食事代としてお渡しします。どちらもお布施とは別の封筒に包み、まとめて渡すのが一般的です。
また、地域によっては葬儀に関わる方に心づけを用意することがあります。霊柩車やマイクロバスの運転手、式場の係員などへの心づけの相場は3,000円〜5,000円程度です。
葬儀に僧侶を呼んだ際のマナー
葬儀に僧侶を呼んだ場合、失礼のないように対応することが大切です。僧侶への挨拶の仕方やお布施を渡すタイミング、封筒の準備など、適切なマナーを知っておくと安心です。
特に、お布施の渡し方には一定のルールがあり、渡し方を誤ると失礼に当たることもあります。ここでは、僧侶への挨拶のポイントやお布施の渡し方について解説します。
僧侶への挨拶について
- 枕経を依頼する場合
お世話になっております。〇〇が先ほどなくなりました。自宅に戻りましたので枕経をお願いできますでしょうか。 - 僧侶が到着した際
お忙しい中、お越しいただきありがとうございます。〇〇も安心することと思います。不慣れな点もございますので、ご指導のほどよろしくお願いいたします。 - 通夜、葬儀の際
本日はお越しいただきありがとうございます。定刻に始めますのでよろしくお願いいたします。 - お布施を渡す際
この度は丁寧なおつとめを賜り、誠にありがとうございました。ささやかではございますが、お納めください。
僧侶へのお布施の渡し方
お布施を渡すタイミングは、葬儀や法要の開始前、または施主が僧侶に挨拶をする際が一般的です。葬儀当日は慌ただしく、渡しそびれることもあるため、その場合は式の終了後に手渡しても問題ありません。もし当日が難しい場合は、前日や後日に時間を設けて渡すこともできます。
お布施の渡し方は、切手盆や袱紗(ふくさ)にのせ、表書きを僧侶の正面に向けて差し出すのが正式なマナーです。
渡す際は「本日はお忙しい中、ありがとうございます。ささやかですがお納めください」と感謝の言葉を添えると丁寧です。
封筒は白無地のものや奉書紙を用いて、表書きには「お布施」と記入します。水引は不要ですが、地域によって異なる場合があるため、事前に確認しておきましょう。
葬儀で僧侶を手配する際に注意すべきこと
葬儀で僧侶を依頼する際は、宗派の違いや菩提寺との関係に注意が必要です。手配の仕方によっては、後々の法要や納骨に影響が出ることもあります。
ここでは、菩提寺以外の僧侶に依頼する際の注意点などについて解説します。
菩提寺以外の僧侶に依頼すると納骨を断られる可能性がある
菩提寺があるのにもかかわらず、別の僧侶に依頼すると、お寺の境内にある先祖代々の墓に納骨を断られることがあります。
菩提寺は、檀家との関係を重視しており、他の僧侶による葬儀が行われた場合「うちの宗派とは異なる形式での供養が行われた」と判断され、納骨を拒否されることがあるためです。
このようなトラブルを避けるためには、葬儀前に菩提寺へ相談し、別の僧侶に依頼することが可能か確認しておくことが重要です。事前に許可を得られれば問題なく納骨できる場合もあるため、慎重に対応しましょう。
菩提寺で行う法要に外部の僧侶は呼べない
菩提寺で法要を行う場合、外部の僧侶を招くことは基本的にできません。
理由は、外部の僧侶を呼ぶことは「自分の寺の僧侶では不十分」という意味に捉えられ、失礼にあたるためです。菩提寺は檀家の供養を担う立場にあります。
また、宗派ごとに儀式の形式が異なるため、菩提寺の方針と異なる僧侶を招くと、宗教的な問題が生じる可能性もあります。法要を菩提寺で行う場合は、そのお寺の僧侶にお願いするのが基本です。
葬儀に僧侶を呼ぶかどうかは自由に選べる
葬儀で読経や引導を渡すための僧侶ですが、あくまでも仏教に基づいた供養の形であり、キリスト教や神道、無宗教の形式で葬儀を行う場合は、僧侶を呼ぶ必要はありません。
近年では、仏教の形式にこだわらず、家族葬や自由葬を選ぶ人も増えています。僧侶による読経の代わりに、故人の好きだった音楽を流したり家族が言葉をかけたりと、遺族や故人の意向に沿った形で送り出すケースも珍しくありません。
僧侶を呼ばない場合の代替案
前述の通り、宗教的な儀式にこだわらず、故人や遺族の意向を重視した形で送りだす方法を選ぶ人も増えてきています。また、供養や納骨の仕方も、従来の寺院墓地にとらわれず、さまざまな選択肢があります。
ここでは、僧侶を呼ばない場合の葬儀の形や供養の方法について解説します。
無宗教葬を行う
僧侶を呼ばずに葬儀を行う方法の一つに、無宗教葬や自由葬があります。
これは宗教儀式にとらわれず、故人や遺族の希望に沿った形で執り行う葬儀のスタイルです。無宗教葬は、読経や焼香などの仏教儀式を行わず、自由な形式で故人を偲ぶのが特徴です。
たとえば、故人の好きだった音楽を流したり家族や友人がスピーチしたりするなど、多様な形式が選ばれています。ホテルや自宅で行われることもあり、会食を中心にした温かみのある式も増えています。
無宗教葬とはいえ、僧侶を招いて読経をお願いするケースもありますが、基本的には宗教的な要素を取り入れないことが一般的です。
家族葬や直葬での供養する
家族葬は、親族や親しい友人のみで行う小規模な葬儀です。
一般的な葬儀と同じように通夜・告別式を行うものの、参列者の範囲を限定する特徴があります。一般葬と比べて静かに故人と向き合えるため、ゆっくりとお別れできることが魅力です。
直葬は、通夜や告別式を行わずに火葬のみを執り行う葬儀形式です。遺体を一定時間安置した後、火葬場へ移送し、火葬を執り行います。読経を希望する場合は、火葬前に行うこともありますが、基本的には宗教儀式を行いません。
納骨は公営墓地や民間墓地を選ぶ
僧侶を呼ばずに葬儀を行った場合、檀家としての葬儀を行っていない、戒名がないといった理由で菩提寺への納骨を拒否される可能性があります。そのような場合でも納骨の選択肢は複数あります。
公営墓地は、宗教を問わず利用できるため、新しくお墓を立てる場合に適しています。また、民間霊園の中にも「宗旨宗派不問」としているところが多く、特定の宗派に属さなくても申し込めます。
お墓を建てたくない場合は、永代供養墓や納骨堂を選ぶ選択肢もあります。寺院や霊園が管理し、後継者がいなくても供養されるため安心です。それぞれ管理費や供養料がかかるため、事前に確認しておきましょう。
僧侶を葬儀に呼ばない場合の注意点
僧侶は必ずしも葬儀に必要な存在ではないものの、呼ばない場合には事前に理解しておくべき注意点があります。十分に理解しないまま葬儀を執り行うと、後にトラブルへと発展する可能性があります。
ここでは、僧侶を呼ばずに葬儀を行う際に注意すべきポイントについて解説します。
事前に家族や親族と十分に話し合う
僧侶を呼ばない葬儀を行う場合、家族や親族に事前に説明し、理解を得ることが大切です。多くの人は「葬儀=僧侶の読経があるもの」と考えているため、知らせずに進めると驚かれたり、反対されたりする可能性があります。
特に、仏教を信仰しており伝統を重んじる親族の中には、無宗教葬や直葬に抵抗を感じる人もいるため、事前に方針を伝えて納得してもらうようにしましょう。
話し合いの際には、故人や遺族の考えを丁寧に説明し、理解を得ることが重要です。
納骨や法要をどうするか決めておく
僧侶を呼ばない場合、納骨や法要をどのように行うか事前に決めておきましょう。通常、仏式の葬儀では、菩提寺で戒名を授かり、四十九日法要を経て納骨する流れが一般的です。
しかし、僧侶を呼ばず戒名などを授かっていない場合、菩提寺への納骨はできないため、公営墓地や民間霊園、納骨堂の利用が一般的です。また、樹木葬や海洋散骨、手元供養などの選択肢もあります。
無宗教の葬儀では四十九日などの法要もないため、故人を偲ぶ方法を家族で話し合い、供養の形を決めておくようにしましょう。
僧侶の役割やお布施の相場を理解して納得のいく葬儀を行おう
僧侶は、葬儀において読経や戒名の授与を行い、故人を成仏へ導く役割を担っています。仏教式の葬儀が主流の日本では、菩提寺の僧侶に依頼するのが一般的です。しかし最近では、葬儀社や僧侶派遣サービスを利用して手配するケースも増えています。
僧侶を手配する場合、お布施の相場や渡し方、納骨の手順などを事前に確認し、適切に対応することが大切です。また、当日は僧侶に対して失礼のないよう、挨拶やお布施の渡し方などのマナーにも気を配るようにしましょう。
一方で、近年は宗教にとらわれない葬儀も増えており、必ずしも僧侶を呼ぶ必要はありません。無宗教葬や家族葬、直葬を選ぶ場合は、納骨や供養の方法を家族で話し合い、親族にも理解を得たうえで進めることが重要です。事前に話し合い、納得のいく形で故人を送り出しましょう。
なお、弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。
また、菩提寺などお寺とのお付き合いがない方に、全国一律価格で僧侶を手配いたします。お車代や心付けなども全て含まれた定額の手配料金ですので、安心してご依頼ください。
依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。