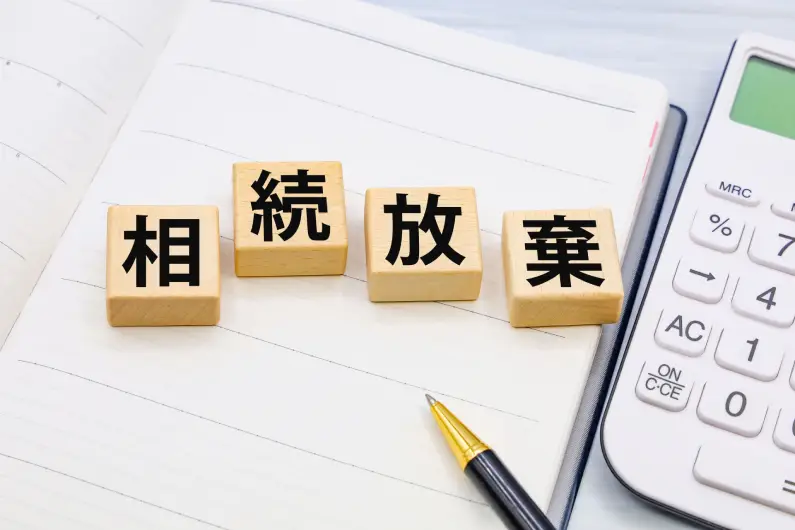「葬儀代を立て替えると相続放棄できなくなるのでは?」「どこまでなら立て替えても大丈夫?」。身内が亡くなり、借金などの事情で相続放棄を検討するなかで、このような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
実は、社会通念上妥当な範囲の葬儀代であれば、立て替えても相続放棄は可能です。
本記事では、葬儀代の立て替えが相続放棄に与える影響や注意すべきポイントまで詳しく解説します。相続放棄を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を要約すると
- 相続放棄とは亡くなった人の財産や借金を一切受け継がないと家庭裁判所に申述する手続きで、借金が多い場合に相続人の生活を守る重要な選択肢です。手続きは相続開始を知ってから原則3か月以内に行う必要があります。
- 社会通念上妥当な範囲の葬儀代であれば立て替えても相続放棄は可能です。ただし、故人の遺産から入院費を支払ったり、過度に盛大な葬儀を行ったり、遺産の一部を使用・売却すると相続承認とみなされ放棄できなくなります。
- 葬儀費用を立て替える際は事前に親族間で負担割合を決め、領収書や明細書をすべて保管し、家庭裁判所への回答書は正確に記入することが重要です。
相続放棄とは?
相続放棄とは、亡くなった人の財産や借金など一切を受け継がないと家庭裁判所に申述する手続きのことです。
通常の相続は、プラスの財産とマイナスの財産を合わせて引き継ぎます。しかし、借金のほうが多いと予想される場合は、放棄したほうが有利です。
相続を放棄をすれば、最初から相続人でなかったことになるため、借金の返済義務を免れます。相続放棄は、相続人の生活を守るための大切な選択肢です。
ただし、手続きは自己のために相続の開始を知ってから原則3か月以内に行う必要があります。もし、手続きを過ぎてしまうと放棄できなくなり、知らないうちに借金を相続してしまう恐れがある点に留意しましょう。
葬儀代を立替しても相続放棄は可能?
葬儀代を立て替える行為は「相続財産を受け継ぐこと」には当たらないため、葬儀代を立て替えても相続放棄は可能です。
ただし、相続財産を自由に処分してしまうと「相続を承認した」とみなされ、相続放棄が認められない恐れがあります。葬儀費用の立替は認められる一方で、それ以外の財産の管理や処分は慎重に対応しなくてはいけない点に注意しましょう。
葬儀費用の控除とは?
葬儀代として立て替えた費用の一部は、相続税の計算上、控除対象として扱われます。つまり、遺族が実際に負担した葬儀費の一部が、税負担軽減につながるということです。
具体的には、葬儀社への支払いや火葬費用・通夜や告別式にかかる費用などが控除対象とされます。
一方で、香典返しや法要の費用などは対象外です。葬儀費用は債務ではないものの、相続税を計算するときは遺産総額から差し引けることを留意しておきましょう。
相続放棄ができなくなるパターン
ここでは、相続放棄ができなくなってしまう主なパターンについて詳しく紹介します。
- 故人の遺産から入院費を支払う
- 熟慮期間の3ヵ月を超えた
- 遺産の一部を使用・売却した
- 過度に盛大な葬儀を執り行った
次の4つのケースについて、それぞれ詳しく見ていきましょう。
故人の遺産から入院費を支払った
相続放棄を検討している状況で故人の遺産から入院費を支払うことは、原則として単純承認とみなされ相続放棄が認められなくなるリスクがあります。
入院費や治療費は、故人である被相続人本人が負担すべき債務であり、相続財産に含まれる負債として扱われます。
そのため、相続放棄が成立すれば相続財産を引き継がないため、相続人は原則として入院費の支払い義務を負わないケースがほとんどです。
しかし、相続人が相続を承認する意思がなかったとしても、遺産から入院費を支払ったという事実により相続を受け入れたものと法的にみなされる恐れがあります。
病院から入院費の請求があったとしても、相続放棄を予定している場合は遺産からの支払いは控えることが大切です。
熟慮期間の3ヵ月を超えた
相続放棄には期限があり、自己のために相続の開始を知った日から原則3ヵ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。この3ヵ月は「熟慮期間」と呼ばれ、遺産や借金の全体像を確認し、相続するか放棄するかを判断するための猶予期間です。
もし、この期間を過ぎてしまうと自動的に相続を承認したものとみなされ、放棄が認められなくなる恐れがあることを留意しておきましょう。ただし、状況によっては家庭裁判所に申し立てることで期間の延長を認めてもらえるケースもあります。借金が多い場合など相続放棄を検討している人は、3ヵ月の期限を意識し早めに行動しましょう。
遺産の一部を使用・売却した
相続放棄を検討している場合でも、故人の遺産を自分のために使用したり売却したりすると、その時点で「相続を承認した」とみなされ、相続を放棄できなくなります。
たとえば、故人の預金を引き出して生活費に充てたり、持ち物を換金してしまうと、相続の意思を示したと判断されます。相続放棄を考えるなら、遺産には原則手をつけず、必要最小限の管理の範囲にとどめることが大切です。
社会通念上相当な範囲での葬儀費用の支払いは処分行為とされませんが、それ以外の相続財産の使用や処分は取り返しがつかなくなる恐れがあります。判断に迷うときは、早めに専門家に相談しましょう。
過度に盛大な葬儀を執り行った
あまりに盛大で高額な葬儀を行うと、葬儀代を相続財産から支払った場合に相続放棄できなくなる恐れがあります。社会的に一般的とされる範囲を大きく超える支出は、遺産を自由に処分したとみなされ「相続を承認した」と判断されかねません。
たとえば、大勢の参列者を想定した豪華な葬儀や高額な付随サービスを利用することは、相続放棄に不利になる恐れがあります。
明確な金額基準はありませんが、社会通念上相当な範囲の葬儀費用であれば問題ないとされています。100万円以内の葬儀代であるなら、基本的に問題ないでしょう。
相続放棄を確実にしたいなら、葬儀は必要最小限の範囲にとどめ、余分な費用をかけないことが大切です。
葬儀費用に該当する費用と該当しない費用
葬儀にかかった費用のすべてが、葬儀費用に該当するとは限りません。国税庁のページには、以下のように説明されています。
| 葬式費用となる費用 | ・葬式や葬送に際し、またはこれらの前において、火葬や埋葬、納骨をするためにかかった費用 ・遺体や遺骨の回送にかかった費用 ・葬式の前後に生じた費用で通常葬式にかかせない費用 ・葬式に当たりお寺などに対して読経料などのお礼をした費用 ・死体の捜索または死体や遺骨の運搬にかかった費用 |
| 葬式費用に含まれない費用 | ・香典返しのためにかかった費用 ・墓石や墓地の買入れのためにかかった費用や墓地を借りるためにかかった費用 ・初七日や法事などのためにかかった費用 |
参考:No.4129 相続財産から控除できる葬式費用|国税庁
葬儀費用に当てはまらないと相続税の債務控除に入れられないため、該当する費用と該当しない費用は正確に把握しておきましょう。
相続放棄しつつ葬儀費用を立て替える場合の注意点
ここでは、相続放棄を行いながら葬儀費用を立て替える際に押さえるべき重要なポイントについて詳しく紹介します。
- 事前に負担割合を決めておく
- 領収書や明細書はすべて保管しておく
- 相続放棄における回答書は正確に記入する
葬儀費用の建て替えを検討している方は、ぜひ参考にしてみてください。
事前に負担割合を決めておく
相続放棄しつつ葬儀費用を立て替える場合、親族の間で事前に費用負担の割合や返済方法をしっかり話し合っておきましょう。葬儀社との契約者が誰かによって、支払い責任や後の費用回収が変わるため、トラブル防止のためにも具体的な分担や取り決めを明確にしておくことが大切です。
親族間の負担割合が曖昧なまま進めると、のちの返金や相続手続きなどで予期せぬ揉めごとにつながりかねません。葬儀前に全員で合意を取っておくことが大切です。
領収書や明細書はすべて保管しておく
相続放棄しつつ葬儀費用を立て替える場合、領収書や明細書はすべて保管しておきましょう。葬儀費用がどの範囲の支出か証明することで、立替分の請求や精算のトラブルを防げます。
また、領収書や明細書は相続財産を仮払い制度や裁判所の手続きで充てる場合も必要な書類です。支払い額や内訳があいまいなままでは、親族間で勘違いや意見の食い違いによる揉めごとを招きかねません。
支払いから時間が経っても領収書一式が揃っていれば、証拠として示せるので、保管場所を決めて紛失しないよう管理しましょう。
相続放棄における回答書は正確に記入する
相続放棄に関する回答書は、家庭裁判所が申立人の意思や状況を審査する重要な書類です。事実と異なる記載や曖昧な表現は避けて、正確に記入しましょう。
被相続人との関係や相続放棄の理由・遺産の処分状況など、質問の趣旨をよく読み、提出書類の内容とも整合性を保つことが求められます。不明な点は正直に「わからない」と明記することも許されています。
また、期限までに提出することや、印鑑など記載事項の漏れがないようにすることが重要です。誤った記載や虚偽の回答は、相続放棄そのものが無効になるリスクにつながるので、慎重に記入しましょう。
故人の預金口座から葬儀費用を引き出す方法
相続放棄を考えている場合は、個人の預金を引き出すことはできるかぎり避けてください。単純承認とみなされ、相続放棄できなくなる恐れがあるためです。
ここでは、相続放棄を希望しない人が故人の資産から預金を引き出す場合の手続きについて詳しく紹介します。
- 口座凍結前に引き出す
- 預貯金の仮払い制度を利用する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
口座凍結前に引き出す
故人の預金口座から葬儀費用を引き出したい場合、銀行が口座名義人の死亡を知る前であれば、通常どおり預金を引き出せます。金融機関に故人が死亡したことが伝わると口座を即座に凍結するため、事前に引き出しておくと、さまざまな支払いをスムーズに進められるでしょう。
なお、口座名義人(今回は故人)以外が預金を引き出すことは、厳密にいうと正当な手続きとはいえません。とはいえ、故人の身内が葬儀費用や未払い医療費の支払いに使うお金を引き出すことが引き金となって、銀行とトラブルに発展することは考えにくいのも事実です。
それより警戒すべきことは、相続人間のトラブルです。故人の預金をどのように使ったのかを明確にするため、領収書等は必ず残しておくようにしてください。
預貯金の仮払い制度を利用する
故人名義の預貯金口座が死亡によって凍結された場合でも「預貯金の仮払い制度」を利用すれば、相続人は遺産分割協議前に一定額まで単独で払い戻しを受けられます。
「預貯金の仮払い制度」とは、金融機関に申請することで最大150万円まで仮払いを受けられる制度です。葬儀費用など緊急かつ必要な支払いに対応するために設けられています。
具体的な計算式は、以下のとおりです。
引き出せる金額 = 相続開始時の預金残高 × 1/3 × 法定相続分
(参考:遺産分割前の相続預金の払戻し制度|一般社団法人全国銀行協会)
ただし、必要書類の準備や時間がかかる場合もあるため、葬儀費用の支払い時期と合わせて計画的に対応する必要があります。手続きの際は、戸籍謄本や印鑑証明など必要書類を揃えて申請しましょう。
葬儀費用は相続放棄しても立て替えられます
相続を放棄する意思があっても、葬儀費用の立て替え自体は問題なく認められています。
たとえば、喪主や遺族がいったん自分の資金で葬儀費用を支払い、あとからほかの相続人と協議して遺産から精算するという方法が一般的です。
葬儀費用は故人への弔いのため社会的に必要な支出とされ、相続財産の単純承認とはみなされません。そのため、葬儀費用を立て替えても相続放棄は可能です。
ただし、過度に高額な葬儀や本来の範囲を超える出費は相続財産の処分とみなされる場合があるため注意しましょう。
立て替えた分を遺産から精算するには領収書や明細を保管し、相続人間で事前に負担割合を決めておくことをおすすめします。
なお「1日葬・家族葬のこれから」では価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。