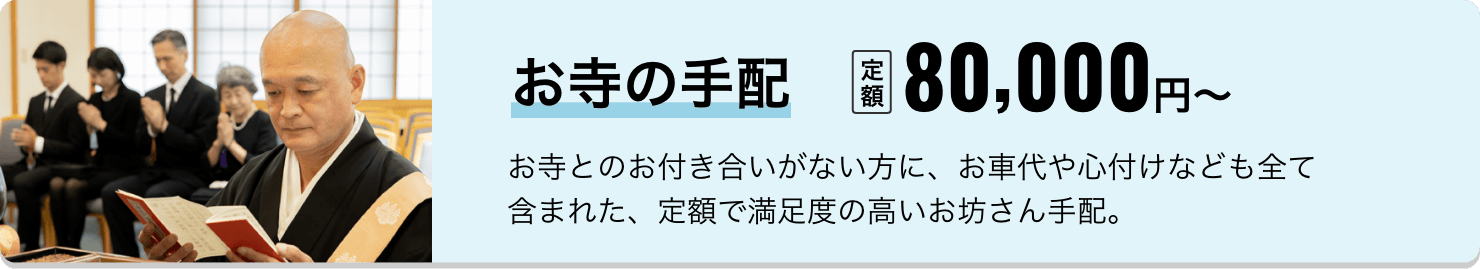親や周囲の大人にとって、子どもの死に立ち会うことは辛いことです。とりわけ生後間もない赤ちゃんや、出生前の胎児が亡くなるのは非常に痛ましく、悲しみに暮れ何も手につかないことでしょう。
そんな折、葬儀をあげて赤ちゃんを送り出すことは、赤ちゃん自身のご供養とともに、親御さんや周囲の人間の気持ちの整理につながる可能性があります。
本記事では、赤ちゃんのお葬式マナーや、火葬のルール、お葬式をあげる場合の流れについて解説します。記事の後半では、赤ちゃん連れで葬儀に参列する際のマナーについても紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事を要約すると
- 赤ちゃんのお葬式は、あげてもあげなくても問題ありません。なるべくご家族の納得いく形で供養するのが大切です。火葬については、明確なルールが法律で定められているため注意が必要です。
- 赤ちゃんのお葬式をあげる場合、まずは葬儀社を決め、僧侶との打合せや役所への手続きを済ませます。遺骨を遺したい場合は、葬儀社や火葬場への相談が必要です。
- 一方、赤ちゃん連れで葬儀に参列する場合、亡くなった方が赤ちゃんの身内であれば問題ないことが多いですが、他人の場合は控えるのがマナーです。赤ちゃんの参列時には、ぐずったときの対策を事前に取っておくよう配慮しましょう。
赤ちゃんのお葬式はあげるべき?
赤ちゃんの火葬については明確なルールが法律で定められていますが、葬儀については決まりはありません。それぞれの心情や家庭の事情に合わせて葬儀をあげたり、火葬のみを行ったりします。
一般的な傾向としては、生まれる直前に死産した場合や、出生後の赤ちゃんについては、葬儀をあげる人が多くみられます。早めの妊娠週数で死産してしまった場合には、火葬のみを行う傾向があるようです。
なお、妊娠12週以降の胎児、および出生後の赤ちゃんが死亡した場合は、法律により火葬が義務付けられています。妊娠24週以降の場合はさらに、24時間ご遺体を安置した後に火葬しなければなりません。
火葬に加え葬儀をあげれば、赤ちゃんのご供養につながります。遺された家族の心の整理にも役立つ可能性があるため、必要に応じて葬儀を検討しましょう。
赤ちゃんが亡くなった場合の流れ
赤ちゃんが亡くなった場合に必要となる手配や手続きなどの流れは、以下のとおりです。
- 葬儀社を手配する
- 僧侶を手配する
- 死産届・死亡届(死亡診断書)を提出し、火葬許可証を受け取る
- 葬儀・火葬・収骨を行う
- 公的手当・金融機関・保険会社などの手続きを行う
- 幼稚園などの除籍届・費用の精算を行う
それぞれ解説していきます。
葬儀社を手配する
火葬に加え赤ちゃんのお葬式を希望する場合は、葬儀社を手配します。
赤ちゃん向けの葬儀プランに対応している葬儀社では、赤ちゃん用の小さな棺や骨壺などを用意しています。赤ちゃんのお骨を遺したい場合、赤ちゃん向けの火葬に対応している火葬場を探すか、火力の弱い朝一での火葬が必要なため、葬儀社へ相談しましょう。
葬儀をあげず、火葬のみを行う場合は、個人的に火葬場へ連絡することでも手配可能です。しかし葬儀社に依頼すれば、スタッフに対応を任せることで心身の負担を抑えられるメリットがあります。必要に応じて利用を検討するとよいでしょう。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、火葬のみも直葬プランも承っております。必要なもののみに厳選したセットプラン価格で、役所の手続きの代行なども含んでおりますので、安心してご利用いただけます。
葬儀社選びのコツについては、以下の記事を参考にしてください。
僧侶を手配する
僧侶が立ち会う一般的な葬儀を希望する場合は、菩提寺に連絡を入れて僧侶を手配します。葬儀の会場やスケジュールとともに読経を依頼し、戒名や位牌の有無などの希望を先方に伝えておきましょう。
この世の穢れを知らずに亡くなった赤ちゃんの場合、本来は戒名がなくても極楽浄土へと旅立てるとされます。位牌についても同様で、必ずしも作る必要はありません。ご供養として依頼するかどうか慎重に検討してください。
菩提寺がない方が僧侶を招きたい場合は、葬儀社で手配してもらえることがあるため相談しましょう。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、全国一律価格でお坊さんのご手配をしております。読経代に加え、戒名代や御車代も含まれた定額のお布施となっておりますので、ご安心してお任せください。
仏式でない葬儀を希望する場合も同様に、宗教者に連絡を入れて葬儀内容を調整します。宗教儀式を省いたお別れ会などの葬儀形式の場合、宗教者の手配は不要です。
死産届・死亡届(死亡診断書)を提出し、火葬許可証を受け取る
妊娠12週以降の胎児、もしくは出生後の赤ちゃんが亡くなった場合は、死亡から7日以内に役所へ死産届・死亡届を提出する必要があります。この用紙の右半分は死産証書(死胎検案書)もしくは死亡診断書(死体検案書)になっており、医師が記入する決まりです。
死産届・死亡届は、いったん提出すると返却や再発行はできないため、必要に応じてコピーを取っておいてください。
死産届・死亡届の提出時、同時に火葬許可申請書を提出することで火葬許可証を発行してもらえます。この時点で火葬場を予約しておかなければなりません。火葬許可証がないと火葬ができないため注意が必要です。
なお誕生後に死亡した赤ちゃんの場合、死亡届に加え出生届を提出します。死亡届の手続きは葬儀社で代行してもらえることがあるので、希望する場合は相談してみましょう。
葬儀・火葬・収骨を行う
希望に応じて葬儀をあげたのち、火葬や収骨を行います。赤ちゃんの場合骨が柔らかいため、遺骨が残らず収骨ができないこともあります。
収骨が可能なケースであっても、絵本やおもちゃ、ぬいぐるみなどの副葬品を棺に入れると、ご遺骨をきれいに残しにくいとされるため注意が必要です。ご遺骨が残らなかった場合、遺灰を持ち帰れる火葬場もあります。
気持ちの整理がつくまで埋葬せず、手元に遺骨や遺灰を置いて供養しても問題ありません。ただし、墓地以外の場所へ遺骨を埋葬することは法律で禁じられているため、自宅の敷地内に埋葬することのないよう注意しましょう。
公的手当・金融機関・保険会社などの手続きを行う
児童手当や児童扶養手当などの公的な手当金を受け取っていた場合には、管轄の自治体で受給停止の手続きが必要です。
また、赤ちゃん名義の銀行口座をもっていたときは、対象の金融機関で解約手続きを行います。赤ちゃんの死亡保険に加入していた場合は、保険会社に申請しましょう。
保育園などの除籍届・費用の精算を行う
亡くなった赤ちゃんが保育園や幼稚園に通っていた場合には、除籍の手続きを行います。未払いの費用があったら精算し、私物を引き取りましょう。
死産した赤ちゃんの火葬について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
お葬式に赤ちゃんは連れて行かない方がいい?
ここまで赤ちゃんのお葬式について解説してきました。ここからは、一般的な葬儀の際に赤ちゃんを連れて行くべきかどうかについて、以下のケースに分けて解説します。
- 親族・身内の葬儀の場合
- 友人・知人の場合
具体的な内容は次のとおりです。
親族・身内の葬儀の場合
赤ちゃんの身内や親族などごく親しい方が亡くなった場合、一般的には赤ちゃん連れで葬儀に参列しても問題ないとされます。
赤ちゃんの参列をよしとするか否かは、家族や地域の風習、葬儀の規模によっても異なるため、念のため事前に遺族に確認しておくと安心です。赤ちゃん連れで参列する場合、赤ちゃんが泣き出したときに退席しやすい席に座ったり、焼香の順番まで控室で待機したりといった配慮はしておきましょう。
ただし、長時間の移動や外出は、少なからず赤ちゃんの負担になります。特に生後1ヶ月くらいまでの場合、母子ともに大きな負担となるため参列を見合わせましょう。長い待機が必要な火葬についても、参列しないほうが無難といえるでしょう。
友人・知人の場合
赤ちゃんの遠縁や、保護者の友人・知人など、身内以外の葬儀の場合には、基本的には赤ちゃん連れの参列は控えましょう。
故人とのご縁が特に深かった場合は喪主に確認してみてもよいですが、他の親族や参列者の理解を得られずひんしゅくを買う恐れがあります。
なお、赤ちゃん本人の友だちが亡くなった場合も、葬儀に連れて行かないのがマナーです。相手の親御さんの気持ちをくみ、慎重に行動しましょう。
赤ちゃんが葬儀に参列する際の服装
葬儀に参列する際の赤ちゃんの服装は、モノトーンのシンプルなコーデを選びましょう。赤ちゃんが快適に過ごせるよう通気性のある素材の服や、おむつ替えしやすい服がおすすめです。靴下は履かせておいてください。
赤ちゃんには大人ほど厳密な服装ルールはありませんが、派手な色や大きな柄物、華美なレースやフリル、キャラクター物の服は避けるのがマナーです。
幼稚園児が葬儀に参列する場合、正式な礼服扱いとなる制服を着用するのが無難です。明るめのカラーの制服でも問題ありませんが、派手なネクタイやリボンがある場合には外しておくとよいでしょう。
赤ちゃんを葬儀に連れて行く際に気をつけるべきポイント
赤ちゃんを葬儀に連れて行く際には、以下の点に注意が必要です。
- 赤ちゃんがぐずったときの対策を考えておく
- ご焼香の間は誰かに見ていてもらう
- おむつや着替えなどの持ち物に配慮する
- 授乳期の場合は授乳しやすい喪服を選ぶ
- 参列する赤ちゃんの香典はいらない
具体的に解説していきます。
赤ちゃんがぐずったときの対策を考えておく
赤ちゃん連れで葬儀に参列する場合には、赤ちゃんがぐずったときの対策を事前に考えておくのが大切です。
赤ちゃんは不快になるとぐずりやすいため、眠気や空腹、おもらしなどに対する対策を行います。赤ちゃんの気を紛らわせる、音の出ないお気に入りのおもちゃや絵本、ぬいぐるみなどを持参するのもおすすめです。
赤ちゃんが泣きだしそうな場合や、吐き戻し、おもらしなどがあった際には、軽く会釈してからすみやかに会場から退席します。目立たず退席しやすい最後尾の席や、出入り口付近の席に着席しておくとスムーズです。ベビーカーで来た場合は、式典中は邪魔にならない場所に折りたたんで置いておきます。
葬儀中ずっと参列している必要はありません。控室で待機しておき、ご焼香の順番が回ってきたら会場に戻る方法もあります。
ご焼香の間は誰かに見ていてもらう
ご焼香の間は、できれば誰かに赤ちゃんを見ていてもらいましょう。赤ちゃんを抱っこしたままではご焼香がしにくく、抹香や煙が赤ちゃんにかかってしまう恐れもあります。
赤ちゃんを見ていてもらうのが難しければ、片手でしっかり赤ちゃんを抱っこしながら、もう片手でご焼香して合掌する方法でも問題ありません。
赤ちゃんではなく、ある程度の年齢のお子さんを連れて行く場合、保護者がご焼香している隣で一緒に合掌するよう指導しましょう。
おむつや着替えなどの持ち物に配慮する
赤ちゃん連れで葬儀に参列する際には、持ち物への配慮も大切です。
紙おむつやおしりふきを多めに持つほか、服を汚してしまったときの着替えや、汚れものを入れられる袋、空腹対策のベビーフードや粉ミルクを準備します。会場が寒い場合やおむつ替えスペースがなかった場合に備え、バスタオルや防水シートもあると便利です。
授乳期の場合は授乳しやすい喪服を選ぶ
授乳期の母親の場合、前開きのブラウスや授乳対応のワンピースなど、授乳しやすい喪服を選ぶのも大切です。
喪服については、一般的な葬儀同様、準喪服を着用するのが基本です。しかし、赤ちゃん連れで準喪服の着用が難しい場合や、産後すぐで楽な服装が求められるときには、略式喪服でも許容されます。ヒールのない靴でも問題ありません。
参列する赤ちゃんの香典はいらない
赤ちゃん連れで葬儀に参列する際、赤ちゃんの香典は親の香典に含めて問題ありません。表書きについても、保護者の名前だけ記載すればよく、赤ちゃんの名前は不要です。
ただし、ある程度の年齢の子どもが葬儀に参列し、精進落としをいただく場合は、子どもの料理代を上乗せして香典をお渡しするのがマナーです。料理代は1人あたり5,000円程度を目安に計算します。
香典の相場やマナーについては、以下の記事で詳しく解説しています。
赤ちゃんのお葬式に関するよくある質問
ここからは、赤ちゃんのお葬式に関するよくある質問を紹介します。
- 赤ちゃんのお葬式に参列してはいけない・火葬場に行ってはいけないというのは迷信?
- 赤ちゃんのお葬式に参列する際に香典は必要?
- 赤ちゃんが亡くなった時にかける言葉は?
それぞれの回答は次のとおりです。
赤ちゃんのお葬式に参列してはいけない・火葬場に行ってはいけないというのは迷信?
自分自身の赤ちゃんが亡くなった場合でも、お葬式への参列を避けたり、火葬場に行くのを控えたりする必要はありません。
子どもが親より先に亡くなることは、かつては逆縁とされ嫌われました。親不孝にあたることや、我が子の火葬を見届けるのが辛いことから、親は子の葬儀や火葬の場に立ち会うべきでないという迷信や風習があったそうです。
しかし現代では、親が自分の意志で火葬に立ち会うかどうか決めるのが一般的です。辛ければ無理に参列しなくても問題ありませんが、しっかりお見送りすることで気持ちの整理をつけやすくなるともいわれています。後悔のないよう、自分の気持ちに従って行動するのが大切です。
赤ちゃんのお葬式に参列する際に香典は必要?
出生後の乳幼児が亡くなった場合の葬儀では、一般の葬儀と同様に香典を渡しましょう。
一方で死産の場合は香典ではなく、家族への気遣いとしてお見舞い金を渡すのが一般的です。お見舞い金の額は、5,000円程度が目安です。
赤ちゃんが亡くなった時にかける言葉は?
赤ちゃんが亡くなった場合、「この度はご愁傷様です」といった一般的なお悔やみの言葉のほか、相手に寄り添った言葉をかけるのがよいとされます。「好きなだけ泣いてよい」「何度でも思い出してよい」などの言葉や、ただ相手の話を聞いたり一緒に泣いたりするなど、共感の態度を示しましょう。
一方で、つい言ってしまいがちな「がんばって」「早く忘れて」などの励ましの言葉は逆効果になりやすいため注意が必要です。次の子を望む言葉や、命を軽んじる言葉、相手を責めるような無神経な言葉は当然タブーのため、一切口にしないようにしましょう。
赤ちゃんのお葬式マナーを押さえて葬儀を実施・参列しよう
赤ちゃんが亡くなった場合、火葬のルールは設けられていますが、お葬式については個々の判断にゆだねられています。赤ちゃん向けのお葬式プランが用意されている葬儀社を手配すれば、手厚いご供養によって気持ちの整理につながるでしょう。
一方、赤ちゃん連れで葬儀へ参列すべきか悩んでいる場合、身内の葬儀であれば問題ないことが多いですが、他人であれば控えておくべきです。周囲に配慮しつつ、葬儀のマナーを押さえてスマートに行動するのが大切です。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。火葬のみの直葬も対応しており、依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。