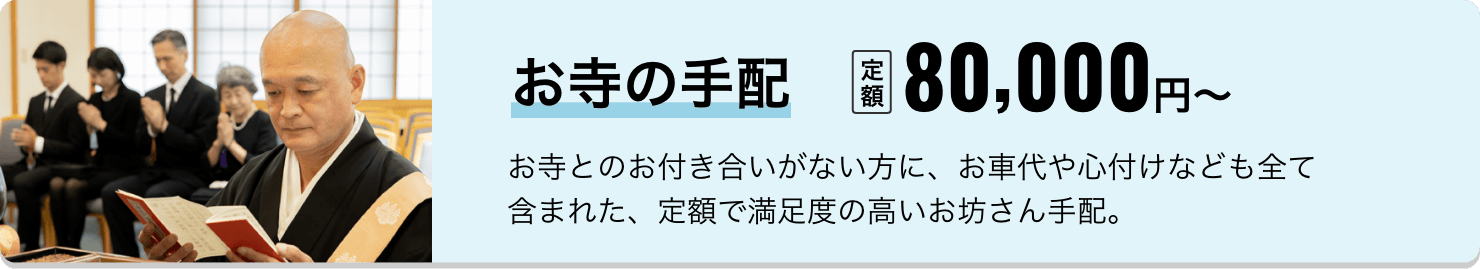仏教では、故人が亡くなった日から49日までの間を「忌中」といいます。四十九日を迎えるまでの期間には、古くから伝わるさまざまな風習があるため、事前に正しい過ごし方を知っておくことが大切です。
今回は、これから四十九日に向けた準備を始める方向けに、亡くなってから49日を迎えるまでにやるべきことや避けるべき行動、四十九日法要の準備内容を詳しく解説します。忌中は節度ある行動を心がけ、故人への冥福を祈りながら過ごしましょう。
この記事を要約すると
- 故人が亡くなってから49日目を「四十九日」といい、仏教ではこの日を境に忌明けとなります。四十九日には「四十九日法要」を執り行います。
- 四十九日を迎えるまでの期間は、毎日の供養や7日ごとの法要を行い、四十九日法要に向けたさまざまな準備を進める必要があります。
- 死はときに「穢れ」と捉えられるため、忌中は新年の挨拶や神社への参拝など、お祝い事を避けるのがマナーです。
四十九日とは
四十九日とは、故人が亡くなってから49日目を表す言葉です。仏教では四十九日をもって故人の魂が成仏すると考えられており、この日に四十九日法要が行われます。四十九日を迎えるまでの49日間を忌中といい、遺族は故人の冥福を祈りながら静かに過ごさなければいけません。
なお、浄土真宗では亡くなってすぐに極楽浄土に往生できると考えられているため、四十九日法要の意味合いが異なります。
「忌中」と似た言葉に「喪中」がありますが、こちらは命日から一周忌までの1年間を指す言葉です。
四十九日までの過ごし方
四十九日を迎えるまでの期間は、故人の死を偲び、日々を慎みながら過ごすことが大切です。ここからは、忌中に行うべきとされているさまざまな風習をご紹介します。
神棚封じ
神道では亡くなってから50日間を忌中としており、死を「穢れ」として扱います。故人が亡くなったらすぐに神棚を封じ、神様に穢れが及ばないように守らなければいけません。神棚封じをする際は、神棚に白い半紙やお札を貼り付けて扉を閉じ、拝礼や供え物を一時的に控えます。
忌明けには、自身を塩で清めたあとに礼拝を行います。神棚を覆っていた半紙やお札を取り除いて、再び普段通りのお供えを再開しましょう。
毎日供養
四十九日を迎えるまでの49日間は、故人が無事に成仏できるよう、祭壇に手を合わせて毎日の供養を行いましょう。
葬儀を終えたら、ご遺骨・仮の位牌・遺影を安置するための「後飾り祭壇」を用意します。祭壇には水・生花・お菓子・果物などをお供えし、できる限り線香や蝋燭の火を絶やさずに灯し続けてください。線香の香りは、故人の食事の代わりと考えられています。
7日ごとの法要
故人が無事に極楽浄土で成仏できるよう、亡くなってから7日ごとに「忌日法要」を行います。仏教の世界では、故人が亡くなってから七日ごとにあの世で裁判が行われると考えられています。故人の魂が彷徨っている忌中は、遺族による供養が欠かせません。
なお、初七日法要は葬儀のあとに繰り上げて行うことが多く、二七日から六七日までの法要は自宅で簡単に済ませるケースがほとんどです。近年では、僧侶や参列者を招いて大々的に法要を行うのは、忌明けの区切りとなる四十九日のみとされています。
| 法要の名称 | 読み方 | 亡くなった日からの日数 |
|---|---|---|
| 初七日 | しょなのか | 7日目 |
| 二七日 | ふたなのか | 14日目 |
| 三七日 | みなのか | 21日目 |
| 四七日 | よなのか | 28日目 |
| 五七日 | いつなのか | 35日目 |
| 六七日 | むなのか | 42日目 |
| 七七日 | なななのか | 49日目 |
仏壇の手配
四十九日を迎えるタイミングで、仮の祭壇である「後飾り祭壇」から、清拭な仏壇への切り替えを行います。自宅に仏壇がない場合は、四十九日までに仏壇・ご本尊・両脇仏を揃えましょう。宗派によっては、過去帳や法名軸を用意する場合もあります。
仏壇を新規購入する際は、僧侶に開眼法要を依頼するのが一般的です。故人の宗派に合わせて、早めに仏壇の準備を整えることが大切です。
本位牌の手配
四十九日法要では、木材でできた仮の白木位牌から漆塗りの本位牌への魂移しが行われます。これを「位牌の閉眼供養・開眼供養」と呼びます。
本位牌の制作には2週間程度時間がかかるため、四十九日に間に合うためには早めに手配することが肝心です。本位牌を依頼する際は、故人の戒名や命日を正確に伝えるようにしてください。
お墓の手配
四十九日法要の後に納骨を予定している場合、お墓の準備もあわせて進めましょう。新しく墓石を建てる場合は完成までに2〜3ヶ月かかるため、四十九日に間に合うかどうか確認が必要です。
先祖代々の墓がある方は、お墓の掃除をしたうえ、墓誌への追加彫刻を依頼してください。墓誌には、戒名・没年月日・俗名などが刻まれます。なお、近年はお墓を閉じて納骨堂を利用するケースも増えています。
遺品整理
故人が生前愛用していたアクセサリーや小物は、四十九日を終えてから形見分けをするのが一般的です。それに先立って、四十九日までに遺品整理を進めておくとスムーズです。
遺品整理では、故人の残した物を残すものと処分するものに選別します。エンディングノートや遺言書がある場合は、その内容に沿って対応してください。日記や手紙などの書類は、思い出として保管しておくとよいでしょう。
香典返しの準備
四十九日法要を終えてから、葬儀の際に受け取った香典に応じた香典返しを行います。香典返しは、いただいた金額の半額程度を返礼する「半返し」の考え方が基本です。
はじめに芳名帳や香典帳を整理し、金額に応じた品物を手配します。贈り物としては、お菓子・コーヒー・洗剤などの消え物やカタログギフトを選ぶのが一般的です。
品物は箱に包み、黒白または双銀の水引が描かれた掛け紙をかけます。表書きには「志」「満中陰志」などと記しましょう。
挨拶回り
葬儀後が終わってから1週間の間に、故人が生前お世話になった病院や関わりのあった知人、勤務先などへ挨拶回りを行います。訪問先に故人の遺品が残されていた場合は、この機会に引き取りましょう。
挨拶の際には簡単な手土産を持参し、生前にお世話になったことへの感謝と無事に葬儀を執り行ったことを報告してください。故人に代わって御礼をすることで、今後の関係性の構築にも繋がるでしょう。
四十九日法要の準備
四十九日法要は、忌明けの日を迎える大切な儀式です。法要に向けてさまざまな物事の手配を行う必要があるため、時間に余裕を持って準備を進めていきましょう。
日程調整
四十九日法要は亡くなった日から数えて49日目に行う法要ですが、平日にあたるときや遺族のスケジュールの都合によっては、直前の週末に繰り上げて行うケースも珍しくありません。
なお、49日目以降に後ろ倒しにすることは「故人が極楽浄土へ成仏するのを躊躇する」という意味合いになってしまうため、必ず当日か前倒しにするのが基本です。
法要を行う会場は、菩提寺・自宅・葬儀場・霊園のいずれかを選択します。法要後に納骨を行う場合は、必ず事前に菩提寺へ連絡を取りましょう。参列者は遺族や親族のほか、故人と生前親交のあった友人・知人を招いてもかまいません。
僧侶の手配
法要の日程が決まったら、すぐに僧侶へ出席の依頼をしましょう。付き合いのある菩提寺や寺院がない場合は、葬儀社や民間サービスを通じて僧侶を紹介してもらうことも可能です。
お布施は葬儀費用の10分の1を目安に包むのがマナーです。奉書紙や水引きのない不祝儀袋を使用し、表書きには「御布施」と記します。
| 納めるお金 | 内容 | 相場 |
|---|---|---|
| お布施 | 四十九日法要への出席に対する御礼 | 葬儀費用の10分の1程度 ※開眼法要・納骨法要もあわせて行う場合は、相場よりやや多めに包む |
| 御車代 | 遺族が僧侶の送迎を行わない場合に包む | 約5,000〜1万円 |
| 御膳料 | 僧侶がお斎を辞退した場合に包む | 約5,000〜1万円 |
案内状の送付
法要の日時や開催場所が決まったら、参列を依頼する人に案内状を送りましょう。こちらの案内状も訃報や葬儀案内と同様に、句読点を用いず、縦書きで記すのがマナーです。
案内状には返信用のはがきや封筒を同封し、開催日の1ヶ月前には発送します。日時に余裕を持って案内することで、より多くの参列者が集まりやすくなるでしょう。
<案内状に記載する内容>
- 故人の名前
- 法要の日時・会場
- 法要後のお斎や納骨の有無
- 施主の連絡先
- 出欠の返信期日・返信方法
お斎の準備
四十九日法要のあとには、参列者や僧侶を招き、お斎(おとき)という会食を行うのが一般的です。遺族の自宅で行う場合は仕出し料理を、寺院や葬儀場を利用する場合は料亭の料理を手配します。
料理は参列者の人数に合わせて用意する必要があるため、参列する人数が確定したら早めに予約を入れましょう。お斎を行わない場合は、代わりに持ち帰り用のお弁当を用意する方法もあります。
納骨法要の準備
四十九日法要にあわせて納骨も行う場合は、事前に菩提寺や霊園の管理者に連絡を取るのがマナーです。先祖代々お世話になっている菩提寺であっても、管理者に許可を得ずに勝手にお墓を動かしてはいけません。納骨の際には火葬後に受け取った「納骨許可証」を提示するため、こちらも忘れずに用意しておきましょう。
また、宗派によっては、木製の板に戒名や没日を記した卒塔婆を墓の裏に建てる場合があります。納骨に間に合うよう、すみやかに手配を進めてください。
返礼品の用意
四十九日法要では、法要へ参列した方へのお礼として返礼品を贈る風習があります。こちらの返礼品は香典返しとは別で用意するもので、1人あたり2,000〜5,000円程度の品を選ぶのが一般的です。
返礼品には、故人が生前好んでいた食品・飲料やタオル・消耗品などの持ち帰りやすいものがおすすめです。表書きには「志」「粗供養」「満中陰志」などと記し、黒白または双銀の結び切り水引をかけて包みましょう。
四十九日までに避けるべき行動
四十九日を迎えるまでの忌中の期間には、祝い事や派手な行動を控え、静かに過ごすのがマナーです。ただし、やむを得ない事情で以前から決まっていた予定をずらすことが難しい場合は、柔軟に対応するケースも増えています。
新年の挨拶
忌中の間は年賀状の送付・初詣・新年会への参加など、新年を祝う行事は控えるのが基本です。年始の挨拶は「今年もよろしくお願いします」にとどめ、年賀状の代わりに喪中はがきや寒中見舞いを送りましょう。
おせち料理は祝い膳とされるため、食べる場合は重箱に詰めずに盛り付けてください。お年玉はポチ袋を避け、普通の封筒で「お小遣い」として渡すと無難です。
<忌中に避けるべき新年の風習>
- 新年の挨拶
- 「明けましておめでとうございます」「謹賀新年」などの挨拶フレーズ
- 年賀状
- 初詣
- おせち料理(重箱に入れたもの)
- お年玉(ポチ袋に入れたもの)
- 新年会への参加
神社への参拝
忌中は、神社への参拝や神社で行われる祭事への参加を控えるべきといわれています。神道では死を穢れと捉えており、地域によっては鳥居をくぐること自体が禁忌とされているため、神聖な場所に穢れを持ち込まないための配慮が必要です。
ただし、地域や神社によっては、鳥居の手前で静かに祈ることが認められている場合もあります。忌中の参詣を望んでいる方は、事前に確認したうえで行動するようにしてください。
入籍・結婚式
忌中に自身の入籍や結婚式の予定があった場合は、両家と十分に話し合いをしたうえで慎重に判断しましょう。
婚姻届の提出は両家の了承があれば決行してもかまいませんが、結婚式は延期をするのが一般的です。やむを得ず、予定通りに結婚式を行う場合は、神前式であれば事前にお祓いを受けることが望ましいとされています。
なお、忌中に友人や知人の結婚式へ招待された場合も、基本的には欠席するのがマナーです。参列できなかった場合は、忌明けに改めてお祝いの品を届けることでお祝いの気持ちを伝えましょう。
お宮参り・七五三
お宮参りや七五三は、神社で行われる子供の成長を祝う儀式です。しかし、忌中は神社への参拝が慎まれるほか、忌中にこれらの儀式を行うことは「祝い事に穢れを持ち込む」とも捉えられてしまいます。そのため、これらの行事も延期することが望ましいでしょう。
成人式や入学式などのお祝い事も同様ですが、こちらは時期をずらすことが難しいため、できるだけ慎ましやかに参加するなどの配慮が求められます。
お中元・お歳暮
忌中にお中元やお歳暮の時期が被った場合の対応方法は、地域によってさまざまです。忌中に贈る場合は、のし紙や紅白の水引は避け、白無地の奉書紙や短冊を用いましょう。
お祝い事とされる贈答を忌中に行うことは、「穢れを贈り先に広めてしまう」という捉え方もあります。忌中を避ける場合は相手方に事情を伝えたうえ、時期をずらして暑中見舞いや寒中見舞いとして贈るのが一般的です。
飲み会・宴会の席
忌中の期間は喪に服す期間であるため、派手な飲み会やにぎやかな祝いの席への出席は好ましくありません。ただし、少人数で静かに過ごす食事会や家族・親戚間での集会など、許容されるケースもあります。遺族としての立場をわきまえ、節度ある行動を心がけることが大切です。
旅行・レジャー
忌中に旅行をしたりレジャーに出掛けたりすることも「旅先に穢れを運ぶ」と捉えられるため、できるだけ控えるべきとされています。大人数での旅行や大きな金額の買い物など、派手な行動は慎みましょう。旅行等で長期間家を空ける場合、毎日供養が滞ってしまうという問題もあります。
ただし、故人が生前に楽しみにしていたイベントや、家族や少人数での慎ましやかな旅行など、一定の配慮をする場合はその限りではありません。旅行やレジャーを決行するかどうかは、柔軟に判断するのが現代的な考え方といえます。
引越し・家の新築
四十九日を迎えるまでの期間は、故人が住んでいた家に魂が留まっていると考えられています。
そのため、忌中には引越しや新築など、住居にまつわる大きな動きは控えるのが好ましいでしょう。地鎮祭や上棟式などの新築のお祝い事も、忌明けまで待つのが一般的です。
しかし、さまざまな事情によって、忌中に予定を決行しなければいけないケースもあるかもしれません。動かせない予定がある場合は、関係者とよく相談のうえ、慎重に判断するようにしてください。
忌中に行うべきことやマナーをしっかり守りましょう
故人が亡くなってから四十九日までの期間は、さまざまな風習やマナーに配慮しながら静かに過ごすことが求められます。故人が無事に極楽浄土で成仏できるよう、毎日の供養や法要を欠かさずに行うことが大切です。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。