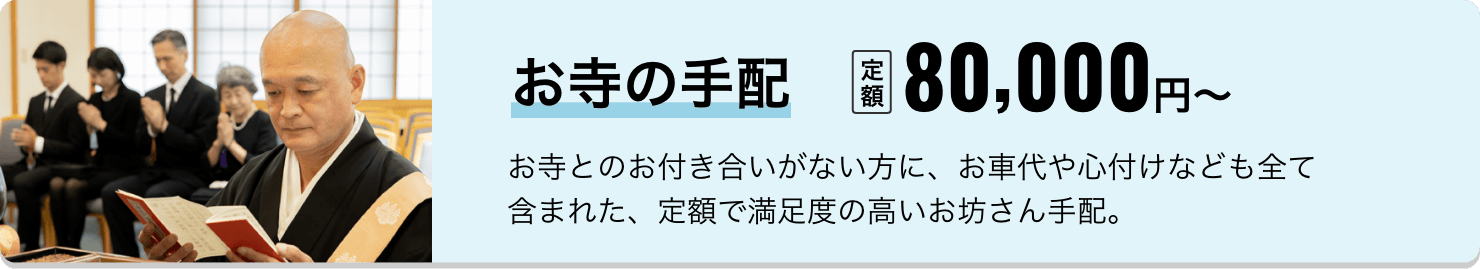さまざまな行事の日取りを決める際に意識されるのが、大安や仏滅といった「六曜」です。特に大安は縁起が良い日として知られていますが「葬儀は大安を避けるべきではないか」と不安になる方もいるのではないでしょうか。
仏教と六曜の関係や参列者の印象など、判断に迷う場面は少なくありません。この記事では、六曜の意味や宗教ごとの考え方を整理し、葬儀の日程を決める際に配慮すべき点について解説していきます。
この記事を要約すると
- 大安に葬式を執り行っても宗教的な問題はないものの、縁起を気にする人もいるため参列者への配慮が必要です。
- 仏教と六曜に直接のつながりはないものの「友引」は故人が友をあの世へ誘うと連想されるため避けられる傾向があります。また、火葬場も休みの場合が多く事前確認が必要です。
- 葬儀日時を決める際には、火葬場や僧侶の予定、親族の都合など実務的な調整を優先することが大切です。
大安に葬式はしないほうがよい?
大安は縁起の良い日とされ、結婚式や新居への引っ越しなどお祝いごとに選ばれることが多いです。とはいえ、あらゆる行事を大安に行うのが最適といえるのでしょうか。ここでは、大安の日に葬儀を執り行うことに対する考え方や地域の習慣について解説します。
大安の日に葬儀を執り行っても基本的に問題はない
大安は吉日とされ、結婚式や開業といったお祝いごとに選ばれることが多い日です。そのため「葬儀に適さないのでは」と心配される方もいますが、六曜は仏教や神道とは無関係の暦注にすぎません。宗教的な意味はないため、大安に葬儀を行っても基本的に問題ありません。
予定の都合や火葬場の空き状況などから大安に葬儀を行うことは珍しくなく、必要以上に気にする必要はないでしょう。ちなみに六曜のなかでは「仏滅」が最も凶とされていますが、これに関しても仏教儀式と関係はなく、通常どおり執り行っても全く問題ありません。
地域によっては六曜を重視することもある
六曜と仏教儀式は全く関係なく、通常通り葬儀を執り行えると前述しましたが、地域によっては六曜を強く意識する風習が残っている場合もあります。特に地元に長く暮らす高齢世代の方の中には、大安に葬儀を執り行うことに違和感を持つ方もいるかもしれません。
地域の習慣に詳しくない場合は、地元の葬儀社に確認しておくと安心です。また、親族などに六曜を強く意識する人がいる場合には、事前に事情を丁寧に話しておくようにしましょう。
大安や仏滅を含む六曜の考え方
六曜(ろくよう)とは、その日の吉凶を占うために中国で生まれた暦注のひとつです。本来は勝負ごとの運勢を占うもので、仏教や神道といった宗教とは関係のない考え方です。
六曜は大安や仏滅を含めて全部で6種類あり、現在もカレンダーの日付欄に記載される形で受け継がれています。ここでは、大安や仏滅を含む六曜それぞれの意味を整理し、葬儀との関わりについて解説します。
先勝|午前は急ぎ事が吉、午後は控えるのが無難
先勝(せんしょう・さきがち)は「先んずれば勝つ」という意味を持ち、午前中は吉、午後は凶と考えられています。結婚式や契約時などは午前に行うのが良いとされていますが、葬儀に関しては宗教的な根拠はありません。
ただし、地域によっては「午後は避けたほうが無難」と意識されることがあり、時間帯を気にする参列者に配慮するケースもあります。
友引|勝負ごとに良いとされる日
友引(ともびき)は、もともと「共引」と表記され、勝負ごとで勝敗がつかず引き分けになるという意味を持ちます。
午前と夕方は吉、正午前後は凶とされ1日の中で運勢が変化するのが特徴です。結婚式や祝いごとに選ばれるケースもありますが、葬儀における解釈については地域や習慣によって異なります。
先負|午前は控えめに、午後は穏やかに過ごすと良い日
先負(せんぷ・さきまけ)は「先んずれば負ける」の意味があり、午前中は凶とされ、午後が小吉とされています。結婚式などは午後に行うと良いとされますが、葬儀に関して特別な制約はありません。ただし、高齢の参列者の中には「午前は縁起が悪い」と気にする方もいます。
仏滅|六曜の中で最も凶とされるが日常生活に影響はない
仏滅(ぶつめつ)は「すべての物事が滅ぶ」という意味から六曜で最も凶とされる日です。
お祝いごとには避けられる一方で弔事には「むしろふさわしい」と捉える考え方もあります。仏という字が使われていますが、仏教徒は無関係で宗教的に禁じられているわけではありません
実際には日程の都合で仏滅に葬儀が行われることも珍しくなく、大きな問題はないでしょう。
赤口|午前・午後は凶で正午前後のみ吉とされる
赤口(しゃっこう)は陰陽道の「赤舌日」に由来し、火や血を連想させることから凶日とされています。午前と午後は凶、正午前後の2時間のみが吉とされるのが特徴です。
結婚式や祝いごとには避けられるケースが多いですが、葬儀の場合は時間の制約が厳しいため、必ずしも六曜に従って調整されるわけではありません。ただし赤口を気にする地域では配慮が求められます。
大安に葬儀を行うことへの参列者の印象
大安に葬儀を執り行うことに対する考え方に正解はなく、地域によっては「大安での葬儀は場違いな感じがする」と考える人がいる一方、以下の通り肯定的に受け止める声も少なくありません。
- 吉日なので葬儀でも心が落ち着く
- 新たな旅立ちを後押しする日にふさわしい
- 悪い日ではないため、嫌な感じがしない
大安は「大いに安し」の意味を持つ日で、六曜の中でも最も縁起が良いとされます。葬儀を大安に営むことで「少しでも明るい気持ちで見送れる」と感じる声もあります。また、葬儀を別れと同時に新たな旅立ちと捉え、大安に行うことで「故人の門出にふさわしい」といった声もあり、良いイメージを持つ人もゼロではありません。
葬儀では大安ではなく「友引」を避ける傾向にある
葬儀を大安に執り行うことについて解説してきましたが、六曜の中で最も葬儀の際に意識されるのが「友引」です。本来は勝負がつかない日を意味しますが「友を引く」とも連想されることから縁起が悪いとされ、古くから避けられてきました。
この考えを受けて火葬場の休業日は友引になることが多く、実務面で日程調整が難しいことも友引を避けるべき要因になっています。ただし、これも一つの考えであり絶対に守らないといけないわけではありません。
特に近年は首都圏を中心に火葬場不足が深刻で、六曜を気にせず友引でも火葬や葬儀を行うケースも増えています。やむを得ない事情がある場合は友引に葬儀を執り行っても全く問題ないといえるでしょう。
仏教以外の宗教と六曜の関係
六曜は仏教とは直接関係がないとされていますが、ほかの宗教ではどのように捉えられているのでしょうか。神道やキリスト教において六曜がどのような位置づけなのか、ここではそれぞれの考え方を解説します。
神道
神道も仏教と同じく六曜とは直接の関わりはありません。ただし風習として葬儀では友引を避ける傾向は残る地域もあります。また、お宮参りや七五三、鎮魂祭など祭礼の日取りを決める際には、大安などの六曜を意識するのが一般的です。
とくに大安に行事を行うと吉とされることが多いですが、これは神道の教理に基づくものではなく、昔からの習慣として根付いているものです。
キリスト教
キリスト教にも六曜との関わりはなく、仏教や神道のように風習として六曜を意識することもありません。前夜式や告別式は原則どの日でも行えます。ただし、日本では友引を休業日にしている火葬場が多いため、葬儀を友引にあたる日に行うケースは少ないといえます。
また、カトリックをはじめとする一部の教派では「聖土曜日」に葬儀を行えないなど、教理上の制約が設けられていることもあります。
大安に葬儀を執り行う際の注意点
大安は六曜のなかで最も縁起の良い日とされていますが、その印象ゆえに「葬儀にはふさわしくないのでは」と考える人もいます。そのため、大安に葬儀を執り行う際には参列者の考え方に注意が必要です。特に年配の方や縁起を気にする人の中には別日にすべきと考える場合があります。
大安でも全く問題ないものの、念のため親族などにはその旨を伝えておくようにしましょう。無理に大安の葬儀が問題ないことを強調するのではなく「火葬場や式場の都合でこの日程になった」と伝えておけば、角も立ちません。
葬儀日程を決める際に考慮すべきポイント
大安などの六曜は基本的に葬儀日程を決めるうえで重視する必要はありません。ただし、日程調整そのものはとても重要です。ここでは、滞りなく葬儀を進めるために押さえておきたい確認事項を整理し、参列者や遺族が困らないようにするためのポイントを解説します。
火葬場の稼働状況や休みの日を確認する
葬儀の日取りを決める際に最も影響を受けるのが火葬場です。地域によっては予約が混み合いやすく、希望する時間がすでに埋まっている場合もあります。
特に都市部は火葬炉の数が限られているため、早めの確認が欠かせません。友引の翌日は利用が集中する傾向があるため、予定がある程度決まった段階で葬儀社を通じて予約を入れておくのが安心です。
遺族の希望や方針を反映させる
葬儀は故人を偲ぶ大切な儀式であり、遺族の希望を反映させることが重要です。親族のなかには「全員で見送りたい」と考える方もいるため、遠方からの移動にかかる時間も考慮しましょう。あまりに急な日程では参列できない人が出る恐れがあるため、余裕を持たせた調整が望ましいです。
式場や僧侶の予定を合わせる
お通夜や葬儀は、会場や僧侶の都合に左右されることも珍しくありません。菩提寺や教会がある場合は、宗教者の予定を確認してから日程を固める必要があります。スケジュールが合わない場合には日程をずらすか、別の僧侶をお紹介してもらうといった調整を検討しましょう。
【菩提寺とは】
菩提寺(ぼだいじ)とは、古くから一家が供養や葬儀をお願いしてきた、家とゆかりの深いお寺のことを指します。多くの場合は、先祖代々の墓が置かれている寺院であり、葬儀や法事の際には読経や供養を依頼する大切な存在です。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、お寺とのお付き合いのない方に、全国一律価格でお坊さんのご手配をしております。戒名代や御車代なども含めたセット価格でのお布施になりますので、安心してご依頼ください。
参列しやすい日程を考える
近しい親族だけでなく、故人と縁のある人々が参列しやすい日を選ぶことも配慮の一つです。平日よりも休日の方が集まりやすい場合や、仕事帰りにお通夜で参列できるように夕刻の時間を選ぶといった工夫もあります。無理のない日程を選ぶことで、より多くの人に見送ってもらえるでしょう。
地域に伝わる慣習やしきたりも考慮する
宗教的な決まりはなくとも、地域によっては「友引は避ける」「大安は避けるべき」など独自の習慣が残っていることがあります。地元での葬儀に慣れていない場合は、葬儀社や親族に相談しておくと安心です。地域のしきたりに配慮することで、後々のトラブルを防ぐことにもつながります。
大安の日取りにとらわれず、家族の想いを大切に葬儀を営もう
大安であっても葬儀に宗教的な問題はなく、六曜にとらわれすぎる必要はありません。ただし、友引を避ける風習や参列者の印象には一定の配慮が求められます。無理に縁起を気にするのではなく、状況や事情に合わせて柔軟に判断することが大切です。
葬儀の日程を決めるうえで重要なのは、火葬場や僧侶の予定、そして遺族や参列者が心を込めて見送れる環境を整えることです。大安かどうかにこだわるより、家族が納得できる形で式を執り行うことが、故人への敬意を示す最良の方法につながるでしょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国一律価格でご提供しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。