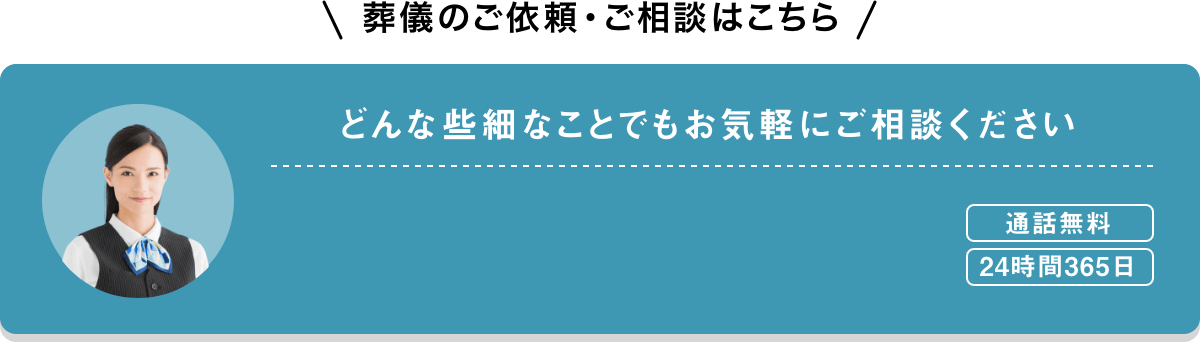大切な人を見送る準備を進めるなかで、「友引」「年末年始」「お盆」「火葬場の休み」など、日取りに関する不安や迷いを抱える方は少なくありません。
実際に葬式ができない日もあれば、配慮をすることで葬式ができる日もあります。この記事では、その違いをわかりやすく整理し、安心して日程を決めるために役立つ情報をお届けします。
まずは全体像を表で確認し、その後、各ケースについて「なぜそう言われているのか」「本当に避けるべきなのか」「気をつけるべき点はなにか」を詳しく解説していきます。
迷いや不安があるときでも落ち着いて判断できるよう、後悔のないお別れのための一助となれば幸いです。
この記事を要約すると
- 葬式ができない・配慮が必要な日は「友引」「年末年始」「長期休暇」「火葬場の休業日」の4つのケースがあります。火葬場が稼働していない日は、葬式が行えません。
- 友引は仏教と関係なく、葬式をしてはいけないわけではありません。ただし友引を火葬場の定休日をしている施設もあり、この場合は葬式ができません。
- 葬式の日程を決めるには、葬儀場・火葬場・僧侶・喪主および親族のスケジュール確認が必須です。
葬式ができない・配慮が必要な4つのケース
葬式の日程を考えるうえで、葬式が「できない日」と「配慮が必要な日」を知っておかなければなりません。
主なケースは以下の4つです。
| ケース | 葬式の可否 | 理由・注意点 |
|---|---|---|
| 友引 | △ 場合による | 地域によって火葬場が休みの場合がある。また、参列者・親族の考えに配慮が必要 |
| 年末年始 | ✕ できない | 火葬場が休業のため、実施不可(具体的日程は施設により異なる) |
| 長期休暇(お盆・GWなど) | 〇 できる | 実施は可能だが、僧侶・親族・参列者の予定が合いづらく、移動や調整が難航しやすい |
| 火葬場の休業日・点検日 | ✕ できない | 定休日・点検日など、火葬場が稼働しない日は葬式も不可 |
なお、友引の葬式については以下の記事で詳しく解説しています。ぜひ合わせてご確認ください。
友引
友引は、地域によっては「葬式ができない日」にあたります。これは、一部の地域で友引が火葬場の休業日となるからです。多くの地域で友引は縁起の悪い日として葬儀が避けられており、友引を休業日として設定している地域は少なくありません。
しかし実際のところ、友引の日に葬儀を行ってはいけないという決まりはなく、友引の葬儀が行われているエリアもあります。
友引はどうして葬儀ができないといわれているの?
「友引」は、「友」を「引く」と書くことから、故人が友を道連れにすることが連想され、縁起が悪いと考えられてきました。特に高齢の方や地域によってはこの考えが根強く、「友引に葬儀は避けるべき」という風習が残っているケースも多く見られます。
ただし「友引」は、暦の上で縁起を占う六曜(ろくよう/六輝とも)のひとつで、本来仏教の教えとはまったく関係ありません。現在の六曜の概念が広まったのは昭和に入ってからで、戦後の暦印刷の広がりによって一般化されたともいわれています。
友引は宗教的な意味で葬式ができない日ではなく、あくまで近年広がった慣習によるものです。
友引に葬式をしてもいい?
友引に葬式を行っても問題はありません。法律的にも宗教的にも「葬式をしてはいけない」と定められてはおらず、風習や縁起を気にするかどうかが判断の分かれ目になります。
ただし、実際には以下のような注意点があるため、柔軟な対応が必要です。
・火葬場が友引を休業日にしているケースがある
地域によっては「友引は避けるもの」という考えが浸透しており、友引が火葬場の休業日となっていることがあります。この場合、火葬ができないため、葬儀の日程を調整する必要があります。
・参列者や親族が気にする場合もある
友引に葬儀を行うこと自体は差し支えありませんが、「友引の葬儀は縁起が悪い」と感じる方もいます。年配の親族や参列者が多い場合は特に注意が必要です。トラブルを避けるためにも、事前に関係者の意向を確認しておくのが安心です。
・関西など一部地域では「友引人形」を入れる風習も
関西などでは、友引の日に葬儀をする場合、棺に「友引人形」を入れる風習があります。友引人形は、誰かが道連れにされないよう、身代わりとして人形を添えるという考え方から生まれたものです。こけしやぬいぐるみなど、火葬可能な人型のものが使われます。
こうした地域性も考慮しながら、家族で相談のうえ判断するとよいでしょう。
友引にお通夜はしていいの?
友引にお通夜を行うことは問題ありません。
友引に葬儀をしないのは、肉体との別れとなる火葬を行う日に人が集まるのを避けるという考えに基づいています。一方、お通夜は故人との「最後の夜を過ごす儀式」であり、火葬は行われません。
従って「友を引く」ことには当たらないとされ、ほとんどの地域で友引のお通夜は普通に行われています。
ただし、地域や家によっては、友引はお通夜も避けると考えられている場合があるかもしれません。気になる場合は、前もって僧侶や葬儀社、年配の親族などに相談しておくと安心です。
友引に法要はしていいの?
友引に法要を行うことは基本的に問題ありません。四十九日や一周忌などの法要は、故人を偲び、供養するための仏教的な儀式です。先に述べたように、六曜は暦上の考え方であり、仏教の教義とは関係ありません。
不安なときは、地域の慣習に詳しい菩提寺や僧侶などに相談するのがおすすめです。出席者の気持ちに寄り添い、納得できる日程を選ぶとよいでしょう。
年末年始
年末年始は、火葬場が休業するため、葬式ができません。年末年始の具体的にいつが休業となるかは施設によって異なりますが、ほとんどの施設が1月1日は休業です。
亡くなられたタイミングが年末年始にかかる場合、 火葬場の営業再開日まで安置・保管が必要になります。事情により年明けすぐの葬儀を希望 するなら、葬儀社や火葬場の予約が必須です。火葬場によって休業日は異なるため、早めに確認しておきましょう。
火葬場が休業により混み合うため、葬儀場も混み合います。希望日に斎場・火葬場が空いていない可能性もあるため、危篤となったら迷わず葬儀社に連絡し、スケジュールを確認しておくと安心です。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」は年末年始問わず、24時間365日葬儀の専門スタッフが無料で葬儀のご相談からご依頼まで受け付けておりますので、お気軽にお問い合わせください。
長期休暇(お盆・GWなど)
お盆やゴールデンウィークなどの長期休暇中でも、火葬場も葬儀社も稼働しているため葬儀は可能です。連休中の葬儀となる場合、喪主や親族、菩提寺などのスケジュール調整も欠かせません。スムーズに進めるためには、早めの確認と準備が重要です。
・親族・参列者の予定に配慮を
長期休暇中は、帰省・旅行・仕事のシフトなどで人の動きが読みにくい時期です。特に遠方の親族が多い場合は、新幹線や飛行機など、移動手段の確保も重要になります。喪主をはじめ、重要な親族・参列者には早めのアナウンスをしておきましょう。
・菩提寺・僧侶のスケジュール確認を
葬儀を行うためには菩提寺・僧侶の確保も必須です。ゴールデンウィーク中は通常時と異なる行事なども開催される時期です。菩提寺の都合がつかないといった状況にならないよう、危篤・臨終となったらすぐに一報を入れましょう。
・夏場のお盆は「ご遺体の管理」に注意
お盆は真夏にあたるため、葬儀まで数日待つ場合、ご遺体の保存管理が大きな課題となります。状況に応じ、以下のような暑い時期ならではの対応が必要です。
- ドライアイスの追加
- 専用冷蔵庫の使用
- 葬儀社での預かり
葬儀は無理に日延べするよりも早めの実施が望ましいこともあります。
その他(火葬場の休業日)
その他の葬式ができない日として知っておきたいのが、火葬場の休業日です。年末年始以外の火葬場の休業日は施設によって異なります。
例えば友引や、毎月決まった日を休業としている施設もあります。施設によっては年に数回、炉の点検や設備メンテナンスのために休業日を設定している場合もあるでしょう。
利用する予定の火葬場の休業日は、市区町村のHPや、葬儀社に問い合わせればわかります。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」でも、24時間365日無料で火葬場の休業日についてご回答いたしますので、お気軽にお問い合わせください。
仏滅・赤口など、六曜で友引以外に気を付ける日は?
六曜には「友引」のほかに「仏滅」や「赤口」など、不吉とされる日もあります。ただし、友引を除けば、基本的に葬儀の日取りとして避ける必要はありません。
六曜(ろくよう)は、14世紀ごろに中国から伝わった占いの一種で、先勝・友引・先負・仏滅・大安・赤口の6つに分けられ、行事の日程を決める際の目安とされてきました。現代でもカレンダーに記載されることが多いですが、仏教そのものとは関係がありません。
葬儀の日程で気にされやすいのは仏滅と赤口ですが、どちらの日も問題なく葬儀が行われています。
| 仏滅 | 何をするにも凶とされがちですが、葬式の日として、むしろ選ばれることもあります |
| 赤口(しゃっこう) | 結婚式など、慶事にはよくないとされていますが、葬式は問題ありません |
葬式の日程はどのように決める?
お葬式の日程は、「亡くなった日から何日後に行う」といった決まりはありません。火葬場・葬儀場・僧侶・親族などのスケジュールをもとに決定されることがほとんどです。
ここでは、日程を決めるときに確認しておきたい基本の流れと注意点を解説します。
葬儀全体の流れ
一般的な葬儀の流れは以下の通りです。
- ご遺体を安置(法律により24時間は火葬不可)
- 通夜
- 葬儀・告別式
- 火葬
通夜〜火葬までにかかる期間は、通常3日〜5日程度です。最近では、通夜を省いた「一日葬」や、家族だけで送る「家族葬」も増えています。
葬儀社に相談し葬儀場の空きを確認
日程調整は、葬儀社への相談からスタートするのがスムーズです。経験豊富なスタッフが、葬儀場・火葬場など、各方面に連絡を取りながら、最短かつ最適なスケジュールを提案してくれます
火葬場の空きを確認
葬儀社に依頼しない場合、火葬場への連絡は喪主や遺族が行います。火葬場が稼働していても、時期やエリアによって予約がとれないこともあります。年末年始などの繁忙期は速やかに予約を取りましょう。
僧侶のスケジュールを確認
火葬場の次に押さえるべきは僧侶のスケジュールです。火葬場と同様、僧侶の予定によっても、葬式の日程は調整が必要になることがあります。菩提寺があるなら、できるだけ早く連絡しましょう。遠方から僧侶に来てもらう場合、移動時間もかかるため、特に注意が必要です。
親族のスケジュールを確認
喪主や親族のスケジュールも確認しておきましょう。全員のスケジュールに合わせることはできませんが、重要な親族については早めに危篤・臨終の連絡をしておくとスムーズです。
葬式できる?できない?不安な時は、まずは専門家に相談を
葬儀を行えない日としては、友引のほか、年末年始や火葬場の休業日などがあります。このうち年末年始や火葬場の休業日は、火葬そのものができないため葬儀も行えません。一方、もっとも耳にする友引については宗教的な禁忌ではなく、地域の慣習や家庭の意向、施設の都合によるものがほとんどです。
また、複数の条件が重なったり、親族間で意見が分かれると、日程調整が難しくなることもあります。迷ったときは、まず葬儀社に相談するのが安心です。早めに確認・調整を行うことで、不安や混乱を減らし、悔いのない形で大切な人を見送ることができるでしょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国一律価格でご提供しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。