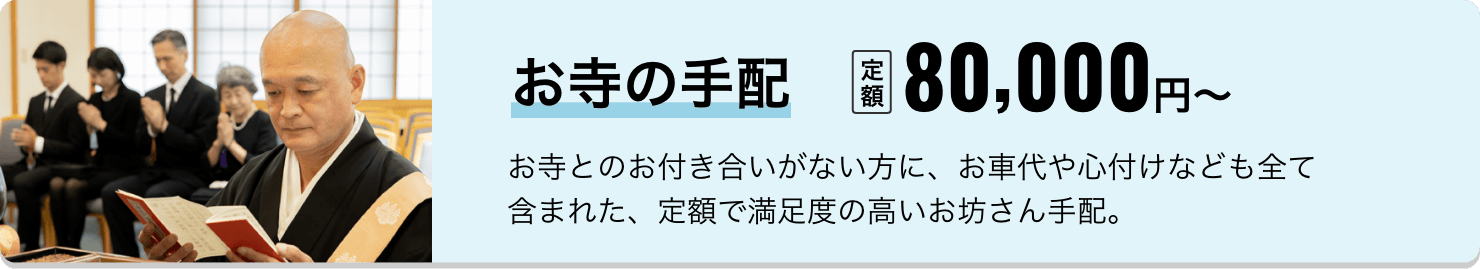日本の葬儀は、仏式で執り行われるのが一般的で、その際には故人が戒名を授かる習わしがあります。戒名にはいくつかのランクがあり、位号によって意味やお布施の相場が変わるため、事前に理解しておくと安心です。
さらに宗派ごとで戒名の付け方や考え方が異なるため、混乱しないためにも基本を押さえておく必要があります。この記事では、戒名の成り立ちや構成要素、位号のランクと相場についてわかりやすく解説していきます。
この記事を要約すると
- 戒名のランクの決め方は、寺院への貢献度や社会的な立場、信仰心の深さなどによって決まります。戒名のランクと呼ばれる部分は「位号」と言われ、戒名の最後につきます。
- 戒名のランクの種類は大きく4つに分かれます。ランクが高い順番に、「①院居士(男性)・院大姉(女性)」「②院信士(男性)・院信女(女性)」「③居士(男性)・大姉(女性)」「④信士(男性)・信女(女性)」があります。
- 戒名のランク毎の金額相場は、地域やお寺との関係によって変わります。目安としては、「院居士・院大姉・院信士・院信女」が50~100万円以上、「居士・大姉」が50~80万円ほど、「信士・信女」が10~50万円とされていいます。
戒名とは
戒名(かいみょう)とは、仏教において亡くなった人に授けられる特別な名前のことです。現代では、宗派や地域によって形式が異なり、位号や構成の違いによって意味も変わります。
ここでは、戒名の歴史や名前を授かる理由、授与の流れなどについて解説します。
戒名の歴史
戒名は、もともとインドの仏教には存在せず、中国に仏教が広まる過程で誕生したとされています。日本には仏教伝来とともに伝わりましたが、現在のように一般的に用いられるようになったのは江戸時代の頃です。
江戸幕府が檀家制度を導入したことで、寺院と檀家の関係を証明する役割を果たすようになり、死後に戒名が授けられる慣習が広がりました。当時は身分や財力によって授かる戒名に違いがあり、位の高い戒名を得るために高額なお布施を収めることもあったと伝えられています。
戒名を付ける理由
戒名には「仏弟子としての証」という意味が込められています。出家しなくても、戒名をいただくことで仏教徒として仏の弟子となり、極楽浄土に導かれると考えられてきました。そのため葬儀の場では、故人が迷わず成仏できるように戒名を授けることが重視されます。
ただし、宗派によって扱いが異なり、浄土真宗では「戒律」を設けないため戒名ではなく「法名」と呼ばれ、日蓮宗では「法号」として伝えられるなど、名称や意味に違いがあります。
戒名の授け方と儀式
戒名は、菩提寺の住職から授かるのが一般的です。ほかの僧侶から授けられた場合、菩提寺に受け入れてもらえない可能性もあるため、事前に確認が必要となります。戒名は、本人や家族の希望がある程度反映されるものの、寺院への貢献や社会での功績、お布施の金額なども考慮されて決められるのが通例です。
授与の儀式は「授戒(じゅかい)」と呼ばれ、浄土真宗では「帰敬式(ききょうしき)」または「おかみそり」と呼ばれることもあります。近年は、亡くなる前に戒名を授かる「生前戒名」を選ぶ人も増えています。
縁起がよいとされるほか、終活の一環として家族に負担をかけないように準備する意味もあります。生前戒名を希望する場合は、まず菩提寺に相談し、どの程度のお布施を収めるかを確認することが大切です。
戒名に使わないとされる文字
戒名には避けるべき文字があるとされます。代表的なのが「三除の法」と「二箇の大事」です。
三除の法
| 区分 | 説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 奇怪な難字 | 読み書きが難しい字 | 珍しい旧字など |
| 無詮の空字 | 意味を持たない字 | 於、乃、也、但 など |
| 不穏の異字 | 不安や不快を連想させる字 | 争、恥、悩、敵、狂、病 など |
二箇の大事
| 区分 | 説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 動物を表す字 | 一般的な動物は不適切。ただし吉祥とされるものは例外 | 牛、馬、猿、蛇、蛙、犬、猫(例外:鶴、龍、鳳、亀 など) |
| 宗派の開祖や高僧 | 各宗派の祖師や歴代本山の戒名と重なるのを避ける | 日蓮、道元、法然、最澄、空海 など |
| 年号・天皇の尊号 | 戒名にふさわしくない格式を持つ | 明治、大正、昭和、平成/崇道、春日宮 など |
これらは戒名の品位や尊厳を保つために避けられてきた文字です。宗派によって解釈に多少の違いはあるものの、基本的にはどのお寺でも共通して配慮される決まりです。
戒名の構成要素
戒名にはいくつかの要素が組み合わされており、その組み合わせによって全体の長さや印象、さらには費用感にも影響します。宗派ごとに多少の違いはあるものの、基本的な構成は共通しています。ここでは、戒名の構成要素と子どもに用いられる位号について解説します。
院号|位の高い人物に付けられる尊称
「院号」は戒名の先端に付けられる部分で「〇〇院」という形をとります。寺院や社会への貢献が大きかった人に授けられる尊称で、基本的に一般の戒名には付きません。さらに上位には「院殿号(〇〇院殿)」があり、歴史的には天皇や大名など高い身分の人物に限られていました。
現代でも院号や院殿号が付くと文字数が増えるため、格が高い戒名として扱われます。
同号|仏弟子としての立場を示す部分
「同号」は戒名の二番目に置かれる要素で、多くの場合2文字で構成されます。悟りを開いた人や人格を表す意味を持ち、故人の人柄や特徴にちなんだ字が選ばれることもあります。いわば戒名の別名のような役割を果たす部分です。
宗派によっては同号を付けない場合もあり、子どもの戒名にも通常含めません。
戒名|故人に授けられる本来の名前の部分
「戒名」は本来、仏弟子となった証として授けられる二文字の名前を指します。現在では院号や同号、位号を含めた全体を「戒名」と呼ぶのが一般的ですが、厳密にはこの部分だけが戒名にあたります。
俗名から一文字と仏典や尊敬する人物の名から一文字取って組み合わせることが多く、宗派によっては特定の文字を付ける決まりもあります。
位号|戒名のランクを示す部分
「位号」は戒名の末尾に位置し、現代でいう「様」に近い敬称の役割を持ちます。同時に仏教徒としての位や功績を示す要素でもあり、寺院への貢献度や信仰心によって付けられる称号が変わります。男女で名称が異なり、男性には「士」女性には「女」といった字が付きます。
最も多いのは「信士」「信女」ですが、上位には「居士」「大姉」さらに高位には「院居士」などがあります。
子供の位号
未成年で亡くなった子供には、大人とは異なる位号が用いられます。主な内容は以下の通りです。
| 年齢 | 男の子の位号 | 女の子の位号 |
|---|---|---|
| 死産 | 水子 | 水子 |
| 5歳以下 | 幼児・嬰児・孩児 | 幼女・嬰女・孩女 |
| 15歳以下 | 童子・大童子・禅童子 | 童女・大童女・禅童女 |
これらは一般的な呼び方であり、地域や宗派によって表記に違いがある場合もあります。また、未成年でも「信士」「信女」が与えられるケースもあります。
位号のランク
いわゆる戒名のランクと呼ばれる部分は、戒名の最後につく「位号」です。位号は、仏弟子としての立場や社会的な浄化、信仰心の深さなどを表す要素とされています。ここでは、代表的な位号の種類とその意味について解説します。
信士・信女
「信士(しんじ)」「信女(しんにょ)」は、最も一般的な位号です。仏教に帰依した在家信者に与えられる称号で、戒名の末尾に付けられます。
男性には「信士」女性には「信女」が用いられ、さらに頭に「清」を付けて「清信士」「清信女」とすることもあり、この「清」には煩悩にとらわれず正しい信仰を持つという意味があります。浄土真宗では同等の位号を「釋(しゃく)」「釋尼(しゃくに)」と呼んでいます。
居士・大姉
「居士(こじ)」「大姉(だいし)」は、在家でありながら特に篤く、社会的にも尊敬を集めた人に与えられる位号です。
男性には「居士」女性には「大姉」が用いられます。場合によっては「大居士」といった形で表されることもあり、信士・信女よりも高い位置づけとされています。宗派によっては対応する独自の呼び名を用いる場合もあります。
院信士・院信女
「院信士(いんしんじ)」「院信女(いんしんにょ)」は、基本の位号「信士」「信女」に院号が加わった形です。戒名の冒頭に「〇〇院」がおかれ、末尾に「信士」「信女」が続きます。かつては身分の高い人にしか授けられない称号とされており、現在でも特別な位号です。
院居士・院大姉
「院居士(いんこじ)」「院大姉(いんだいし)」は「居士」「大姉」に院号を組み合わせたものです。形式としては「〇〇院〜居士・大姉」となり、戒名の中でも高位に位置づけられています。
歴史的には、寺院に大きく貢献した人や地位の高い人物に授けられることが多く、今でも格式のある戒名として扱われています。
位号ごとのお布施の相場
戒名を授かる際には、菩提寺の住職にお布施(戒名料)を収める必要があります。明確な金額設定はなく、地域やお寺との関係によっても変わります。ここでは位号ごとのお布施の相場について解説します。
信士・信女
「信士」「信女」を付けてもらう際にかかるお布施の相場は10〜50万円程度とされています。あくまでも相場であり「無理のない範囲で感謝を伝えること」が最も大切です。地域によっても差があるため、金額で迷った場合は葬儀社のスタッフに相談してみるといいでしょう。
居士・大姉
「居士」「大姉」の相場は50〜80万円程度とされています。信士・信女よりも高額になりますが、金額の大小だけで位号が決まるわけではありません。寺院への日ごろの関わりや、家の事情も考慮されるため、相場はあくまで参考程度に捉えることが大切です。
院居士・院大姉・院信士・院信女
「院号」が付く戒名のお布施は50〜100万円以上となることが多く、高額になります。特別な格式を伴うため、希望する場合には住職としっかり相談する必要があります。先祖代々の位号との兼ね合いを考えることもあり、必ずしも相場どおりに決まるわけではありません。
宗派別に見る戒名の付け方
戒名の基本的な構成は共通していますが、宗派によって呼び方やつけ方に違いがあります。そのため同じ戒名でも表現や構成に違いが見られることがあります。ここでは、代表的な宗派ごとの戒名の付け方について解説します。
浄土宗|道号の代わりに「誉号」を用いる
浄土宗では、戒名の真ん中あたりに入る「道号」の代わりに「誉号(よごう)」を付けます。文字としては「誉」や旧字の「譽」を使うのが一般的で「院号+誉号+戒名+位号」という並びになります。位牌に刻むときに、阿弥陀如来を示す梵字を添えることもあります。
真言宗|戒名の冒頭に「アの梵字」を入れる
真言宗では、戒名の最初に「ア」の梵字を置くのが大きな特徴です。この「ア」は大日如来を表し、仏弟子になった証とされます。
子供の場合には地蔵菩薩を意味する梵字を用いることもあり、年齢や状況によって柔軟に変わるのも真言宗ならではです。その後は「院号+道号+戒名+位号」という流れで付けられます。
天台宗|基本構成に加え梵字を刻む場合もある
天台宗は、基本的には「院号+道号+戒名+位号」という一般的な形を取ります。ただし、戒名の冒頭に大日如来を表す「ア」や阿弥陀仏を示す「キリーク」の梵字を添えるケースもあります。梵字を加えるかどうかは寺院ごとの判断によるため、同じ天台宗でも戒名に違いが出ることがあります。
禅宗(曹洞宗・臨済宗)|「新帰元」や「空」を用いる
曹洞宗や臨済宗では、基本の形は変わらず「院号+道号+戒名+位号」ですが、戒名や位牌に特徴的な言葉が入ることがあります。たとえば、白木位牌に「新帰元」を記して「現世を終え仏の世界に帰る」意味を表したり「空」という字を冠して禅宗の思想である「諸行無常」を示したりします。
浄土真宗|「法名」と呼び位号を用いない
浄土真宗では「戒名」という言葉を使わず「法名(ほうみょう)」と呼びます。構成は「院号+釋号+法号」となり、位号を付けないのが特徴です。これは「阿弥陀如来の前ではみな平等」という浄土真宗の教えに基づくものです。
男性は「釋(しゃく)」女性は「釋尼(しゃくに)」を付け、お釈迦様の弟子であることを示します。
日蓮宗|戒名の代わりに「日号」を付ける
日蓮宗では、戒名の部分に「日」の字を入れる独自の形式を取ります。これを「日号(にちごう)」といい「日+俗名の一文字」を組み合わせるのが一般的です。弟子であることを「日」の字で表し、日蓮聖人の教えを継承していることを示す形になっています。
戒名のランクに関するよくある質問
戒名の必要性やつけ方は、疑問や不安を感じやすい部分です。ここでは戒名に関する、4つのよくある質問に答えていきます。
戒名は必ず必要?
仏式の葬儀においては戒名を付けることが前提となっています。戒名がなければ葬儀や納骨を受け付けない寺院もあるためです。
一方で、無宗教葬なら俗名(生前の名前)のまま葬儀を行うことも可能です。神道やキリスト教の葬儀では、そもそも戒名は用いません。
ただし、仏式以外を選ぶ場合は、納骨先の墓地が宗派不問かどうかを確認する必要があります。公営墓地や永大供養墓であれば俗名でも問題ないケースがほとんどです。
戒名を付けない場合の注意点は?
菩提寺にお墓がある方は注意が必要です。菩提寺の規定により、戒名がないと納骨できないとしているケースが多いためです。さらに、戒名がなければ子孫がお墓に入れないなど将来的なトラブルが起こる可能性もゼロではありません。
菩提寺が未定の場合は、俗名で葬儀を行い、四十九日までに正式な戒名を授かる方法があります。なお、戒名は付け直すことも可能ですが、四十九日を過ぎると位牌や墓石を作り直す必要があり、費用が増えるリスクがあります。
戒名は自分で考えても大丈夫?
戒名は自分で考えること自体は可能ですが、菩提寺がある場合は必ず相談してからにしましょう。宗派や寺院ごとに付け方のルールがあり、勝手に作った戒名は認められない可能性があります。
ただし、無宗教葬や新たに墓を建てる場合など、宗派に縛られない葬儀であれば自分で考えた戒名を使っても問題ありません。
戒名は亡くなる前に付けてもらえるって本当?
戒名は亡くなる前に付けてもらうこともできます。これを「生前戒名」と呼び、終活などでつけてもらう人も少なくありません。
仏教では縁起がよいとされており、生前に葬儀や供養の準備を整える行為は「預修(よしゅ)」「逆修(ぎゃくしゅう)」といい、大きな功徳を得られると考えられてきました。
また、自分が望む文字を取り入れてもらったり、費用も事前に確認できたりするため安心です。亡くなってバタバタしている中でつけてもらうこともないため、遺族の負担も減らせます。さらに、生前のうちに位牌を作ることも可能です。
戒名とランクの意味を踏まえて、故人にふさわしい供養をしよう
戒名は仏弟子となった証であり、位号や院号によるランクが存在します。お布施の相場や宗派ごとの呼び方の違いもあり一見複雑に感じるかもしれません。しかし、本来、戒名は故人を敬い極楽浄土へ導くために授けられるものです。
形式や金額にとらわれることなく、故人にふさわしい供養をどう整えるかが大切です。宗派の教えや菩提寺の方針を確認し、家族としっかり話し合ったうえで納得のいく戒名を付けてもらいましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国一律価格でご提供しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。
また、菩提寺がない方に、全国一律価格でお坊さんをご手配しております。戒名代やお車代も含めた価格ですので、安心ください。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。