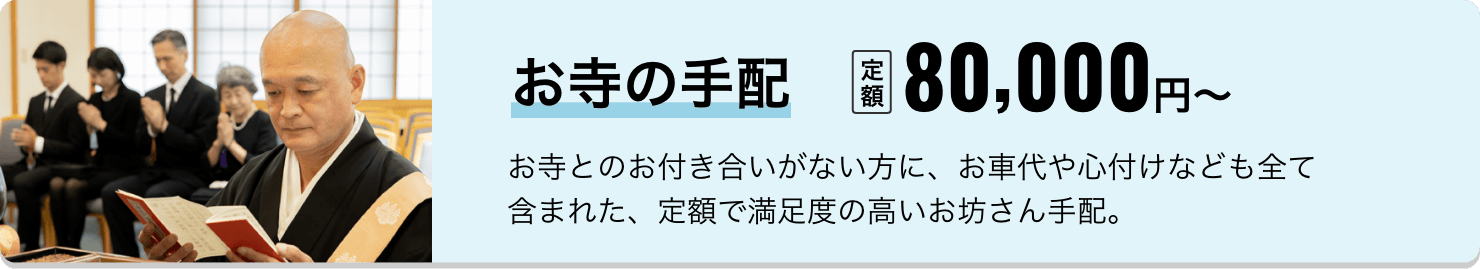さまざまな行事の日取りを決める際、参考にされることが多いのが仏滅や大安などの「六曜」です。誰もが一度は聞いたことがあるほど、日本では広くなじみのある考え方といえるでしょう。そこで気になるのが、仏式葬儀と六曜の関係性です。
「仏滅に葬儀をしてはいけないのではないか」と不安に思う方もいるのではないでしょうか。この記事では、六曜の意味や仏式葬儀とのかかわり、宗教ごとの考え方、さらに日程を決めるうえで優先すべきことについて解説していきます。
この記事を要約すると
- 仏滅の日にお葬式行うことは問題ありません。結婚式や開業などのお祝い事は避けられることが多いですが、葬儀は仏滅に行っても大丈夫です。
- 六曜において葬儀を行ってはいけない日は特にありません。六曜は中国の考え方で、仏教の教えには含まれていないため、仏滅や大安に葬儀を行うことも問題ありません。
- 葬儀の日程を決める際に優先すべきことは、火葬場の利用状況や休業日です。友引に火葬すること自体は問題ありませんが、多くの火葬場が友引の日を休業日としているため、注意が必要です。また、僧侶や参列者が集まりやすい日程を優先することをおすすめします。
【結論】仏滅の日に葬儀を執り行っても問題はない
仏滅は「仏も滅する」といわれるほど不吉な日とされ、結婚式や開業といった祝い事では避けられることが多い日です。そのため、葬儀も行ってはいけないのではないかと心配される方がいます。しかし実際には、仏滅と葬儀には直接の関係はありません。
仏教の教えに六曜は含まれておらず、宗派によっては六曜の考え方自体を否定している例もあるほどです。さらに火葬場や式場も仏滅を理由に休業することはなく、ほかの日と変わらず葬儀を執り行えます。仏滅であることを理由に日程を変える必要はありません。
仏滅や友引などを含む「六曜」の考え方
六曜(ろくよう)とは、その日の吉凶を占うために用いられてきた暦注のひとつです。もともとは中国で考えられ、日本には鎌倉時代から室町時代に伝わったとされています。現代では冠婚葬祭の日取りを決める際によく参考にされ、一般的なカレンダーにも記載されています。
六曜には全部で6種類の区分があり、日ごとに順番で巡る仕組みです。1週間は7日であるため、少しずつずれていくのも特徴といえるでしょう。ここでは、それぞれの六曜がどのような意味を持つのかを解説します。
先勝|午前は吉、午後は凶とされる
先勝(せんしょう・さきがち)は「先んずれば勝ち」という意味を持ち、物事を急いで行うほうが良い日とされています。
午前中は吉、午後2時から6時頃までは凶とされるのが一般的です。葬儀に関しては、午前中に執り行うことが好まれる地域もありますが、全国的な習慣というより一部の解釈にとどまります。
友引|吉事に適するとされる日
友引(ともびき)は、もともと「共引」と書かれ、勝負ごとに決着がつかず引き分けに終わる日を意味していました。そのため、吉事を行うには縁起が良いとされ、結婚式などに選ばれることもあります。時間帯は朝が吉、正午前後が凶、午後は大吉とされています。
葬儀に関連して特別な意味合いが語られることもありますが、本来はあくまで日の吉凶を占う考え方のひとつです。
先負|午前は凶、午後は吉とされる
先負(せんぷ・さきまけ)は「先んずれば負け」という意味を持ち、勝負事や急ぎの行動を避けるほうがよいとされる日です。午前中は凶で午後が吉とされています。
葬儀においては、午後からお通夜や告別式を行う方が縁起が良いと考えられる地域もありますが、実際には日程調整の都合が優先されるケースがほとんどです。
仏滅|最も凶とされるが実害はない
仏滅(ぶつめつ)は「仏も滅する凶日」という意味で、六曜の中で最も不吉とされます。祝い事を避ける日とされる一方で、葬儀には不都合がないと考えられています。実際には仏教とは無関係であり、字面の印象から嫌われているにすぎません。
そのため、仏滅に葬儀を行っても問題はなく、火葬場や式場も通常どおり利用できます。
大安|すべてに吉とされる日
大安(たいあん)は「大いに安し」を意味し、何をするにも良いとされる最良の日です。結婚式など慶事に選ばれることが多く「大安吉日」という言葉でも知られています。葬儀に関しても執り行うこと自体に禁忌はなく、予定どおり行って差し支えありません。
ただし、あまりにお祝いの印象が強いため「葬儀には場違い」と感じる人もいるため、地域の参列者の意識には配慮が必要です。
赤口|正午前後だけ吉とされる
赤口(しゃっこう・せきぐち)は凶日とされ、特に祝い事には不向きといわれています。「赤」の字から火事や血を連想させるため、火や刃物に注意すべき日ともされています。正午午前のみ吉で、それ以外の時間帯は凶です。
葬儀との関わりで特に避ける必要はないものの、午前や夕方を選ぶ場合には一部で縁起を気にする声もあります。
各宗教と六曜の関係
六曜は本来、宗教的な儀式から生まれたものではなく、暦の上で吉凶を占う考え方です。しかし、日本では仏教や神道の儀式と結び付けて意識される場面が多く、宗教によって受け止め方や位置づけが異なります。ここでは、仏教・神道・キリスト教それぞれにおける六曜との関係について解説します。
仏教における六曜の考え方
仏教と六曜の関係性について前述しましたが、実は仏教そのものと六曜には本来つながりがありません。たとえば浄土真宗では、六曜を理由に葬儀日を避ける考え方を明確に否定しています。宗派を問わず、仏教行事は六曜と無関係に営まれるのが基本です。
ただし日本では六曜を意識する人が多いため、特に友引の日をわざわざ選んで葬儀を行うことは少なく、習慣として避けられる傾向は残っています。
神道における六曜の考え方
神道も六曜とは直接の関係はありません。しかし地域の習慣から、友引を避けて葬儀を行うことが多いのが実情です。一方で、鎮魂祭や七五三、お宮参りなどの祭祀では、大安や先勝といった六曜を吉日として選ぶことも珍しくありません。
宗教的な教えではなく、あくまで世間の風習として六曜が取り入れられていると考えられます。
キリスト教における六曜の考え方
キリスト教は西洋由来の宗教であり、六曜との結びつきは全くありません。そのため、教会での葬儀やミサに六曜が影響することはありません。ただし日本では火葬場が友引に休業する地域が多く、結果としてその日程を選べない場合があります。
またカトリック教会などの一部教派では「聖土曜日(イースター前日)」に葬儀を行えないといった、独自の宗教的制約が存在します。
地域によっては「友引」の葬儀を避ける考え方もある
友引の日に葬儀を行うこと自体に決まりはなく、法律的・宗教的に禁じられているわけではありません。
しかし現実には、友引に葬儀を避ける地域が多く存在します。その背景には2つの理由があります。1つは「友を冥土に引く」という意味合いが広まったことで、縁起を気にする人々に敬遠されてきた点です。
参列者や親族の気持ちに配慮し、あえて友引を選ばない傾向が今も残っています。もう1つは物理的な事情です。
全国の多くの火葬場は友引を休業日に設定しており、実際に葬儀を組めないケースが少なくありません。これは「友を引く」という習慣が広まったことに合わせ、施設側が定休日としたことが理由です。
そのため、友引を気にせず葬儀を行いたい場合でも、火葬場の稼働状況を確認する必要があります。お通夜については友引でも行えますが、告別式は調整が難しいため、あらかじめ地域の火葬場や関係者と相談して日程を決めることが重要です。
葬儀日程を決めるときに優先すべきこと
葬儀日程を決める際に、仏滅だからといって特別に避ける必要はありません。ただし、葬儀そのものは家族や関係者にとって大切な儀式であり、日取りの判断を誤ると不都合が生じかねません。適切な配慮を行いながら判断することが重要です。
ここでは、日程の調整で失敗しないために押さえておきたい視点について解説します。
火葬場の利用状況や休場日
日本の葬儀はほとんどが火葬を伴うため、火葬場の予約状況を確認する必要があります。多くの火葬場は「友引」を休場日にしており、翌日は予約が集中する傾向があります。
まずは葬儀社に連絡し、希望日で火葬炉が確保できるか確認しましょう。都市部では数日先まで埋まることもあるため、早めの調整が欠かせません。
式場や僧侶の予定
火葬場の枠が取れたら、次は式場と僧侶の予定を確認します。菩提寺がある場合は、喪主が直接住職に電話して日程を打診するのが基本です。希望日が合わない場合は、他の僧侶を紹介してもらえるか尋ねましょう。
菩提寺がない場合は、葬儀社に僧侶の手配を依頼するのが一般的です。セレモニーホールについても同様に、空きがあるかを葬儀社に確認し、火葬場との調整を同時に進める必要があります。
【菩提寺とは】
菩提寺(ぼだいじ)とは、先祖代々の供養や葬儀をお願いしてきた家と縁の深いお寺のことです。家族の墓がある寺院を指す場合が多く、葬儀や法事の際には読経を依頼する中心的な存在となります。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、菩提寺がない方に、全国一律価格でお坊さんのご手配を承っております。御車代や戒名代も含めたお布施となっておりますので、安心してご依頼ください。
参列者が集まりやすい日程
葬儀は家族だけでなく、多くの親族や縁の深い人々が集まる儀式です。できるだけ多くの参列者が来やすい日程を考慮することが大切です。
まずは近親者(両親、兄弟姉妹)に電話で連絡し、移動に必要な時間や仕事の調整が可能かを確認します。その後、遠方の親族や特に参列を望む親しい人へ順に連絡しましょう。
急な連絡では予定を調整できない場合もあるため、可能な限り早く情報を伝えることが重要です。連絡時には「通夜は〇日、告別式は〇日を予定しています。ご都合はいかがでしょうか」と具体的に伝えると相手も判断しやすくなります。
遺族の意向や希望
参列者の予定を確認するだけでなく、何よりも遺族の気持ちを最優先にします。「できるだけ早く送りたい」「親族が揃ってからみんなで送り出したい」など、家族ごとに思いは異なります。喪主はまず配偶者や子どもたちに希望を聞き、そのうえで兄弟姉妹や親族の意見を調整するとよいでしょう。
全員の意見を揃えることは難しくても、中心となる家族が納得できる形で日程を決めることが大切です。
地域に根付いた慣習や風習
葬儀には地域ごとの習わしも影響します。たとえば、亡くなった当日にお通夜を行う地域、先に火葬を済ませて骨葬とする地域など、地方によって大きな違いがあります。喪主一人で判断せず、地元の親族や近隣住民、葬儀社に「この地域ではどうするのが一般的か」を確認してみましょう。
また、手伝いに来てくれる人が多い地域では、近隣の方の都合も尊重することが望まれます。地域の風習に合わせることで、周囲に違和感を与えずに故人を送り出せます。
仏滅と葬儀の関係に関するよくある質問
仏滅と葬儀の関係について基本的な考え方を解説してきましたが、日程を決めるうえでまだ疑問に思うことや不安があるという方もいるのではないでしょうか。ここでは、葬儀にまつわる日取りや習慣に関して、よく寄せられる質問に答えていきます。
仏滅以外で葬儀を行ってはいけない日はある?
葬儀をしてはいけない日というものはありません。仏滅であっても支障はなく、絶対に避けなければならない日は存在しません。ただし、友引は「友を冥土に引く」と連想されるため、縁起を気にして避ける方が多いのも事実です。
また、年末年始は火葬場の休業日が重なり、物理的に葬儀が行えないこともあります。特に正月三が日は火葬場が閉まっており、参列者も集まりにくいため三が日明けに執り行われるのが一般的です。
ただし、近年は密葬や家族葬といった小規模な葬儀を選択する人も増えており、年末年始に関係なく執り行われることもあります。
仏滅や大安で葬儀費用は変わる?
六曜によって葬儀費用が変わることはありません。仏滅や大安といった日の吉凶が料金に影響することはなく、葬儀社の基本料金や式場・火葬場の使用料は暦に関わらず同じです。
結婚式場では「仏滅割引」といった料金設定が見られる場合がありますが、葬儀ではそうした割引制度は一般的にありません。費用はあくまで規模やプラン、利用する施設の条件によって決まるため、六曜は料金に無関係と考えて問題ありません。
仏滅に行ってはいけない行事は?
仏滅は「仏も滅する」とされ、祝い事や新しい始まりを避ける日と考えられてきました。そのため、以下のような行事は敬遠されがちです。
- お祝い品の贈呈
- 結婚式や入籍
- 納車や不動産契約
ただし、これらは絶対に禁止されているわけではなく、本人や家族が気にしなければ問題はありません。一方でお通夜や葬儀、お墓参り、厄払いなどの弔事や厄除けの行事は仏滅でも問題ありません。むしろ仏滅を「悪縁を断ち切る日」として、新しい生活のスタートに活かす人もいます。
法事をやってはいけない日はある?
法事を「やってはいけない日」は基本的にありません。六曜は仏教の教えとは無関係であり、仏教儀式である法事の実施に支障はありません。
ただし、友引を避けるなど縁起を気にする人も一定数いるため、日程を決める際には遺族の意見や地域の風習を尊重することが望ましいです。
また年末年始は寺院やその他施設が休業となる場合があるため、現実的に日程が組めないこともあります。最終的には、参列者の都合や菩提寺の予定を踏まえて調整し、全員が納得できる形で執り行うことが大切です。
仏滅よりも大切なのは家族の想い、納得のいく葬儀を執り行おう
六曜はもともと中国の暦注であり、仏教の教えや葬儀そのものとは直接の関係がありません。そのため、仏滅の日に葬儀を行っても問題はなく、宗教的にも実務的にも差し支えはありません。ただし、友引は縁起を理由に避けられたり、火葬場が休業日になるなど現実的な制約がある場合があります。
大切なのは六曜にとらわれすぎることではなく、家族の思いや参列者の都合を尊重しながら納得できる日程を選ぶことです。火葬場や式場の状況を確認し、親族や菩提寺と話し合って日程を調整してみましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国一律価格で全国にご提供しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。