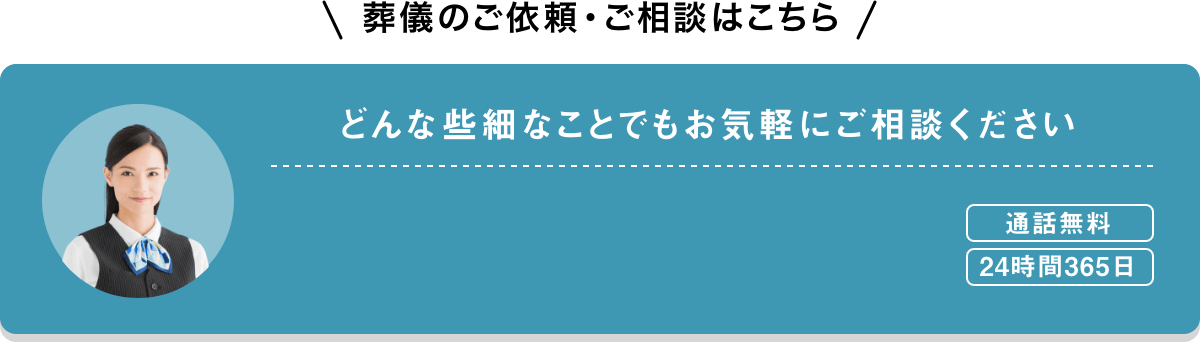故人の親戚やとくに親しかった相手のみを招いて小規模な式を執り行う家族葬は、近年人気を集めている葬儀形式です。参列者を限定する家族葬では、親戚であっても呼ぶかどうか迷うシーンがあるのではないでしょうか。
今回は、家族葬に誰を招くか迷っている方向けに、葬儀に招く親戚の基準や、呼ばない選択をした親戚に対する対応方法をわかりやすく解説します。今後の円滑な親戚付き合いのためにも、参列をお断りした相手には誠意のある対応をすることが大切です。
この記事を要約すると
- 一般的に親族やごく親しかった人のみを招く家族葬ですが、参列者の基準はとくに定まっていません。そのため、故人の親戚であっても葬儀に呼ばないケースが珍しくありません。
- 葬儀に呼ぶかどうか判断に迷う親戚がいる場合、故人との生前の付き合いの深さや遺族との関係性から総合的に判断しましょう。故人が生前に意向を固めていた場合は、それに従います。
- 葬儀に呼ばなかった親戚に対しては、後のトラブルや関係悪化を防ぐためにも、誠意のある対応が求められます。参列をお断りした背景を丁寧に説明したうえで、一言お詫びを入れましょう。
家族葬とは?
家族葬とは、ごく親しい親族や故人と深い関係にあった相手のみで行う小規模な葬儀の形です。参列人数にとくに決まりはありませんが、おおよそ10〜30人程度が相場です。
家族葬は一般葬に比べて参列者が少なく、静かで落ち着いた空間でお別れができることから、故人の生前の意向や遺族の希望を尊重できる形式として近年人気を集めています。
家族葬に親戚を呼ばないのはOK?
結論からいうと、家族葬では、故人との血縁がある親戚を呼ばなくてもまったく問題ありません。「家族葬」と名前はついていますが、実際には参列する条件に決まりはなく、故人や遺族の判断で参列者を決定できます。
そのため、親戚であっても参列しないケースや、血縁関係はなくても生前深い親交があったことで参列するケースがあります。
家族葬に呼ぶ親戚の範囲
家族葬で親戚をどこまで呼ぶかに明確な決まりはありませんが、一般的には3親等以内の親族が1つの基準とされています。3親等には、故人の父母・子どものほか、兄弟姉妹・祖父母・孫などが含まれます。これはあくまで目安のため、故人や遺族との生前の付き合いの深さを優先してかまいません。
家族葬に呼ぶ親戚の判断方法
家族葬に呼ぶか呼ばないか迷う親戚がいる場合は、故人の遺志や遺族との関係性などを考慮したうえで判断しましょう。
故人の遺志を尊重する
家族葬で誰を招くかを決める際に、もっとも重要なのが故人の遺志です。近年は、終活として故人が生前に参列者を決めている場合や、エンディングノートに意向をまとめているケースが珍しくありません。このような場合は、遺族の意向よりも、故人の生前の希望が優先されます。
故人との生前の関わりの深さを考慮する
葬儀に呼ぶかどうか判断に迷う相手がいた場合は、故人との生前の関わりの深さを考慮しましょう。同居していた・頻繁に交流していたなど、故人とのつながりが深かった親戚は葬儀に参列するのが一般的です。一方、疎遠でほとんど付き合いのなかった親戚については、無理に声をかける必要はありません。
故人との血の繋がりから判断する
呼ぶかどうかの判断に迷った場合、血縁関係を目安にするのもひとつの方法です。一般的には、兄弟姉妹・甥姪・祖父母などの3親等までの親族は、声を掛ける範囲とされています。血縁関係を基準に線引きをすれば、親族間でのトラブルや誤解を招きにくいといえるでしょう。
葬儀の規模に合わせて調整する
家族葬を行う際は、スペースや予算の都合上、事前に斎場の収容人数を把握したうえで参列人数を調整する必要があります。あらかじめ参列する人数を決めてから、誰を招くかを考えると判断がスムーズです。
判断に迷った場合は「呼ぶ」を選択
さまざまな事情を鑑みたうえでも、なお判断に迷うケースも考えられます。呼ぶかどうか決めきれない場合は、できるだけ呼ぶ方向で考えるのが無難でしょう。
葬儀に招かなかったことで後日トラブルになるよりも、参列を打診したうえで断られた方が関係性に悪影響を与えません。また、故人の葬儀をきっかけに、関わりが深まる可能性もあります。
家族葬に親戚を呼ばないメリット
家族葬に親戚を呼ばないことで、遺族と親戚双方の負担を軽減できることが大きなメリットです。ここでは、家族葬に親戚を呼ばないメリットを解説します。
親戚への接待や対応の手間がかからない
葬儀の参列者を限定することで、受付・香典・料理の用意・返礼品の準備などにかかる手間を大幅に軽減できます。
葬儀準備から当日の対応、葬儀後の整理までの一連の流れが簡略化されるため、結果的に葬儀全体の準備がスムーズになり、遺族の気持ちにも余裕が生まれるでしょう。
親しい人だけで静かにお別れできる
限られた家族や近親者、故人と親しかった友人のみで構成された式にすることで、アットホームで温かい空間を作り上げることができます。
古典的な葬儀形式にとらわれることがなく、故人との思い出を共有しながらゆっくりとお別れの時間を持てるでしょう。遺族が心の整理をつけやすいという点も、家族葬のメリットのひとつです。
葬儀費用を抑えられる
参列者数が少なければ、そのぶん斎場使用料・飲食接待費・返礼品費などの葬儀にかかる一式の費用を安く抑えられます。
一般葬の葬儀費用の相場は100〜200万円ですが、家族葬は30〜100万円と、かなり安上がりといえるでしょう。遺族の金銭的な負担を軽減できるのも、家族葬の魅力です。
遠方に住む親戚や高齢の親戚に負担がかからない
故人の親族のなかには、遠方に住んでいて訪問に手間がかかる方や足腰に不安がある高齢者がいることも考えられます。このような事情を抱える親族の移動や体力的な負担を考えた結果、参列者を限定できる家族葬を選択するケースも珍しくありません。
家族葬に親戚を呼ばないデメリット
家族葬の参列者を限定することにはさまざまなメリットがありますが、一方でいくつかデメリットも考えられます。
葬儀前後の連絡の手間がかかる
葬儀に招かない親戚には、訃報と合わせて参列をお断りする旨を伝えたり、葬儀終了後に事後報告をしたりする必要があります。こちらから参列をお断りするという経緯から、連絡をするのに気が重く感じるかもしれません。また、相手に不信感を与えないためにも、丁寧な事情の説明が求められます。
葬儀のときに人手が足りなくなる
家族葬の参列者が少ないと、受付・車での移動・僧侶への接待などの業務を少人数の遺族でこなさなければならず、人手不足になる可能性があります。
とくに、自宅を会場にする場合や火葬場への移動距離が長い場合など、力仕事が多く発生するケースでは、呼んでおけばよかったと思うかもしれません。集まる人数が少ない場合は、事前に事情を葬儀社に伝えておき、適宜協力を仰ぎましょう。
香典収入が減少する
葬儀の参列者数が少ないと、そのぶん香典収入も減少します。とくに、相場の高い血縁家族や年齢の高い親族の香典を得られないとなると、金銭的な負担が増えることが予想されます。参列人数を限定する場合は、香典収入がいくらになりそうかを事前に計算しておくと安心です。
葬儀後の弔問対応が増える
家族葬の参列者を限定すると、呼ばれなかった親戚が後日弔問を希望することが多くなります。弔問を辞退する場合は申し出をお断りしてもかまいませんが、できるだけ対応する方がよい印象を与えられるでしょう。
複数の親戚が葬儀後に自宅に訪れるとなると、対応する遺族や返礼品の用意などの負担が増えるというデメリットがあります。
親戚間でトラブルになる可能性がある
親戚間で葬儀に呼ぶ相手と呼ばない相手が分かれる場合、後にトラブルや不信感を招く可能性があります。とくに親族内で訃報を伝えるタイミングがずれたり、参列をお願いした親戚が招いていない親戚に葬儀情報を漏らしてしまったりすると、混乱が起こるかもしれません。親戚付き合いは今後も長く続くため、相手に合わせて適切な対応を行うことが求められます。
家族葬に呼ばない親戚への対応方法
家族葬に呼ばない親戚に対しては、失礼な印象を与えないよう、適切なタイミングでの丁寧な対応が必要です。
訃報を伝えると同時に参列をお断りする
参列をお断りする最も誠意のある伝え方は、訃報を伝えるときに合わせて参列を辞退する旨を伝える方法です。「故人の遺志により、ごく親しい親族のみで葬儀を執り行います」などと説明し、相手への理解を求めましょう。参列をお断りする場合は、訃報と参列や香典の対応状況のみを伝え、葬儀に関する情報は伏せておくのが一般的です。
葬儀を終えてから訃報を連絡する
葬儀前の負担を増やしたくない場合や、葬儀に関する詮索を避けたい場合は、家族葬を終えてから訃報を連絡する選択肢もあります。すでに葬儀を終えたことを伝えれば、参列に関するやり取りを避けられるため、相手に余計な気を遣わせることもありません。
ただし、事後報告による寂しさを感じさせることもあるため、「故人の遺志で静かに執り行いました」など、理由をきちんと伝える配慮が必要です。
香典や弔問の辞退も合わせて伝える
参列をお断りする場合は、香典や弔問も合わせて辞退するのが一般的です。「お気持ちだけ頂戴いたしますので、香典やお供え等はご遠慮ください」「失礼ではありますが、ご厚志やご弔問はご辞退申し上げます」といった表現で、丁寧に辞退の意向を伝えましょう。辞退する旨をはっきりと伝えることで、すれ違いや後日対応の手間を軽減できます。
葬儀社に相談する
親戚への対応に悩む場合や丁寧な断り方に不安がある場合は、葬儀社に相談するのも1つの方法です。葬儀社にはさまざまなケースに対応してきた実績があるため、適切な文例や対応方法を提案してもらえます。
また、訃報や案内状の作成サポートなども行ってくれる葬儀社もあるため、利用を希望する場合は申し出ましょう。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、家族葬に特化した葬儀サービスを全国に一律価格で提供しています。そのため家族葬の実績豊富ですので、ご不安な点ありましたら些細なことでも構いませんので、お気軽にお問い合わせください。
家族葬に呼ばない親戚への案内文の例
案内文をメールや手紙などの書面で送る際は、文中で句読点を用いないのが習わしです。句読点を用いらない代わりに、改行や空白などを活用して、読みやすい文章に仕上げましょう。
葬儀前に連絡する場合は、葬儀に関する情報は伏せ、亡くなった事実と香典・弔問の辞退のみを簡潔にまとめるのが一般的です。葬儀後に連絡する場合は、無事に葬儀を執り行った旨とともに、連絡が遅くなったことへのお詫びも添えると丁寧です。
葬儀前の場合
◯◯の娘の◯◯です
◯月◯日に 母の◯◯が永眠いたしました
葬儀は本人の生前の希望を尊重し 家族葬にてごく近親者のみで執り行います
誠に勝手ながら ご厚志 ご弔問の儀は 謹んでご辞退申し上げます
故人の冥福を祈りつつ 略儀ながらご報告申し上げます
葬儀後の場合
◯◯の娘の◯◯です
◯月◯日に 母の◯◯が永眠いたしました
葬儀は本人の生前の希望を尊重し 家族葬にてごく近親者のみで合済ませました
誠に勝手ながら ご厚志 ご弔問の儀は 謹んでご辞退申し上げます
ご報告が遅くなり恐縮ですが ◯◯様におかれましては 生前のご厚誼を賜り深く感謝申し上げます
故人の冥福を祈りつつ 略儀ながらご報告申し上げます
家族葬に親戚を呼ばないときの注意点
家族葬に招かない親戚がいる場合は、今後も滞りなくお付き合いを続けるためにも、誠意のある対応が求められます。
訃報をまったく伝えないのはNG
葬儀に招かない親戚に対して、訃報をまったく伝えないのは避けるべきです。ほかの親戚から又聞きで訃報を聞くことで不信感を持たれる可能性もあるため、必ず故人が亡くなった事実を直接知らせましょう。訃報を伝える際は、ごく近しい親族のみで葬儀を行う旨を丁寧に説明することが重要です。
参列をお願いする親戚に口止めする
一部の親戚のみを葬儀に招く場合は、ほかの親戚に知らせないよう口止めをしておく必要があります。呼ばなかった親戚に葬儀情報が漏れると、「なぜ自分は呼ばれなかったのか」と思われる可能性があるため注意が必要です。
葬儀案内の際には、「ほかの皆様には葬儀後にお知らせいたしますので、どうぞご内聞にお願い申し上げます」などと一言添えましょう。
呼ばなかった親戚へ配慮する
家族葬に招待しなかった親戚に対しては、訃報を伝える際になぜ呼ばなかったのかを丁寧に説明しましょう。斎場への距離や高齢、故人の意向などの正当な理由があれば、誠実に伝えることで相手の理解を得やすくなります。
また、誠意を伝えるためにも、参列をお断りしたことへのお詫びや故人との生前のお付き合いへの感謝を伝えることを忘れないでください。
呼ばなかった親戚から香典を受け取った場合も香典返しを用意する
参列をお断りした親戚から香典を受け取った場合は、香典辞退の有無に限らず香典返しを用意するのがマナーです。葬儀の後に受け取った場合でも、四十九日の忌明けのタイミングに合わせてお返しを送れるように準備しましょう。香典返しはいただいた金額の三分の一から半額を目安に、手元に残らない消え物を選ぶのが一般的です。
SNSで情報を公開しない
遺族の意向で葬儀に招かない親戚がいる場合、葬儀に関する情報が漏れないようにSNS上で情報を発信するのは避けましょう。SNSを通して葬儀に参列しなかった親戚や知人の目に触れることで、誤解やトラブルを招く可能性があります。訃報や葬儀について公開する場合は、個別に連絡するのが賢明です。
家族葬に呼ばれなかったときの対応方法
家族葬に呼ばれなかった場合は、状況に合わせて適切な対応をすることが大切です。訃報の連絡を受けた際は、まず遺族に対するお悔やみやお見舞いの気持ちを伝えましょう。「心中お察しいたします」「お悔やみ申し上げます」などといった言葉を手短に述べるのがポイントです。
香典や弔問などは、遺族の意向に沿って対応してください。遺族が香典や弔問を辞退している場合は、無理強いはせず、お悔やみの言葉のみにとどめるのがマナーです。自分が呼ばれなかった事情を理解し、誠実な対応を心がけることで、今後も良好な関係性を維持することができます。
家族葬に呼ぶか呼ばないかの判断は慎重に行いましょう
家族葬に呼ぶ親戚を決める際は、故人との生前の関わりの深さや遺族との関係性を考慮したうえで、慎重に判断することが求められます。参列をお断りする親戚に対しては、後にトラブルを招かないよう、丁寧に事情を説明しましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。