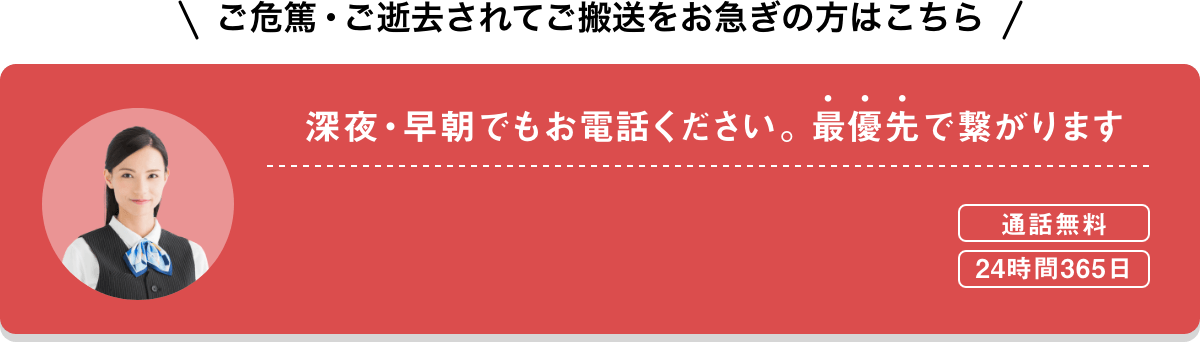身内の行動に対し異変を感じていたり、病状が思わしくなかったりして、もしかしたら死が近いのではと感じている方もいるのではないでしょうか。
死が近い人には、何らかの兆候が現れる場合があるとされます。家族にとっては辛いことですが、死のサインから目をそむけなければ、悔いのないよう最後の時間を大切に過ごせるでしょう。
本記事では、死が近い人の行動と、見た目や身体に現れる特徴について紹介します。本人に対して最後にしてあげられることや避けるべきこと、遺される家族に必要な準備もあわせて解説するので、ぜひお役立てください。
家族が余命宣告を受けた場合の心構えや準備について詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
この記事を要約すると
- 死が近い人には何らかの兆候が現れることがあります。人間関係の整理をしようとしたり、独り言や感謝の言葉を口にしたりするほか、手のひらを凝視するなど一見変わった行動を取ることもあるようです。
- 死の兆候は行動だけでなく、見た目や体臭の変化として現れることもあります。例えば、目の力がなくなって顔色が悪くなり、食事や排泄の量が減ることがあるとされます。
- 死の兆候がある人に対しては優しく接し、親戚や友人と最後のお別れを済ませてから家族そろって看取るのが大切です。万が一に備え、事前に葬儀社や葬儀プランを検討しておけば、家族の負担を緩和しつつ納得のいく葬儀を実施できるでしょう。
死が近い人には兆候がある?
死が近い人には、何らかの兆候が見られる場合があるとされます。
病院に入院している場合であれば、医師や看護師から危ない状態であると伝えられることもあるでしょう。しかしそうでない場合には、周囲の人間が予兆を素早く察知しなければなりません。
サインを見逃せば、亡くなった後になってから「最後に十分なことをしてあげられなかった」と後悔する可能性があります。最後の時間を悔いのないよう過ごすためにも、死の兆候を把握しておきましょう。
老衰の初期症状については、以下の記事で詳しく解説しています。
死が近い人に見られる5つの行動
死が近い人によく見られるとされる行動としては、次の5つが挙げられます。
- 物や人間関係の整理をする
- 感謝の言葉を口にする
- 手のひらを凝視する手鏡現象が起こる
- 独り言が増える
- 変わった行動を取るようになる
具体的に解説していきます。
物や人間関係の整理をする
死が近い人は、物や人間関係の整理を始めるようになるとされます。潜在的に死期を感じ取ることで、身綺麗にしてから旅立ちたいという思惑からこのような行動を取るようです。
具体的には、衣類や持ち物を整理し、部屋をきれいに片づけます。大切にしていた趣味のものを手放すこともあるようです。
疎遠になっていた人へ連絡を取ったり、遺産相続・遺言関係の準備を行ったりする場合もあります。友人・知人の連絡先やSNSアカウントの整理をすることもあるでしょう。
感謝の言葉を口にする
死が近い人には、周囲に感謝の言葉を口にする行動もよく見られます。死を前にすると、心が穏やかになり、周囲に対する感謝の気持ちが強まるようです。
家族や親しい友人に対して、普段であればなかなか素直に言えない「ありがとう」の言葉が自然と口をつくようになります。これまで気難しかった人でも、急に穏やかな雰囲気になる場合があるようです。仲たがい中の相手と仲直りしたがることもあるでしょう。
手のひらを凝視する手鏡現象が起こる
死が近い人は、手のひらを凝視する行動を取ることがあります。死へ向かう自身の変化を、手のひらを通して感じ取っているようです。
手鏡現象と呼ばれるこの行動は、死期が迫った人によく見られるとされます。本人は手のひらの色や形に異常を感じたり、手相がぼやけて見えたりするため手を凝視するようですが、周りの人は異常を感じられないようです。
独り言が増える
死期が迫った人は、独り言が増えるといわれています。ぶつぶつと何かをつぶやいているだけでなく、目に見えない誰かと会話をかわしているかのように感じられることもあるようです。
変わった行動を取るようになる
一見変わった行動を取るようになるのも、死期が迫った人にはよく見られる兆候です。雑念が払われて本来の姿を取り戻したり、霊的な存在を感じたりすることで、周囲からは理解しがたい行動をとることがあるようです。
例えば、やたらと窓を開けたがったり、普通の人には見えない何かが見えている様子で行動を取ったりするとされます。亡くなった人やペット、神様や仏様が見えるお迎え現象が起きているともいわれています。お迎え現象によって独り言が増えているケースもあるでしょう。
なかには性格ががらっと変わったような言動を取ることもあるようです。
ご紹介したような行動が見られると、「もしかして、最期が近いのではないか」と強い不安を感じる方も多いでしょう。
そのようなとき、何をしてあげるべきか、これからどのような準備が必要になるのかを、一人で判断するのは簡単なことではありません。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、ご家族の状況をお伺いしながら、今後の流れや、心構えとして知っておきたいことについてのご相談を承っています。
まだ何も決まっていない段階でも構いません。不安な気持ちを抱えたままにせず、必要であればお電話でご相談ください。
死が近い人の特徴は行動以外にも現れる
死が近い人の兆候は、以下のように行動以外の特徴として現れることもあります。
- 目の力が失われる
- 呼吸が大きくなる
- 肌が青白く見える
- 手足が冷たい
- 寝てばかりいる
- 食事と排泄の量が減少する
- 特徴的な体臭がする
- せん妄や意識の混濁が見られる場合がある
- 一時的に元気が戻る中治り(なかなおり)が起こる
それぞれ詳しく見ていきましょう。
目の力が失われる
死が近い人は、目の力が失われる傾向にあります。体力が削がれることで、顔の筋肉が衰えて目の周囲に力が入れられなくなるようです。目が落ち窪んだり濁ったりするため、表情が暗く見えるでしょう。
目を開けたまま眠ってしまい、傍から見ると目の焦点が合っていないように感じられる場合もあるとされます。人によっては目に涙を浮かべたり、突然目を見開いて周囲を驚かせたりすることもあるようです。
呼吸が大きくなる
死が迫っている人は、呼吸が大きくなることがあります。心肺機能や喉の筋肉の衰えから呼吸が困難になるためです。
自然な呼吸の機能が失われることで、顎をガクガクさせながらあえぐように呼吸する下顎呼吸(かがくこきゅう)を行うことがあります。また喉の奥で痰や唾液が溜まり、呼吸時にゴロゴロと音がする死前喘鳴(しぜんぜんめい)が起きる場合もあるでしょう。
一見すると苦しげに見えますが、脳内麻薬であるβ-エンドルフィンの効果で苦しさが麻痺し、本人はさほど苦しさを感じていないとされます。
肌が青白く見える
肌が青白く感じられるのも、死が近い人に見られる現象です。この現象は心肺機能の衰えによって体内の酸素量が不足し、血管が青紫色に見えるために起こります。
人によっては皮膚に斑点ができたり、爪が青みがかったりすることもあるようです。
手足が冷たい
死期が迫った人は手足が冷たく感じられることがあるようです。肌が青白く見える場合と同様に、血流悪化による酸素不足が原因で起こる現象です。
体温の低下が原因で手足が冷えているわけではないため、布団をかけても温まりにくいといわれています。重たい布団を重ねればかえって負担になる可能性があるため、優しくさすって血行をよくするほうが無難とされます。
寝てばかりいる
寝てばかりいるのも、死が近い人の兆候です。脳の働きが鈍り意識を保ちにくくなることで、昼夜を問わず寝ているようになります。無理に起こそうとすると負担になるため、寝かせてあげながら見守りましょう。
食事と排泄の量が減少する
死が近づくと、食事と水分の摂取量や、排泄量が減少することがあります。体力が失われることで物を飲み込む力が弱まり、自然と食事量が減っていくためです。
そもそも身体機能や活動量の低下からエネルギー消費量が減少するため、必要な飲食量も減少します。飲食量の減少や、心臓・腎臓の機能低下によって、それに伴う排泄量も減少していきます。体重も減少していくでしょう。
無理やり飲食をすすめたり点滴をしたりしても、栄養分や水分を吸収しにくい状態になっているため、かえって本人の負担になる可能性があります。医師と相談しながら、本人の食べたい物を少しだけ食べさせてあげましょう。
老衰で食事が摂れなくなった場合の対応については、以下の記事で詳しく解説しています。
特徴的な体臭がする
特徴的な体臭がするのも、死が近い人によくある兆候とされます。身体機能の低下によって独特の体臭や口臭になるようです。
例えば、線香の香りや飴のような甘い匂いが感じられることがあるようです。強烈な異臭を感じる場合もあるとされます。
せん妄(せんもう)や意識の混濁が見られる場合がある
死が近づくにつれ、せん妄や意識の混濁があるとされます。せん妄は、夢と現実を行ったり来たりするような状態です。脳機能の低下を発端に幻覚や妄想にとらわれることで、支離滅裂な会話をする可能性があるでしょう。感情の起伏が激しくなり、場合によっては奇声をあげることもあるとされます。
意識が混濁すれば、話しかけに応じなくなったり、会話の途中で寝てしまったりすることもあるようです。反応が薄い場合であっても、本人には会話の内容が届いていることが多いとされます。はっきりとした声で優しく話しかければ、伝わる可能性があるでしょう。
しかし会話は成立しにくくなるため、話し合っておきたいことがあるのであれば、意識の混濁が起こる前までに済ませておくのが無難です。
一時的に元気が戻る中治り(なかなおり)が起こる
死が近い人には中治りが起こる可能性があります。中治り(別名ラストラリー)は、あたかも病気や不調が治ったかのような現象が現れることを指します。中治りが起こる原因には脳内の神経伝達物質が関与しているという説がありますが、はっきりしたメカニズムはわかっていません。
中治りにより、これまで食欲がなかった人が急に食べられるようになったり、寝たきりだった人が急に起き上がれたりするケースもあるようです。
危篤から持ち直す可能性や臨終の兆候については、以下の記事で詳しく解説しています。
死が近い人にしてあげられること
死が近い兆候がある人に対しては、次のことをしてあげましょう。
- 親戚や友人に連絡を取る
- 優しく話しかける
- 家族の誰かがそばにいる
- 臨終の際には家族そろって看取る
詳しく解説していきます。
親戚や友人に連絡を取る
身内に死の兆候を感じるのであれば、早い段階から親戚や友人に連絡を取りましょう。連絡を後回しにしていると、二度と会えなくなってしまう可能性があります。連絡を受けた側にも都合があり、すぐには駆けつけられないこともあるため、なるべく余裕をもって連絡したいところです。
一般的には、3親等内の交流のある親族やごく親しかった友人に連絡します。本人が会いたがっているであろう人を呼んで喜ばせてあげましょう。
優しく話しかける
死期が迫っている人には優しく話しかけてあげましょう。家族の優しい声が近くで聞こえれば、安心して最後の時を過ごせます。
聴覚の機能は最後まで残りやすいといわれているため、たとえ反応が薄くても本人には届いていることが多いようです。話しながら手を優しく握ったりさすったりすることも、本人の不安をやわらげる効果が期待できます。
感謝の言葉を伝えておくのも大切です。本人のためだけでなく、遺される家族が後悔しないためにも、思いをしっかり伝えておきましょう。
家族の誰かがそばにいる
死が近づいているのであれば、なるべく家族の誰かがそばにいるようにしましょう。反応がない状態だとしても、家族の気配が伝われば本人の安心感につながります。遺される側も、最後に一緒に過ごす時間を十分に取ることで後悔しにくくなります。
目やにや涙、唾液などの汚れが見られる場合には、優しくふき取って清潔にしてあげましょう。負担がかからないよう、家族が交代で付き添うようにするのがベターです。
臨終の際には家族そろって看取る
臨終の際には、なるべく家族全員で看取れるよう調整しましょう。親しい家族に見守られることで、安らかな気持ちで最後の時を迎えられます。遺される側も、最後の瞬間に立ち会うことで後悔を感じにくいでしょう。
身内が危篤になったときにするべきことについては、以下の記事で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
死が近い人に対し避けるべき行動
死が近い人に対しては、以下の配慮が必要です。
- 本人のそばで葬儀や遺産の話をしない
- 本人に対し愚痴や不満を言わない
具体的に解説します。
本人のそばで葬儀や遺産の話をしない
本人のそばで葬儀の予定や遺産分割にまつわる話をしないよう注意しましょう。死期が迫っているのが事実だとしても、自分が死んだ前提で進められる葬儀や遺産の話題は不快に感じるものです。
呼びかけに反応がなく意識がないように思えても、実は聴覚がしっかり働いている可能性があります。葬儀の準備や遺産の相談は、本人の耳に届かない場所で静かに行いましょう。
本人に対し愚痴や不満を言わない
本人に対し、愚痴や不満をぶつけるのも避けましょう。人生の最後を目前に控えた状態で負の感情をぶつけられれば、不安や悲しみを抱えたまま最後の日を迎える場合があります。伝えた側も、本人の死後に後悔する可能性があります。
せん妄により「ご先祖様が迎えにきた」といった嘘のような発言をしたとしても、頭ごなしに否定したりせずに受け入れてあげるのが大切です。
意識がないように感じられる状態であっても聞こえていることもあるので、悔いを残す可能性のある行動は控えましょう。
遺される家族に必要な準備
死の兆候を感じるのであれば、遺される家族は以下の準備を進めておきましょう。
- もしもに備え葬儀社や葬儀プランを探しておく
- 訃報を送る相手をリストアップしておく
詳しい内容を説明していきます。
もしもに備え葬儀社や葬儀プランを探しておく
家族の死が近いと感じるのであれば、もしもの場合に備えて葬儀社や葬儀プランを探しておきましょう。事前に葬儀社や葬儀プランの候補をいくつかに絞っておくことで、臨終後の遺族の精神的・肉体的な負担の軽減につながります。プランを精査する時間ができるため、葬儀の費用や内容面でも納得がいきやすく、後悔を感じにくくなります。
生前から葬儀のことを考えるのに抵抗を覚える人もいるかもしれませんが、縁起の悪い行為というわけではありません。葬儀について事前に知っておくことで心に余裕が生まれ、死期が迫った人に対してしっかり向き合えるようにもなるものです。遺される家族はもちろん、相手のためにもなるため、ある程度の準備を進めておきましょう。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、全国に必要なものを含んだ明瞭なセットプランでの葬儀を提供しています。24時間365日、葬儀の専門スタッフが受付けておりますので、些細なことでもお気軽にお問い合わせください。
訃報を送る相手をリストアップしておく
いざというときのために、訃報を送る相手を事前にリストアップしておきましょう。臨終から葬儀までには時間的な余裕がありません。亡くなってから慌てて連絡先を探したり検討したりするのでは、訃報の遅れや伝え漏れにつながります。
結果的に周囲に迷惑をかける事態になり、葬儀にも影響が出る可能性があるため、事前に準備を進めておくのが大切です。リストアップさえ終わっていれば、家族と分担して連絡を進めやすくなります。
死のサインを見逃さず、最後の時間を悔いなく過ごそう
死が近い人には、行動はもちろん、表情や身体にいくつかのサインが現れるといわれています。思い当たる兆候が見られたら、最後に会わせておきたい人に連絡を取りつつ、家族が優しく見守って最後の時間を大切に過ごしましょう。意識がはっきりしているうちに感謝の気持ちを伝えておくのも重要なポイントです。
いざというときに慌てずに済むよう、あらかじめ連絡先をリストアップしたり、葬儀社や葬儀プランを検討したりすることも大切です。葬儀は後からやり直しができません。後悔しないためにも、少しずつ準備を進めておきましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国に一律価格でご提供しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。