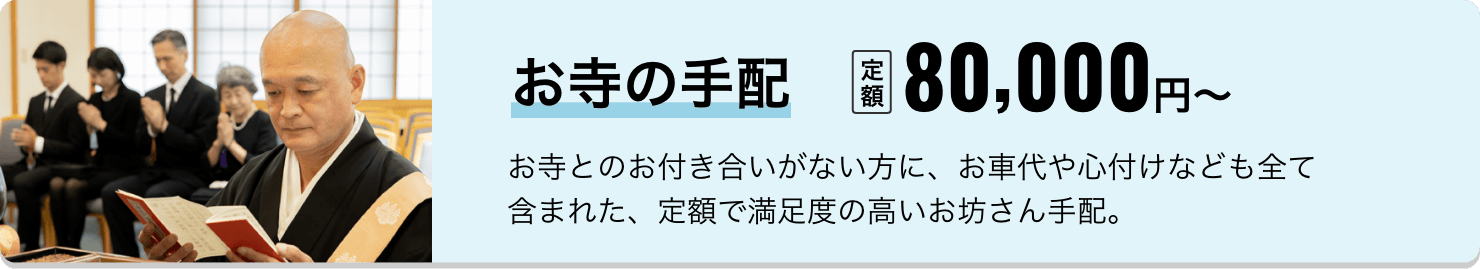天台宗で葬儀を行う場合、なじみがないと葬儀の流れや作法がわからず、戸惑うかもしれません。仏式の葬儀といっても、宗派によって葬儀の意味や儀式、マナーなどが異なります。
本記事では、天台宗の葬儀に対する考え方や、流れや作法について解説します。「天台宗とはどのような宗教か」など基本的なことから、お布施の相場まで詳しく説明しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事を要約すると
- 天台宗は、平安時代に最澄が伝えて日本独自の発展を遂げました。天台宗には「すべての人が仏になれる」という考えがあり、葬儀では故人が仏になる準備として「顕教法要」「例時作法」「密教法要」の3つの儀式があります。
- 通夜では剃度式、葬儀式では奠茶(てんちゃ)や引導下炬(いんどうあこ)など特徴的な儀式があります。
- 天台宗の葬儀では、平たい数珠を持ち、焼香は3回行うのが基本です。お布施の相場は20〜30万円ですが、地域やお寺との関係によっても異なります。
天台宗の葬儀とは?
天台宗というと、学校で習った記憶があるという方も多いのではないでしょうか。ただ、実際にどのような教えがあるのか、葬儀ではどんなことを行うのかといった点については、信仰していないとなかなか知る機会がないかもしれません。
天台宗とはどのような宗派なのか、そして葬儀における考え方について、わかりやすく解説していきます。
天台宗の基本情報
天台宗は、中国の智顗(ちぎ)によって確立された仏教の一つで、大乗仏教の宗派に分類されます。お釈迦様が出家された後、弟子に説かれたといわれている「法華経」を根本経典としています。
日本では、平安時代に伝教大師である最澄(さいちょう)によって伝わりました。中国の教えだけでなく密教や禅の教えを取り入れ日本独自の発展を遂げました。本山は、滋賀県大津市にある比叡山延暦寺で、信者は約277万人いるといわれています。
| 基本情報 | |
| 創始・ルーツ | 智顗(中国) |
| 経典 | 法華経 |
| 日本での開祖 | 最澄 |
| 総本山(日本) | 比叡山延暦寺 |
天台宗の葬儀に対する考え方
天台宗では、「すべての人々が仏になれる」という「一乗の教え」があります。人は亡くなると仏弟子(ぶつでし)になり、阿弥陀仏のお迎えによって現世から離れ、極楽浄土へ旅立つとされています。
そして天台宗における葬儀は、故人の生前の罪を懺悔し、祈りを行うことで極楽浄土へ導き、仏になる準備を行うための儀式と位置づけられています。また、遺族にとっても、功徳を積み仏の道を成していくという意味があります。
天台宗の葬儀の特徴
天台宗の葬儀では、法華経や阿弥陀経などが読経されます。仏の教えを「顕教」と「密教」に分類し、葬儀では「顕教法要」「例時作法」「密教法要」の3つの重要な儀式があります。
仏教では、さまざまな宗派の葬儀が簡略化されることが増えていますが、天台宗ではこれらの儀式を重んじる傾向にあります。
顕教法要(けんぎょうほうよう)
顕教法要とは、法華経を唱えて、故人の生前の行いに対する懺悔をし、生前の罪を軽くすることです。人は皆、仏の子どもでありその身に仏性を宿していると考えられているため、懺悔により仏性を高めるために行います。
顕教法要の顕教とは、お釈迦様の教えを経典など言葉や文字など明らかにして、広く教えを説くことを指しています。
例時作法(れいじさほう)
例時作法とは、阿弥陀経を唱えて阿弥陀如来に救いを求め、故人が極楽浄土へ行けるように祈願することです。故人の供養だけでなく、先祖の霊を供養し、「この世も極楽のような素晴らしい世界にしよう」という意味もあります。
例時作法は葬儀だけでなく、修行としても行われており、引声という曲調に合わせて阿弥陀経を唱えます。
密教法要(みっきょうほうよう)
密教法要とは、定められた印をつくり「光明真言」を唱えることで、故人が極楽浄土へ導かれるように祈ることです。
密教は、大日如来の教えを示したもので仏の境地に達しようとするものです。広く教えを説く顕教と異なり、真言は修行を積んだ弟子にのみ伝えられる真実を現す秘密の教えとされています。
光明真言はサンスクリット語で「オン、アボキヤ、ビロシャナ、マカボダラ、マニハンドマ、ジンバラ、ハラバリタヤウン」と言います。
天台宗の葬儀の流れ
ここからは、天台宗の葬儀がどのような流れで行われるか解説します。具体的な流れや儀式を知っておくと、それぞれの儀式の意味やするべきことがわかり、落ち着いて対応できるでしょう。
ただし、地域や寺院によって儀式の内容や順番が異なることがあるため事前に確認することが大切です。
通夜の流れ
通夜が行われる前日の読経から儀式は始まります。通夜は主に遺族が出席し、「剃度式」と「授戒式」と呼ばれる特徴的な儀式を行います。
- 臨終誦経(りんじゅうずきょう):亡くなった後、通夜の前日に阿弥陀経を枕元で読経をします。
- 通夜読経(つやどっきょう):通夜の当日の朝になると法華経の読経をし、夕方に阿弥陀経の読経をします。
- 剃度式:出家をするために髪を剃る「剃度式」を執り行います。現代では、実際に髪を剃らずに、カミソリを当てて髪を剃る真似だけを行うことがほとんどです。
- 授戒式:戒名が授けられます。
- 位牌開眼式(いはいかいがんしき):位牌に読経をして故人の魂を移します。
葬儀式の流れ
天台宗の葬儀式は、遺族以外の友人や知人も参列して執り行われることが一般的です。天台宗の葬儀式の流れは寺院や地域差もありますが、一般的な流れは以下のとおりです。
- 僧侶の入場と列讃(れっさん):導師である僧侶が入場し、楽曲に合わせて楽器が鳴らされます。
- 随法回向(ずいほうえこう):故人の成仏を祈る声明を行います。
- 奠茶(てんちゃ)と奠湯(てんとう):霊前にお茶を供えます。
- 引導下炬(いんどうあこ):故人が成仏して極楽へ旅立つための引導を渡します。 僧侶がたいまつか線香を手に持って宙に梵字を結んだ後、読経が行われ、参列者が焼香を行います。
- 弔辞拝受:弔電を拝読します。
- 回向:葬儀の終わりに述べられる回向文(えこうもん)を唱えます。
- 僧侶の退場
- 出棺
天台宗の葬儀の作法
実際に葬儀に参列する場面を想像すると、どのように振る舞えばよいのか不安に感じる方も多いかもしれません。
特に焼香は、故人と関係の深い方から順番に行うため、最初に焼香を行う喪主は作法がわからず戸惑うこともあります。ここでは、焼香の手順や数珠の持ち方について紹介します。
焼香の方法
天台宗の焼香は、基本的に3回行うのが一般的とされていますが、厳密な決まりはなく、1回だけの場合もあります。
順番が来たら焼香台の前へ進み、まず僧侶や遺族に一礼し、続いて祭壇の故人の遺影にも一礼します。その後、親指・人差し指・中指で抹香をつまみ、額に軽くいただいてから静かに香炉にくべます。
線香を使って焼香を行う場合もあり、その際は数珠を持ったまま右手で線香を香炉に置きます。線香は中央に1本立てる形のほか、後ろに2本添えて3本で供えることもあります。
数珠の種類と持ち方
天台宗では、一般的によく見られる丸い玉の数珠は使用せず、楕円形の玉が連なった平たく特徴的な数珠を用います。
天台宗の数珠は、108個の「主玉」に加え、親玉が1つ、天玉が4つ、そして親玉の下には「弟子玉」が連なっています。男性は9寸、女性は8寸のサイズを使うのが一般的です。
持ち方としては、数珠を親指と人差し指にかけるようにして手を合わせ、弟子玉が下に垂れるように持ちましょう。
天台宗の葬儀に関してよくある質問
天台宗の葬儀における考え方や、葬儀の流れ・作法について理解していても、実際に準備を始めると戸惑うことは少なくありません。ここでは、お布施や戒名料の目安、葬儀後の法要など、天台宗の葬儀に関してよく寄せられる疑問をまとめました。
天台宗のお布施の相場は?
お布施は、通夜や葬儀での読経に対する謝礼としてお渡しするもので、相場はおおよそ20〜35万円とされています。ただし、金額は地域の慣習やお寺との関係性によって異なるため、一概には決められません。
判断がつかない場合は、寺院や葬儀社に相談すると安心です。また、「4」や「9」は「死」や「苦」を連想させるため、金額に含まないよう注意しましょう。
お布施は「布施袋」と表書きされた専用の袋に包み、お盆に乗せてお渡しします。渡すタイミングは、葬儀前のごあいさつ時か、終了後のお別れの際が一般的です。あわせて「御車代」も別途用意し、相場は5,000円〜1万円程度とされています。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、菩提寺などお寺とのお付き合いがない方に、全国一律価格で僧侶を手配いたします。読経に加え、戒名、お車代や心付けなども全て含まれた定額の手配料金ですので、安心してご依頼ください。
天台宗の戒名料はいくら?
お布施とは別に、戒名を授かるための「戒名料」も必要です。通常はお布施と一緒に包んでお渡ししますが、戒名の位や文字数によって金額は大きく異なります。
天台宗では、一般的に男性には「居士(こじ)」、女性には「大姉(だいし)」という位がつけられ、相場は50万円〜70万円ほどです。それより位が低い「信士」「信女」の場合は、30万円〜50万円程度とされています。さらに高位の「院信士」「院信女」は80万円前後、「院居士」「院大姉」となると100万円を超えることもあります。
ただし、戒名料は地域やお寺の方針によっても異なります。また、高額な戒名料を包めば高い位が授けられるとは限らないことに留意しましょう。
なお、菩提寺以外で戒名を授かった場合、納骨を断られる可能性もあるため、事前に確認しておくことが大切です。
天台宗の葬儀後の法要は?
天台宗では葬儀のあとに、亡くなってから7日目の「初七日」や、49日目の「四十九日」に法要を行うのが一般的です。
天台宗では、人は亡くなった後に生まれ変わるという「輪廻転生」の考え方を大切にしています。命日から7日ごとに次の生まれ変わりが決まるとされており、故人が無事に成仏し、新たな命へと生まれ変われるよう祈りを捧げます。
天台宗の法要は、故人を偲び、遺族の心を癒す大切な時間でもあります。特に四十九日法要は「忌明け」の節目とされることが多く、納骨を行うタイミングにもなります。その後も一周忌や三回忌など、節目ごとに法要を行う習わしがあります。
天台宗で葬儀を行うなら経験豊富な葬儀社に相談を
天台宗の通夜では「剃度式」、葬儀式では「奠茶(てんちゃ)」や「引導下炬(いんどうかこ)」といった特徴的な儀式が行われます。天台宗に馴染みのない方や、葬儀に参列した経験がない方にとっては、わかりづらいと感じることもあるかもしれません。
葬儀の準備や当日の進行を慌てずスムーズに進めるためにも、事前に寺院や天台宗の葬儀に詳しい葬儀社に相談し、流れや作法を確認しておくと安心です。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、天台宗に対応し、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国一律価格でご提供しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。