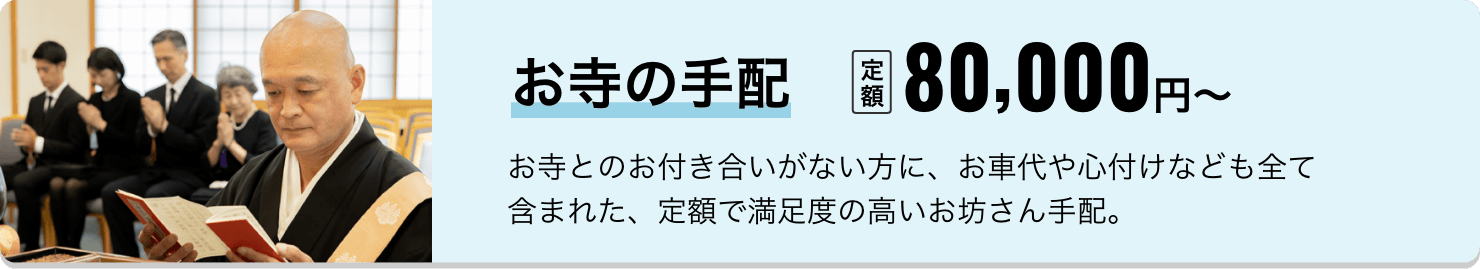仏式葬儀では、僧侶に読経や戒名の授与を依頼する際、その謝礼として「お布施」を渡します。
お布施には明確な金額の基準はなく、宗派や地域、寺院との関係性などによって大きく異なります。真言宗も例外ではなく、葬儀の内容や戒名の位などによって相場に差が出ることがあります。
さらに、封筒の選び方や渡し方などにも一定の作法が求められるため、事前に確認しておくことが大切です。この記事では、真言宗の葬儀におけるお布施の相場や内訳、対応時の注意点についてわかりやすく解説していきます。
この記事を要約すると
- 真言宗における葬儀の相場は、30万〜100万円が目安で内訳や依頼内容によって差がある。読経料や戒名料の位によって金額が上下するのが一般的。
- 真言宗の葬儀で渡すお布施の金額を抑えたい場合は、寺院や葬儀社に事前相談し、内容の調整をお願いするのが有効。状況に応じて柔軟に対応してもらえる場合もある。
- 真言宗でお布施を渡す際には、封筒や表書きの形式に注意し、切手盆や袱紗を使って僧侶から読める向きで差し出すのが基本。直接手渡しは避けるようにする。
真言宗の葬儀におけるお布施の相場は30~100万円ほど
真言宗の葬儀において僧侶へ渡すお布施の相場は30〜100万円程度が一つの目安とされています。ただしこれはあくまで一般的な相場であり、実際の金額は地域や寺院、葬儀内容などによって異なります。
お布施とは本来、読経や儀式に対する対価ではなく、施主が仏教の教えに則って「施しの心」をもって差し出すものとされています。つまり、単なる金銭的なやりとりではなく、故人を供養したいという気持ちや僧侶への感謝の念を形にしたものです。
そのため、必ずしも相場に合わせる必要はなく、自分たちの事情や思いに応じて、無理のない範囲で誠意を込めて包めば差し支えありません。
真言宗の葬儀におけるお布施の内訳
真言宗の葬儀で渡すお布施には、あらかじめ決まった金額があるわけではなく、相場にも大きな幅があります。
その背景には、お布施に含まれる項目の内容が関係しています。読経の回数や戒名の内容など、依頼内容によって金額が変わるため、同じ宗派でもお布施の総額は一律ではありません。
ここでは、真言宗の葬儀で見られる代表的なお布施の内訳について解説します。
読経料|20万円前後
読経料は、通夜や葬儀、初七日などで僧侶に読経をお願いした際に渡す謝礼で、真言宗ではおおむね20万円前後が相場とされています。
ただし、どの葬儀も一律というわけではなく、儀式の構成による読経の回数などによって包む金額は異なり、地域や寺院などによって幅があるのが一般的です。
真言宗の葬儀では、木鉦(もくしょう)や太鼓などの鳴り物を伴いながら、力強く読経を行うのが特徴です。
戒名料|30~80万円
戒名料は、故人に仏弟子としての名前である「戒名」を授けてもらうために渡す謝礼で、真言宗では30〜80万円程度が一つの目安とされています。
戒名には位があり、以下のとおりそれぞれで相場が異なります。
- 信士・信女:30万〜50万円
- 居士・大姉:50万〜70万円
- 院信士・院信女:60万〜80万円
- 院居士・院大姉:80万〜100万円以上
上位の位号になるほど格式が高いとされ、戒名料も高額になる傾向があります。自由に選べるわけではないものの、故人の人柄や家族の意向を反映したものが授けられます。
ただし、必ず相場どおりの金額を支払わなければならないわけではなく、事情に合わせて金額を下げてもマナー違反ではありません。
御車代・御膳料|各1万円前後
御車代と御膳料は、それぞれ僧侶の移動や食事に関する謝礼として渡すもので、いずれも1万円前後が相場とされています。
御車代は、寺院ではなく葬儀会館などへ僧侶に来ていただく際に、その交通費や出向への感謝を込めて渡すものです。自家用車などで送迎したり、寺院で葬儀を執り行ったりする場合は用意する必要はありません。
御膳料は、本来であれば葬儀後に感謝の気持ちを込めて用意する食事の代わりに渡す金額です。近年は、会食を設けないことが増えてきており、そのような場合に御膳料を僧侶へ渡します。どちらもお布施とは分けて別に包むのがマナーとなります。
必ず1万円である必要はなく、5,000円ほどを渡すケースもあります。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、菩提寺などお寺とのお付き合いがない方に、全国一律価格で僧侶を手配いたします。戒名、お車代や心付けなども全て含まれた定額の手配料金ですので、安心してご依頼ください。
よりお布施の詳細について知りたい方は以下の記事も併せてチェックしてみてください。
真言宗の葬儀でお布施の金額を抑える方法
真言宗の葬儀でお布施の金額を抑えたい場合は、状況に応じていくつかの方法があります。
菩提寺がある場合は、打ち合わせの段階で事情を率直に伝えれば、読経の回数を減らすなどの配慮を受けられることもあります。ただし、お布施の金額を一方的に決めるのではなく、事前に相談する姿勢が大切です。
菩提寺がない場合は、葬儀社に寺院を紹介してもらうことで、比較的安めの金額で依頼できるケースがあります。特に葬儀社と提携している寺院は、あらかじめ目安の金額が設定されていることが多く、費用感をつかみやすいのもメリットです。
どちらの場合でも、無理のない範囲で誠実に相談することが、負担を抑えるうえでの第一歩となります。
真言宗の葬儀におけるお布施のマナー
真言宗におけるお布施の相場や内訳について解説してきましたが、実際にお渡しする際にも注意すべきマナーがあります。封筒の種類や表書きの書き方、渡すタイミングなどに決まった作法があるため、事前に確認しておくことが大切です。
ここでは、お布施を準備・手渡しする際に注意すべきマナーについて解説します。
封筒の選び方|白無地のもので水引は不要
お布施は、奉書紙または白無地の封筒を使って包むのが一般的です。より丁寧な形式を望む場合は、紙幣を半紙に包んでから奉書紙で包む「二重包み」が正式とされていますが、現在では白無地封筒が主流となっています。
封筒を選ぶ際は、郵便番号欄や柄の入ったものを避け、無地のものを使用しましょう。水引は基本的に不要です。地域によっては白黒や双銀の結び切りを用いる場合もあります。御車代や御膳料も白無地封筒を使い、水引はつけないのが一般的です。
表書きの書き方|通常の墨で金額は旧字体で記入する
封筒の表書きは、上段に「お布施」または「御布施」と記し、下段には施主のフルネームを縦書きで書くのが基本です。封筒の裏面には、金額・住所・氏名を記入します。中袋がある場合はその表面に金額、裏面に住所と氏名を記入します。
金額は「金伍萬圓也」「金参拾萬圓也」など、旧字体を用いるのが正式とされています。筆記具は毛筆または筆ペンを使用し、薄墨ではなく通常の墨を使いましょう。ボールペンや鉛筆はマナー違反です。御車代や御膳料についても、それぞれ表書きで記入する必要があります。
渡す際のマナー|直接手渡しは避けて切手盆にのせて渡す
御布施は、葬儀が始まる前または法要後など、儀式の合間に僧侶へ渡します。直接手渡しは避け、切手盆にのせて渡すのが正式な作法です。切手盆が用意できない場合は、袱紗(ふくさ)に包んで持参し、取り出してから袱紗のうえにおいて差し出します。
封筒は僧侶から読める向きにして渡すのがマナーです。また、お札は香典と異なり、表(肖像のある面)を上にして揃えます。新札を用意するのが理想ですが、必須ではありません。渡す際には「本日はありがとうございました」など、何か一言添えると感謝の気持ちがより伝わります。
真言宗の法要で渡すお布施の相場
真言宗では、葬儀の後にも四十九日や一周忌、三回忌といった法要が営まれ、その都度僧侶へのお布施を用意します。これらの法要で包むお布施の金額は、一般的に3〜5万円が多く、内容や地域によっては7〜10万円包むこともあります。
納骨法要も3〜5万円が目安となりますが、年忌法要や納骨を同時に行う場合は、事前に寺院へ確認するようにしましょう。あくまでも目安であるため、無理のない範囲で、誠実に準備することが大切です。
真言宗の葬儀におけるお布施に関するよくある質問
真言宗の葬儀におけるお布施の相場や渡す際のマナーなどを解説してきましたが、まだまだ気になることがあるという方もいるのではないでしょうか。ここでは、お布施に関する4つのよくある質問に答えていきます。
真言宗のお布施って他の宗派よりも高い?
真言宗だからといって、他の宗派よりお布施が特別に高くなることはありません。浄土宗・天台宗・臨済宗などとも大きな差があるとは言い難く、実際の金額や寺院や地域、葬儀の規模によって異なります。
戒名の位が高かったり、読経の回数が多かったりする場合はお布施の金額も上がりますが、真言宗に限ったことではありません。
お布施が少ないって言われることはある?
お布施を渡した際に金額について僧侶から指摘を受けることはほとんどありません。お布施は施主の気持ちに基づいて包むものであり、寺院側が具体的な金額を指定するものではないためです。
ただし、戒名の位に対して極端に少なかったり、お布施自体を渡さなかったりした場合は、確認されることもあります。もし後になって相場よりも明らかに少ない金額を渡していたことがわかった場合は、後日あらためてお布施を渡しても失礼にはあたりません。
葬儀後は寺院との関係が長く続くため、不安がある場合は早めに対応するようにしましょう。
お布施の相場に差がある理由は?
お布施の相場に差がある理由は、明確な基準が存在せず、寺院や地域ごとの事情に委ねられているためです。宗派によって儀式の構成や考え方が異なるほか、寺院の規模や僧侶の人数、日々の活動内容なども金額に影響します。
さらに、信徒が多い地域では一人当たりの負担が抑えられる一方、信徒の少ない地域では相場が高くなる傾向があります。お布施は定価ではなく、あくまでも感謝の気持ちを形にするものです。そのため、宗派や地域の違いによって金額に差があるのは自然なことといえるでしょう。
お布施はどのタイミングで渡すべき?
お布施は、葬儀が始まる前や終わった後、繰り上げ法要の前後など、儀式の区切りのタイミングで渡すのが一般的です。寺院によって流れが異なるため、葬儀社や僧侶に確認しておくと安心です。
渡す際は、切手盆または袱紗の上に封筒を置き、僧侶から文字が読める向きで差し出します。直接手渡しするのは避けて「本日はありがとうございました」など一言添えるのが丁寧な対応とされています。
真言宗のお布施は“気持ち”と“相場”のバランスが大切
真言宗の葬儀におけるお布施の相場は、全体でおよそ30〜100万円が目安とされています。内訳には読経料や戒名料、御車代、御膳料などが含まれ、依頼内容によって金額に幅があります。経済的な事情がある場合は、菩提寺や葬儀社に相談すると無理のない範囲での調整が可能です。
渡す際は、封筒の種類や表書き、切手盆や袱紗の使い方など、基本的なマナーにも注意が必要です。お布施は定価ではなく、僧侶への感謝や供養の気持ちを形にするものです。形式だけにとらわれず、誠意を込めて丁寧に用意することが何より大切です。
弊社では、真言宗に対応し、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国に一律価格で提供しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。