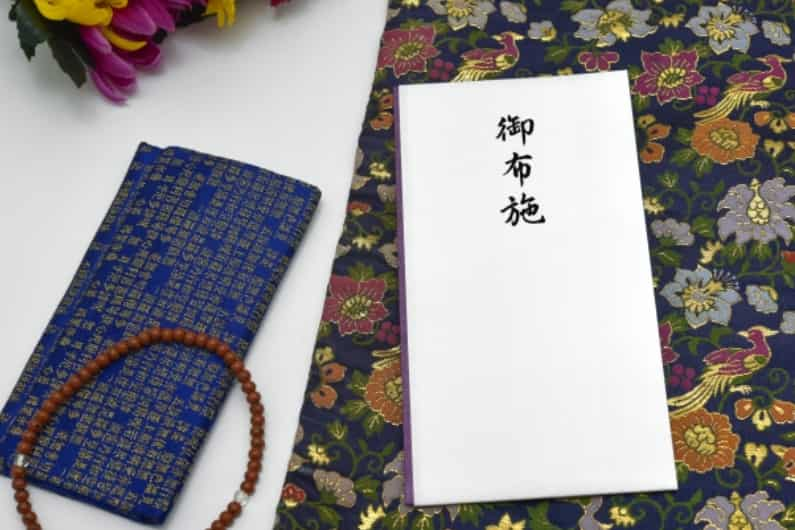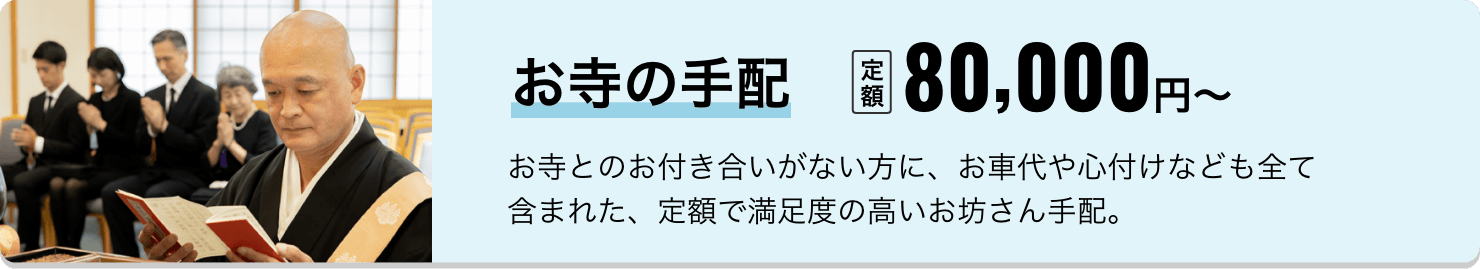日本では仏教形式の葬儀が一般的で、お通夜や告別式に僧侶を招いた場合には、読経や戒名などへの謝礼としてお布施を渡します。お布施には明確な金額の決まりはないものの、宗派ごとに考え方や相場に違いがあるため、予想以上の費用がかかる可能性もあります。
葬儀の際に慌てず丁寧に対応するには、お布施の目安やマナーをあらかじめ把握しておくことが大切です。この記事では、日蓮宗の葬儀におけるお布施の相場や内訳、年忌法要における目安などわかりやすく解説していきます。
この記事を要約すると
- 日蓮宗の葬儀におけるお布施の相場は、20万〜50万円程です。 ただし、「読経の回数」「法号(戒名)のランク」「地域性やお寺の習慣」などによって異なるため、葬儀社や菩提寺に確認すると良いでしょう。
- 日蓮宗の葬儀でお布施を渡す際の封筒は、白い無地のものを選びましょう。香典袋のような水引の封筒ではなく「白無地で一重の封筒」を使うのが一般的です。また、表書きのマナーは、薄墨ではなく濃墨を使うのが正式です。
- 日蓮宗の四十九日法要のお布施相場は、3万〜5万円程です。ただし、あわせて納骨式や開眼供養を行う場合は、5~10万円程になることもあります。また、日蓮宗の一周忌・三回忌のお布施相場は、1~5万円程が一般的です。
日蓮宗の葬儀で渡すお布施の相場は20~50万円
日蓮宗の葬儀で僧侶に渡すお布施の相場は、おおよそ20〜50万円程度です。読経や法号(戒名)の授与、通夜から葬儀・初七日法要までの流れを全て依頼した場合、この金額に収まるケースが一般的とされています。
ただし、読経の回数や法号の種類によっては、この相場を超えることもあります。たとえば通夜・告別式・火葬・初七日など、複数回の読経を依頼した場合や、高位の法号を授かる場合は、それに応じて金額も高くなります。
また、地域やお寺の習慣によっても差が生じるため、迷ったときは事前に葬儀社や菩提寺に確認しておくのが安心です。
日蓮宗の葬儀で渡すお布施の内訳
日蓮宗の葬儀で渡すお布施には、明確な金額の決まりはありませんが、読経料や法号料(戒名料)など内訳ごとにある程度の相場があります。最終的な金額は、各依頼内容によって変わってきます。ここでは、お布施の内訳とその相場について解説します。
読経料
日蓮宗の葬儀では、僧侶による読経の回数によって「読経料」の金額が決まります。通夜・告別式・火葬・初七日法要など、読経が複数回行われるケースが多く、一回あたり5〜7万円が相場です。
たとえば、3回お願いした場合は15万円前後、6回行えば30万円を超えることもあります。読経料は、お布施の中でも大きな割合を占めるものであり、僧侶の読経に対する謝礼として渡します。ただし、金額はあくまでも目安であり、地域やお寺によって変動があります。
葬儀社に読経の内容や回数を事前に確認したうえで、適切な金額を包むといいでしょう。
法号料(戒名料)
法号(戒名)は、仏門に入った証として授かる名前で、葬儀や納骨の際には欠かせないものです。この法号を授かる際に必要となるのが「法号料」です。
日蓮宗では、法号に複数のランクがあり、その詳細は以下の通りです。
- 信士・信女:2万円~5万円
- 院信士・院信女:5万円~10万円
- 院日信士・院日信女:15万円~20万円
- 院居士・院大姉:20万円~25万円
高位の法号が必ずしも望ましいとは限らず、故人の人柄や人生にふさわしい呼び名を授かることが大切です。
実際には「信士・信女」や「院信士・院信女」などの法号が、遺族の希望や事情に応じて授けられるケースが多く、無理に高位を求める必要はありません。
御膳料・御車代
御膳料と御車代は、それぞれ僧侶の食事や移動に関する謝礼であり、お布施とは別に包むのが一般的です。
御膳料とは葬儀後の会食に僧侶が参加できなかった場合に渡す食事代の代わりで、相場は5,000円〜1万円ほどです。会食に出席される場合や、料理を持ち帰ってもらう場合は不要です。
一方、御車代は、火葬場や斎場などに来ていただく際の交通費として渡すもので、こちらも5,000円〜1万円程度が目安です。どちらも「お布施」とは目的が異なるため、封筒を分けて用意し、タイミングを見て丁寧に渡すことがマナーとされています。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、菩提寺などお寺とのお付き合いがない方に、全国一律価格で僧侶を手配いたします。読経だけでなく、戒名やお車代、心付けなども全て含まれた定額の手配料金ですので、安心してご依頼ください。
日蓮宗の年忌法要で渡すお布施の相場
葬儀におけるお布施の相場について解説してきましたが、葬儀後の法要についても、僧侶や読経などを依頼した場合には謝礼としてお布施を渡します。法要の種類や規模によって金額は変わるため、あらかじめ目安を知っておくと安心です。
ここでは、四十九日や一周忌などの年忌法要、お盆や彼岸の供養におけるお布施の相場を解説します。
四十九日法要のお布施|3〜5万円が相場
日蓮宗における四十九日法要のお布施相場は3〜5万円程度が一般的です。ただし、法要をあわせて納骨式や開眼供養(仏壇・位牌に魂を入れる儀式)を行う場合は、5〜10万円程度になることもあります。
金額は地域差やお寺の考え方によって変わるため、事前に菩提寺や葬儀社に確認しておくと安心です。四十九日法要とは、7日ごとの追善供養のうち、7回目にあたる節目の法要であり、故人の魂が次の世界へ向かう審判の日とされています。
日蓮宗では「南無妙法蓮華経」のお題目を唱えることで誰でも成仏できるとされており、この考え方に基づいて四十九日は「忌明け=成仏の完了」という意味合いが特に強くなります。法要後に納骨を行うことも多く、準備すべき内容も含めて余裕を持った段取りが大切です。
一周忌・三回忌のお布施|1〜5万円で規模に応じて調整
一周忌や三回忌の法要では、1〜5万円程度のお布施を用意するのが一般的です。読経の回数や納骨・開眼供養を伴うかどうか、招く参列者の人数によって金額を調整します。
さらに、僧侶への御車代・御膳料はそれぞれ5,000円前後を別途包むのが基本です。
自家用車での送迎や、会食を提供する場合には省略されることもありますが、原則として別封筒で用意しておきましょう。一周忌は四十九日に次いで重要な節目とされ、家族や親族に加え、親しい知人を招いて営むことが多い法要です。
三回忌は命日から数えて2年後に行われ、一周忌よりやや規模を抑えて行う傾向があります。いずれも故人を偲び、感謝の気持ちを伝える大切な時間となります。
お盆・彼岸・施餓鬼のお布施|1〜3万円が一般的
お盆やお施餓鬼、お彼岸法要では、お寺に渡すお布施として1〜3万円が目安となります。金額は地域やお寺によって差がありますが、無理のない範囲で包むのが基本です。お盆は、ご先祖様の霊を迎えて供養する時期で、仏壇やお墓の前で手を合わせる習慣があります。
一方、お施餓鬼は苦しみの世界にいる「餓鬼(がき)」と呼ばれる存在に食べ物やお経を施すことで、自分の心も清めていくという仏教の教えに基づいた行事です。
お寺ではこの2つの法要をまとめて「盆施餓鬼」として同時に行うことも多く、混同されがちですが、それぞれ意味が異なります。
御会式のお布施|宗派行事として謝礼を包む場合もある
御会式(おえしき)は日蓮宗の宗祖・日蓮聖人の命日にあたる10月13日前後に営まれる法要です。故人のための年忌法要とは異なり、日蓮聖人への感謝を表す宗派独自の行事となります。
御会式は、寺院での合同法要に参列する形が一般的ですが、地域によっては檀家ごとに僧侶を招いて自宅で営むこともあります。
その際には、読経や法話への謝礼としてお布施を用意することがあります。金額や渡し方はお寺や地域ごとに異なるため、事前に寺院へ確認するようにしましょう。
日蓮宗の葬儀におけるお布施のマナー
日蓮宗のお布施の相場について解説してきましたが、お布施は金額だけでなく、包み方や渡し方にも作法があります。こうしたマナーを守ることは、僧侶や寺院に対する敬意を示すうえで大切です。
ここでは、封筒の選び方や表書きの書き方、渡すタイミングなど、日蓮宗の葬儀におけるお布施のマナーについて解説します。
封筒の選び方|白い無地の封筒を使う
日蓮宗のお布施は、香典袋のような水引の封筒ではなく「白無地で一重の封筒」を使うのが基本です。郵便番号の枠や柄のある封筒は避け、表も裏も何も書かれていないタイプを選びましょう。二重封筒は「不幸が重なる」と受け取られかねないため、使ってはいけません。
地域によっては白黒や銀色の水引を使う場合もありますが、迷ったときは白無地封筒が最も無難といえます。正式なマナーとしては、奉書紙と呼ばれる白い和紙でお布施を入れた袋を包む方法もあります。
用意できる場合は、奉書紙で「左・右・下・上」の順で折りたたんで包みましょう。
封筒の書き方|薄墨ではなく濃い墨を使う
お布施の表書きには、薄墨ではなく濃墨を使うのが正式なマナーです。香典袋は悲しみを表すため薄墨を使いますが、お布施は僧侶への感謝や敬意を込めて渡すため、はっきりと濃墨で書きましょう。
筆記具は毛筆が基本ですが、濃い筆ペンでも問題ありません。書き間違いに備えて、予備の封筒を複数枚用意しておくと安心です。封筒の書き方は以下の通りです。
- 表面、中央上部:大きく「お布施」または「御経料」と記入する
- 表面、その下:喪主または施主のフルネームを記載
- 裏面、左下:住所と金額を記入し、金額は旧字体を使う(金壱萬圓也など)
お札は封筒の表面に対して「肖像画が上向き」になるように入れます。香典とは逆になるため注意しましょう。また、お札も新札を用意するのが一般的です。
渡し方と渡すタイミング|基本的に食事のタイミングで渡す
お布施は、法要後に僧侶と食事の席を共にする場合、お食事の前に手渡すのが一般的なマナーです。食事を提供することで感謝を伝える場でもあるため、そのタイミングで渡すと自然です。
渡す際は、封筒を袱紗(ふくさ)や小さめの風呂敷に包んで持参し、僧侶に対して両手で丁寧に差し出します。袱紗の色は、寒色系や紫などがふさわしく、派手な色は避けましょう。
僧侶が食事を辞退される場合は、法要が終わった直後のタイミングでお渡しします。その際は、御膳料や御車代があれば一緒に渡します。
もしタイミングが合わず直接手渡しできなかった場合は、できるだけ当日に寺院へ持参するようにしましょう。誠意を持って対応することが何よりも大切です。
日蓮宗の葬儀におけるお布施に関するよくある質問
日蓮宗の葬儀に関するお布施の相場やマナーについて解説してきましたが、実際に準備を進めるなかで、まだまだ気になることがあるという方もいるのではないでしょうか。ここでは、お布施に関する4つのよくある質問について答えていきます。
水子供養を依頼する場合のお布施は?
水子供養のお布施は、1〜3万円が相場です。内容が読経のみであれば1万円前後、戒名をつけたり永代供養を希望したりする場合は、金額が上がります。明確な決まりはないため、無理のない範囲で用意すれば問題ありません。
封筒は白無地の一重で、郵便番号欄なしのものを使用し、表書きには「お布施」と濃墨で記入します。名前は表の下段、必要があれば裏面に住所と金額(旧字体)を書きましょう。水子供養でも、他の仏事と同様に形式を整えることが大切です。
日蓮宗のお布施って高い?
日蓮宗だから特別にお布施が高いということはありません。仏教の他の宗派(曹洞宗・真言宗・天台宗・臨済宗など)と比べても、相場に差があるとはいえ、あくまで寺院や地域、法要の内容によって変動します。
お布施の内訳でも解説した通り、宗派関係なく戒名の位が高かったり読経を多くお願いしたりするとその分お布施の額も上がります。そのため、日蓮宗が他より高額とは一概にはいえません。
日蓮宗の葬儀はお金がかかるって本当?
日蓮宗の葬儀は、他の宗派と比べて大幅にお金がかかるようなことはありません。祭壇の形式や葬儀の流れに多少の違いはあるものの、大まかな流れは同じです。
ただし、祭壇や演出にこだわったり、オプションで棺を高価なものに変更したりした場合は高くなります。近年は一般葬のほかに家族葬や一日葬、直葬といった形式を選ぶ人も増えてきており、それぞれ相場が異なります。
予算に制限がある場合は、事前に葬儀社のプランを確認したうえで、対応可能か相談してみましょう。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、不要なものを省き、相場よりも価格を抑えたセットプラン料金を全国一律価格で提供しています。さらに、事前にお問い合わせいただいた方には特別価格でご案内しておりますので、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ。
お布施が少ないって言われることはある?
基本的にお布施の金額について僧侶から指摘されることはありません。お布施は施主側の気持ちで包むものであり、寺側が金額を指定するものではないためです。
ただし、戒名の位に対して明らかに金額が不相応だった場合や、お布施自体を入れ忘れたなどのミスがあれば、確認される可能性はあります。
万が一、あとから「地域の相場より大きく下回っていた」とわかった場合は、後日改めて追加でお布施を納めるのが丁寧な対応です。
お布施は法要の時に限らず、後からでも納められます。お寺とはこの先も長く付き合っていく関係になるため、気まずさや後悔が残らないよう、誠意をもって対応することが大切です。
日蓮宗の葬儀におけるお布施の考え方やマナーを正しく理解しよう
日蓮宗の葬儀で渡すお布施の相場は、全体で30〜50万円程度が一般的です。その内訳には、読経料や法号料のほか、御車代や御膳料があります。
また、葬儀以外の法要(初七日・四十九日・一周忌など)でも感謝の気持ちを込めて僧侶にお布施を渡します。
お布施を用意する際は、金額だけでなく封筒の選び方や書き方、渡すタイミングなどにも気を配ることが大切です。形式にとらわれすぎる必要はありませんが、基本のマナーを押さえておくことで、失礼のない対応ができます。
大切なのは、感謝と誠意をもって向き合う姿勢です。丁寧なお付き合いを心がけましょう。
弊社では、日蓮宗に対応し、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国一律価格で提供しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。