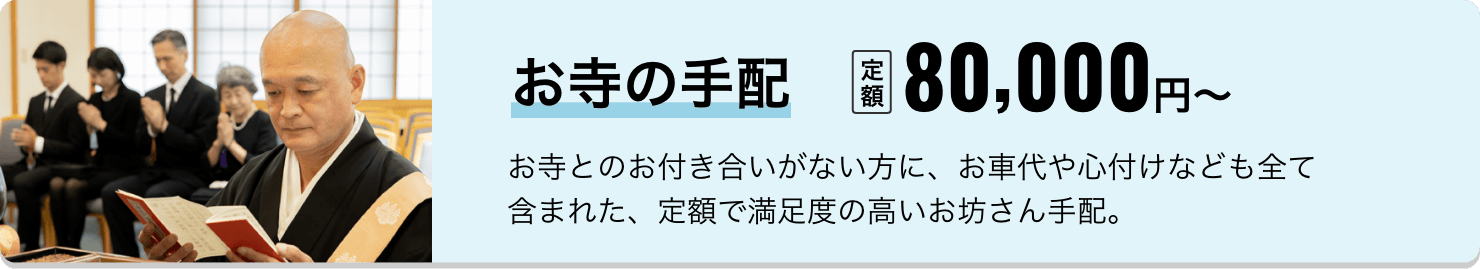江戸時代に浄土真宗本願寺派と分かれる形で誕生した浄土真宗大谷派は、「お東さん」という名で親しまれています。真宗大谷派の葬儀は、「絶対他力」や「往生即身仏」の独自の考え方のもと執り行われ、故人が無事に成仏したことへの感謝を分かち合います。
今回は、浄土真宗大谷派の葬儀について詳しく知りたい方や、これから参列を予定している方向けに、浄土真宗大谷派の葬儀の特色や流れを詳しく解説します。葬儀に参列する際に押さえておきたいマナーも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
この記事を要約すると
- 真宗大谷派の葬儀の流れは、「①通夜」「②納棺式」「③告別式」「④火葬・初七日法要」という流れです。また、特徴として「告別式」は「葬儀第一」と「葬儀第二」の二部構成で行われます。
- 真宗大谷派の葬儀のお布施相場は、10~30万円ほどです。しかし、地域や菩提寺によってお布施は変わりますので、事前に葬儀社やお寺に確認するとよいでしょう。
- 真宗大谷派の葬儀での香典相場は、両親の場合は3~10万円、祖父母の場合は1~5万円ほどです。参列する際のマナーは、焼香の回数は2回であることです。また、香典の表書きは「御仏前」か「御香典」としましょう。
浄土真宗とは?
浄土真宗は、鎌倉時代に法然の弟子・親鸞によって開かれた仏教の一派です。浄土真宗では、法然が開いた浄土宗の「念仏を唱えれば誰もが成仏できる」という教えをさらに発展させ、「念仏の功徳ではなく、阿弥陀仏の力によって極楽浄土へ導かれる」と考えます。これを“絶対他力”といい、念仏を唱えるかどうかに関係なく、阿弥陀仏を信じる心があれば誰もが往生できるとされています。
浄土真宗では、絶対他力により、死後は必ず極楽浄土に生まれ変われると考えます。これを「往生即身仏」といい、浄土真宗の葬儀もこの独自の考え方を前提に執り行われます。
浄土真宗大谷派とは?
浄土真宗大谷派は、浄土真宗のなかで本願寺派に次ぐ規模を持つ宗派で、全国に約8,500の寺院が存在します。京都にある真宗本廟(東本願寺)を本山に持つため、「お東」や「お東さん」とも呼ばれています。
ご本尊は阿彌陀佛で、阿弥陀如来の慈悲に感謝し、その教えを信じて生きることを大切にしています。寺院にはご本尊のほか、仏教を広めた聖徳太子や歴代門首の影像を安置する決まりがあります。
浄土真宗大谷派の誕生
浄土真宗はもともと大きな宗派として全国に広がっていましたが、戦国時代から江戸初期にかけて対立と跡継ぎ問題が起こりました。その影響を受け、最大宗派の本願寺派から分裂する形で大谷派が生まれました。
浄土真宗本願寺派との違い
浄土真宗大谷派と本願寺派は、「絶対他力」や「往生促進仏」などの基本の考え方は同じですが、さまざまな点で違いが見られます。葬儀では、式の構成はもちろん、使用する数珠の形や焼香の回数も異なるので、必ず違いを知ったうえで参列しましょう。
| 真宗大谷派 | 真宗本願寺派 | |
|---|---|---|
| 本山 | 真宗本廟(東本願寺) | 龍谷寺本願寺(西本願寺) |
| 葬儀の特徴 | 葬儀式が2部構成 | 簡素な形式 |
| 数珠の房の形 | 飾り編み | 撚り房 |
| 焼香の回数 | 2回 | 1回 |
浄土真宗大谷派の葬儀の特徴
浄土真宗大谷派の葬儀は故人を供養するためのものではなく、阿弥陀仏の教えに感謝し、極楽浄土への往生を喜ぶという意義があります。即身成仏の考え方が基盤となっているため、ほかの宗派と異なる点がいくつかあります。
<浄土真宗大谷派の葬儀の特徴>
- 引導・授戒の儀式がない
死者の供養や成仏祈願を行わないため、引導・授戒・末期の水などの儀式を行わない - お清めの塩を用意しない
死者を「穢れ」と考えないため、お清めを行わない - 死装束を着せない
すでに極楽浄土へ成仏しているため、死装束ではなく白衣を身につけさせる - 戒名ではなく法名と呼ぶ
法名にランクがなく、生前に帰敬式を受けることが多い - 位牌を安置しない
祭壇や仏壇に飾る位牌を用意しない - 枕飾りを設置しない
供養の文化がないため、枕団子・枕飯・水は不要
なお、弊社は浄土真宗大谷派に対応した葬儀を全国に提供しており、相場よりも抑えた価格で、必要なものを含んだ明瞭なセットプランの葬儀をご用意しております。事前のお問い合わせで特別価格でご案内しておりますので、まずはお気軽に資料をお取り寄せください。
浄土真宗大谷派の葬儀の流れ
真宗大谷派の葬儀は、「葬儀式第一」と「葬儀式第二」の2部構成で行われます。かつては葬儀式第一を自宅・葬儀式第二を斎場で行っていましたが、現代ではどちらもひとつの会場で執り行うのが一般的です。
お通夜
真宗大谷派のお通夜は、仏間に祭壇を設置して行うのが一般的です。祭壇には南無阿弥陀仏の掛け軸を飾り、仏壇にはお茶・仏飯・お花をお供えします。お通夜を行う前に故人の身体に白衣を着せ、顔に白布をかけて北枕に安置します。
式では、僧侶を招いて勤行をあげてもらいます。これは故人を見守り続けてくれた仏様に感謝を伝えるものであり、故人への祈祷ではありません。故人が生前に法名を授かっていなかった場合には、お通夜のなかで「帰敬式」を行うこともあります。
納棺式
葬儀・告別式の前に、故人を納棺する儀式を行います。湯灌を行って故人の身だしなみを整えた後、手に木製の念珠をかけて合掌させた形で棺に納めます。
ご遺体の上には南無阿弥陀仏と記された「納棺尊号」という紙を置き、万が一の際に阿弥陀仏を拝む形を取れるようにします。これは、故人に対して祈りを捧げるのではなく、阿弥陀如来へ祈りを捧げるという前提からくる風習です。最後に棺に七条袈裟がかけられ、納棺勤行が行われます。
葬儀・告別式
真宗大谷派の葬儀・告別式は、「葬儀式第一」と「葬儀式第二」の2部に分かれています。
葬儀式第一では、阿弥陀如来への感謝を示す「棺前勤行」と読経・焼香をする「葬場勤行」の2つの儀式を行います。葬儀式第二では、故人が阿弥陀仏の救いによって極楽浄土へ導かれたことを讃え、旅立ちを見送ります。葬儀を通して仏への感謝が新たになり、参列者の信仰心も高められます。以下は、一般的な真宗大谷派の葬儀の流れです。
<葬儀式第一>
◯棺前勤行
- 総礼
参列者全員で敬礼する - 勧衆偈 (かんしゅうげ)
中国の経典『観経疏』のお経を唱える - 短念仏十遍
短い念仏を10回唱える - 回向(えこう)
- 総礼
参列者全員で敬礼する - 三匝鈴(さぞうれい)
小さな鈴から大きい鈴へ順に鳴らす - 路念仏(じねんぶつ)
南無阿弥陀仏四句を一節とする念仏を唱える
◯葬場勤行
- 三匝鈴
小さな鈴から大きい鈴へ順に鳴らす - 路念仏
南無阿弥陀仏四句を一節とする念仏を唱える - 導師焼香
僧侶による焼香 - 表白(ひょうびゃく)
仏や参列者に葬儀を行う意義を伝える - 三匝鈴
小さな鈴から大きい鈴へ順に鳴らす - 路念仏
南無阿弥陀仏四句を一節とする念仏を唱える - 弔辞
代表者が弔辞を述べる - 正信偈
親鸞による経典『教行信証』を唱える - 和讃
阿弥陀如来を褒め称える讃歌を唱える - 回向
回向文を唱える - 総礼
参列者全員で敬礼する
<葬儀式第二>
- 総礼
参列者全員で敬礼する - 伽陀(かだ)
僧侶が着座したことを知らせる - 勧衆偈
仏道を勧める偈文を読経する - 短念仏十遍
短い念仏を10回唱える - 回向
回向文を唱える - 総礼
参列者全員で敬礼する - 三匝鈴
小さな鈴から大きい鈴へ順に鳴らす - 路念仏
南無阿弥陀仏四句を一節とする念仏を唱える - 三匝鈴
小さな鈴から大きい鈴へ順に鳴らす - 導師焼香
僧侶による焼香 - 表白
仏や参列者に葬儀を行う意義を伝える - 三匝鈴
小さな鈴から大きい鈴へ順に鳴らす - 正信偈
親鸞による経典『教行信証』を唱える - 短念仏
短い念仏を唱える - 三重念仏
法然が説いた三つの念仏を唱える - 和讃
阿弥陀如来を褒め称える讃歌を唱える - 回向
回向文を唱える - 総礼
参列者全員で敬礼する
火葬・初七日法要
葬儀を終えたら、遺族や親族のみで火葬を行います。火葬の前には僧侶が「重誓偈(じゅうせいげ)」というお経を唱え、故人が阿弥陀仏の誓いの中にあることを確認します。
火葬後は遺骨を拾い上げて骨壷に詰める「お骨上げ」の儀式を行いますが、真宗大谷派はほかの仏式の宗派と一部内容が異なります。一般的なお骨上げの儀式では、すべての遺骨を骨壷に納めます。一方で真宗大谷派では、喉仏のお骨以外を骨壷に納め、取り分けた喉仏は本山である東本願寺に納骨するのが習わしです。
火葬を終えたら、自宅や斎場で初七日法要を行います。本来は亡くなってから7日目に行う法要ですが、近年は火葬の後に繰り上げて行うのが一般的です。初七日法要では、仏の教えを再確認しながら、故人への感謝を捧げます。
なお、弊社では浄土真宗大谷派の僧侶のご手配も全国で承っております。読教や戒名・御車代なども含んだ定額のお布施のため、ご安心してご利用いただけます。
四十九日法要
仏教では亡くなってから49日目を忌明けの日と定め、この日を境に故人の魂が成仏すると考えられています。真宗大谷派は往生即身仏の考えを持ちますが、四十九日も大切な節目として法要を行います。
真宗大谷派における四十九日法要は、故人の成仏を願うものではなく、遺族が仏の縁に感謝し、教えに触れる機会です。僧侶による勤行と法話を通じて浄土真宗への理解を深め、残された家族が心の安らぎを得られるように祈ります。
浄土真宗大谷派の葬儀に参列するときのマナー
真宗大谷派の葬儀では、他の宗派とは異なる作法がいくつかあります。参列前に正しいマナーを知り、故人と阿弥陀仏への敬意を示しましょう。
焼香の回数は2回
浄土真宗大谷派では、焼香の際に香を額に押しいただく作法を行いません。焼香の回数は、2回が一般的です。なお、真宗大谷派の焼香回数は1回と異なるため、間違えないように注意してください。
浄土真宗の葬儀における焼香は、故人に香を手向けるというよりも、仏様への敬意を表す意味合いが大きいといわれています。自分の番が回ってきたら、香をつまんで香炉にそっと置き、「南無阿弥陀仏」と唱えながら合掌しましょう。
切り房の付いた数珠を用いる
真宗大谷派では、太い切り房の飾り房が付いた数珠を使用します。僧侶は本式のものを用いますが、参列者は略式数珠でかまいません。浄土真宗では、数珠はあくまで祈祷のための道具という位置付けのため、念仏の回数を数えにくいデザインになっています。
合掌時は親指に挟むようにかけ、飾り房は左手親指の外に垂らします。合掌していないときは左手に持ち、女性用や子供用の数珠は二重にしたままでも問題ありません。なお、信州本願寺派は撚り房のついた数珠を使用するため、宗派による違いに気を付けましょう。
香典の表書きは「御仏前」や「御香典」
浄土真宗大谷派では、故人が亡くなってすぐに成仏できると考えるため、香典の表書きは「御仏前」や「御香典」とするのが適切です。他宗派で使われることが多い「御霊前」は、浄土真宗での使用は避けましょう。
香典の金額は故人との関係性や地域によって異なりますが、一般的な相場に合わせて包むのがマナーです。故人が両親の場合は3〜10万円、祖父母の場合は1〜5万円程度を包みましょう。
用意した香典袋はふくさに包み、渡すときにはふくさから取り出して両手で手渡します。そのほかにも香典袋の書き方や包み方にはさまざまなルールがあるため、ぜひ以下の記事でチェックしてください。
喪服を着て参列する
真宗大谷派の葬儀に参列する際の服装は、一般的な喪服で問題ありません。男性は黒のスーツに黒のネクタイ、女性は黒のワンピースやアンサンブルなどのブラックフォーマルを身に付けましょう。真宗の門徒の方は「門徒式章」や「門徒肩衣」を掛けて参列する風習があります。
なお、葬儀の装いは服装だけでなく、小物や身だしなみにもさまざまなマナーがあります。以下の記事では家族葬における服装のマナーを詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
線香は寝かせて供える
真宗大谷派の線香の供え方には、独自の作法があります。一般的な線香は香炉に立てて供えますが、真宗大谷派では線香を2つまたは3つに折り、香炉の中に寝かせて供えます。向きは火がついた方を左にし、香炉の大きさに応じて本数を調整します。
この供え方は、古くに常香盤という香炉を使ってお香を焚いていた名残といわれています。宗派ごとの違いに配慮して、正しい作法でお供えしましょう。
念仏の発音に気を付ける
浄土真宗で広く用いられる「南無阿弥陀仏」の念仏ですが、実は宗派によって発音方法に違いがあります。真宗大谷派では、「なむあみだぶつ」と一息で発音するのが正式です。なお、本願寺派では「なもあみだぶつ」と発音するため、混同しないように注意しましょう。
お悔やみに使用できない言葉がある
真宗大谷派では、亡くなった方はすでに阿弥陀仏のもとで仏となっているとする「往生即身仏」の考え方が基本です。そのため、葬儀の場で「ご冥福をお祈りします」や「安らかにお眠りください」などの往生を願う言葉をかけるのはふさわしくありません。
葬儀に参列する際は、これらの言葉の代わりに、「このたびはご愁傷さまでございます」や「仏さまのお導きのもと、安らかにお浄土へ向かわれたことと存じます」など、真宗大谷派の考え方に合った言葉を選ぶようにしましょう。
浄土真宗大谷派のお布施のマナー
真宗大谷派のお布施の相場は10〜30万円で、ほかの仏教の宗派に比べてやや安めです。ただし、地域や寺院によって目安の金額が異なる場合もあるため、不安な方は事前に寺院や葬儀社に確認しましょう。
僧侶の送迎代や食事代として「御車料」や「御膳料」を包む場合は、お布施と同じタイミングで手渡します。なお、真宗大谷派では、法名を授けてもらったお礼は基本的に発生しません。これは、「法名をは葬儀のなかで必然的に付くもの」という考え方によります。
| 宗派 | 金額相場 |
|---|---|
| 浄土真宗 | 10〜30万円 |
| 浄土宗 | 15〜50万円 |
| 真言宗 | 30〜70万円 |
| 曹洞宗 | 30〜100万円 |
| 天台宗 | 40〜70万円 |
| 臨済宗 | 30〜50万円 |
| 日蓮宗 | 30〜60万円 |
浄土真宗大谷派の葬儀費用の相場
真宗大谷派の葬儀費用の相場は、一般的な仏式の葬儀費用の相場とほとんど変わりません。
近年主流となっている家族葬であれば30〜100万円程度が目安で、それよりも簡素な形式を選ぶ場合は50万円以下で収まる場合もあります。反対に、会葬者が多い一般葬や会場の規模が大きい場合などは200万円に上ることもあるため、希望する形式と予算に応じて適切に計画を立てることが重要です。
| 葬儀形式 | 費用相場 |
|---|---|
| 一般葬 | 100~200万円程度 |
| 家族葬 | 30~100万円程度 |
| 一日葬 | 30~50万円程度 |
| 直葬・火葬式 | 20~50万円程度 |
なお、弊社は相場よりも抑えた価格で浄土真宗大谷派に対応した葬儀を提供しております。こちらは葬儀に必要なものを含んだ分かりやすいセットプランとなっておりますので、葬儀が初めての方もご安心して利用いただけます。
大谷派の葬儀の特徴を知り、マナーを守って参列しましょう
浄土真宗の一派である真宗大谷派は、「絶対他力」や「往生即身仏」の考えのもと葬儀を執り行います。葬儀では、故人が無事に極楽浄土へ成仏できたことを讃え、阿弥陀如来に感謝の祈りを捧げましょう。
弊社では、浄土真宗大谷派に対応し、価格を抑えたプランパックでの葬儀を全国一律価格でご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。