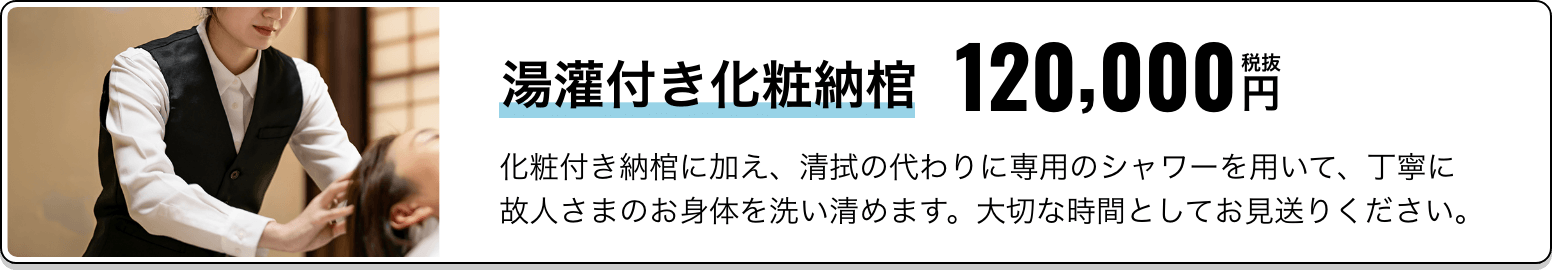葬儀を執り行う際には、お通夜や告別式、焼香といった一連の儀礼が行われますが、そのなかの一つに「湯灌(ゆかん)」があります。湯灌とは、故人を見送る前に最後の身支度を整える儀式であり、故人への感謝や敬意を表す意味でも多くの方が選択しています。
湯灌を知ってはいるものの「実際の流れや費用、儀式が必要なものなのかわからない」という方もいるのではないでしょうか。この記事では、湯灌の意味や費用相場、プランの選び方などについて分かりやすく解説していきます。
この記事を要約すると
- 湯灌とは、故人の体を洗い清めて身支度を整える儀式で、感謝と敬意をこめて見送るための儀式。
- 湯灌の費用相場は3〜10万円ほどで、清拭プランやパッケージプランを選ぶことで費用を抑えられる。
- 湯灌は必ず実施しなければならないわけではなく、遺族の気持ちや事情に合わせて判断して問題ない。
湯灌とは、故人に最後の身支度を整えるための儀式のこと
湯灌(ゆかん)とは、故人を棺に納める前に、髪や体を洗い清めて衣服を整え、必要に応じて化粧を施す一連の儀式です。もともとは遺族や近親者が協力して行うものでしたが、現在は専門の湯灌業者が自宅や安置所に専用の設備を持ち込んで執り行うのが一般的です。
宗教儀礼というよりは、故人に感謝と敬意をこめて身支度を整える”最後のケア”として行われるケースが多く、形式やタイミングは地域や遺族の意向によっても異なります。立ち合いを希望する人が限定されることもあり、納棺とセットで静かに執り行われます。
湯灌は必須ではないものの「きれいな姿で送り出してあげたい」と願う家族にとって、心を込めて見送るための大切な時間です。
湯灌にかかる費用の相場は?
湯灌にかかる費用は、その方法や依頼内容によって変わります。代表的な方法として「古式湯灌」と「普通湯灌」の2種類があり、それぞれで金額の目安が異なります。
古式湯灌は、ご遺体を湯船に入れることなくアルコールやぬるま湯で清める比較的簡易な儀式で、費用相場は3〜5万円程度です。
一方で、湯船やシャワー設備を使って全身を洗い、着替えや死化粧までを行う「普通湯灌」は10万円前後が一般的です。
なお、湯灌は多くの葬儀プランには含まれておらず、オプションとして追加する必要があります。費用を抑える方法として、遺族らが自ら行う「家族湯灌」という選択肢もありますが、スペースや準備、知識が必要になるため、慎重に判断しましょう。
事前に葬儀社とよく相談して納得のいく内容を選ぶことが大切です。
湯灌の費用が変動するポイント
湯灌は葬儀の基本プランに含まれていないことが多く、追加で依頼する際の費用は以下の内容によって変動します。
- 湯灌方法:古式湯灌や普通湯灌など
- 実施場所:自宅や安置所など
- 時間帯:遺族が全員揃うタイミングでの実施など
- オプションの有無:死装束の種類や納棺とのセットプランなど
葬儀会社にもよりますが、安置所で湯灌する場合は施設の設備を利用できるため費用を抑えられる一方で、自宅で執り行う場合は設備の持ち込みなどで追加費用が発生する可能性があります。
遺族が揃うタイミングによって、深夜や早朝など湯灌の日程を希望する場合も、追加料金が発生することがあります。なかにはプランに含まれているケースもあるため、事前に内容と詳細を確認するようにしましょう。
湯灌の費用はなぜ高い?料金の内訳を解説
湯灌の費用が高額になりやすいのは、衣装やメイクといった目に見える部分だけでなく、背後にかかる多くのコストが含まれているためです。
具体的には、湯灌を担当する専門スタッフ2名以上の人件費、専用の簡易浴槽やバスタブの運搬、設置にかかる費用、使い捨ての清拭用品や消毒用品、お湯の準備といった内容です。
また、死装束やメイク用品の質によっても価格は変動します。安価な死装束は数千円程度からありますが、正絹製や刺繍入りなど高級なものは数万円以上となることもあります。死化粧も専門技術を伴うため、オプション扱いで別途料金が発生するケースがあります。
このように、湯灌は一見シンプルな儀式に見えても、細かな工程や準備に多くの手間と費用がかかっているため、相応の価格設定となっているのが実情です。
湯灌費用を安くする方法
湯灌を取り入れたいものの、費用はできるだけ抑えたいと考える方もいるのではないでしょうか。湯灌には内容や依頼方法によって費用を抑える方法がいくつかあります。
ここでは、無理なく湯灌を行うための具体的な節約ポイントを紹介します。
清拭のみのプランを選ぶ
湯灌の費用を抑える方法の一つが「清拭のみ」のシンプルなプランを選ぶことです。入浴設備を使わず、故人の顔や手足などをタオルで丁寧に拭き清めるもので、必要最低限の身支度にとどめられます。
費用の目安は3〜5万円程度で、一般的な湯灌よりも手頃です。葬儀社によっては清拭ではなく、メイクのみを依頼するプランもあるため、どこまで対応してもらえるか、事前に詳細を確認しておきましょう。
湯灌付き納棺のパッケージを選ぶ
湯灌と納棺の儀式を個別に依頼するよりも、セットになったパッケージプランを選ぶことで費用を抑えられます。
たとえば「納棺の儀プラン」「湯灌付き納棺プラン」などの名称で提供されており、湯灌・死装束・納棺の一連の流れが含まれていると費用を抑えやすくなります。
このようなプラン内容は葬儀社によって細かく分けられているため、公式サイトやパンフレットを確認し、比較することが大切です。
複数社に見積もりを依頼する
同じ湯灌サービスでも葬儀社や業者によって価格帯や提供内容には大きな差があります。そのため、湯灌だけでなく全体のプラン内容を比較するためにも、必ず複数社に見積もりを依頼しましょう。
また、ちょっとした要望であれば作業内容を追加してくれたり、別の儀式を簡略化して費用を調整してくれたりすることもあります。気になることがあれば、遠慮せずに相談してみましょう。
複数の葬儀社に見積もりを依頼する際には、費用だけでなく対応の速さや丁寧さ、スタッフの態度なども総合的に判断することで、満足度の高い葬儀を執り行えます。
湯灌費用のよくある質問Q&A
湯灌の費用相場や内訳、安くするポイントなどについて解説してきましたが、まだまだ湯灌について気になることがあるという方もいるのではないでしょうか。
ここでは、湯灌の費用や内容に関する7つのよくある質問に答えていきます。内容を理解したうえで湯灌の内容を検討してみましょう。
葬儀費用に湯灌は含まれている?
葬儀費用は、葬儀社によってさまざまな料金プランが用意されていますが、湯灌は含まれていないのが一般的です。オプション扱いであるケースが多く、依頼する場合は追加料金が発生します。
葬儀社によっては「納棺の儀」などに湯灌が含まれていることもありますが、メイクだけや簡単な身支度のみの場合もあります。全身の洗体や本格的なメイクなどを希望する場合は、事前に相談しておきましょう。
市町村の補助金は使える?
故人が健康保険に加入していた場合、遺族や市区町村に申請すると、葬儀費用の一部を補助する給付金を受け取れることがあります。社会保険加入者には「埋葬料」国民健康保険加入者には「埋葬費」として、一般的に1〜5万円が支給されます。
支給額や申請先は自治体によって異なり、申請期限も通常は死亡翌日から2年以内と定められているため、早めに手続きをしましょう。申請時には、故人の保険証や喪主名義の振込口座、葬儀の証明書などが必要になるため、事前に確認しておくと安心です。
なお、遺族が生活保護を受けているなど経済的に厳しい場合は「葬祭扶助制度」が利用できるケースもあります。こちらは、直葬にかかる最低限の費用(棺や火葬費など)を自治体が負担する制度で、申請は葬儀前に行う必要があります。
湯灌はキャンセルできる?
湯灌は葬儀プランに最初から含まれていないことも多く、希望しない場合はそもそも依頼しなければ問題ありません。ただし、湯灌をオプションとして追加し、その後キャンセルしたい場合は、契約内容やキャンセルのタイミングによって対応が異なります。
準備や人員手配が進んでいた場合、キャンセル料やそのままの料金が発生する可能性があるため、早めに意思を伝えましょう。
相見積もりはとれる?
湯灌を含む葬儀サービスでも、ほかのサービスと同様に相見積もり(複数社から見積もりを取ること)は可能です。
特に湯灌はオプション扱いとなっていることが多く、葬儀社や業者によってサービス内容や費用に大きな差が出やすいため、比較することには大きな意味があります。
相見積もりを行うと、適正価格が把握できるだけでなく「必要なサービスだけを選ぶ」という視点で無駄な出費を防ぐことにもつながります。ただし、見積もりを依頼する際は、同じ条件で依頼すること、そして強引な営業を受けた際にはきっぱりと断る姿勢も大切です。
なお、葬儀や湯灌に関する検討は、亡くなってからでは時間に追われてしまいがちです。できるだけ元気なうちから、ある程度の希望を話し合っておくことで、いざというときに冷静に判断できます。
そもそも湯灌は必要?
湯灌とは、故人の体をきよめて身なりを整えて旅立ちの支度をする儀式です。故人への感謝や敬意をこめて行われることが多く「きれいな姿で送り出してあげたい」という遺族の想いを形にするものといえます。
しかし、湯灌は仏教僧において必須とされているわけではありません。近年では、費用面や時間的な都合、宗教的な理由から湯灌を行わないケースも増えてきました。依頼したとしても清拭や整容だけで納棺する方も少なくありません。
大切なのは、形式にとらわれすぎず、故人と遺族の想いや希望に沿った内容で執り行うことです。葬儀社と相談しながら、自分たちにとって納得のいく送り方を選ぶことが何よりも大切です。
湯灌には誰が立ち会える?
湯灌は、湯灌師や葬儀社の専門スタッフが行う儀式で、必要に応じて遺族が洗髪や拭き清めなどを手伝うこともあります。ただし、故人のプライバシーに配慮するため、湯灌に立ち会えるのは遺族や親族などの近親者に限られるのが一般的です。
実施にあたっては、専門業者が浴槽や必要な設備を準備し、目隠しとなる屏風などで空間を仕切ります。親しい友人などに立ち合いを希望された場合、断ってもマナー違反にはあたらず、原則として湯灌は家族だけで見守る静かな時間とされています。
なお、遺族であっても立ち合いは義務ではなく、精神的な負担を避けるために全てを専門スタッフに任せることも可能です。
エンゼルケアやエンバーミングとの違いは?
湯灌と混同されやすい処置として「エンゼルケア」と「エンバーミング」がありますが、それぞれに目的や方法が異なります。
エンゼルケアは、主に病院や介護施設で看護師や介護士が行うケアで、体を拭いたり綿を詰めたり、簡単なメイクを施すなど、ご遺体を清潔な状態に整える処置です。
一方、エンバーミングは腐敗処置のための専門技術で、ご遺体に防腐剤を注入することにより長期保存が可能です。費用は15〜25万円で、専門施設にて「エンバーマ」と呼ばれる技術者が実施します。海外への輸送や遺体保存が必要なケースで選ばれることがあります。
湯灌は精神的・儀式的な意味合いが強いのに対し、エンゼルケアやエンバーミングは、医療的・実務的な性質が強い処置といえるでしょう。
費用だけでなく意味も踏まえて湯灌を検討しよう
湯灌とは、故人の体を清めて身支度を整える、旅立ち前の大切な儀式です。費用の相場は、3〜10万円程度で、方法や実施場所、サービス内容(着替え・メイクの有無など)によって変動します。
清拭のみのプランや、納棺とのパッケージを選べば費用を抑えることも可能です。湯灌は必須の儀式というわけではなく、遺族の意向や事情に応じて実施しない選択肢もあります。大切なのは形式にとらわれることではなく、故人をどう送りたいかという気持ちです。
費用だけで判断するのではなく、湯灌の意味も踏まえたうえで、無理のない範囲で検討してみましょう。
なお、弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。