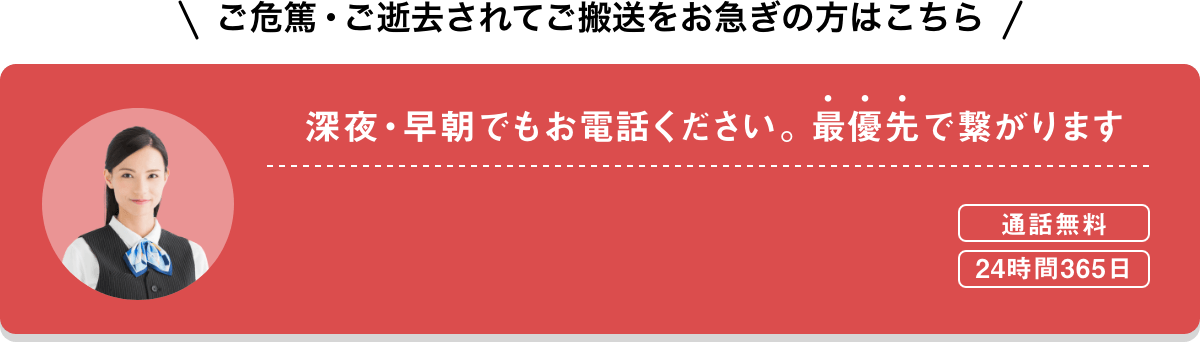親が亡くなった際は、葬儀の準備など、やるべきことが数多く発生します。そんななかで、仕事を何日くらい休めるのか不安に感じる方もいるでしょう。
忌引き休暇の取得日数は、会社の規定や故人との関係性によって異なります。また、会社への休暇連絡も必要です。場合によっては、葬儀の案内状を送付したり業務の引き継ぎを行ったりすることもあるでしょう。
本記事では、親が亡くなった場合に何日程度の忌引き休暇を取得できるのか、会社への連絡方法について解説します。さらに、忌引き明けの挨拶の仕方や忌引き休暇が取得できない場合の対処法についても紹介しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事を要約すると
- 忌引き休暇は会社の規定や故人との続柄によって異なりますが、親が亡くなった場合は7日間取得できるのが一般的です。
- 忌引き休暇を取得する場合は、メールよりも電話で連絡するほうがより状況が伝わりやすくなります。必要に応じて葬儀の案内状を出したり、参列や香典を遠慮することを伝えたりしましょう。
- 忌引き明けは、なるべく早くお礼の挨拶をするとよいでしょう。菓子折りや香典返しを準備し、お休みをいただいたことや仕事を代わってもらったことなどについて具体的に感謝を伝えましょう。
親が亡くなったら何日休める?
葬儀に参列するだけであれば、2〜3日程度の休暇で対応できる場合もあります。しかし、自分が喪主や遺族として葬儀の準備を担う場合は、さらに多くの休暇が必要になるでしょう。ここでは、忌引き休暇が何日程度取得できるのかを解説します。
忌引き休暇の日数は7日が一般的
そもそも忌引き休暇は、会社の福利厚生として用意されていることが多く、法律では定められていません。会社によって長く休めたり休暇を取れなかったりすることもありますが、一般的な例を紹介します。
忌引き休暇の日数は、故人との関係性によって取得できる日数が異なります。大切な方が亡くなると精神的に負担が大きく、やることも多いため長めに設定されています。親が亡くなった場合は、一般的に7日間(1週間)取得できる傾向があります。
| 故人との続柄 | 忌引き休暇の日数 |
|---|---|
| 両親 | 7日間 |
| 配偶者 | 10日間 |
| 子ども | 5日間 |
| 兄弟姉妹 | 3日間 |
| 祖父母 | 3日間 |
| 義理の両親 | 3日間 |
| 孫 | 1日間 |
| おじ・おば | 1日間 |
たとえば、兄弟姉妹や祖父母が亡くなった場合でも、自分が喪主を務めるときは、通常よりも長めに休暇を取得できることがあります。
亡くなる時期が読めず病院へ頻繁に通ったり、亡くなったあとの年金・保険の手続きを行ったりなど、やるべきことは数多くあります。
忌引き休暇の起算日や休日の扱いには、注意が必要
忌引きの日数を確認したあとに注意したいのが、日数の数え方です。開始日や、土日・祝日が忌引きに含まれるかどうかは、会社の慶弔規定によって異なります。必ず就業規則を確認するか、人事部門に問い合わせましょう。
一般的には、亡くなった当日または翌日を1日目として数えるケースが多いものの、通夜の日を開始日とする企業もまれにあります。また、休日も忌引き日数に含まれることが一般的です。この場合、たとえば7日間の忌引き休暇を取得できても、土日を挟むと実際に平日に休めるのは5日間となります。
親が亡くなったら会社に連絡が必要
たとえ家族が危篤であることを事前に伝えていても、いつ亡くなったのか、いつまで休むのかがわからないままでは、会社に心配や迷惑をかけてしまいます。必ず状況を連絡しましょう。
多くの会社では、結婚・出産・死亡といった場合に備えて、休暇や見舞金に関する慶弔規定が設けられています。休暇の取得や見舞金の受け取りには、所定の手続きが必要です。また、休暇中に業務を上司や同僚に引き継ぐ際も、できるだけスムーズに進められるよう、わかりやすく伝えることが大切です。
口頭で連絡する
亡くなった直後は、まず会社に電話で連絡を入れましょう。葬儀の日程がまだ決まっていない場合も多いですが、わかっている範囲の情報だけでも、できるだけ早く直属の上司に伝えることが大切です。メールなどの文面よりも、電話のほうが迅速に状況を伝えることができます。
電話で連絡したあと、落ち着いてから改めて葬儀の案内や仕事の引き継ぎに関する詳細をメールで正確に伝えるようにしましょう。特に、急ぎの対応を必要としない取引先などには、メールで連絡したほうが丁寧で、誤解も生じにくくなります。
訃報連絡を行うタイミングや連絡手段については、以下の記事でも詳しく解説しています。
伝えるべき内容を整理する
次に伝えるべきことを整理します。以下の内容を盛り込むとよいでしょう。
- 亡くなった日
- 故人との続柄
- 緊急連絡先
- 引き継ぐ仕事内容
連絡するタイミングにもよりますが、最初の連絡では、亡くなった日と故人との続柄を伝えるようにしましょう。その後の手続きでは、さらに詳細な情報や死亡診断書の提出を求められる場合もあります。
また、忌引き休暇中に仕事上で確認が必要な場面が出てくることも考えられます。あらかじめ緊急連絡先を伝えておくと安心です。あわせて、仕事の引き継ぎが必要な場合は、どなたに依頼するかを明確に伝えておくと、よりスムーズに進められます。
会社への連絡や休暇の手続きを終えると、次は葬儀の準備や各種手続きを進めていくことになります。
突然のことで、仕事と並行しながら何を優先すべきか分からず、不安を感じる方も少なくありません。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、葬儀の進め方はもちろん、ご家族の状況に合わせた段取りについてもご相談を承っています。弊社は、必要なものを含んだ明瞭なセットプランでの家族葬を、全国に提供しています。
まだ何も決まっていない段階でも構いませんので、お困りのことがあればお電話でお気軽にご相談ください。
会社への訃報連絡のマナーについては、以下の記事で詳しく解説しています。連絡する相手やメールの書き方に迷った際は、ぜひ参考にしてください。
状況に応じた葬儀に関する連絡の仕方
葬儀の日程や形式が決まったら、改めて勤務先にも連絡を入れましょう。葬儀への参列をお願いする場合や、香典をいただく場合はもちろん、参列をご遠慮いただく場合でも、その旨をきちんと伝えることが大切です。
参列いただく場合や弔電をいただく場合は案内状を出す
会社の風土や故人との関係性によっては、遺族の勤務先の方が葬儀に参列されることもあります。参列していただく可能性がある場合は、故人の友人や知人と同様に案内状を送付しましょう。
ただし、通夜や告別式まであまり時間がないことがほとんどです。案内状が届くまでに時間がかかるため、決まり次第、先にメールで以下の内容を連絡しておくと親切です。
- 故人の氏名や続柄
- 葬儀の日時
- 葬儀の場所
- 喪主の氏名や連絡先
また、香典やお花を受け取るかどうかも、あらかじめ決めておきましょう。遠慮するつもりであっても、事前に伝えておかないと相手が準備を進めてしまうこともあります。特に、香典については連絡がないと用意してくださる場合が多いため、相手に余計な気遣いをさせないよう注意が必要です。
参列を遠慮する場合はその旨を伝える
葬儀の会場が遠方にある場合や葬儀形式が家族葬となる場合は、参列をご遠慮いただくこともあるでしょう。訃報を受けた方が参列すべきか悩まないよう、あらかじめ参列をご遠慮いただく旨を伝えておくことが大切です。
連絡する時点で詳細が決まっていない場合は、後日改めて連絡し直すか、「家族葬になる可能性がある」と伝えておくとスムーズです。電話連絡をした際には、「全体に伝えていただけますか」と一言添えると情報共有が漏れにくくなります。
また、一人ひとりに案内状を送付して連絡する方法も丁寧です。参列しない場合でも、弔電を送りたいと考える方もいるため、案内状には故人の氏名や葬儀会場を明記しておくとよいでしょう。ただし、家族葬であること、弔問はご辞退させていただく旨を必ず記載します。
忌引き明けにすること
「忌引き休暇が終わっても、次のことを考えられないまま、気づけば明日が出勤日。」と、慌てることもあるでしょう。前日までに菓子折りを用意し、当日は朝一番に挨拶を済ませることで、スムーズに職場復帰しやすくなります。ここでは、忌引き明けに行うべきことを紹介します。
すぐに上司や同僚にお礼の挨拶をする
忌引き明けの初日は、出勤したら朝一番に挨拶をしましょう。休暇をいただいたことや仕事を代わってもらったこと、香典をいただいたことなど、具体的に感謝の気持ちを伝えると、より丁寧な印象になります。
また、お悔やみの言葉をかけてもらう場面もあるでしょう。その際は、葬儀が滞りなく終わったことや今日から通常通り業務に復帰することを伝えると、相手に余計な心配をかけずに済みます。
香典返しや菓子折りをお渡しする
会社によっては、香典をまとめて渡してくださる場合もあります。その際は、受け取った香典の金額に応じて香典返しを用意しましょう。香典返しの目安は、いただいた香典の半額程度です。万人受けしやすいおかきやクッキーなど、賞味期限が比較的長く、個包装になっているものを選ぶとよいでしょう。
一般的には、故人の友人で香典をいただいていない方や弔電のみの方には、特別なお礼の品を用意する必要はないとされています。ただし、勤務先に対しては、休暇をいただいたことへの感謝を込めて菓子折りを準備しておくと無難です。
取引先にもアポイントの変更をお願いした場合など、必要に応じてお礼の品を用意しておくとよいでしょう。
直接会えない方には電話やメールで伝える
リモートワークや出張などで、直接顔を合わせる機会がないこともあるでしょう。その場合でも、対面できるタイミングを待たず、忌引き明けにすぐ連絡を取ることが大切です。
メールでの連絡でも問題ありませんが、可能であればビデオ通話や電話など、対面に近い手段を使ったほうが感謝の気持ちが伝わりやすくなります。より丁寧にお礼を伝えたい場合は、お礼状を準備するのもよいでしょう。
連絡するときの文言集
連絡する必要があるとわかっていても、どのように伝えればよいか、わかりやすさや失礼がないかに迷うこともあるでしょう。そこで、実際に連絡する際に使える文例をまとめましたので、ぜひ参考にしてください。
訃報の連絡をする場合(電話)
お疲れ様です。〇〇部の△△です。
今朝(昨晩)、私の父親が亡くなりましたので、ご連絡させていただきました。
急なご連絡となり、大変申し訳ありません。
〇月〇日まで、忌引き休暇を申請させていただきたく存じます。
葬儀および告別式は、親族のみで執り行う予定ですが、詳細が決まり次第、改めてご連絡いたします。
葬儀についての連絡をする場合(メール)
件名:【訃報】〇〇〇〇儀(父)
本文:
〇〇部の△△です
急なご連絡となり大変恐縮ですが父〇〇〇〇が〇年〇月〇日に永眠いたしました
なお葬儀は親族のみで執り行う予定です
つきましてはご参列ご香典ご供花はご辞退させていただきます
取り急ぎメールにてご連絡申し上げます
△△ △△
忌引き明けの挨拶(対面)
この度は、父の葬儀にあたり、皆様から弔電やご香典を賜りまして、誠にありがとうございました。
また、急な申し出であったにもかかわらず、何日もお休みをいただき、ご迷惑をおかけしました。不在の間に仕事を引き継いでくださり、心より感謝申し上げます。
おかげさまで、無事に父を見送ることができました。本日より業務に復帰いたしますので、改めてよろしくお願いいたします。
これらの文例を使って連絡を終えたあとは、葬儀の準備や今後の流れについて考える必要が出てきます。
突然のことで、仕事や手続きと並行しながら判断しなければならず、「何から進めればよいのか分からない」と感じる方も少なくありません。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、全国に必要なものを含んだセットプランでの家族葬を提供しています。
ご家族の状況をお伺いしながら、葬儀の進め方や段取りについてのご相談を承っています。
親が亡くなった際の会社連絡でよくある質問
ここまで、忌引き休暇の日数や会社への連絡方法、忌引き明けのお礼の仕方について基本的なポイントを説明しました。ここからは、忌引きに関連してよくある質問をまとめました。
故人が就業していた場合はどうする?
遺族の勤務先に忌引きの連絡をするだけでなく、故人が勤めていた会社にも連絡が必要です。連絡の際は、要件とあわせて、故人の名前や関係性、自分の名前をはっきりと伝えましょう。故人が所属していた部署名などがわかれば、事前に確認してから連絡するほうが安心です。
また、故人が現役で勤務していた場合、勤務先の方から葬儀への参列を希望されることもあります。案内状を送る際に、送り先を確認しておくとよいでしょう。参列や香典を辞退する場合は、その旨もきちんと伝えるようにします。
遠方の場合は、忌引きの日数は増える?
故人の住んでいた地域や葬儀会場が遠方であれば、移動だけでも多くの時間を要することがあります。通常は、移動時間も含めて忌引き休暇に含まれる傾向があります。飛行機や新幹線などの手配が必要な場合は、できるだけ早めに予約を行い、見通しを立てて行動しましょう。
ただし、会社によっては、通常の忌引き休暇に加えて移動日も別途休暇として認められる場合もあります。事情を説明したうえで、早めに相談してみるとよいでしょう。
忌引きが使えなかったらどうする?
忌引き休暇は取得できることがほとんどですが、あくまで会社の福利厚生制度のひとつであり、必ず用意されているとは限りません。勤続年数や雇用形態によっては使用できない場合もあり、制度があっても、入社して間もない場合には適用外となることもあります。
忌引き休暇が使えない場合は、有給休暇を利用できるか確認してみてください。欠勤扱いになると勤務評価に影響が出る可能性もありますが、有給休暇として取得できれば欠勤にはならずに済む場合が多いでしょう。必ず就業規則を確認することをおすすめします。
葬儀をスムーズに行うなら経験豊富な葬儀社に相談を
大切な人が亡くなると、葬儀の準備や会社・親戚への連絡など、やるべきことが山積みになります。さらに、保険や年金の手続き、遺品整理などを始めると、忌引き休暇中には終わらないことも少なくありません。
少しでも負担を減らし、葬儀をスムーズに進めるためには、経験豊富な葬儀社に依頼することをおすすめします。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。