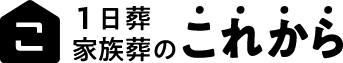孤独死が発生した場合、警察への通報から葬儀の手配まで、さまざまな手続きが必要です。とくに「警察による現場検証のあと、どのような手順で葬儀を進めれば良い?」「補助金は使えるの?」といった疑問を抱える方は、多いのではないでしょうか。
本記事では、孤独死が発生した際の葬儀の進め方から、活用できる補助金にいたるまで詳しく解説します。孤独死という突然のできごとに直面された方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を要約すると
- 孤独死発見時は警察への通報から始まり、現場検証・遺族への連絡・死亡届の提出を経て、専門業者による特殊清掃が必要です。続いて葬儀・火葬が執り行われ、遺族が見つからない場合は自治体が対応します。
- 孤独死が発生した際に使える葬儀費用の補助金には、国民健康保険の葬祭費や生活保護の葬祭扶助などを利用できます。また葬儀以外に必要な手続きには、賃貸契約の解約や特殊清掃・遺品整理などの手続きがあります。
- 孤独死を発見した際の注意点は、部屋の清掃は、警察の許可を得てから専門業者に依頼し、害虫処理から消臭まで行わなくてはいけません。
孤独死が発生したときの対応と葬儀までの流れ
孤独死が発生した際の対応には、いくつかの重要なステップがあります。
- 救急・警察への通報
- 警察による現場検証
- 遺族への連絡
- 死亡届の提出
- 特殊清掃の手配
- 葬儀・火葬の実施
救急・警察への通報から葬儀・火葬の実施まで、それぞれのステップについて詳しく解説します。
1. 救急・警察への通報
孤独死を発見した場合、まず生死の確認が必要です。呼びかけに反応がある場合や、脈や呼吸の有無が不明な場合は119番通報します。
「異臭がする」「体が硬直している」「皮膚が変色している」など、明らかな死亡徴候がある場合は110番通報するのが適切です。
通報時は「いつ」「どこで」「誰が」「どのような状態で」発見したかを正確に伝えます。警察が到着するまでは、現場の状況をそのまま保持しましょう。警察による調査の結果、孤独死と判断された場合は遺体の搬送や葬儀の手配といった次の手続きに進みます。
自宅で身内が死亡したときの対応方法については、以下の記事を参考にしてみてください。
あわせて読みたい!

葬儀の流れ
自宅で死亡したらどうしたらいい?|連絡先や死亡後の流れについて解説
2. 警察による現場検証
警察は、事件性の有無を確認するため、実況見分や必要に応じて現場検証を実施します。部屋の施錠状態や家財の散乱具合・遺体の損傷の有無などを綿密に調査されるでしょう。検証中は遺族を含むすべての関係者の立ち入りが制限されます。
そして、検視により死因や死亡推定時期が特定される流れです。現場で発見された現金や通帳・免許証・家の鍵などの貴重品は、一時的に警察が保管します。
なお。遺体の腐敗が進行している場合は、DNA鑑定による身元確認が必要です。遺体の引き渡しまでの期間は通常1週間~1か月程度が目安。現場検証から身元確認まで、状況に応じて数日から数か月を要する場合があります。
3. 遺族への連絡
警察は戸籍謄本や住民票の調査から、最も近い親族を特定します。たとえば、配偶者がいない場合は子供、子供がいない場合は親というように、法定相続人の順位に従って連絡するのが一般的です。
事件性がないと判断された場合、遺体の引き取り方法や必要な行政手続きについての説明が行われます。
遺族は死亡の事実を知った時点から3ヵ月以内に、相続を承認するか放棄するかを決めなければなりません。事前に親族間で話し合い、相続に関する方針を決めておくことで、スムーズな手続きを進められます。
4. 死亡届の提出
死体検案書の受領後、死亡の事実を知った日から7日以内に死亡届を提出する必要があります。アパートで孤独死が発見された場合、まず警察による検視が行われ、死体検案書が発行されます。
死亡届の提出先は、死亡地、本籍地に加えて、届出人の住所地でも可能です。
提出に必要な書類は、死体検案書や届出人の印鑑・死亡者の保険証などです。なお、遺族が遠方に住んでいる場合は、委任状があれば代理人が死亡届を提出できます。
期限内の手続きを確実に行うため、できるだけ早めに対応しましょう。
5. 特殊清掃の手配
孤独死の現場は、専門業者による特殊清掃が必要です。体液の染み込みや異臭の除去など、畳や床材に体液が染み込んでいる場合は、交換しなくてはいけません。
孤独死した場合の原状回復費用として、平均約38万円かかっているというデータもあります。(参考:第5回孤独死現状レポート|一般社団法人日本少額短期保険協会孤独死対策委員会)
孤独死現場の特殊清掃は専門的な技術を要するため、部屋の状態によってはさらに高い料金がかかる恐れがあることを留意しておきましょう。
6. 葬儀・火葬の実施
孤独死の場合、発見された地域で火葬されるのが一般的です。
遺族が見つからない場合は、行旅死亡人として自治体が火葬を執り行います。遺骨は自治体が一定期間保管したのち、引き取り手がない場合は無縁墓地に埋葬される流れです。
火葬については、以下の記事でも詳しく解説しています。
あわせて読みたい!

葬儀の基礎知識
火葬とは?必要な手続きや流れ・費用を解説|注意点や当日のマナー
孤独死が発生した場合に使える葬儀費用の補助金
孤独死の葬儀費用をサポートするために、いくつかの補助金制度が用意されています。
- 葬祭費
- 埋葬料
- 埋葬費
- 葬祭扶助
- 家族埋葬料
それぞれの制度について、詳しく見ていきましょう。
1. 葬祭費
国民健康保険または後期高齢者医療制度の加入者が死亡した場合、葬祭費が支給されます。制度と支給額は以下のとおりです。
| 制度 | 支給額 | 申請方法 |
|---|---|---|
| 葬祭費補助金制度 | ⚫︎国民健康保険加入:1~7万円(自治体によって異なるが5万円を支給されるケースが多い) ⚫︎後期高齢者保険加入:3~7万円 | ⚫︎市区町村役場での申請 ⚫︎申請 |
申請時には、以下の書類を用意する必要があります。
- 故人の保険証
- 死亡事実の確認書類
- 申請者の本人確認書類
- 喪主であることを証明する書類
なお、申請期限は葬儀実施日から2年以内です。
2. 埋葬料
健康保険の加入者が死亡した場合、埋葬料が支給されます。
給付額は一律5万円(参考:健康保険法第100条)です。保険組合によっては、独自の付加給付として追加の支給があります。
申請期限は、死亡した翌日から2年以内です。手続きは、故人が加入していた保険組合で行います。なお、故人との親族関係や同一世帯であることは必須条件ではありません。
3. 埋葬費
埋葬料を受け取る遺族がいない場合、実際に葬儀を執り行った人に埋葬費が支給されます。実費相当額(上限5万円)の埋葬費を申請できます。
対象となる費用は、霊柩車代や火葬料・葬壇一式料などです。この制度は、身寄りのない人の葬儀を執り行う第三者を支援する役割を果たします。
申請は、故人が加入していた保険組合で行います。
4. 葬祭扶助
生活保護法に基づく葬祭扶助は、経済的困窮者の葬儀費用を支援する制度です。以下のような場合が、葬祭扶助の対象です。
- 遺族が経済的に困窮している(生活保護受給者など)
- 扶養義務者がおらず、第三者が葬儀を執り行う
たとえば、年金暮らしの単身高齢者が孤独死し、葬儀を執り行う遺族も経済的に困窮している場合に利用できます。
詳細は以下のとおりです。
| 制度 | 支給額 | 申請方法 |
|---|---|---|
| 葬祭扶助 | 亡くなった人が12歳以上:約20万円 | 市町村の役所または福祉事務所で葬儀前に申請 |
| 亡くなった人が12歳未満:約15万円 |
検案料や遺体搬送費・火葬料・納骨料など、必要最低限の費用が葬祭扶助の対象です。葬祭扶助の申請は、葬儀前に行政窓口で行う必要がある点に留意しましょう。
支給された費用は、自治体から葬儀社に直接支払われます。
なお、葬祭扶助制度については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
あわせて読みたい!

葬儀の準備
葬祭扶助制度とは?支給金額は?申請方法や注意点などを解説
5. 家族埋葬料
健康保険加入者の扶養家族が死亡した場合、家族埋葬料が支給されます。給付額は一律5万円です。(参考:協会けんぽ|ご本人・ご家族が亡くなったとき)給付されたお金は、霊柩車代や火葬料・僧侶への謝礼などの実費にあてられます。
ただし、会食費用や香典返しの費用は対象外です。申請期限は、死亡した日の翌日から2年以内で、加入している健康保険組合で手続きします。
給付金の受け取りには、死亡診断書や葬儀費用の領収書が必要です。
孤独死が発生したときに必要な葬儀以外の手続き
孤独死が発生した際には、葬儀の手配以外にもいくつかの重要な手続きがあります。
- 賃貸契約関係の終了手続き
- 遺品整理
- 特殊清掃
それぞれの手続きについて詳しく説明します。
1. 賃貸契約関係の終了手続き
賃貸借契約の解除は、相続人が手続きする必要があります。アパートで孤独死が発見された場合、以下の書類を管理会社に提出しましょう。
- 死亡証明書
- 戸籍謄本
- 賃貸借契約解約届 など
なお、賃貸借契約の解除は、相続人全員の同意が必要です。敷金は、原状回復費用と未払賃料を差し引いて返還されます。
公共料金の解約も必要です。電気やガス・水道・電話などの契約を解除し、未払い料金を精算しましょう。
2. 遺品整理
遺品は、以下の4つに分類して整理します。
- 遺産相続に必要な書類
- 換金可能なアイテム
- 思い出の品
- 処分するもの
孤独死の現場では、遺体の腐敗による汚染や体液の染み込みなどの問題が発生している恐れがあります。そのため、特殊清掃業者に依頼するのがおすすめです。
3. 特殊清掃
特殊清掃は、警察の許可が出てから開始できます。作業は、以下の順序で進められます。
- 害虫の処理
- 汚染物の処理
- 薬剤による特殊清掃
- 家財の搬出
- 壁紙の張り替え
- オゾン脱臭による消臭
業者選びでは、複数の見積もりを取って比較します。とくに近隣への配慮として、不快な臭いを広げない対策をしたり、共用部での作業時の配慮が丁寧な業者を選んだりすると、近所トラブルを避けられます。
レビューや口コミなどを見て、サービスのクオリティを事前にチェックしましょう。
孤独死を発生させないために今からできること
孤独死を防ぐためには、事前の対策が重要です。
- 見守りサービスを導入する
- 定期的に安否を確認する
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 見守りサービスを導入する
見守りサービスには、3つの基本的なタイプがあります。
| タイプ | 概要 |
|---|---|
| 非接触型 | 玄関に人感センサーを設置し、24時間以上動きがない場合は自動で通報される |
| 接触型 | 体調が悪くなった時にペンダント型の通報ボタンを押すと、すぐに警備会社に連絡が入る |
| 対面型 | ヘルパーが定期的に訪問することで、食事の準備をしながら体調や生活状況を確認できる |
警備会社のサービスでは、異常を検知した場合の緊急対応も含まれるケースが一般的です。利用者の生活習慣や希望に合わせて、最適なサービスを選択しましょう。
2. 定期的に安否を確認する
孤独死を防ぐには、定期的に安否を確認する体制を整えておく必要があります。たとえば、デイサービスを週2回利用している場合は、残りの日を家族や近所の人が分担して確認すると良いでしょう。
地域のサロン活動に参加することで、近所の人との定期的な交流機会が生まれます。複数の見守り方法を組み合わせることで、より確実に安否を確認できるでしょう。
孤独死の葬儀に関するよくある質問
最後に、孤独死の葬儀に関してよく寄せられる質問について、解説します。
- 遺族が相続放棄したらどうする?
- 葬儀までの日数はどれくらいかかる?
- 葬儀をしないという選択肢はある?
- 遺族がいない場合はどうなる?
それぞれの状況について、詳しく見ていきましょう。
1. 遺族が相続放棄したらどうする?
遺族が相続放棄を選択する場合でも、被相続人の預貯金から葬儀費用を支払えます。ただし、この場合の葬儀費用は「身分相応の、遺族として当然営まなければならない程度」に限定される点に留意しましょう。
葬儀費用として個人の預貯金から支払えるものと、そうでないものの目安は以下のとおりです。
| 遺産から支払える費用 | 遺産から支払えない費用 |
|---|---|
| ⚫︎遺体の搬送費用 ⚫︎安置費用通夜・葬式の直接費用 ⚫︎火葬料、埋葬料 ⚫︎納骨料 ⚫︎お布施 など | ⚫︎不相当に高額な葬儀費用 ⚫︎香典返しの費用 ⚫︎位牌・墓地の購入費用 ⚫︎法要費用 など |
葬儀費用の支出時には、領収書を保管して支出内容を明確にしておくことが重要です。
2. 葬儀までの日数はどれくらいかかる?
一般的には、亡くなられてから2~5日で葬儀が行われますが、火葬場の予約状況によっては1週間以上かかることもあるでしょう。
法律により、死亡確認から24時間以上経過しなければ火葬できません。たとえば、月曜日の朝に死亡が確認された場合、火葬は早くても火曜日の朝以降となります。この間、遺体は自宅か火葬場の霊安室で保管されます。
火葬をするために必要な手続きは、以下のとおりです。
- 死亡届の提出
- 火葬許可証の取得
- 火葬場の予約 など
孤独死の場合は警察による検視が入るため、通常より時間がかかります。
3. 葬儀をしないという選択肢はある?
葬儀を執り行うことは、法律で定められた義務ではありません。たとえば、葬儀や告別式などの宗教的な儀式を省略し、火葬のみを執り行う「直葬」という方法があります。
ただし、直葬の場合でも最低限の手続きは必要です。
- 遺体の搬送
- 納棺
- 火葬場の手配など
このような手続きは、葬儀社に依頼するのが一般的です。なお、直葬の葬儀費用はほかの形式と比較すると割安になる傾向があります。
| 葬儀 | 費用 |
|---|---|
| 直葬 | 20〜50万円 |
| 一般葬 | 100〜200万円 |
| 家族葬 | 約70万円 |
| 一日葬 | 30〜50万円 |
直葬を選択すると、葬儀費用を大幅に抑えられるでしょう。直葬については、以下の記事を参考にしてみてください。
あわせて読みたい!

葬儀の基礎知識
直葬を選んで良かったと思えるのはどんな人?選ばれる理由を解説
4. 遺族がいない場合はどうなる?
遺族不在の場合、死亡地の自治体が葬儀を執り行う法的責任を負います。自治体は、まず戸籍調査で親族を調べます。親族が見つからない場合、職員立ち会いのもと簡素な火葬を執り行うという流れです。
このような場合、読経などの宗教的儀式は省略され、最低限の形式で葬儀が執り行われます。
遺骨は自治体によって一定期間保管され、引き取り手が現れない場合は無縁塚と呼ばれる共同墓地に埋葬されます。
後日遺族が判明した際は、自治体が負担した火葬・埋葬費用の請求を受けるケースがあるでしょう。
なお、故人が国民健康保険などに加入していた場合、1~7万円程度の葬祭費補助を受けられます。葬祭費の申請期限は、葬儀を執り行った日の翌日から2年以内です。このように、遺族不在でも行政による必要最低限の葬送が保証されています。
遺族がいない場合の葬儀の進め方については、以下の記事を参考にしてみてください。
あわせて読みたい!

葬儀の準備
身寄りのない人の葬儀はどうなる?流れや生前の準備を解説
孤独死の葬儀については葬儀社に相談しましょう
孤独死の場合、警察による検視から火葬までの手続きが複雑です。死亡してから一定期間経過している場合、遺体の腐敗が進んでいる恐れがあるため、専門業者による特殊清掃が必要です。
なお、葬儀社は死亡届の提出から特殊清掃の手配・火葬場の予約まで、一連の流れをサポートしてくれるでしょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。