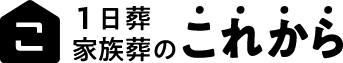「身寄りがない場合、葬儀はどうなるのだろう」「将来に備えて、今からできる準備はあるのだろうか」と不安を感じている方は多いのではないでしょうか。実は、身寄りのない人の死亡は平成30年日から令和3年の約3年間で10万件を超えています。(参考:遺留金等に関する実態調査結果報告書|総務省行政評価局)
本記事では、身寄りのない方の葬儀の基本的な流れから、生前に準備できることまで詳しく解説します。費用面の不安や具体的な手続きについても説明していますので、将来への不安を抱えている方はぜひ参考にしてください。
この記事を要約すると
- 身寄りのない人が亡くなった場合、警察による身元確認後、死亡場所の自治体が遺体を引き取り、火葬を執り行い、遺骨は一定期間保管後に合葬墓へ納められます。
- 遺品や借金は、相続財産清算人が法的手続きに従って処理します。相続放棄をすることで借金を引き継がないという選択肢もあります。
- 身寄りのない人が生前に準備できることとして、遺言書作成や任意後見契約・死後事務委任契約などが挙げられます。
身寄りのない人の葬儀の流れ
身寄りのない方の葬儀には、いくつかの重要なステップがあります。
- 息を引き取ったことが確認される
- 身元確認が行われる
- 遺体が安置される
- 遺体は自治体によって引き取られる
- 火葬が執り行われる
- 遺骨が自治体に保管される
- 合葬墓や無縁墓に埋葬される
ここでは、息を引き取ってから遺骨が埋葬されるまでの流れを、順を追って見ていきましょう。
1. 息を引き取ったことが確認される
自宅で亡くなった場合、発見者はかかりつけ医または警察へ通報する必要があります。連絡先は、以下のとおりです。
| かかりつけ医がいる場合 | かかりつけ医が在籍する病院 ●直近24時間以内に診察を受け、持病による死亡が明らかな場合は死亡診断書を発行可能 ●24時間以上経過していても、医師が訪問して死因が確認できれば発行可能 |
| かかりつけ医がいない場合 | 警察 |
かかりつけ医がいれば、医師による確認を受ければ死亡診断書を発行してもらえますが、原因不明の死亡や事故死の場合は、警察による検視や検案が必要です。
2. 身元確認が行われる
警察は遺体発見後、戸籍調査から始まる身元確認作業を実施します。所持品からの手掛かりや、近隣住民への聞き込み調査なども行われます。
身寄りが見つからなかったり、発見された親族が引き取りを拒否したりした場合は、死亡地の自治体が対応するのが一般的です。検視・検案の結果を受けて死体検案書が発行され、次の段階へと進みます。
3. 遺体が安置される
遺体は、主に、自宅や葬儀社の安置室・民間の遺体安置所のいずれかで安置されます。
法律では、死亡から24時間以内の火葬は禁止されており、2〜3日間の安置期間が必要です。ご遺体の安置については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
あわせて読みたい!

葬儀の基礎知識
ご遺体安置とは?費用相場や安置場所の決め方を解説
4. 遺体は自治体によって引き取られる
身寄りのない人が亡くなった場合、死亡場所の自治体が遺体を引き取ります。自宅での死亡時は、発見者の通報を受けた警察が検視を実施します。
たとえば、アパートで独居していた高齢者が亡くなった場合を考えてみましょう。この場合、大家からの通報で警察が駆けつけて、自治体は戸籍調査を通じて親族の有無を確認します。引き取り手が見つからない場合「墓地・埋葬等に関する法律」に基づいて対応を進められるという流れです。
5. 火葬が執り行われる
遺体を引き取って火葬する親族がいない場合、法律に基づいて自治体が火葬を執り行います。
親族調査をどの範囲まで行うべきか、火葬をいつ行うべきかなど、国による明確なルールがないため、各自治体が独自に対応せざるを得ない状況です。実際に、火葬後に親族が判明して苦情を受けるなどのトラブルが過去5年余りで少なくとも14件発生しています。
6. 遺骨が自治体に保管される
火葬後の遺骨は、一定期間自治体が保管します。保管期間は自治体によって大きく異なり、約7割の自治体では明確な期限を定めていません。
期間を定めている自治体でも、1年から永久保管まで幅広く、地域によって対応が異なります。保管期間が経過すると、遺骨は自治体が管理する合葬墓や無縁墓地に納められ、他の身寄りのない方の遺骨とともに永代供養されます。
7. 合葬墓や無縁墓に埋葬される
保管期間が終了すると、遺骨は合葬墓や無縁墓へ納骨されます。
合葬墓では、骨壺から取り出された遺骨が他の方の遺骨とともに供養されます。一度、合葬墓に納骨された遺骨は、あとから親族が現れても個別に取り出せません。
納骨費用は一般的な墓地と比べて安価です。永代供養のなかでも合葬型の場合、通常1柱あたり5万円〜で埋葬できます。
身寄りのない人が亡くなったときに発生する疑問
身寄りのない方が亡くなった際には、さまざまな疑問が生じます。ここでは、以下のよくある疑問について詳しく解説します。
- 葬儀費用はどうなる?
- 電気や水道などのライフラインの料金はどうなる?
- 遺品はどうなる?
- 借金はどうなる?
ぜひ参考にしてみてください。
1. 葬儀費用はどうなる?
故人に財産がある場合は、その財産から葬儀費用を支払います。財産がない場合は、各種給付制度を利用しましょう。国民健康保険などの加入者は葬祭費補助金を受けられます。
たとえば、東京都23区では、国民健康保険加入者に対する支給額は7万円です。
また、生活保護受給者や経済的困窮者には葬祭扶助制度が用意されています。補助される金額は、故人の年齢や自治体によって異なりますが、目安は以下のとおりです。
| 亡くなった人の年齢 | 金額 |
|---|---|
| 12歳以上 | 約20万円 |
| 12歳未満 | 約15万円 |
ただし、このような給付には事前申請が必要です。また、自治体によって支給額や条件は異なります。
2. 電気や水道などのライフラインの料金はどうなる?
銀行口座からの自動引き落としは、口座凍結まで継続されます。口座凍結後は故人の住所宛に振込用紙が届き、銀行やコンビニエンスストアなどで支払うことになるでしょう。
そのため、契約者が死亡したあとは、名義を変更するか解約の手続きが必要です。
3. 遺品はどうなる?
遺品は相続財産の一部として扱われます。第三者が独自の判断で遺品の処分はできません。たとえば、隣人や知人が善意で遺品を片付けても、後日トラブルになる恐れがあります。
賃貸住宅に住んでいる人が亡くなった場合、貸主はまず遠縁の親族や法定相続人に遺品整理を依頼するケースが一般的です。関係者が不在の場合、利害関係人(債権者・不動産の共有者など)が家庭裁判所に申立てを行い相続財産清算人を選任します。
相続財産清算人とは、遺産の管理や債権者への弁済・残余財産の国庫帰属手続きを執り行う人のことです。清算人が遺品の整理や処分・賃貸契約の解除などの手続きを進めます。
たとえば、アパートに残された家具や衣類の処分・賃貸契約の解約手続きなどを担います。このような手続きには相当な時間を要するため、遺品の処分が完了するまでに長期間かかることも珍しくありません。
4. 借金はどうなる?
借金も相続財産の一部として扱われます。故人がのこした借金は、相続人が支払い義務を引き継ぐのが一般的です。なお、相続放棄をすることで借金を引き継がないという選択肢もあります。
身寄りのない人の場合は、債権者は裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てます。選任された清算人は、故人の財産を管理して債権者への支払いを行う流れです。
このように、身寄りのない方の遺品や借金は法的手続きに従って進められます。
身寄りのない人が生前に準備できること
身寄りのない方が生前から行える準備について、以下の項目を詳しく解説します。
- 遺言書を用意する
- 任意後見契約を締結する
- 利用できる国の制度を確認する
- 死後事務委任契約を結んでおく
- 葬儀信託を利用する
- 葬儀会社に相談する
生前に準備を整えておくことで、将来への不安を軽減できるでしょう。
1. 遺言書を用意する
身寄りのない人は、遺産の行き先を明確にしておく必要があります。遺言書がない場合、相続人不在として財産は最終的に国庫に納められます。
特定の人や団体に遺産を相続したい場合は、公正証書遺言を作成しましょう。公正証書遺言とは、公証人と2名の証人の立ち会いのもとで作成される正式な遺言書です。
原本は公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。遺言執行者を指定すれば、死後の手続きもスムーズに進みます。
2. 任意後見契約を締結する
任意後見契約を結ぶことで、判断能力が低下する前に将来の支援者を自分で選べます。本人の意思を尊重した柔軟な支援内容を事前に決められるのが主なメリットです。
たとえば、預貯金の管理方法や医療機関の選択などを具体的に定められます。任意後見契約は、公正証書での締結が必要です。契約内容に基づいて支援が行われるため、判断能力が低下してしまっても本人の意思に沿った支援を受けられるでしょう。
3. 利用できる国の制度を確認する
葬儀を執り行ううえで利用できる国の制度を確認しておくことが大切です。具体的には、以下のような制度を使えます。
| 制度 | 支給額 | 申請方法 |
|---|---|---|
| 葬祭費補助金制度 | 国民健康保険加入:1~7万円(※自治体によって異なるが5万円を支給されるケースが多い)後期高齢者保険加入:3~7万円 | 市区町村役場での申請 郵送申請 |
| 埋葬料 | 一律5万円 | 故人の勤務先関連の社会保険事務所や健康保険組合に申請 |
| 葬祭扶助 | 亡くなった人が12歳以上:約20万円亡くなった人が12歳未満:約15万円 | 市町村の役所または福祉事務所で葬儀前に申請 |
日常生活自立支援事業や成年後見制度など、行政による支援制度を把握しておきましょう。
葬儀費用を安く抑えるためのポイントについては、以下の記事を参考にしてみてください。
あわせて読みたい!

葬儀の費用相場
葬儀費用を安く抑えるために工夫できることは?費用を抑える際に注意すべきポイントも解説
4. 死後事務委任契約を結んでおく
死後事務委任契約とは、死後の手続きを円滑に進めるための契約です。信頼できる人や法律の専門家と契約を締結でき、葬儀や埋葬の手配などさまざまな事務手続きを委任できます。
たとえば、アパートの退去手続きや公共料金の解約なども依頼可能です。契約時に具体的な希望を伝えることで、希望通りに対応してもらえるでしょう。
5. 葬儀信託を利用する
葬儀信託は、生前に葬儀費用を信託銀行に預ける制度です。死後、信託銀行が葬儀社に直接費用を支払います。
費用は、葬儀のグレードによって異なり、具体的な費用の違いは以下のとおりです。
| 葬儀 | 費用 |
|---|---|
| 一般葬 | 100〜200万円 |
| 家族葬 | 約70万円 |
| 一日葬 | 30〜50万円 |
| 直葬 | 20〜50万円 |
信託銀行による資金管理は安全性が高く、葬儀費用が他の目的に使用されることも防げます。
6. 葬儀会社に相談する
葬儀会社は、24時間365日相談を受け付けている業者がほとんどです。費用や形式について、具体的な相談が可能です。たとえば、火葬のみの簡素な形式から一般的な葬儀まで、さまざまなプランがあります。
複数の葬儀社に相談することで、サービス内容や費用を比較できます。このように、事前の準備で本人の希望に沿った葬儀を実現できるでしょう。
身寄りのない人は生前に葬儀社に相談しておきましょう
身寄りがない方の死後の手続きは、行政による対応が基本です。しかし、本人の希望が反映されにくい面があるでしょう。そのため、生前から準備をしておくことで、自分らしい最後を迎えられます。
具体的には、葬儀信託や死後事務委任契約の締結、遺言書の作成などの対策が有効です。とくに、葬儀社への事前相談は重要で、費用や形式について具体的な打ち合わせができるでしょう。
24時間365日相談可能な葬儀社も多いため、まずは気軽に相談してみることをおすすめします。複数の葬儀社に相談することで、サービスや費用の比較検討も可能です。このように、しっかりとした準備があれば、本人の意思を尊重した葬儀を実現できます。弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。