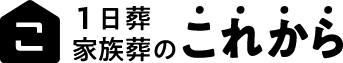余命1年と宣告された場合、突然のことで動揺し、何から始めればよいのか分からなくなる人がほとんどでしょう。限られた時間の中で後悔を残さないためには、治療方針や日々の過ごし方について考える必要があります。
また、家族との時間や仕事との向き合い方についても、事前にしっかりと整理しておく必要があります。
この記事では、余命宣告を受けた際にまず知っておきたいことや、残された時間を充実させるための具体的な方法について解説します。
この記事を要約すると
- 余命宣告とは、残りの生存期間の目安を伝えるもので、主に「生存期間中央値」が用いられる。これは統計に基づく数値で、宣告より短命や長生きする場合もある。
- 余命宣告をされた後の過ごし方に正解や不正解はなく、趣味を楽しむ人や家族といる時間を最優先する人、大切な人に手紙を書くなど、それぞれが自分らしい選択をしている。
- 余命宣告を受けた際には、加入している保険の確認やエンディングノート作成、遺品整理などの準備を進めておくことが大切。
余命宣告とは
「余命宣告」とは、医師が患者やその家族に対して、どのくらいの期間生きられるかの目安を伝えるものです。主に進行性の癌など、重い病気にかかっている方に行われます。
伝え方に明確なルールはなく「余命1年」と告げられることもあれば「余命半年から1年ほど」と幅を持たせて伝えられるケースもあります。
この期間は、過去に同じ病気を患った人々のデータを基に推測されるもので、個人の状態や治療の効果によって大きく異なることがあります。
特に癌の場合「生存期間中央値」という指標がよく使用されます。これは、同じ病気を持つ人たちを生存期間順に並べたとき、真ん中の50%が亡くなる時期を示す数値です。
つまり、余命宣告は統計に基づく目安であり、告げられた期間が必ずしも当てはまるわけではありません。医師から余命宣告を受けた場合は、あくまで参考値であると理解し、その後の治療や生活の過ごし方を考えることが大切です。
余命宣告は統計の中央値で正確ではない
前述の通り、癌などで余命宣告する場合は「生存期間中央値」が指標としてよく使用されます。この数値は平均値ではないため注意が必要です。
たとえば、ある種類の癌患者100人を対象にした場合、生存期間中央値が「1年」とされている場合、そのうち50人は1年以内に亡くなり、残りの50人は1年以上生きるという意味になります。「50人目に亡くなった人の期間が1年だった」ということです。
そのため、1年の余命宣告を受けても、なかには数ヵ月で亡くなる方もいれば、数年以上生存する方もいます。個人の病状や治療の進展により大きく変わるため、1年という数字にとらわれ過ぎないようにしましょう。
1年の余命宣告を受けた際の主な治療方針
余命1年と宣告を受けた場合、病気の種類や進行具合によりますが、治療方針は主に以下の3つに分けられます。
- 完治を目指す治療
- 延命を目的とした治療
- 痛みや苦しみを和らげる緩和ケア
それぞれの治療法は、目的や期待できる効果が異なり、患者さんへの身体への負担や生活の質にも違いが生まれます。残された時間を後悔なく過ごすためには、これらの治療方針の特徴や選択肢について理解し、自分や家族の希望に合った道を選ぶことが大切です。
ここでは、それぞれの治療法の概要と注意点について解説します。
完治を目指す治療を受ける
完治を目指す治療では、病気そのものを完全に治すことを目標とします。たとえば、癌の場合、手術で癌細胞を全て取り除いたり、抗がん剤や放射線治療を行って癌を消滅させたりすることがこれに該当します。
これまでは、標準治療が限界と判断された場合、完治を諦め延命治療や緩和ケアを選ぶのが一般的でした。しかし、近年は免疫療法などが導入されたことで、これ以上の治療が難しいと言われた人が回復した例も報告されています。
ただし、これらの治療法はすべての患者さんに適用できるわけではなく、場合によっては高額な医療費が必要です。主治医や家族と十分に相談しながら検討しましょう。
延命治療を受ける
延命治療とは、病気の完治を目指すものではなく、寿命を伸ばすことを目的とした治療です。たとえば「子どもの結婚式に出席したい」といった患者さんの目標を達成するために選択されることがあります。
この治療では、人工呼吸器や栄養補給などの医療処置が行われ、命をつなぐ効果があります。一方で、治療を受けることで病院で過ごす時間が増えたり、生活の質が下がったりすることもあるため、患者さんや家族にとって大きな判断となります。
自分の意志を伝えるためには、家族や医療関係者と話し合い、自分がどのような治療を望むのかを明確にしておくことが大切です。
治療に関する希望を具体的に文書にまとめておく方法もあります。これを「事前指示書(リビングウィル)」と呼び、本人の意思が尊重されやすくなります。
緩和ケアを受ける
緩和ケアとは、癌による体や心の痛みを和らげ、生活の質(QOL)を保つことを目的とした治療です。緩和ケアは終末期ケアと混同されがちですが、異なる点があります。終末期ケアは、最後を迎える患者さんが自分らしい人生を閉じるための支援を重視するものです。
一方、緩和ケアはまだ治療の可能性がある段階でも行われ、治療による負担や不安を軽減し、患者さんが安心して病気と向き合えるようにサポートするのが目的です。そのため、癌と診断された時点から受けられます。
具体的には「通院・入院・在宅」の3つがあり、受けられる施設は、がん診療連携拠点病院や緩和ケア専門病院などがあります。患者さんや家族の状態や、経済的負担などを踏まえて総合的に考慮することが大切です。
1年の余命宣告をされた人が実際に選んだ過ごし方
1年の余命宣告を受けた場合、突然のことでショックを受けてしまい何をすべきか、どのように過ごせばいいのか分からなくなる人も少なくありません。
過ごし方に正解や不正解はありませんが、体調や治療スケジュールに制限があるため、自分の心や体と向き合いながら慎重に考えることが大切です。
ここでは、実際に余命宣告を受けた人たちがどのような生活を選び、限られた時間をどう過ごしているのかについて、体験談をもとに紹介します。
趣味を楽しんだ
余命宣告を受けた人たちの中には、趣味を通じて心の安定を保ち、最後まで生活を楽しんで過ごす人がいます。
たとえば、音楽を楽しむ時間を作ったり絵を描くことに没頭したりと、自分のペースで趣味を続けるケースです。
また、思い出の場所へ旅行に出かけたり、行きたかった場所に行ったりするのもおすすめです。ただし、趣味を尊重する場合は、体力や体調に無理がないかを最優先で考えることが大切です。
具体的な過ごし方や頻度を家族や医療スタッフに相談しながら計画を立て、安全面やサポート体制を整えることも忘れないようにしましょう。
家族といる時間を増やした
家族と過ごす時間を最優先にして過ごす人も多くいます。
ある男性はステージ4の癌が見つかり、余命数ヶ月と宣告されます。男性はとにかく病院が嫌いだったこともあり、入院は望まず自宅での緩和ケアを選択し、家族と共にすごす時間を最優先にしました。
家族全員で協力し、最後に時間を支えた結果、これまで以上に絆が深まり安心して旅立つことができたといった体験談もあります。このように、家族と過ごす何気ない時間は、患者さんにとって大きな心の支えとなるものです。
ただし、在宅での看護や介護は、家族にとって負担が大きくなる可能性もあります。訪問介護や緩和ケアの専門家など、外部のサポートを積極的に活用し、家族全員が無理なく過ごせる環境を整えましょう。
大切な人に手紙を書いた
大切な人達に向けて手紙を書くことで、感謝の気持ちや想いを伝えて心の整理を行う人も多くいます。ある女性は、余命宣告を受けた後、家族や友人に手紙を書いて自身の思いを伝えることで心の安定を保ちました。
このような手紙は、受け取った側にとっても大切な思い出となり、故人を思いを感じる貴重なものとなります。手紙を書く際は、無理に感動的な言葉やエピソードを選ぶ必要はありません。日常の出来事や感謝の気持ち、相手への思いを素直に表すことで、心のこもった手紙となります。
手紙は想像以上に負担がかかることもあるため、無理し過ぎないようにペースを調整しましょう。ほかには「大好物だったものをたくさん食べた」「自分の考えを最後までブログに書き続けた」といった体験談もありました。
1年の余命宣告を受けた場合の終活準備
余命宣告を受けた場合、個人でどう過ごしたいかを考えることも大切ですが、体力や時間に限りがあるため、早めに取り組むべき準備も別にあります。具体的な準備内容は以下の通りです。
- 加入している保険の確認
- お世話になった方や友人に連絡する
- エンディングノートを作成する
- 遺品整理や遺言を作成する
これらの準備は、後悔を減らし大切な人たちに思いを伝えるための第一歩です。各準備について具体的なポイントや注意すべき点を解説します。
加入している保険の確認
余命宣告を受けた場合、まずはじめに確認すべきなのが自身の加入している保険の内容です。
特に生命保険に付帯されている「リビングニーズ特約」は重要です。これは、余命6ヶ月以内と診断された場合、死亡保険金の一部または全額を生前に受け取れる特約です。治療費や生活費、終活準備に当てられます。
また、医療保険やがん保険に加入している場合、先進医療特約や入院給付金など、受け取れる給付金がないか確認しましょう。これらの給付金は、医療費の負担軽減に役立ちます。
さらに保険料の支払い免除特約が付いている場合、所定の条件を満たしていれば、以降の保険料が免除されることがあります。
保険の内容や特約の適用条件は、契約内容によって異なります。保険証券を確認し、保険会社の担当者に相談しましょう。
お世話になった方や友人に連絡する
余命宣告を受けた際、お世話になった人たちや友人に連絡することは、感謝の気持ちを伝え、自身の心を整理するうえでとても大切なステップです。直接会うことが難しい場合は、手紙やメール、電話などで思いを伝えましょう。
また、連絡を取る際には、自身の状況や気持ちを素直に伝えることで相手も適切なサポートや理解を示しやすくなります。無理をせずに自分のペースで進めていきましょう。
エンディングノートを作成する
エンディングノートとは、人生の最終段階に備えて、自分の希望や情報を記録するためのものです。
財産分与や介護・医療、葬儀の方法など、自分がどうしてほしいかを具体的に伝えられます。また、家族の負担を軽減させることにも繋がります。
たとえば、自分の財産分与に関する希望を記録しておけば、家族が迷うことなくスムーズに手続きを進められます。また、葬儀の方法やお墓についての考え方を記しておけば、家族が悩むこともなくなります。
ただし、暗証番号やセキュリティに関わる情報を直接記載するのは避けましょう。また、ノートの存在と保管場所を家族に共有しておくことが大切です。エンディングノートは法的効力を持たないものの、自分の意志を伝える重要な手段となります。
遺品整理や遺言を作成する
余命宣告を受けた際、遺品整理や遺言書の作成は家族の負担を軽減するために重要な準備です。
遺品整理では、生前に持ち物を整理しながら不要なものを処分することで、家族が迷わず対応できる環境を整えられます。また、思い出の品や貴重品を見直すことで、自分の人生を振り返る機会にもなります。
遺言書は、財産の分配や自分の意志を法的に明確に伝えるための文書です。自筆証書遺言を作成する場合、全文を自筆したうえで日付と署名、押印が必要です。
また、財産の分配内容を具体的に記載し、不明確な表現を避けるようにします。作成した遺言書は、信頼できる家族に保管場所を伝えましょう。
1年の余命宣告を受けた場合に身内ができること
1年の余命宣告を身内が受けた場合、本人だけでなく、周囲の家族もどうすればよいのか分からず、頭が真っ白になってしまうものです。「こうしないと本人を傷つけてしまうのではないか」「何もしないのでは冷たいのでは」と、悩む方もいるでしょう。
余命宣告を受けた身内に対するサポートや接し方に、正解や不正解はありませんが、身内としてできることを知り、適切な選択肢を見つけることが大切です。ここでは、身内ができる具体的な行動や考え方について、いくつかの方法を紹介します。
特別な考えは必要なく普段通り寄り添うことが大切
身内が1年の余命宣告を受けた際、特別な対応を考えるよりも、普段通りに寄り添うことが大切です。
患者さんは日常の継続や家族の暖かいサポートを求めています。過度な気遣いや特別扱いは、かえって負担になることもあります。
日常の会話や活動を一緒に楽しみ、患者さんの気持ちに寄り添うことで、安心感を提供できます。余命宣告を受けた本人は、突然のことで心の整理ができていない可能性があるため、落ち込んだり、家族に対して怒ったりすることもあるでしょう。
そのような際にも、家族は聞き役に徹して、本人に寄り添いながら共感する言葉をかけてあげることが大切です。
やりたかったことを聞いてみる
身内が1年の余命宣告を受けた際、家族としてできる行動の1つに、本人の「やりたかったこと」を聞いてみることがあります。
これは残された時間を充実させるうえでとても重要なものです。旅行や食事など、本人が望むことを一緒に考え、可能なサポート範囲について検討していきましょう。
本人の満足感や生きがいを高めるだけでなく、家族との絆を深める機会にもなります。体調や時間的な制約も考慮しながら、無理のない計画を立てていきましょう。
1年の余命宣告を受けた場合の仕事に対する考え方
余命宣告を受けた際、多くの人が「仕事を辞めよう」と考えます。しかし、仕事を続けることにはいくつかのメリットがあります。
たとえば、働き続けることで、社会とのつながりを維持して日常生活のリズムを保ちやすくなります。また、職場での役割を果たすなかで生きがいや達成感を感じられる人もいるでしょう。さらに、収入を得られるため、治療費や家族の生活費を支えられるメリットもあります。
一方で、仕事を辞めて治療に専念する選択もあります。この場合、まずは経済的な準備が必要です。また、退職手続きでは、有給休暇や退職金、健康保険の継続手続きなどを確認しましょう。
どちらの選択肢を取る場合でも、主治医や家族と相談しながら、自分にとって最も納得のいく選択をすることが大切です。
余命宣告1年の原因になる主な病気
余命宣告をうける原因となる病気は多岐に渡りますが、主に以下のような病気が挙げられます。
- 癌(悪性腫瘍):余命宣告の原因として最も多い病気の1つで、進行がんや転移が確認された場合、治療の難易度が高まる。
- 慢性心不全:心臓の機能が低下し、血液を十分に送り出せなくなる病気。症状が進行すると、命に関わる状況になりやすい。
- 肝硬変:肝臓の機能が著しく損なわれる病気で、特に合併症を伴う場合は余命宣告が行われることがある。
- 末期腎不全:腎臓の働きが著しく低下し、人工透析でも体を支えられなくなる場合、余命宣告となるケースもある。
- 神経変性疾患:筋萎縮性側索硬化症(ALS)やその他の神経変性疾患は、症状が進行するにつれて呼吸機能が低下し、命に関わることがある。
ほとんどの病気は、早期に発見することで命に関わるリスクを大幅に減らせます。
特に癌や心疾患などは、定期的な健康診断などで早期発見が可能です。疲れやすさや体重減少、慢性的な痛みが続く場合は、早めに医療機関を受診するようにしましょう。
余命宣告とともに新しい時間の価値を考えてみよう
余命宣告を受けることは、大きな衝撃と不安を伴いますが、新しい時間の価値に気付くきっかけでもあります。限られた時間の中で何を大切にし、どのように過ごすかを考えることは、自分自身や家族にとっても重要です。
やりたかったことに挑戦したり、大切な人との時間を増やしたりすることで、日々に充実感を生みだせます。また、終活の準備や家族との対話を通じて、残された時間をより安心して過ごす環境を整えることも可能です。時間の価値を見つめ直し、前向きに向き合い、限られた時間を充実させましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。