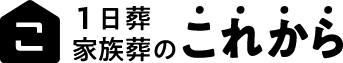大切な方が余命宣告を受けたとき、本人や家族が受ける衝撃や悲しみは計りきれません。「もう本当にこれ以上は生きることができないのか」「家族として何かしてあげられることはないか」と考えるのではないでしょうか。
治療方針や本人にどんな声をかけるか、残された時間にやりたいことをして欲しいなど考えることはたくさんあるでしょう。また、亡くなった後に備えて、保険や財産の確認、葬儀の準備も必要です。
本記事では、家族が余命宣告を受けたときにできることや、やっておくと良いことをご紹介します。ご本人や家族が残された時間を後悔なく過ごせるように、ぜひ参考にしてください。
この記事を要約すると
- 余命は寿命ではなく残された時間は正確にはわかりませんが、後悔なく過ごすためには治療方針や今後の過ごし方を考えることが重要です。
- 今後のことが考えられるようになると、遺言書や財産、加入している保険の確認をすると良いでしょう。生きている間に一時金を受け取ることができる保険もあります。
- なるべく早く葬儀やお墓の準備をしましょう。いざというときに慌てずに済み、ご本人の意志を反映したお見送りをしやすくなります。
余命宣告とは?
余命宣告を受けると、本当にその期間までしか生きられないのか、余命は正確なのかと疑問に感じた方もいるかもしれません。余命は寿命ではなく、それより早く亡くなってしまうこともあれば、それより長く生きることもあります。
医師といえども未来が見えるわけではないため、患者の病状や進行具合、年齢などから客観的に判断しています。同じ病気の人の生存期間の中央値などのデータを参考にして判断するのが一般的です。残されている時間を予測することで、積極的な治療を行うか、緩和ケアを行うかなどの指標となります。
そのため、「思ったより早く亡くなってしまい、やりたいことができなかった」というケースもあります。反対に「宜告された余命より長く生きることができたから、病院を退院して自宅で過ごさせてあげたかった」という経験をされる方もいらっしゃいます。
余命は、残された期間を有意義に過ごすうえで参考になりますが、絶対ではないということを覚えておきましょう。
余命1年と宣告された場合の過ごし方や終活準備などは、以下の記事でも紹介しているので、ぜひ参考にしてみてください。
余命宣告を受けた本人にかける言葉や接し方
残された時間が少ない方に対して、どのように接して良いかわからないと戸惑ってしまうでしょう。
まず本人が宣告を受けていない場合は、余命を伝えるか考えなくてはなりません。人によっては受け入れることができずに自暴自棄になったり絶望して体調を崩してしまったりすることもあります。本人の希望や病状などを考慮のうえ、医師と相談して慎重に決めましょう。
余命宣告を受けた本人と接する際は、基本的には悲観的な言葉は避け、本人の言葉に耳を傾けましょう。「頑張って」「きっと治る」などの安易な励ましは傷つけてしまうかもしれません。
なんと声をかけていいかわからないときは、無理に話さず静かに寄り添うのも一つの方法です。
余命宣告を受けたときの家族の心構え
余命の宣告は本人だけではなく家族にとってもつらいものです。余命宣告を受けたときは、絶望することや混乱してしまうことも自然なことです。これからどのように過ごしていくかは、気持ちが落ち着いて冷静に判断できるようになってから考えましょう。
「本人が一番つらいのだから」「私が支えなくては」と思い詰めてしまうと、家族が体調を崩してしまうこともあります。家族も人に話を聞いてもらったり息抜きをしたりして、無理をしないように心がけましょう。
本人や同じ悲しみを持つ家族と話せない場合は、信頼できる友人や医師やカウンセラーなど専門家を頼りましょう。同じ病気の家族を持つ方の家族会などのコミュニティや支援団体などもあります。同じ境遇の方と悩みを共有することで、悩みの解決や心の支えになるかもしれません。
病院で「危篤」といわれた場合の考え方や、お亡くなりになるまでの期間などは、以下の記事で解説しています。医療スタッフへの確認や準備すべきことなども紹介しているので、参考にしてください。
余命宣告を受けたあとの方針や選択肢
余命宣告を受けた後は、今の受けている治療をそのまま継続するのか、別の治療法に変えるのか、治療を中止する方がいいのか悩む方も多いでしょう。ここでは、余命宣告を受けたあとの選択肢について紹介します。
積極的な治療や延命治療を受ける
一日でも長く生きたい、病気が完治する可能性にかけたいと考える場合、今の治療を継続する、延命治療を受けるという選択肢もあります。なかには、孫の成人式や結婚式など大事なイベントの日に晴れ姿を見せたいと家族が考えているケースもあるでしょう。
ただし、積極的な治療や延命治療はメリットばかりではありません。治療の継続にあたって、薬の副作用がつらい、効果が見られないなど身体面でも精神面でも負担になることが予想されます。
家族としても、医療機器やチューブが繋がっているのがかわいそうと感じる方も少なくありません。本人の意思や家族の希望、残された期間などを鑑みてよく考えて決めましょう。
セカンドオピニオンを受ける
「今の病院で受けられるもの以外の治療方法を知りたい」「別の角度からも医師の意見を聞きたい」という場合は、セカンドオピニオンを受ける選択肢もあります。
セカンドオピニオンとは、今かかっている主治医とは別の医師に、診断や治療方針などについて意見を求めることです。
セカンドオピニオンを受けることは、すでにお世話になっている医師に失礼ではないかと気がひけるという声もお聞きします。しかし現代では、セカンドオピニオンを受けることは珍しくありません。
今の主治医に黙って別の病院へ受診すると、今までの病気の経過がわからず検査が増えたり、最善の治療を受けられなかったりする可能性があります。
病院によっては、前医の紹介状がないと受け入れが難しい場合もあるので、セカンドオピニオンを希望する場合は、まず主治医に相談をしましょう。
緩和ケアを受ける
つらい治療を受け続けるよりも、緩和ケアを受けて残された時間を穏やかに過ごしたいと考える場合、緩和ケア病棟やホスピスを探すと良いでしょう。
緩和ケアは、病気の完治を目指す治療とは異なり、病気や治療に伴う痛みや息苦しさなどの苦痛を和らげるような支援です。専門のスタッフから身体面だけでなく、精神的なケアや社会的な支援を受けられます。
施設によって設備はさまざまですが、自分らしい生活を送るためのさまざまな工夫がされています。季節の花々が楽しめる庭園で散歩ができたり、日常生活に近いようにキッチンコーナーがあったりします。季節ごとにイベントや音楽会が開催されて、家族も一緒に参加できる場合もあります。
最後に住み慣れた自宅に戻って家族と大切な時間を過ごしたいという場合には、介護できる家族がいるかも重要なポイントです。また、介護ベッドのレンタルや訪問看護や訪問入浴などのサービスを取り入れられるかも検討してみてください。
「自宅でも介護できそうか誰かに相談したい」「どんなサービスを利用できるのか知りたい」といった不安がある方は、病院で看護師やソーシャルワーカーに相談してみると良いでしょう。
家族の過ごし方も考える
より納得のできる日々を過ごすためには、本人だけでなく家族もどう過ごすか考えるのが大切です。本人に伝えておきたい感謝の言葉や一緒にしたいと思っていたことを整理しましょう。今だからできる親孝行もあるかもしれません。
また、本人が自宅で過ごす場合は、介護が必要になることもあるため、誰が・いつ・何を担当するか決めなくてはなりません。
介護が必要となる期間は、どれくらいの期間になるかわかりません。余命より長く生きることができるのは喜ばしいことですが、家族自身の生活もあるため、一人で抱え込まないようにできると理想的です。
本人がやりたいことをできるようにする
まずは、本人がやりたいことは何か意思を確認すると良いでしょう。本人にやりたいことをさせてあげられれば、家族にとっても良い思い出になるでしょう。
会いたい人は?
最後に大切な人に会うことは、人間関係を通して人生を振り返るきっかけになります。「少しでも元気なうちに会いたい」「自分で話ができるうちにお礼を言いたい」といった気持ちもあるでしょう。早めに本人に確認を行い、相手にも連絡しましょう。
どこまでの範囲で連絡をするかは難しいものですが、家族が知らない友人関係がある場合もあるので、本人に交流関係も確認すると良いでしょう。ただし、入院中の場合は面会の制限がある場合もあるため、病院にも確認をするようにしましょう。
やっておきたいことは?
誰しも人生を終えるまでにやりたいこと、もう一度行きたい思い出の場所などがあるのではないでしょうか。
食べたいものや聞きたい音楽など本人が熱中していた趣味のことを思い出しながら、やりたいことを整理すると良いでしょう。やりたいことをイメージする段階や計画する段階でも、気持ちが明るくなる方もいらっしゃいます。
病状によっては、外出できなかったり食べられるものが限られていたりするなど、制限があることも少なくありません。写真や映像で思い出を振り返る、嚥下機能を確認してから看護師の付き添いのもとに少し食べるなど、工夫すると良いでしょう。
外出する場合も、どのくらいの時間なら外出できるか医師に相談し、万が一に備えて病院までのルートを確認しておくことが重要です。
本人に聞いておくと良いことは?
残された期間の過ごし方だけでなく、亡くなった後のことも考えて本人に聞いておいた方が良いことがいくつかあります。
しかし、本人も家族も病気や余命のことで頭がいっぱいで、今後のことまで考えられないまま、亡くなることもあります。無理に聞き出す必要がないこともあります。
言いにくいことや聞きにくいことは、本人の気持ちの整理がある程度落ち着いてから行い、本人が話すのを待つ方法などを取り入れましょう。
臓器提供を希望するか聞く
臓器提供は、本人の自由意志に基づいて行われます。本人が希望していても、家族が反対する場合は臓器提供することはありません。また、感染症に罹患している場合など、医学的な条件により移植ができない場合もあります。希望していないのであれば、無理に聞く必要はないことを覚えておきましょう。
しかしもともと、「臓器提供したい」という本人の意思を聞いている場合もあるかもしれません。臓器移植に反対していた家族も、本人と話して価値観が変わったという方もいらっしゃいます。本人から話があれば、意思を尊重する一つの選択肢として耳を傾けられると良いでしょう。
遺言書を作成しているか聞く
相続トラブルを避けるためには、遺言書を残しておいてもらうと良いでしょう。
法務局の遺言書保管所や公証役場に届けている場合は、ご本人が亡くなった後に、遺言書を確認できますが、自宅保管などは誰も存在を知らず後から出てきたというケースもあります。
話せない方や字が書けない方でも、立会人にもと公正証書遺言を残すことはできますが、認知症など判断能力がない場合は作成ができないので、早めに作成したほうが無難でしょう。
遺言書を準備しているか聞くにあたって、タイミングを間違えることや、ストレートに伝えてしまうことで「縁起が悪い」「財産を狙っている」と思われてしまう可能性があります。無理に書かせるものではないので、あくまで本人の意思であることが大切です。
余命宣告を受けてから準備すること
今後の過ごし方を決めて、本人への意思確認をしたあともやることはたくさんあります。余命宣告を受けてから準備しておくと良いことについて解説します。
加入している保険の確認
保険に加入している場合は、早めに自宅にある書類や保険会社に確認をして加入している保険の内容や受取人を確認しましょう。
複数の保険会社に加入していた場合などは、家族が把握できずに期限を過ぎて受け取れないというケースもあるので注意が必要です。
生命保険には「リビングニーズ特約」といわれる、存命の間に一時金を受け取るプランもあります。余命半年以内と宣告を受けた場合に使用できるなど受け取りの条件はありますが、基本的に使い方は自由です。治療費や緩和ケア、やり残したことや思い出づくりに使うこともできます。
財産や相続人の確認
不動産や土地などの財産状況を把握して、財産目録を作成しておくと良いでしょう。
場合によっては遺言執行者などの本人以外も作成できますが、本人の意思を確認して押印し、遺言書に添付できると、後々のトラブルを避けやすいでしょう。遺言書や財産目録が無効にならないように、弁護士や行政書士に依頼する方法もあります。
また、ご本人が亡くなったことが銀行側で確認されると、銀行口座は凍結されます。手続きをすれば、遺族が引き出せるようになりますが、限度額があり日数がかかることもあるため、早めに確認しておくことをおすすめします。
持ち物の確認
生活で使用していた衣服や雑貨などの多くは、高価なものでない限り不用品として廃棄することになるでしょう。大きな家具や布団などを処分するのは気力も必要になるので、業者へ依頼するのもひとつの選択肢です。
一方で贈り物や嫁入り道具、長年大事にしていたものや思い入れの強いものは、家族としても捨てられずに困ることも少なくありません。また、趣味で集めていたコレクション品などは、取り扱いが難しく手入れができない、価値がわからず高価なものを廃棄してしまうこともあります。
神社やお寺で供養してもらったり、価値のわかる人へ譲ったり、ネットオークション出品したりして整理しましょう。
パソコンやスマホなどのデジタルまわりの確認
スマートフォンやパソコンなどのデジタル機器やアプリケーションは、IDやパスワードがわからなければログインできません。持っているデジタル機器と利用しているサービスとともに、IDやパスワードを確認しておくようにしましょう。
本人が亡くなったあとで家族からネット銀行の手続きやサブスクの解約ができないと消費者センターに相談されるケースも少なくありません。
また、ポイントやマイレージも財産ですが、時間が経過して失効してしまうこともあります。ポイントの残高によっては早めに使ってしまった方が良い場合もあるでしょう。
葬儀の規模や形式を考える
いざその時が来たら準備しなくてはいけないのが葬儀です。
葬儀は、訃報の連絡・日程や葬儀場の決定・副葬品や喪服の準備・お布施と香典返しの用意など、やるべきことがたくさんあります。お亡くなりになってから慌ただしく準備をするより、早く始めておくほうが本人の意思も反映させやすくなります。
葬儀に呼ぶ知人や友人はどこまでの範囲にお声がけするか考えておくと良いでしょう。親族だけで行う家族葬などもあり、葬儀の形式や規模によって予算や準備することも変わります。
また、お世話になっている菩提寺がある場合は、葬儀の形式や僧侶に来てもらえるか確認しておくと良いでしょう。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、相場より抑えた価格で、葬儀に必要なものを含んだ分かりやすいセットプラン料金で葬儀のお手伝いをいたします。
事前にお問い合わせいただいた方には、特別価格でご案内しておりますので、まずはお気軽にご連絡くださいませ。
※葬儀と分からない封筒で資料をお届けいたします。
以下の記事では、葬儀の流れや葬儀社・葬儀場の選び方について詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
お墓の準備をする
先祖のお墓に入る場合、菩提寺の僧侶に葬儀に来てもらい、戒名や読経などの儀式が必要になる場合も少なくありません。葬儀の形式や宗教を決めるうえでも、どのお墓に入るのか確認しておくと良いでしょう。
先祖の墓に入らない場合は、新たにお墓を準備する必要があります。お墓は、本人の馴染みのある土地に立てるという考え方もありますが、残された家族が墓参りをしやすいような場所を検討することもポイントです。
また、個人でお墓を持たない「手元供養」や「永代供養」、「散骨」といった方法もあります。
お墓を持たない場合の供養の方法は、以下の記事で詳しく解説しています。お墓を持たないことのメリットやデメリット、注意点も紹介しているので、参考にしてください。
葬儀の準備を始めるときは葬儀社に相談を
葬儀に関して地域や予算が決まったら、葬儀社に見積もりを依頼しましょう。家族葬にするかなど形式を迷われる方や、初めてのことでよくわからないという方もいらっしゃるでしょう。経験豊富な葬儀社に相談することで、よりスムーズに進めやすくなります。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。