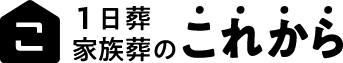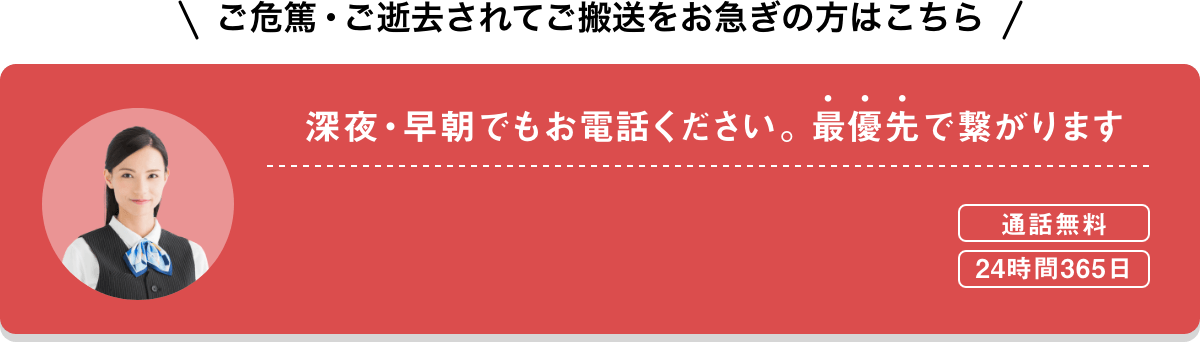「孤独死した親族の遺体を引き取るべきか迷う」「遺体の引き取り拒否はできるのかな」このような不安を抱えている方は多いのではないでしょうか。
実は、遺体の引き取りは法的に拒否することが可能ではあるものの、相続や費用負担など、引き取り拒否に伴って検討すべき問題も多く存在します。
本記事では、身内が孤独死した場合における相続の手続きや遺体発見後の対応まで詳しく解説します。遺体の引き取り拒否を検討されている方は、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を要約すると
- 孤独死した遺体の引き取りは法律上拒否できるものの、相続権は消失せず、火葬費用などの負担は残る可能性があります。
- 遺体の引き取りを拒否した場合、自治体が火葬を執り行います。遺骨の引き取りや費用の支払いについて別途対応が必要です。
- 相続については、財産状況を調査したうえで承認か放棄かを決定し、期限内に必要な手続きを進めなくてはいけません。
孤独死が発生したときに遺体の引き取りは拒否できる
孤独死した遺体の引き取りについて、法律上の義務付けはありません。
一般的には、配偶者や直系血族・兄弟姉妹などの近親者が遺体を引き取ります。しかし、故人との関係が疎遠だった場合や経済的な負担が大きい場合は、遺体を引き取らない選択をとることも可能です。
遺体の引き取りを拒否すると、遺体は自治体によって火葬され、無縁仏として供養されます。
引き取りを拒否する場合は、警察や自治体にその意思を伝える必要があります。ただし、遺体の引き取り拒否は相続とは別の問題です。相続権は引き取り拒否によって消失するわけではないことに留意しましょう。
孤独死遺体の引き取りを拒否したときの相続手続き
相続手続きを適切に進めるには、以下の3つのステップが重要です。
- 亡くなった人の財産情報を調べる
- 故人の財産を相続するのか放棄するのかを決める
- 相続手続きを進める
それぞれ詳しく解説します。
1. 亡くなった人の財産情報を調べる
相続財産の調査は、遺産分割の第一歩として必要な手続きです。まず、故人の自宅から通帳やキャッシュカード・郵便物などを探し、取引のある金融機関を特定します。
預貯金調査では残高証明書の取得が重要で、相続税申告の際にも必要です。不動産については、固定資産税納税通知書や登記済権利証から所在地を確認し、法務局で登記事項証明書を取得します。
また、市区町村で名寄帳を請求すれば、その地域内の所有不動産を一括して確認できます。株式や投資信託は、証券会社からの郵便物や残高証明書で確認しましょう。借金などの債務も併せて調査する必要があります。
ただし、自宅で孤独死が発見された場合は、遺体の腐敗によって室内が汚損されているケースがよくあります。
その場合は専門業者に室内の清掃を依頼して、清掃担当のスタッフに通帳やキャッシュカードなどの財産情報がわかるものをピックアップするよう依頼しましょう。
2. 故人の財産を相続するのか放棄するのかを決める
相続の選択には単純承認・限定承認・相続放棄の3つの方法があり、相続開始を知ってから3ヶ月以内に決定する必要があります。それぞれの違いは、以下のとおりです。
| 単純承認 | 被相続人の財産を無条件・無制限にすべて相続する方法プラスの財産(不動産、預貯金など)もマイナスの財産(借金など)もすべて引き継ぐ |
| 限定承認 | プラスの財産の範囲内でマイナスの財産を引き継ぐ方法たとえば、預貯金1,000万円・借金1,500万円の場合、1,000万円分の借金のみ返済義務が生じ、残りの500万円は支払う必要がない |
| 相続放棄 | 被相続人のプラスの財産もマイナスの財産も一切引き継がない方法一度相続を放棄すると取り消しはできず、最初から相続人ではなかったものとして扱われる |
とくに、借金の有無は慎重に調査し、プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は相続放棄を検討しましょう。
ただし、一度相続を放棄すると撤回できないため、財産状況をできる限り把握してから判断することをおすすめします。
3. 相続手続きを進める
相続手続きは、法定期限に従って進めなくてはいけません。
相続放棄や限定承認を選択する場合は、相続開始を知った日から3ヶ月以内に家庭裁判所に届け出る必要があります。相続開始を知った日から10ヶ月以内には、相続税を申告して納付しなくてはいけません。
また、2024年4月からは不動産の相続登記が義務化され、相続を知った日から3年以内に登記を完了させる必要があることも留意しておきましょう。
以上の手続きは複雑で専門的な知識が必要なため、税理士や司法書士などの専門家に相談するのがおすすめです。
孤独死遺体の受け取りを拒否する際の流れ
ここでは、遺体引き取り拒否から火葬までの流れについて、4つのステップを詳しく解説します。
- 警察から遺体の引き取りを依頼する連絡が入る
- 自治体が遺体を火葬する
- 自治体から遺骨引き渡しの連絡が来る
- 自治体から火葬などにかかった費用を請求される
1つずつ見ていきましょう。
1. 警察から遺体の引き取りを依頼する連絡が入る
身内に孤独死が発生した場合、警察から連絡が入ります。
孤独死が発見されると、警察が現場検証し、遺体の身元確認が進められます。身分証明書や指紋照合・DNA鑑定などにより故人の身元が特定されると、警察から親族に知らされる流れです。
この時点では、遺体の引き取りはまだできません。まずは警察署で死亡状況の説明を受け、身元確認の手続きをする必要があります。
警察署への訪問時には、自身の身分証明書・印鑑・故人との続柄を証明する戸籍謄本などの書類を持って行きましょう。
事件性の有無や死因の特定のための検視が行われ、その結果を待って正式な引き取り依頼の連絡が入ります。遺体の引き取りを拒否する場合は、遺体の引き取りを依頼されたタイミングで伝えましょう。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、事前にご連絡いただいていなくても、お電話をいただければ直ぐにお迎えに上がります。
相場より価格を抑えたセットプラン料金でご案内いたしますので、ご安心くださいませ。
2. 自治体が遺体を火葬する
遺族が遺体の引き取りを拒否した場合は、死亡地の自治体が火葬を執り行います。自治体による火葬は最低限の簡素な形式で行われ、通夜や告別式などの宗教儀礼は省略されます。
火葬や埋葬にかかった費用は、自治体によって一時的に立て替えられ、後日法定相続人や扶養義務者に請求される流れです。
なお、孤独死が発生した場合でも遺族が葬儀を執り行うケースもあります。孤独死が発生した際の葬儀の流れについては、以下の記事を参考にしてみてください。
3. 自治体から遺骨引き渡しの連絡が来る
自治体による火葬後、自治体から遺族に対して、遺骨の引き渡しについての連絡が入ります。
遺骨の引き取りを拒否する場合は、自治体が契約する合同墓地や無縁墓に納骨されるケースが一般的です。
ただし、関東圏では遺骨の引き取りを拒否することは難しい傾向があり、火葬場から強く引き取りを求められる場合もあります。
遺骨の引き取りについては、地域によって対応の違いが大きいことに留意しましょう。
遺骨を受け取らない場合については、以下の記事を参考にしてみてください。
4. 自治体から火葬などにかかった費用を請求される
自治体による火葬執行後、遺族に対して火葬費用の請求が行われます。公営火葬場の場合、市内在住者は0~2万円程度、市外在住者は5~10万円程度の費用が発生します。
費用を負担するのは、主に遺産を相続した相続人や故人の配偶者や子ども・兄弟姉妹です。
なかには、火葬費用の支払いを求めない自治体も存在しますが、請求されることのほうが多いと考えておきましょう。
孤独死の遺体引き取りを拒否する際の注意点
遺体引き取り拒否を検討する際は、以下の3つの重要な注意点があります。
- 故人が生前に引き取り手を指定している場合がある
- 相続を放棄しても火葬費用は負担しなくてはいけない
- 遺品を整理すると相続を承認したとみなされるケースがある
1つずつ解説します。
1. 故人が生前に引き取り手を指定している場合がある
遺体の引き取り拒否を検討する前に、故人が生前に遺言や契約で引き取り手を指定していないか確認しましょう。引き取り手が指定されていた場合は、故人の意向に沿って対応するのが一般的です。
ただし、故人の意向には法的な拘束力はありません。生前の指定があったとしても、引き取りを拒否する法的な権利は残されており、最終的な判断はその場の状況によります。
2. 相続を放棄しても火葬費用は負担しなくてはいけない
相続を放棄しても、火葬費用の支払い義務から完全に逃れられません。遺体の処理費用はまず故人の財産から充当され、それで不足する場合は相続人や扶養義務者に請求される流れです。
特に配偶者や子供・兄弟姉妹などの近親者は、相続を放棄していても扶養義務者として費用負担を求められる可能性があります。
なお、故人が加入していた国民健康保険や健康保険を利用すれば、葬祭費が給付されます。ただし、葬儀なしで火葬のみ執り行った場合は、葬祭費の支給対象にならない自治体もあるので注意が必要です。
役所に申請できる給付金については、以下の記事を参考にしてみてください。
3. 遺品を整理すると相続を承認したとみなされるケースがある
相続放棄を検討している場合、遺品整理に着手しないことが大切です。
遺品のなかでも金銭的価値のある物を処分したり売却したりすると、法定単純承認とみなされ、相続放棄が無効になる恐れがあります。
とくに、不動産の売却や解体・貴金属類の処分・預貯金の使用などは避けましょう。相続放棄が家庭裁判所で認められたあとでも、遺品整理をすると相続したものとして扱われる可能性があります。
孤独死が発生したときに発生する費用
孤独死発生時に必要となる費用について、2つの主要な項目を詳しく解説します。
- 警察に引き取られるときに発生する費用
- 特殊清掃業者に支払うサービス料
それぞれ詳しく見ていきましょう。
1. 警察に引き取られるときに発生する費用
孤独死が発見された場合、警察による検死や遺体の保管に関連する複数の費用が発生します。具体的な費用は、以下のとおりです。
| 費用項目 | 金額 | 内容 |
|---|---|---|
| 検死費用 | 約5万円 | 検察官や医師による検視・検案に必要な費用 |
| 遺体検案料 | 2〜3万円 | 死因特定のための専門的な調査に使用される費用 |
| 死体検案書の発行費用 | 5,000円〜1万円 | 死体検案書の発行にかかる費用 |
| 遺体の保管料 | 1泊あたり2,000円程度 | 身元確認や死因特定までの期間に発生する保管料 |
とくに、行政解剖が必要となった場合は、8~12万円の追加費用が発生することに留意しましょう。
2. 特殊清掃業者に支払うサービス料
特殊清掃の基本料金は、部屋の広さによって大きく異なります。部屋の広さと清掃費用の相場は、以下のとおりです。
| 部屋の広さ | 特殊清掃費用の相場 |
|---|---|
| 1R・1K | 5〜30万円 |
| 1LDK〜3LDK | 7〜50万円 |
| 4LDK以上 | 20〜60万円 |
さらに、個別の作業内容に応じた費用が発生します。
| 作業内容 | 相場 |
|---|---|
| 浴室の清掃 | 3~10万円 |
| 消臭・除菌 | 1~2万円 |
| 体液や血液の除去 | 5~10万円 |
| 汚染された畳の撤去 | 3,000~9,000円/1枚 |
作業時間は、部屋の広さによって1時間から半日程度かかり、消臭作業は4~72時間程度を要するでしょう。
孤独死遺体の引き取りを拒否する際は周囲の人と相談しましょう
孤独死遺体の引き取りを拒否するのは、精神的にも経済的にも大きな決断を伴います。
遺体の引き取り拒否は法律上可能ですが、その後の相続や費用負担など、複雑な問題が絡んできます。
遺体の引き取り拒否を検討している場合は、一人で悩まず、専門家のアドバイスを受けながら、慎重に進めていきましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックで火葬のみ(直葬)も対応いたします。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。