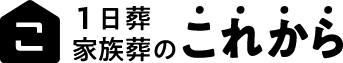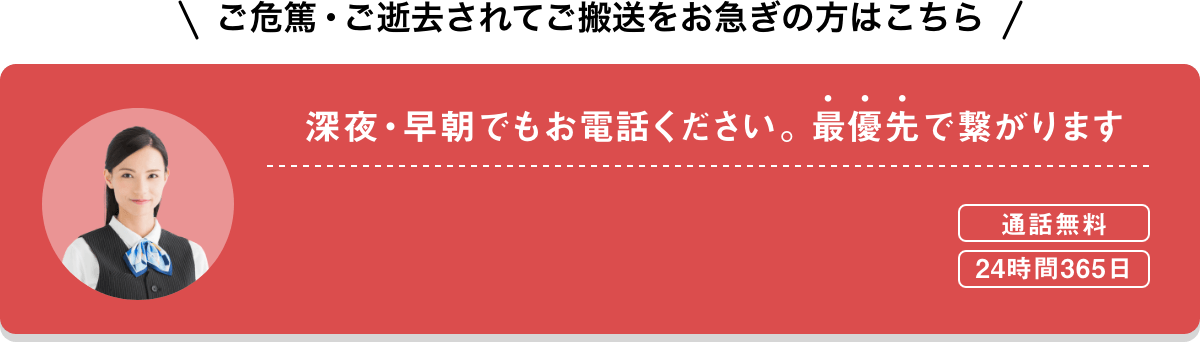急逝とは、予兆なく突然人が亡くなることです。しかし、急逝(きゅうせい)という言葉の意味を正確に把握していないという方もいるのではないでしょうか。
似た言葉がいくつかあるので、葬儀の際に正しく使い分けるためには、まずは内容を詳しく知っておく必要があります。
また、なかには身内が急逝し、なにから手を付ければよいのかわからず混乱している方もいるかもしれません。突然のことで準備もままならないでしょうが、まずは冷静になることが大切です。
今回は、急逝の言葉の意味や葬儀の際の使い分けについて解説します。身内や知人が急逝した際に取るべき行動についても紹介するので、記事の内容を参考に落ち着いて対処してください。
この記事を要約すると
- 急逝(きゅうせい)とは、急死の丁寧語で、事故や事件で前触れなく急に亡くなることを指します。逝去(せいきょ)との違いは、「突然」「予想外」というニュアンスを含む点です。
- 家族が急逝した場合、入院中や自宅療養中であれば主治医に、蘇生の可能性があれば救急車に、それ以外では警察に連絡を取ります。医師からの死亡診断書もしくは警察からの死体検案書がないと火葬や納骨ができないため、適切に対処する必要があります。
- 急逝の訃報を受けた側は、お悔やみを述べたうえで葬儀内容を確認します。急逝の理由についての話題はタブーのため注意が必要です。
急逝(きゅうせい)とは元気な人が急に亡くなること
急逝とは、それまで元気だった人が、前触れなく急に亡くなることを指します。病気やケガもなく、前日まで普通に過ごしていたのにもかかわらず、次の日になって突然死亡するようなケースで使用するのが一般的です。
急に亡くなる原因としては、事故や事件、自殺などが挙げられます。重い病気にかかり、療養中に亡くなった場合には「急逝した」とはいいません。亡くなることが予想外とはいえないからです。
しかし、軽度の病気や、症状が軽減・消失していたにもかかわらず唐突に重篤化して亡くなった場合には、急逝という言葉を使うことがあります。
急逝と呼ぶかどうかのポイントは、予想外の死であったかどうかです。急逝の言葉を使う際には、この点に注目しましょう。
突然死や事故死、自殺の際の葬儀については、以下の記事で詳しく解説しています。
急逝と逝去(せいきょ)の大きな違いは急であるかどうか
急逝と似た言葉に逝去(せいきょ)がありますが、双方の大きな違いは、急な死であったかどうかと、言葉を向ける対象です。
逝去は「死ぬ」の尊敬語であり、亡くなったことを丁寧に表現する言葉です。急であったというニュアンスは含まれません。
逝去は尊敬語であるため、身内が亡くなった際には使わず、目上の方や著名人が亡くなった際に使用します。慣習的にあえて二重敬語を使い、「ご逝去された」のように表現することもあります。
一方、急逝は丁寧語であり、身内が亡くなった際にも使用します。
急逝と関連性の深い言葉
急逝と関連性の深い言葉には、逝去以外にも以下のようなものがあげられます。
- 急死
- 即死
- 死去
- 他界
- 永眠
それぞれの言葉の意味は次のとおりです。
急死
急死とは、文字通り急に亡くなることを指します。事故や自殺などが原因で、予想外のタイミングで亡くなった場合に使用します。
急死の丁寧語が急逝であるため、両者の意味はほぼ同一です。急死は口語的、急逝は文語的な表現ともいえます。
即死
即死は、死に要した時間に着目した表現で、死の原因を受けた後、亡くなるまでの時間が極端に短かった場合に使用する言葉です。
事故や災害にあったとき、救急車が間に合わず、その場ですぐに死亡したようなときには即死したと表現されます。原因を受けてから死に至るまでの時間には、明確な定義はありません。
死去
死去とは、死を表す一般的な表現で、死んでこの世を去ることを指します。
死去は、身内が亡くなったときに使用し、目上の人には使用しません。
他界
他界は、「死」の文字を使わずに、亡くなったことを遠回しに伝える言葉です。故人が他の世界、つまり死者の世界に旅立ったと表現することで、露骨にならないように死を伝えます。
他界は身内が亡くなった際に使用しますが、もともとは仏教用語だったため、仏教徒や仏式の葬儀の際に使用するのが一般的です。仏教であっても浄土真宗の場合やキリスト教徒の場合は、他界という表現は避けたほうが無難とされます。
永眠
永眠は、身内の死を眠りに例えて伝える表現です。
永い眠りについたと伝えることで、ストレートに「死」と伝えるより表現が和らぎ、ネガティブな印象を抑えられます。
家族が急逝した場合の手順
家族が急逝した場合には、以下の手順に沿って冷静に対応を進めましょう。
- 家族が自宅で急逝した場合は警察に連絡する
- 身内や親戚に連絡する
- 死体検案書・死亡診断書を受け取る
- 葬儀社・菩提寺に連絡する
- 葬儀内容を周知する
それぞれの具体的な内容を解説します。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、事前にお問い合わせされていなくても、専門スタッフが親身にお客様のご要望に合わせて直ぐに、葬儀のご手配をいたしますので、ご安心くださいませ。
家族が自宅で急逝した場合は警察に連絡する
家族が自宅で急逝した場合には、まずは警察に連絡しましょう。
警察が介入した場合、現場検証や事情聴取が行われ、ご遺体は警察に搬送されます。警察が来るまでの間、ご遺体や周りの物品は動かしてはいけません。なるべくその場に手を加えないよう留意しましょう。
持病が寛解し自宅療養していた際に急逝したようなケースでは、警察ではなく主治医に連絡します。病気が原因で亡くなった可能性があるためです。
蘇生の可能性があるケースはもちろん、完全に亡くなっているのか判断がつかない場合には、警察ではなく救急車を呼びましょう。
なお、自宅ではなく病院で亡くなった場合は、事件性がない限りは警察への連絡は不要です。病院の医師にゆだねましょう。
警察の検視にかかる日数や具体的な流れが知りたい方は、以下の記事も参考にしてください。
身内や親戚に連絡する
身内や親戚に故人の急逝を連絡します。迅速かつ正確に訃報を知らせるためには、電話での連絡がベターです。
故人と親しかった順に連絡していきます。この段階では、三親等までの親族に連絡するのが一般的です。故人と親しくしていた友人がいれば、この段階で連絡しても構いません。
日頃付き合いのない親戚には、葬儀日程が決まってからの連絡で問題ないでしょう。
死体検案書・死亡診断書を受け取る
警察や医師の確認が済んだら、死体検案書もしくは死亡診断書が発行されるので速やかに受け取りましょう。
自宅で亡くなった場合や、事件性が疑われ警察が介入した場合には、死体検案書が発行されます。一方、病院で亡くなった場合や、自宅で主治医が死亡を確認した場合には、死亡診断書が発行されます。
これらの書類は、死体火葬許可証を発行してもらう際に必要です。死体火葬許可証がないと火葬や納骨ができないため、紛失しないよう十分に注意しなければなりません。
警察が発行する死体検案書の詳細は、以下の記事で解説しています。
葬儀社・菩提寺に連絡する
死体検案書や死亡診断書が発行され、故人の死亡が確定した段階で、葬儀社や菩提寺に連絡しましょう。
病院で亡くなった場合には、速やかにご遺体を引き取り、安置所まで運ばなければなりません。葬儀社に依頼すれば、安置所の手配や移送を引き受けてくれます。
ご遺体を安置所に移したら、葬儀内容や日程について葬儀社と打ち合わせします。死体火葬許可証の申請については、弊社では代行いたしますのでご安心ください。
菩提寺がある場合には、葬儀日程が決まり次第連絡を入れ、お通夜や告別式で読経してもらう手はずを整えます。
近年では直葬や無宗教葬など、僧侶を呼ばないスタイルのお葬式も珍しくありません。葬儀に僧侶が不要だからと自己判断し、連絡を怠った場合には、菩提寺への納骨を断られるケースがあるため注意が必要です。
葬儀社は、病院から紹介してもらえる場合もありますが、基本的には自分の好みで選べます。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では相場より価格を抑えた葬儀を行えます。
葬儀に必要なものが含まれたセットプランでお手伝いいたしますので、ご安心してお任せください。
葬儀内容を周知する
葬儀の手はずが整った段階で、訃報や葬儀内容を周知します。
日頃付き合いのなかった親戚や、故人の会社関係、知人、必要に応じて町内会などに対し、訃報を知らせましょう。
訃報の伝え方や文例については、以下の記事で詳しく解説しています。
急逝の知らせを受けた側の適切な対応方法
急逝の知らせを受けた際には、以下の点に留意して対応しましょう。
- お悔やみを伝える
- 急逝の理由には触れない
- お通夜・告別式の予定を確認し参列準備を整える
対応内容について解説していきます。
お悔やみを伝える
訃報を受けたら、まずはお悔やみを伝えましょう。
凝った言葉を伝える必要はなく、「このたびはご愁傷さまです」「心からお悔やみ申し上げます」と伝えれば問題ありません。
ただし、宗教や宗派により、ふさわしいお悔やみの言葉は異なります。死を神からの祝福ととらえるキリスト教の場合、「安らかな眠りをお祈りいたします」と伝えるのが適切とされます。
電話で連絡を受けた際には、あまり長々と話し込んでは相手の迷惑になります。遺族にはしなければならないことが山積みのため、端的にやり取りするよう配慮が必要です。
相手との会話や返信のなかで、忌み言葉を使わないよう注意しましょう。
「重ね重ね」や「まだまだ」のような重ね言葉は、不幸が重なることを連想するため使用を避けます。死をストレートに想起する「死去」や「亡くなる」という言葉も避け、「ご逝去」を使いましょう。「ご存命」についても強い表現のため、「お元気な頃」など婉曲表現に言い換えます。
急逝の理由には触れない
訃報を受けた際、急逝の理由には触れないでおきましょう。
遺族にとって、故人の死因に触れることはつらいものです。蒸し返せば傷つけることになるため、こちらから話題に出すのは控えましょう。
お通夜・告別式の予定を確認し参列準備を整える
先方から葬儀日程や場所、葬儀形式、宗派に関する説明がなかった場合には、こちらから確認しましょう。日程や形式に合わせて参列準備を整えます。
場合によっては遺族が身内のみの葬儀を希望し、弔問を辞退していることもあるものです。このようなケースでは、無理に参列するのはマナー違反となるため注意が必要です。
急逝にまつわる4つの注意点
急逝にまつわる主な注意点としては、以下の4つが挙げられます。
- 相手によって連絡手段を変える
- 訃報やお悔やみを伝える時間帯に配慮する
- 故人の銀行口座の手続きは慎重に行う
- 故人の携帯電話内の情報を引き出すには工夫が必要
具体的に解説していきます。
相手によって連絡手段を変える
遺族が周囲に訃報を伝える際には、相手によって連絡手段を変えましょう。
身内に対しては、基本的に電話で訃報を伝えます。しかし、知人や会社関係に関して逐一電話していたのでは、手間や時間がかかります。故人との関係性に応じて、適宜メールを利用するなど連絡を取りやすい方法を選択しましょう。
電話では急逝したことのみを端的に伝え、具体的な葬儀内容についてはメールする方法も有効です。
メールや書面など文章でやり取りする際には、句読点を使わないのがマナーです。忌み言葉についても、文章にすると口頭より目立つため注意が必要です。
訃報やお悔やみを伝える時間帯に配慮する
遺族側から訃報を伝える際や、訃報への折り返しでお悔やみを伝える際には、時間帯に配慮しましょう。
身内以外へ電話で連絡する場合には、早朝・深夜は避けるよう配慮が必要です。連絡を受けた側は、訃報にはすぐに返信するのがマナーですが、常識的な時間外に連絡するのはかえってマナー違反です。
留守電やメールで訃報を受け、折り返し電話するような際には、日中や夜が更ける前までに連絡しましょう。
故人の銀行口座の手続きは慎重に行う
故人の銀行口座の手続きは慎重に行いましょう。
亡くなった人の銀行口座は凍結手続きを行うものです。凍結後はお金が引き出せなくなりますが、かといって凍結手続き前に勝手に引き出すのも問題です。
葬儀代や当面の生活費が必要な場合には、親族間の同意を取り付ければ引き出せます。
また、仮払い制度も利用可能です。故人が死亡した時点での預金残高の三分の一に法定相続割合をかけた金額を、上限150万円まで引き出せます。(参考:法務省「相続に関するルールが大きく変わります」)
必要に応じて、親族や金融機関に相談しましょう。
故人の携帯電話内の情報を引き出すには工夫が必要
故人の携帯電話内の情報を引き出すには工夫が必要です。
近年では、銀行やクレジット、サブスク、投資などの情報を携帯電話で管理している人も多く、遺産整理の際に情報が必要な場合があります。しかし、遺族がパスワードを知らない場合、携帯電話は開けません。携帯会社に依頼しても故人の携帯電話のロック解除はできないことも多々あります。
指紋認証していたようなケースでは、故人の指紋を使えばロック解除可能です。パスワードで管理していた場合には、生年月日や記念日など、あたりをつけて番号を入力していくことになるため、根気がいります。
携帯を解約しただけではサブスクは解約できないため、なんらかの手段で情報を得る必要があります。遺族が把握している情報や送付された請求書があれば、それをもとに解約することも可能です。
どの銀行やクレカを使っていたかがわかる場合には、相手の会社に直接連絡して凍結すれば、引き落としができずに連絡がくる可能性が高いでしょう。
急逝のマナーを押さえ冷静に対処しよう
急逝とは、なんの前触れもなく急に亡くなることを指します。
突然のことに平常心ではいられないものですが、ケースに応じて主治医や警察、救急車に連絡し、冷静に手続きを進めていくのが肝要です。
マナーを押さえ、一つずつ適切に処理していきましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。