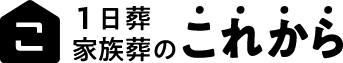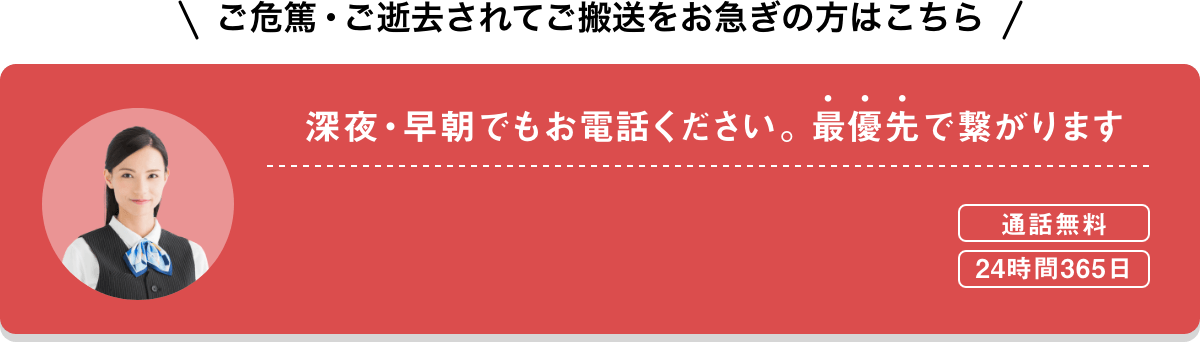「突然死」とは、これまで元気に過ごしていた方が突然病気を発症して亡くなることを指します。突然死は年齢や性別を問わず、誰しもに起こりうるものです。しかし、予想していなかったお別れは遺族にとってショックが大きく、気が動転してしまうかもしれません。
今回は、家族が突然倒れて亡くなったときの対応方法を知りたい方向けに、倒れた家族を発見したときの対処方法や突然死から葬儀までの流れなどを詳しく解説します。家族が突然倒れた場合、倒れた場所や体の状態に合った冷静な対応を取ることが大切です。
この記事を要約すると
- 突然死とは、急に病気を発症して24時間以内に亡くなることを指します。突然死の原因として多いのは、心臓病や脳血管障害です。
- 家族が突然倒れて亡くなっているところを発見したら、かかりつけ医がいる場合はかかりつけ医を呼び、かかりつけ医がいない場合は警察を呼びましょう。
- 死因や身元がすぐに判明しないときは、警察によって検視や司法解剖が行われることがあります。葬儀の手配は、遺族にご遺体が引き渡されてから進めましょう。
突然死とは?
「突然死」とは、これまで健康に過ごしていた方が急に病気を発症し、24時間以内に死亡することを指します。なかでも発症から1時間以内に死に至った場合は、「瞬間死」と呼ばれます。事故死や自死も突然亡くなるケースのひとつですが、これらは突然死に含まれません。
突然死の原因として多いのが、心臓病や脳血管障害です。しかし、なかには病気の症状が見られず、死亡原因が不明とされることもあります。
突然死は、治療中の病気や既往症がない方にも突然訪れます。遺族にとっては予期せぬお別れであり、心の準備ができていないケースがほとんどでしょう。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、突然のことで初めての問い合わせの方でも、葬儀の専門スタッフがご相談から親身に承ります。納得のセットプラン料金で、相場よりも価格を抑えて葬儀を行えますので、まずは安心してご連絡くださいませ。
<主な突然死の原因>
- 心筋梗塞
- 虚血性心疾患
- 心筋症
- 致死性不整脈
- 大動脈瘤破裂
- 脳梗塞
- くも膜下出血
- 脳出血
- てんかん重積発作
- 喘息重積
急逝との違い
「突然死」とよく似た言葉に、「急逝」という言葉があります。急逝とは、これまで元気に見えていた方が前触れもなく急に亡くなってしまうことです。
突然死とほとんど同じ意味合いを持ちますが、急逝には事故死・事件死・自死・軽症の病気の急な悪化なども含まれます。また、若くして亡くなった方に対して急逝と表現することもあります。
家族が突然死したときの対応方法
家族が突然倒れて亡くなっているところを発見した場合、どこで倒れたかによって正しい対応方法が異なります。病院以外の場所で急に倒れたら、かかりつけ医の有無や体の状態によって救急と警察のどちらを呼ぶかを適切に判断する必要があります。
病院で亡くなった場合
故人が別の病気で入院していたケースや、倒れたところを発見した人が救急車を呼んだケースなど、突然死であっても病院で息を引き取ることは珍しくありません。
病院で亡くなった場合は、病死の場合と同様に医師が死亡診断を行い、死亡診断書を作成します。その後、遺族に対して死因や治療内容の報告がなされます。
しかし、なかには死に至った直接的な原因がわからないこともあります。その場合は病院が警察に連絡を取り、警察による事情聴取や死体の検視が行われます。警察によって死亡確認や検案が行われるケースでは、死亡診断書の代わりに死体検案書が発行されます。
以下の記事では、検視や死体検案書の発行についてより詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
かかりつけ医がいる方が病院以外で亡くなった場合
突然死では、自宅や外出先をはじめとした病院以外の場所で倒れるケースが珍しくありません。倒れた方に普段からお世話になっているかかりつけ医がいる場合は、すぐにかかりつけ医を呼びましょう。
その後、駆け付けたかかりつけ医が診察を行い、病院で亡くなった場合と同様に死亡診断が下されます。
かかりつけ医はその方の普段の体調や病状を一番よく認識しています。倒れて亡くなっているところを発見した際にかかりつけ医ではなく警察を呼んでしまうと、かえって手続きが煩雑になってしまう可能性があるため注意が必要です。
かかりつけ医がいない方が病院以外で亡くなった場合
かかりつけ医がいない方やかかりつけ医の有無がわからない方が病院以外の場所で倒れた場合、その場で亡くなっているかどうかによって対応方法が異なります。
倒れた方にまだ脈や呼吸がある場合は、救急車を呼んで病院へ搬送しましょう。その後の流れは病院で亡くなった場合と同様です。
一方ですでに息を引き取っていることがはっきりとわかる場合は、救急搬送ができません。体を動かしたり手を触れたりせず、すみやかに警察に連絡しましょう。警察が到着すると事情聴取や現場検証のうえ死亡確認が行われ、死体検案書が作成されます。
その場で死因が特定できないケースや事件性が疑われるケースでは、ご遺体を警察署に搬送して検視や司法解剖が行われます。この場合は死因が特定され、死体検案書が作成され次第ご遺体が遺族に引き渡されます。
以下の記事では家族が自宅で亡くなった際の対応方法を詳しく解説しています。ぜひこちらも参考にしてみて草さい。
突然死から葬儀までの流れ
ここからは、突然死した方の死亡確認から葬儀が行われるまでの流れを解説します。葬儀の準備や葬儀内容は、病死した方とほとんど変わりません。
以下の記事では、亡くなってから葬儀までの一般的な流れをより詳しく解説しています。ぜひ、あわせてチェックしてみてください。
ご遺体の搬送・安置
死亡が確認され、ご遺体が遺族の元に引き渡されたら、葬儀が始まるまでご遺体を安置する必要があります。ご遺体の安置所は自宅・葬儀社の霊安室・公営や民営の霊安室などを利用するのが一般的です。
安置所が手配できたら、葬儀社スタッフの先導のもと、ご遺体を安置所まで搬送します。搬送されたご遺体には腐敗が進まないように必要な処置や消毒が施され、ドライアイスで保護されます。
弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、初めての問い合わせでもご連絡いただければ、すぐにお迎えに上がります。
相場より抑えた価格で、葬儀に必要なものを含んだ分かりやすいセットプラン料金でお手伝いいたしますので、ご安心してご連絡くださいませ。
葬儀準備
依頼する葬儀社を決定したら、すみやかに手配の連絡を入れましょう。葬儀の打ち合わせでは、はじめに喪主を決定したのち、葬儀の日程・宗教形式・参列者数・葬儀内容などを細かく詰めていきます。
葬儀の日程が決まったら、参列を依頼する方に対して葬儀案内を送ります。死亡届の提出や火葬許可証の受け取りも、このタイミングで行いましょう。お通夜や葬儀・告別式などで僧侶を招く場合は、お布施の用意も必要です。
お通夜
お通夜は故人と最後の夜を過ごす儀式で、夕方から夜の時間帯にかけて1〜2時間程度執り行われます。お通夜に先駆け、故人を棺に納めて死装束を着せる「納棺の儀」も行われます。
お通夜には故人の遺族や親戚らが参列し、僧侶の読経を聞いたり、1人ずつ焼香をあげたりします。式後には「通夜振る舞い」という会食の席が行われるのが一般的です。
葬儀・告別式
葬儀・告別式は、お通夜の翌日の昼に行われます。仏式で行う場合はお通夜と同様に僧侶が読経をし、故人が無事に極楽浄土へ向かえるよう戒名の儀を行います。
式の終わりには遺族や参列者たちが故人の棺の周りに集まり、棺の中に花を手向けます。故人との最後のお別れをした後、棺は火葬場へと出棺されます。
火葬
火葬場に棺が到着したら、火葬炉で火葬が行われます。火葬場には遺族や故人ととくに関係の深かった人のみが参列するのが一般的です。
無事に火葬が終わったら、収骨室でお骨上げを行います。この儀式は、「故人を無事にあの世へと橋渡しする」という意味合いを持った重要な儀式です。
参列者は長い竹の箸を使って遺骨を1本1本拾い上げ、骨壷へと納めていきます。故人の遺骨を納めた骨壷は、四十九日法要後に納骨が行われるまで、遺族の自宅の祭壇で保管されます。
法要・納骨
葬儀が終わった後は毎日の供養のほか、亡くなった日から7日目に初七日法要、49日目に四十九日法要を行います。
初七日法要では遺族や親戚の参列のもと、僧侶による読経が行われます。1時間程度の短い式のため、昨今は葬儀・告別式当日に繰り上げて執り行うケースも珍しくありません。
四十九日法要は仏教における「忌中明け」の区切りとなるため、簡略化せずに必ず行いましょう。法要では、僧侶による読経や法話が行われます。式後は、その足のまま納骨を行うのが一般的です。
家族が突然死した場合の注意点
家族が突然倒れて亡くなったとき、急なお別れであっても冷静に対応することが求められます。ここからは、家族が突然死した際に注意すべき点を解説します。
救急と警察のどちらを呼ぶか正しい判断をする
病院以外の場所で倒れている方を発見したとき、救急車と警察のどちらを呼べばよいか迷うことがあるかもしれません。もし迷った際は救急車を呼んでかまいませんが、到着した救急隊員によってその場で亡くなっていると判断された場合は、病院に搬送できないため警察を呼ぶことになります。
救急車を呼んでから救急隊員を介して警察を呼ぶことになると、死亡確認とご遺体の引き取りまでに時間がかかってしまう可能性があります。
ご遺体には手を触れない
ご家族が亡くなっているところを発見した場合、死亡確認が行われるまで体に手を触れたり動かしたりしてはいけません。
気が動転して思わず体に触れてしまいたくなるかもしれませんが、事件性を疑われないようにするためにも、医師や警察による判断が終わるまでは体をそのままの状態にしておく必要があります。
ご遺体の引き取りまで時間がかかる場合がある
病院以外の場所で亡くなっているところを発見された場合や、病院で明確な死因が特定できなかった場合は、ご遺体を警察に引き渡すことがあります。
警察署では死亡に対する事件性がないかどうかを調査するために検視を行ったり、場合によっては司法解剖を行ったりします。
このとき、病院で死亡確認が行われるケースと比べてご遺体の引き取りまでに時間がかかるのが一般的です。検視の場合は半日〜1日程度、司法解剖の場合は数日〜1ヶ月程度が目安で、ご遺体を引き取るまでは葬儀日程を決められません。
病院以外で死亡確認が行われた場合は死体検案書が発行される
故人が病院で亡くなった場合は医師によって「死亡診断書」が発行されますが、病院以外の場所で亡くなり警察によって死亡確認が行われた場合は「死体検案書」が発行されます。
死体検案書は死亡診断書と同等の扱いを受ける文書で、死亡届の提出に必要です。死体検案書には発行手数料が3万円〜10万円程度かかります。
病院には公共交通機関を利用して向かう
家族が突然倒れて病院に搬送されたという連絡を受けた場合、急いで病院に向かう必要があります。このとき、自家用車は利用せず、できるだけ公共交通機関を利用しましょう。突然の事態に気が動転してしまい、運転に支障が出る可能性があります。
また、死亡診断書の発行には手数料がかかるため、まとまった現金や自身と倒れた方の身分証明書などを持っていくといざというときにスムーズです。
家族が突然死した場合の訃報の伝え方
医師や警察によって死亡の確認がなされたら、葬儀準備と並行して訃報を伝える必要があります。訃報は相手との間柄によって、伝えるタイミングや内容が異なります。
伝える範囲
訃報を伝える範囲は、家族・親戚や友人などの親しい間柄はもちろん、故人が勤めていた職場・通っていた学校や遺族の関係者、近隣住民も対象となります。
訃報を伝える際は連絡先リストを作成し、1件ずつチェックをつけながら連絡していくと抜け漏れが起こりません。一般的には、故人と近しい関係性の方から順に連絡を入れていきます。
<訃報を伝える範囲と順番>
- 家族・親戚
- 友人・親しくしていた人
- 知人・故人の勤め先の関係者・故人の通っていた学校の関係者
- 遺族の関係者
- 近隣住民・自治体関係者
伝えるタイミング
訃報を伝えるタイミングは、故人と相手との生前の関係性によってさまざまです。家族や親戚に対しては、亡くなった直後に連絡を入れましょう。この場合はすぐに伝えることが重要であり、夜中や明け方であっても連絡をしてかまいません。
葬儀に参列を依頼する間柄の人に対しては、葬儀日程や葬儀の詳細が決定したタイミングで葬儀案内とともに伝えるのが一般的です。葬儀に参列しない人に対しては、葬儀前に葬儀の詳細を伏せて連絡する方法や、葬儀後に無事に葬儀を執り行った旨も含めて連絡する方法があります。
伝える方法
訃報を伝える方法には、電話・メール・書面・死亡広告などがあります。なかでも家族や親族に連絡する際は、緊急性が高いため電話を用いるのが一般的です。
電話が繋がらなかった場合は、留守番電話を入れて折り返し連絡してもらうように頼んだり、代わりにメールを送ったりして対応しましょう。また、電話で概要をいち早く伝えたあと、詳細をメールで伝えるのもひとつの方法です。
なお、緊急を要さない間柄の人に対しては、葬儀の詳細が決まってから葬儀案内とともにメールや書面で訃報を伝えます。
伝える内容
訃報を伝える際は、必要な内容をできるだけ簡潔にまとめましょう。メールや手紙を用いる際は、「葬儀が滞りなく取り行えますように」という意味合いで句読点を使わないのがマナーです。時候の挨拶も使用しません。
伝える項目
- 故人が亡くなったこと
- 亡くなった日時や場所
- 葬儀の日程(すでに決定している場合)
- 喪主や遺族代表者の連絡先
電話で伝える場合
「突然のお電話申し訳ございません。◯◯の娘の◯◯でございます。母の◯◯が昨日午前に急逝いたしました。葬儀の日程については、決まり次第あらためてご連絡いたします。」
「◯◯の娘の◯◯です。母の〇〇が一昨日息を引き取りました。つきましては通夜を◯月◯日◯時より、葬儀告別式を◯月◯日◯時より、◯◯斎場にて仏式で執り行います。何かご連絡いただく際は、私の携帯電話までお願いいたします。」
メールで伝える場合
件名:【訃報】〇〇急逝のお知らせ
母の〇〇が◯月◯日◯時◯分に急逝いたしました
享年◯歳でした
ここに生前のご厚誼を深謝し謹んでお知らせいたします
通夜ならびに葬儀告別式は下記の通り仏式にて執り行います
- 通夜:◯月◯日(◯)午後◯時〜
- 葬儀告別式:◯月◯日(◯)午前◯時〜◯時
- 斎場:◯◯斎場にて(住所/電話番号)
- 仏式:◯◯宗
- 喪主:◯◯(間柄)
- 連絡先:(電話番号/メールアドレス)
突然のお別れでも後悔の残らないようにしましょう
突然死はその名のとおり、突然訪れます。遺族の方は大切な方との予想していなかったお別れにショックを受けるかもしれませんが、できるだけ冷静に葬儀の準備を進めましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。