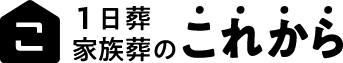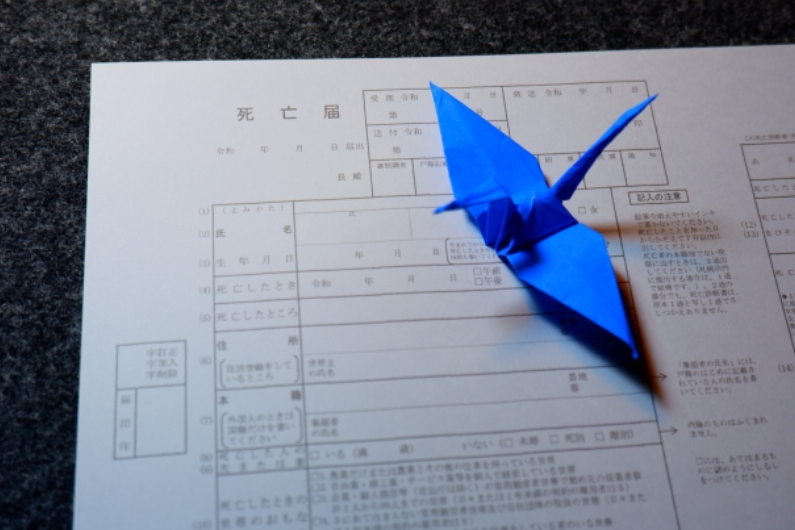人が亡くなった際に必要となる書類の1つに「死体検案書」があります。この書類は、故人の死因などを医師が確認し、記録するために作成されますが、発行には費用がかかります。
特に、不慮の死や医師が直接診察していない場合に必要となる死体検案書の発行費用は、地域や状況により大きく異なるため、注意が必要です。葬儀準備を進めるうえで「どの程度の費用がかかるのか、どのような場合に高額になるのか」と、不安に感じる方もいるでしょう。
この記事では、死体検案書の発行費用の相場や費用を工面するのが難しい場合の対処方法などについて解説していきます。内容を理解したうえで葬儀準備を進めていきましょう。
この記事を要約すると
- 死体検案書とは、故人の死因や死亡状況を記録した書類で、発行費用として3~10万円ほどかかる。
- 死体検案書の費用内訳には、検視費用、検案費用が含まれており、司法解剖費用は国が負担する。ただし、承諾解剖を希望する場合は別途費用がかかり、遺族負担となる。
- 自治体によっては死体検案書の作成費用を補助してくれる制度がある。また、複数の条件を満たし、葬祭扶助制度を利用すると、葬儀費用を補助してもらうこともできる。
死体検案書とは死亡を証明する書類のこと
死体検案書は、故人の死亡を医学的・法律的に証明する重要な書類です。不自然な死因や医師が死亡に立ち会っていない場合に、警察医や監察医が検視や解剖を行った後に発行します。
この書類がなければ、死亡届の提出や火葬許可書の取得ができず、葬儀やその後の手続きが進められません。また、国の死因統計や行政施策の基本資料としても活用され、その役割は非常に重要です。
死体検案書には、故人の基本情報や死亡日時、死因、死亡場所、死亡の種類、発行医師の署名などが記載されます。死亡診断書と記載内容に大きな違いはないものの、発行される状況や発行者が異なります。(参考:医の倫理の基礎知識 2018年版【医師と社会】G-4.死亡診断書と死体検案書|日本医師会)
死体検案書は、作成までの流れや発行者が異なる分、発行にかかる費用が異なります。相場を理解したうえで、準備しておくようにしましょう。死体検案書の詳細については、以下の記事で詳しく解説しているので、気になる方はチェックしてみてください。
死体検案書の発行費用は3~10万円
死体検案書の発行にかかる費用は、一般的に3〜10万円といわれています。一方で、死亡診断書の発行費用が数千円程度であることを考えると、両者には大きな差があることが分かります。
この差の理由として、事故や自殺など死因が特定しにくい場合の検案作業や、医師による詳細な確認が必要になる点が挙げられます。ここでは、死体検案書の発行費用の内訳や、別途費用が発生するケースについて解説します。
死体検案書の発行費用の内訳
死体検案書の発行費用は、「検視」「検案」「解剖」それぞれの内容によって異なります。検視は、警察官が現場を確認する過程で、数万円程度が相場です。検案は医師が行い、相場は2~3万円ほどです。
解剖はさらに種類によって異なり、犯罪性が疑われる場合の司法解剖は、全額国が負担するため無料となります。一方、行政解剖は自治体ごとに費用負担が異なり、一部または全額が自己負担になるケースもあります。
自治体による葬祭費の支給制度を活用することで、負担を軽減できる可能性がありますので、事前に確認してみましょう。
なお、検視は刑事訴訟法第229条により定められたものであるため、「費用を抑えたいから」といって拒否することは原則できません。司法解剖に関しても警察の判断のもと実施されます。
承諾解剖を行う場合は別途費用が発生する
死体検案書を作成する際に行われる解剖には、主に「司法解剖」「行政解剖」「承諾解剖」の3種類があります。一般的に行われる司法解剖は、犯罪性が疑われる場合に実施され、その費用は全額国が負担します。
一方、承諾解剖は、遺族の同意を得て行われ、費用は遺族の負担となります。承諾解剖とは、監察医制度のない地域で、病気や事故など、事件性がない場合に死因を詳しく調べるために行われる解剖です。費用費用は数万円〜数十万円が相場です。
承諾解剖の費用は、解剖を行う医療機関や地域によって異なります。また、解剖後の遺体の修復や葬儀の日程調整など、追加の費用や手続きが発生する場合もあるため、事前に医療機関や自治体に確認し、適切な対応が取れるようにしましょう。
自治体によっては死体検案書にかかる費用を補助してくれる制度もある
一部の自治体では、死体検案書にかかる費用を補助する制度が設けられています。たとえば、奈良県では犯罪被害者の遺族の経済的負担を軽減するため、司法解剖に伴う死体検案書料を公費で負担する制度があります。
この制度では、犯罪行為による死亡が認められた場合、遺族や医療機関が費用の請求を行うことで、必要な金額が補助されるというものです。
補助を受けるには、犯罪行為が確認され、遺族が公費支出を希望する必要があります。ただし、暴力団関係者が被害者の場合などは対象外とされる可能性があります。(参考:司法解剖に係る死体検案書料公費支出制度の実施について|奈良県警察本部)
なお、死体検案書のためのものではないものの、葬儀費用の工面が難しい遺族などに向けては、葬祭扶助制度なども利用可能です。補助の有無や条件は、警察や自治体の窓口で相談してみましょう。
死体検案書の費用を払えない場合は自治体への相談がおすすめ
死体検案書の費用を負担できない場合、自治体に相談することで経済的な支援を受けられる可能性があります。前述の通り、一部の自治体では死体検案書の費用を公費で補助する制度が設けられているほか、葬儀費用については葬祭扶助制度を利用できる場合があります。
葬祭扶助制度とは、生活保護を受けている方や一定の収入条件を満たす方を対象に、自治体が葬儀費用を補助する制度です。この制度により、火葬や埋葬に必要な最低限の費用が公費で支給されます。支給金額は自治体ごとで異なり、役所で事前に申請が必要です。
各自治体の福祉課や生活支援課が窓口になるので、詳細を知りたい場合は事前に相談しておくとよいでしょう。
死体検案書は役所に提出する前にコピーを取っておく
死体検案書や死亡診断書は、役所に提出する前に必ずコピーを取っておきましょう。死亡届の提出や火葬許可を得るためだけでなく、銀行口座の解約や保険金の請求、各種契約の名義変更などに必要となるためです。
役所に提出してしまった場合、あとから原本を返却してもらうことはできません。そのため、10枚程度はコピーを用意しておくようにしましょう。
万が一、役所に提出してしまった場合、原本の返却はされないものの「死亡届の記載事項証明書」であれば発行してもらえます。
また、3親等以内の家族や配偶者であれば、死体検案書の再発行も条件付きで依頼可能です。ただし、再発行には手数料と指定の書類が必要となるため、大切に保管しなくさないようにしましょう。
死体検案書の費用や発行の流れを理解して葬儀準備を進めよう
死体検案書は、故人の死亡を証明する重要な書類であり、発行には3〜10万円の費用がかかります。発行の流れや費用は地域によって異なり、必要に応じて承諾解剖などが行われる場合、追加費用が発生することもあります。
これらの費用は遺族負担となりますが、自治体による補助制度や葬祭扶助制度を活用することで、経済的負担を軽減できる可能性があります。今回解説した内容を理解したうえで、葬儀の手続きをスムーズに進めていきましょう。
弊社では、葬儀準備や各種手続きについてご相談いただけます。役所への書類提出といった手続き代行にも対応しておりますので、葬儀準備でお困りの方は、どうぞお気軽にご相談ください。