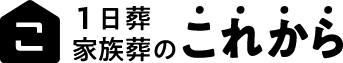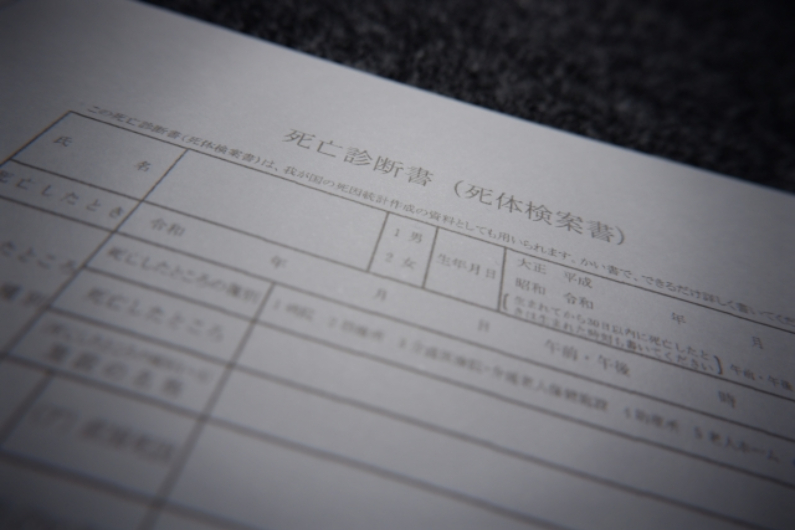人が亡くなった際、まず必要となるのが役所への「死亡届」の提出です。この際に添付する「死亡診断書」や「死体検案書」は、故人の死因などを記録する重要な書類であり、葬儀の手続きや各種契約にも欠かせないものです。
しかし「死体検案書とはなんなのか、その発行や手続き方法がよく分からない」という方がほとんどでしょう。死体検案書は死亡診断書と発行の流れや発行にかかる費用が異なるため、注意が必要です。
この記事では、死体検案書とは何なのか、その役割や発行される流れを中心に分かりやすく解説していきます。内容を理解したうえで葬儀準備を進めていきましょう。
この記事を要約すると
- 死体検案書とは、故人の死因や死亡状況を記録した書類で、死亡届の提出や火葬許可の申請時に必ず必要な書類。
- 入院や通院中に医師が死亡を確認した場合は「死亡診断書」が発行され、事故死や不審死などで警察が検視や検案を行なった際には「死体検案書」が作成される。
- 警察が検視や検案を行う場合、状況によっては司法解剖まで行われるケースもあり、死体検案書の発行には数日かかることもある。
死体検案書とは警察医が作成する死亡を証明する書類のこと
冒頭でも解説した通り、死体検案書とは故人の死因や死亡状況を記録した書類で、死亡届の提出や各種契約の解約手続きに必要となる重要なものです。死亡診断書と混同されることも多いですが、発行者や作成の背景、役割に違いがあります。
ここでは、死体検案書の役割や、死亡診断書との違いなどについて解説します。
死体検案書の役割
死体検案書とは、故人の死亡を医学的・法律的に証明するための書類です。
死体検案書がなければ死亡届の提出ができず、火葬や埋葬の許可も得られません。また、死体検案書は国の死因統計作成の基本資料となり、保険・医療・福祉に関する行政の重要な基礎資料として活用される役割も担っています。
さらに、死亡届の提出により戸籍が抹消され、年金の停止や各種契約の解約手続きが適切に行われます。死体検案書は、故人の死亡に伴う法的手続きや社会的手続きを円滑に進めるために欠かせない書類です。
参考:医の倫理の基礎知識 2018年版【医師と社会】G-4.死亡診断書と死体検案書|日本医師会
死亡診断書と死体検案書の違い
死亡検案書と死体検案書は、どちらも故人の死亡を証明する重要な書類ですが、発行される状況や内容に違いがあります。
【死亡診断書が発行されるケース】
- 病気や老衰など、自然な死因で亡くなった場合
- 入院中や通院中に医師が死亡を確認した場合
【死体検案書が発行されるケース】
- 事故、自殺、災害、不審死といった不自然な死因の場合
- 医師が死亡に立ち会わず、死因が明確でない場合
- 警察の検視や解剖が必要となる場合
死亡診断書は、主治医や担当医が作成し、死体検案書は警察医や監察医により作成されます。どちらも死亡届の提出や火葬許可証の取得に欠かせませんが、発行者や発行の流れが異なるため注意が必要です。
なお、2020年12月25日の法改正により、これらの書類には医師の署名が必須となっています。
参考:死亡診断書(死体検案書)の押印廃止に係る当面の取扱いについて|厚生労働省
死体検案書の記載内容
死体検案書には、以下の内容が記載されます。
- 故人の基本情報:氏名・性別・生年月日
- 死亡日時:死亡した年月日と時刻
- 死亡場所および種別:死亡場所の名称とその住所
- 死亡原因:直接の死因、その原因となった疾患や状態
- 死亡の種類:病死・自然死・外因死・不詳の死など
- 医師の情報:診断年月日・医療機関名・医師の署名
ちなみに、死亡診断書に関しても記載項目に大きな違いはなく、同じような内容が記載されます。
死体検案書が発行されるまでの流れ
死亡診断書が主治医や担当医によって作成されるのに対し、死体検案書は警察医や監察医が作成し、発行までの流れが異なります。
死体検案書が必要な場合は、警察や監察医の検視が行われるのが一般的で、その手続きに時間がかかることがあります。葬儀の準備にも影響が出る可能性があるため、事前に流れを把握しておくことが大切です。
ここでは、死因がすぐに分かった場合と、事件性があり、解剖が必要な場合の具体的な流れについて詳しく解説します。
死因がすぐに分かった場合
状況にもよりますが、仮に自宅で家族が亡くなっているのを発見した場合、死体検案書の発行の流れは以下となります。
| 1.家族が自宅で死亡しているのを発見する |
| かかりつけ医がいる場合は医師に連絡するかかりつけ医がいない場合で、既に亡くなっていることが明らかな場合は警察に連絡する救急車を呼んだ場合も、死亡が確認されると警察に連絡が入る |
| 2.警察が事情聴取や検視を行う |
| 警察は現場で状況確認を行い、事件性がないか判断する事件性がないと判断された場合は、警察医や監察医が検視、検案を行う |
| 3.死体検案書が作成される |
| 検案した結果、死因が明確であり事件性がないと判断された場合、死体検案書が作成されるその後、ご遺体は遺族へと引き渡され、死体検案書をもとに死亡届を役所に提出する火葬許可を得た後に、葬儀準備を始めていく |
このように、死因がすぐに判明した場合の手続きは比較的迅速に進みます。しかし、状況によっては時間がかかることもあります。まずは警察の指示に従いましょう。
関連記事:自宅で死亡したらどうしたらいい?|連絡先や死亡後の流れについて解説
事件性があり解剖を必要とする場合
自宅などでご遺体が発見され、警察による調査で事件性が疑われた場合や、死因がその場で特定できず、解剖が必要となった場合には、以下の流れで進みます。
| 1.警察が現場で事情聴取を行い、警察医が現場検証を実施する |
| 通報を受けた警察は、現場で事情聴取を行い事件性を調査するまた、警察医や監察医が現場検証を行い、死因を確認する |
| 2.死因が特定できない場合は司法解剖が行われる |
| 現場で死因が特定できない場合、ご遺体は専用の施設に搬送され司法解剖が行われる司法解剖は死因や死亡経緯を調べるためのもの。司法解剖の結果をもとに死体検案書が作成される解剖にかかる時間は数時間から数日ほどが一般的 |
| 3.死体検案書が作成される |
| 司法解剖により死因が特定され、事件性がないと判断された場合は死体検案書が作成されるその後、遺族へ連絡が入り、遺体を引き取る |
検視は、刑事訴訟法第229条により定められており、原則として拒否することはできません。司法解剖に関しても同様に警察の判断のもと実施されます。
死体検案書を市役所に提出する際の注意点
作成された死体検案書を市役所に提出する際は、以下の内容に注意しましょう。
- コピーを作成しておく:死亡届の提出のほかに、金融機関での口座解約や保険金の請求など、各種手続きで必要となる場合がある。市役所に提出した原本は返却されないため、必ずコピーを作成しておく。
- 提出期限の遵守:死亡届は亡くなったことを知った日から、7日以内に市役所へ提出しなければならない。期限を過ぎると罰則が科される可能性があるため、速やかに対応する。
- 火葬許可証の申請:死亡届の提出と同時に火葬許可証の申請を役所にて行う。既に葬儀社に連絡している場合、葬儀社のスタッフが代行して申請するのが一般的。
司法解剖などにより死体検案書の作成が遅れている場合、死亡届の提出は死亡してから7日以降でも問題ありません。事前に役所へ事情を説明しておくようにしましょう。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、火葬許可証の申請代行をプラン料金内に含んでおりますので、ご安心ください。
死体検案書は再発行も可能
死体検案書は、条件付きで再発行が可能です。再発行を依頼できるのは3親等以内の家族か配偶者に限られます。申請の際には身分証明書や戸籍謄本、委任状(代理人の場合)が必要です。
また、市役所に提出した場合、原本の返却はされないものの「死亡届の記載事項証明書」を発行してもらえます。この証明書は、年金関連や高額簡易保険の支払い手続きなど、用途が限られているため、事前に申請理由を証明する必要があります。
万が一、死体検案書を紛失したり証明書が発行できなかったりする場合には、医師または警察署で再発行の手続きを行いましょう。再発行には手数料と指定の書類が必要となるため、事前に確認しておきましょう。
死体検案書に関するよくある質問
死体検案書について解説してきましたが、書類発行や費用に関する疑問をお持ちの方もいるでしょう。ここでは、死体検案書に関する2つのよくある質問に応えていきます。
- 死体検案書は誰が作成する?
- 死体検案書の費用を払えない場合はどうする?
内容を理解したうえで葬儀準備を進めていきましょう。
死体検案書は誰が作成する?
死体検案書は、警察医や監察医が作成します。警察医は都道府県の警察署長などから嘱託を受け、変死体の検案や被留置者の診療、検察職員の健康管理などを行う医師のことです。
通常、所轄警察署管内の開業医が嘱託されるケースが多く、法医学の専門知識は必須ではありません。
一方、監察医は、犯罪性がなく検案しても死亡した理由がわからない遺体を行政解剖する医師のことです。伝染病や災害死の検案なども担当し、死因証明書を作成します。
監察医制度は、限られた自治体でしか実施されておらず、制度がない都道府県では、大学の法医学教室が担当しています。
死体検案書の費用を払えない場合はどうする?
死体検案書の作成に関わる費用は保険適用外であり、遺族の負担となりますが、自治体によっては費用の一部または全額を負担してくれる場合もあります。
また、生活保護を受給している場合や、経済的に困難な状況にある場合は、福祉事務所や市区町村の福祉課に相談することで、費用の免除や公的支援を受けられる可能性があります。費用を工面できない場合は、事前に相談してみましょう。
なお、死体検案書を作成する際の費用は、地域や医療機関によって異なります。一般的に、検案料として2〜3万円、死体検案書の発行料として5,000〜1万円かかります。
費用の公的支援に関する情報や死体検案書の費用については、以下の記事で詳しく解説しているので、参考にしてみてください。
死体検案書ができるまでは警察の指示に従うようにしよう
死体検案書は、警察医や監察医が状況を詳しく調査し、必要に応じて解剖を行った後に作成される重要な書類です。
不自然死や死因が不明な場合は、警察が関与し、遺族の判断だけで手続きは進められません。事故などで死体検案書を作成する際には、警察の指示に従うようにしましょう。
弊社では、役所への書類提出や手続きの代行も承っております。葬儀準備でお困りの場合は、どうぞお気軽にご相談ください。