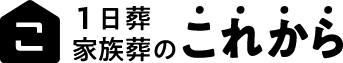交通事故や飛行機事故・水難事故など、何らかの事故に巻き込まれることによって亡くなることを事故死といいます。事故はいつ自分の身に起こるかわからないため、残された遺族は突然のお別れにショックを受けるかもしれません。
今回は、事故死した場合の葬儀について詳しく知りたい方向けに、事故死した場合の葬儀までの流れや加害者がいた際の対応方法などを解説します。病死と異なり、事故死はご遺体確認や事故後の損害賠償などが発生するため、遺族による冷静な対処が必要です。
この記事を要約すると
- 事故死の場合の葬儀までの流れは、死亡確認までの流れに違いがあります。①警察によって検視が行われる。②故人の身元と死因が特定されたら、警察から遺族に連絡が入る。③遺族がご遺体を確認し、本人確認をする。④警察から、ご遺体が引き渡される。
- 事故死の場合の葬儀費用は、ご遺体の修復などの処置が必要なため、通常よりも高額になる場合が多いです。事故に加害者がいる場合は、葬儀費用を請求できますので、保険会社に問い合わせましょう。
- 事故死で遺体の損傷が激しい場合は、「エンバーミング」という修復や化粧といった処置を行います。しかし、修復が困難な場合は、故人様と対面できないまま葬儀が行われることもあるため、注意が必要です。
事故死とは
事故死とは、交通事故・墜落死・火焼死・中毒死・溺死など、何らかの事故に巻き込まれて命を落とすことを指します。
事故の状況や背景によっては被害者と加害者という立場ができ、遺族と加害者との間で損害賠償や示談・裁判が発生するケースがあります。
事故死の連絡を受けてからの流れ
ここからは、事故死の連絡を受けてから葬儀を執り行うまでの一般的な流れを解説します。ご遺体の状態によっては、通常の葬儀と異なる順序や方法で進めていくケースも珍しくありません。
検視と検案
事故によって亡くなった場合、病院で亡くなったときや病死したときとは死亡確認までの流れが大きく異なります。
事故死では警察によって検視と検案が行われ、ご遺体やその周辺の状態について細かく調査したうえで「死体検案書」を作成します。検視では身元や死因の特定はもちろん、事故に事件性がないかどうかの判断もなされます。もし事故ではなく事件が疑われる場合は、司法解剖を実施して死因の特定を進めます。
また、ご遺体の損傷が激しく、その場では身元の特定が困難な場合は、DNA鑑定によって身元を明らかにするケースも珍しくありません。もし司法解剖やDNA鑑定を行った場合、ご遺体が遺族に引き渡されるまで数日〜1ヶ月程度の時間がかかります。
以下の記事では、検視の流れや死体検案書の詳細についてより詳しく解説しています。気になる方はぜひチェックしてみてください。
遺体確認
警察によって検視と検案が行われ、故人の身元と死因が特定された段階で遺族に連絡が入ります。
遺族は警察署内のご遺体安置室でご遺体に対面し、本人に間違いがないかどうか確認を行います。もし故人のご遺体が激しく損傷していた場合、ご遺体確認の際に大きなショックを受けるかもしれません。
また、場合によっては故人の事故前後の様子について事情聴取が行われ、遺族調書が作成されることもあります。
ご遺体の引き渡し
遺族によるご遺体確認が終わったら、警察から遺族にご遺体が引き渡されます。ご遺体は事故当時の状態のままになっているため、このタイミングで新しい服に着せ替えるのが一般的です。
なお、ご遺体の損傷が激しかったり腐敗が進んでいたりするなどの事情がある場合は、ご遺体を引き渡す時点で納棺を行うケースもあります。遺族がこれ以降故人との対面を希望しない場合は、納体袋に遺体を納めてから引き渡されます。
ご遺体引き渡しにあたって、死亡届の提出の際に必要な死体検案書が交付されます。この書類には3万円〜10万円程度の発行手数料が発生するため、あらかじめ現金の用意が必要です。
葬儀準備・葬儀
故人の葬儀手配や日程の決定は、遺族にご遺体が引き渡されてから行いましょう。これ以降の葬儀までの流れは、通常とほとんど変わりません。
葬儀内容についても通常通り行うのが一般的ですが、ご遺体の状態によってはお通夜や葬儀・告別式よりも先に火葬を行うケースがあります。前火葬を行った場合は、祭壇に骨壷を飾った状態で葬儀を行います。
また、遺族が式中に故人との対面を希望しない場合は、拝顔をせずに葬儀を行います。この場合は棺のお顔が見える部分に、代わりとなる写真を飾ることがあります。
事故死した方の葬儀費用
事故死の場合の葬儀費用は、通常の葬儀費用に比べて割高になりやすいといえます。とはいえ、加害者がいる場合は、葬儀にかかった費用の請求が可能です。
事故死の場合は通常よりも費用が高額になる
事故によって亡くなった方の葬儀費用は、通常の葬儀費用よりも高額になるケースがほとんどです。
ご遺体の損傷や外傷が激しい場合は通常よりもご遺体の処置に時間がかかるほか、追加でエンバーミングを行ってご遺体の一部を修復することがあります。エンバーミングにかかる費用の相場は15万円〜25万円程度です。
また、身元や死因の特定のために解剖が行われた際にも費用が発生します。司法解剖の場合は国が費用を負担しますが、行政解剖の場合、自治体によっては解剖料や検案料が遺族の負担になるケースがあります。解剖料の相場は8万円〜12万円、検案料の相場は2万円〜3万円程度です。
加害者がいる場合は葬儀費用を請求できる
事故に加害者がいる場合は、葬儀費用も損害賠償の対象となるため、葬儀後にかかった費用の請求が可能です。
請求できる金額の目安は自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準の3種類で定められており、それぞれ補償限度額が異なります。どの基準が適用されるかは保険会社とのやり取りによって決定しますが、補償限度額を超えない場合はかかった費用分のみが補償されます。
また、香典返しや返礼品にかかる費用は請求ができないので注意が必要です。遺族は葬儀社や石屋などに支払いを行う際、必ず領収書を発行するようにしてください。
| 種類 | 補償限度額 |
|---|---|
| 自賠責基準 | 100万円 |
| 任意保険基準 | 100万円程度 |
| 弁護士基準 | 150万円 |
<請求できる費用の例>
- 葬儀一式費用(式場利用料・祭壇代・花代など)
- 火葬料・埋葬料
- 寺院費用(読経代・法名代など)
- 祭壇費用
- 墓石費用
- 初七日法要・四十九日法要の費用
事故遺族となった場合の注意点
ここからは、事故死した方の遺族になったときに気を付けるべきポイントを解説します。
遺体確認で精神的ショックを受ける可能性がある
事故死の場合、ご遺体を引き取る前に遺族による「遺体確認」を行う必要があります。これはご遺体の身元が本人で間違いないかを確認するものです。
場合によってはご遺体の損傷や外傷の具合が激しく、対面の際に大きなショックを受けるかもしれません。少しでも気持ちを落ち付けられるよう、できるだけ1人ではなく遺族複数人で向かうほうがよいでしょう。
ご遺体の引き渡しまでに時間がかかるケースがある
事故死では、身元や死因の判別を行うため、ご遺体が一度警察に預けられます。検視・検案のみを行ってから死体検案書が発行される場合は、半日〜1日程度で遺族の元に引き渡されます。
一方、事件性が疑われたり身元の特定が難しかったりして司法解剖やDNA鑑定が行われる場合は、ご遺体が遺族の元に引き渡されるまで数日〜1ヶ月程度かかる可能性があります。
遺体の損傷がひどい場合はエンバーミングを行う
ご遺体の損傷や外傷がひどい場合は、「エンバーミング」と呼ばれる処置を行います。エンバーミングではご遺体の消毒・殺菌のほか、損傷を負った部分に修復や化粧を施します。この処置は専門の業者や湯灌業者によって行われ、別途の費用が発生します。
ご遺体の損傷が全身にある場合は、服で隠れる部分はそのままで、首から上の部分のみを修復するのが一般的です。エンバーミングを行うことで、故人のご遺体を生前の状態に近付けることができます。
遺体の状態によっては故人と対面できない
ご遺体の損傷や外傷の具合によっては、エンバーミングでの修復も難しく、弔問や葬儀の際に故人と対面できない可能性があります。その場合は拝顔をせずに葬儀を行いますが、最後に故人の顔を見てお別れできなかったことが心残りになるかもしれません。
警察からの説明をよく聞いておく
ご遺体が警察から遺族の元に引き渡される際、警察によって事故の状況や死因について詳しい説明がなされます。
引き渡しに立ち会う遺族は、警察から得た情報をほかの人にも説明できるようにしっかりと話を聞いておきましょう。場合によってはメモをとっておくと後々困らないかもしれません。
死亡診断書ではなく死体検案書が発行される
病院で亡くなり、医師によって死亡診断がなされた場合は「死亡診断書」が発行されます。
一方、事故死の場合は死亡診断書の代わりに「死体検案書」が発行されます。この書類はご遺体引き渡しの際に警察によって作成され、3万円〜10万円程度の発行手数料が発生します。
死体検案書は死亡診断書と同様の位置付けで、死亡届の提出の際に必要です。
加害者がいた場合の対応と注意点
事故内容によっては、故人に対する加害者がいるケースも珍しくありません。ここからは、加害者がいた場合に遺族が対応すべきことを解説します。
損害賠償が発生する
事故による加害者がいる場合、被害者遺族は加害者に対して損害賠償を請求することが可能です。請求できるのは本人への慰謝料・家族への慰謝料・葬儀費用などで、交通事故の場合は示談金も発生します。
金額決定までの交渉は当事者間ではなく、それぞれが保険会社等の第三者を介して行うのが一般的です。事故後に加害者と被害者遺族が直接やり取りをしてしまうと、さらなるトラブルの発生を引き起こす可能性があるため、あまり好ましくありません。また、交渉には事故の損害賠償に関する専門知識が必要です。
双方の意見がまとまらない場合は交渉が長引くことがありますが、できるだけ冷静に対処する姿勢が求められます。
示談を行う場合は弁護士に依頼する
交通事故による死亡の場合は、被害者の慰謝料や車両に対する賠償を含めた示談金が支払われます。示談交渉を行う場合も保険会社や弁護士等の専門家に依頼するのが一般的です。
交渉中に加害者側の代理人が示談を急かしてくる可能性もありますが、金額や内容に納得がいくまで焦らないことが賢明です。
裁判に発展した場合は弁護士費用を請求できる
事故後の示談交渉や双方の折衝が決裂した場合、裁判に発展する可能性があります。
裁判を行う場合は弁護士を立てる必要がありますが、加害者への請求金額に弁護士費用を含めることが可能です。弁護士費用は請求金額の10%程度が目安とされています。
加害者が弔問・参列した場合の対応を決めておく
事故死した方の葬儀を執り行う際、事故の加害者が弔問や参列に訪れるケースがあります。当日トラブルやパニックが起こらないためにも、遺族が加害者を受け入れるかどうかをあらかじめ遺族間で話し合って決めておきましょう。
また、加害者が参列する際に香典を包んでくることも考えられます。示談や裁判の際、相場より高額の香典を受け取ってしまうと加害者の減刑につながる可能性があるため、冷静に判断することが重要です。
事故の加害者となった場合の注意点
いつ起こるかわからない事故では、誰でも加害者になり得ます。ここからは、もし自分が加害者になってしまった際の注意点を解説します。
被害者の葬儀には第三者と参列する
もし自分自身が事故の加害者となり、被害者の相手が亡くなってしまった場合は、相手方の葬儀に参列するべきなのでしょうか。
自分が参列することによって被害者遺族に不快な気持ちを与えてしまわないかと不安になるかもしれませんが、結論としては「行かないよりも行くほうがよい」といえます。
ただし、加害者が1人で被害者の葬儀に参列するのはあまり好ましくありません。もし参列して弔意と謝意を伝えたい場合は、保険会社や弁護士などの第三者を連れて行きましょう。
相場に合った金額の香典を包む
亡くなった方へのお悔やみの気持ちや、遺族へのお見舞いの気持ちをあらわす香典。加害者として被害者の葬儀に参列する場合も、香典を包んでいくのがマナーです。
包む金額は相場の金額に合わせたり、保険会社から遺族に支払われる10万円程度の見舞い金に合わせたりする方法があります。
しかし、あまりにも高額を包むと、遺族から「香典の金額で反省の意図を示すことで量刑が軽くなるのを狙っている」と捉えられてしまい、受け取ってもらえない可能性があるので注意しましょう。
事故遺族となった場合は冷静な対応が求められる
いつ自分の身に起こるかわからない事故。事故死した方の遺族になった場合、亡くなってから葬儀の後までさまざまな手続きを行う必要があり、冷静な対応が求められます。事故に加害者がいた場合は、専門家の力を借りながら慎重に折衝しましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。