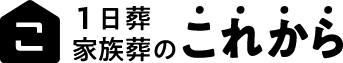「友引」とは、「六曜」という中国由来の吉凶の考え方において、日々を6種類に分類したうちのひとつにあたる曜です。友引には「友を引く」という意味合いがあり、葬儀などの凶事には不向きとされています。
本記事は、葬儀の日程を決めている方や友引の日に葬儀日程が被りそうな方向けに、友引の日に葬儀が行われにくい理由や友引の日に葬儀を行う場合に気をつけるべきポイントを詳しく解説します。友引の日の意味合いを知って、後悔のない葬儀日程を選びましょう。
この記事を要約すると
- 友引とは、六曜のうちのひとつの曜で、「友を引く」という意味合いがあります。友引は祝い事には適した日ですが、凶事には適しません。
- 友引の日の葬儀は、縁起が悪いとして昔から避けられてきました。友引の日に休業している斎場や火葬場も数多くあります。
- 友引の日に葬儀を行いたい場合は、参列者の理解を得ることが大切です。地域によっては「友引人形」という人形を棺に納めることもあります。
友引とは?
カレンダーで「友引」という言葉を見たことがある人もいるのではないでしょうか。これは「六曜」とよばれる中国から伝わった考え方で、日々を6種類の「曜」に分けて吉凶を判断します。
友引は六曜の2番目にあたる日で、その名のとおり「友を引く」という意味を持ちます。結婚式や還暦祝いなどの祝い事には適していますが、「故人が友を呼び寄せる」という意味合いから葬儀には不向きとされています。
| 六曜の種類 | 基準日 | 意味 |
|---|---|---|
| 先勝 | 旧暦1月・7月の1日 | 午前の運勢は良く、午後の運勢は悪い。先手必勝の日 |
| 友引 | 旧暦2月・8月の1日 | 友を引くという意味合いを持つ。祝い事には適しているが、凶事には不向き |
| 先負 | 旧暦3月・9月の1日 | 午前の運勢は悪く、午後の運勢は良い。大事な物事は避けた方が良いとされる |
| 仏滅 | 旧暦4月・10月の1日 | 仏をも滅ぼすほどの凶日とされる。凶事を行うのは問題ない |
| 大安 | 旧暦5月・11月の1日 | 最も縁起が良いとされている。祝い事や大事な物事に適している |
| 赤口 | 旧暦6月・12月の1日 | 朝と夕方の運勢は悪く、正午の運勢は良い。火や刃物に注意が必要な日 |
友引に葬儀をしても良い?
「友を引く」という意味合いを持つ友引の日は、葬儀を行うのに適さないという考え方が一般的です。とはいえ、友引の日に絶対に葬儀を行ってはいけないという明確な決まりがあるわけではありません。
また、友引の日であっても、お通夜や法事は行っても問題ないとされています。
友引に葬儀を避ける理由
葬儀日程を決める際に友引の日を避ける理由は、大きく2つあります。友引の日が避けられている理由を知ったうえで、友引の日に葬儀を行うかどうかを判断しましょう。
六曜を重んじている人がいる
六曜は古くから日本に伝わる考え方のため、六曜に基づいて日々の予定を立てている方や、六曜の考え方を生活に取り入れている方もいることでしょう。
六曜を重んじている方にとって、友引の日に葬儀に参列するのは抵抗があるかもしれません。「友を引く」という意味があることから、参列者に不安な思いをさせないようにと友引の日を避けるケースは多いようです。
友引が休業の火葬場が多い
友引の日は昔から葬儀を避ける人が多いため、友引の日を休業としている火葬場が数多くあります。友引の日に火葬場を使用する場合は、通常の日よりも予約が取りにくいことが予想されます。
友引の日に葬儀を行おうとしていても、火葬場が空いていなかった場合は日程を改めなければいけません。必ず事前に火葬場の空き状況を確認するようにしましょう。
友引の葬儀は宗教的には問題ない
六曜は暦のうえで日々の吉凶を判断する考え方で、特定の宗教との関わりは持っていません。「仏滅」という曜があるため、一見仏や仏教と関係があるようにも思えますが、仏教由来の考え方ではないため注意しましょう。
仏教・神道・キリスト教などの宗教形式で葬儀を行うにあたって、六曜や友引はとくに気にするポイントではありません。
友引の日に葬儀をする場合の注意点
葬儀日程を調整した結果、友引の日に葬儀を行うことになるかもしれません。友引の日に葬儀をする場合は、いくつかの注意点を押さえておきましょう。
参列者に配慮する
昔から友引の日の葬儀は縁起が悪いとして避けられることが多いため、参列者のなかには友引の日に葬儀に参列することに抵抗がある方もいるかもしれません。友引の日に葬儀を行う場合、親族や参列者からの理解を得ることが大切です。
もし、親族や参列者のなかに友引の日に葬儀をすることに反対する人がいた場合は、日程を考え直す必要があるでしょう。
斎場や火葬場の予約状況を確認する
友引の日は火葬を行う人が少ないため、斎場や葬儀場が友引の日を休業日にしていることがよくあります。友引の日に葬儀を行いたい場合は、はじめに斎場や火葬場に空きがあるかどうかを確認しましょう。
もし営業している斎場・火葬場が見つかったとしても、通常の日に比べて施設が混み合うことが予想されます。なかでも直前に予約をしようとした場合は、すでに予約がすべて埋まっているかもしれません。
地域によっては友引人形を使うことも
友引の日に葬儀を行う場合、地域によっては古くからの慣習で棺の中に人形を入れることがあります。これを「友引人形」といい、「友の代わりに人形に身代わりになってもらう」という意味合いで用いられます。
友引人形は一般的なぬいぐるみ・木彫りの人形・故人が大切にしていた人形など、どのような人形を用いてもかまいません。とくにこだわりがない場合は、葬儀社に用意してもらうことも可能です。
友引の日を避けて葬儀をする場合の注意点
亡くなった日の直後に友引の日があった場合、友引の日を避けて葬儀を行うことがあるでしょう。ここからは、友引の日を避けたい場合に注意すべきポイントを解説します。
よく考えて日程を決める
一般的に、お通夜は亡くなった日の翌日、葬儀・告別式は亡くなった日の翌々日に行われます。亡くなった日の翌々日や3日後が友引だった場合、その日に葬儀と火葬を行うかどうかを考える必要が出てくるでしょう。
本来葬儀を行いたい日と友引の日が重なってしまった場合は、遺族同士や葬儀社とよく話し合って日程を決める必要があります。
火葬場が混み合う可能性がある
友引の日の葬儀を避けたい人たちが友引の日の前後に葬儀を執り行おうとして、通常の日よりも火葬場が混み合うケースが考えられます。とくに首都圏は通常の日でも火葬場の予約が埋まりやすいため、火葬場の空き状況を必ず確認しましょう。
ご遺体の安置期間を延長する必要がある
友引の日を避けて葬儀を行うため、亡くなってから葬儀を行うまでの期間が通常より長くなるケースもあります。その場合はご遺体の安置期間も長くなり、追加でドライアイスやエンバーミングなどの処置を施す必要が出てくる可能性があります。
とくに夏はご遺体の腐敗が進みやすいため、ご遺体の安置に追加費用がかかるかもしれません。
葬儀日程の決め方
葬儀日程は六曜だけでなく、参列者や宗教者の都合も加味したうえで決定します。ここからは、葬儀日程を決める際に確認すべきポイントを解説します。
また、以下の記事では亡くなってから葬儀までの日数の目安や葬儀日程の決め方について解説しています。ぜひ、あわせてチェックしてみてください。
亡くなってから24時間後以降に火葬する
日本では、法律によって亡くなってから24時間以内は火葬を行うことができません。亡くなってからすぐに葬儀と火葬を行いたい場合でも、最低1日間は待つ必要があります。
火葬を行う際には死亡届と火葬許可申請書を提出した際に受け取る「火葬許可証」が必要です。火葬までに間に合うよう、葬儀準備と並行して役所で申請手続きを行いましょう。
なお、弊社の「1日葬・家族葬のこれから」では、火葬手続きの代行をセットプラン料金内に含んでおりますので、ご安心くださいませ。
親族の予定を合わせる
葬儀の日程を決める際は、親族や友人をはじめとした参列者の都合の良い日を選ぶことが大切です。なかでも、遠方からの参列者がいる場合や参列者の人数が多い大規模な葬儀の場合は、できるだけ多くの人が参列できるように余裕を持った日付を選ぶと良いでしょう。
近年は、亡くなった日を問わず、参列者や会葬者が集まりやすい週末に葬儀を行うケースも増えています。
火葬場の予約状況を確認する
葬儀の日程を決めるにあたって、出棺後に火葬を行う火葬場を必ず確保しなければなりません。
火葬場には公営の施設と民営の施設があり、利用料が安い公営の火葬場は予約が取りにくい可能性があります。火葬場が埋まっていた場合は葬儀の日を延期せざるを得ないため、火葬場の空き状況を先に確認することが大切です。
僧侶の予定を確認する
仏式の葬儀であれば僧侶、神式の葬儀であれば神主など、特定の宗教形式で葬儀を行う場合は宗教者の都合も加味する必要があります。葬儀の手配を進めるタイミングで、都合を確認しておきましょう。
地域の風習に基づいて決める
住んでいる地域によっては、葬儀の日程や葬儀の形式に特有の風習がある場合もあります。地域に根差した葬儀を行いたい場合は、事前に地域に伝わる文化や風習を調べておくことも大切です。
法要やお墓参りは友引でも問題ない
友引の日の葬儀は縁起が悪いとして避けられますが、葬儀の7日後に行われる「初七日法要」や49日後に行われる「四十九日法要」などの法要は、友引の日に行ってもかまいません。
また、納骨やお墓参りなどの儀式も、六曜を気にせずに行って良いとされています。六曜を気にするのは、あくまで葬儀・告別式と火葬の日のみです。
参列者へ配慮しながら日程を決めましょう
六曜のひとつである友引は、「友を引く」という意味合いを持ちます。友引の日の葬儀は「故人が友を呼び寄せる」「友を道連れにする」と捉えられることがあるため、古くから避けられてきました。
縁起の悪い日とはいえ、友引の日に葬儀を行うかどうかは遺族の意志に委ねられています。友引の日に葬儀が当たりそうな場合は、遺族や葬儀社とよく話し合って日程を決めましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。