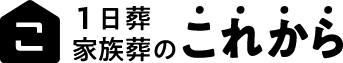一般的に、大切な方がお亡くなりになると葬儀を行い、火葬して遺骨をお墓に納めて供養します。しかし近年、核家族化や高齢化が進み、宗教観の変化から、葬式をしない・お墓も持たないという選択肢が注目されつつあります。
葬儀をしてお墓を建てるにはまとまったお金が必要で、体力的な負担や手間もかかります。故人としても遺族に負担をかけたくないと考える方も増えています。故人に身寄りがない、遠い親戚でお墓までは面倒をみることができないということもあるでしょう。
本記事では、葬儀をしない場合のお見送り方法やお墓を持たない場合の供養方法について紹介します。メリットやデメリット、注意点についても解説しているので、ぜひ参考にしてください。
この記事を要約すると
- 葬儀をしない場合は、火葬のみを行うことになります。火葬だけでは忍びないという場合には、一日葬や家族葬など葬儀の形式や規模を検討してみる方法もあります。
- お墓を持たない場合は、ゼロ葬のほか手元供養や永代供養、散骨といった方法があります。遺族が供養しやすい方法や故人の意向に沿ったものを選ぶと良いでしょう。
- 葬儀をしない場合やお墓を持たない場合は、費用や体力的な負担が抑えられるといったメリットがあります。一方で親族の理解を得にくい、弔問対応や「墓じまい」が必要になる場合もあり注意が必要です。
葬式をしない場合のお見送り方法は?
一般的には、亡くなった翌日か翌々日に通夜を行い、その次の日に告別式と火葬を行います。しかし、法律上は、葬式をしなくても特に問題はありません。葬儀を行わない場合は、火葬のみを行うことになります。
火葬だけを行う
葬儀をしない場合、遺体を安置している病院や自宅から直接火葬場に遺体を搬送してお別れをするという方法もあります。「火葬式」や「直葬」と呼ばれたりしますが、葬儀のように斎場に参列者をお呼びしたり、僧侶をお呼びする儀式を行なったりするケースはほとんどありません。
ただし、宗教的な儀礼が全くないのは忍びないという場合、僧侶を呼んで読経や焼香などを行うこともあります。しかし、葬儀と違って短時間で終わるため体力的な負担が抑えられますが、故人とのお別れの時間がほとんどありません。ゆっくりお見送りしたいという方には向いていないといえるでしょう。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、必要なものを含んだ安心のセットプランで、相場よりもお得に直葬をご提供します。24時間365日、事前相談から承っておりますので、どんなことでもお気軽にご相談ください。
葬儀の規模や儀式を減らす
「本当は葬儀をしたいけれど、参列者もほとんどいない」「葬儀を行うのは負担が大きくて迷っている」という方もいらっしゃるでしょう。火葬だけでは寂しいと考える場合、葬儀の規模や形式を検討してみてください。
通常2日間かかる葬儀を1日で行う「一日葬」であれば、準備の手間や体力的な負担・費用を抑えられるでしょう。また、故人の知人や友人など親族以外の参列者がいない場合は、「家族葬」という選択肢もあります。気心の知れた親族だけで故人をお見送りしたいという方に向いています。
一日葬や家族葬についてはこちらの記事で詳しく解説しています。どんな人に向いているのか、費用やメリット、デメリットなども詳しく解説しているので参考にしてください。
お墓を建てずに供養する方法は?
今ある先祖のお墓に入ることができない、お墓を引き継ぎ面倒をみる人がいないなどの事情でお墓を持つか悩む方も多いようです。ここでは、お墓を建てない場合の遺骨の供養の方法をご紹介します。いくつか種類があるため、故人の意向や遺族が供養しやすい方法を選ぶと良いでしょう。
火葬場から遺骨を持ち帰らない
一般的に遺骨は、火葬のあと骨壷に入れて持ち帰り、お墓に納めます。お墓を建てない場合は、そもそも遺骨を持ち帰らない「ゼロ葬」と「焼き切り」という選択肢もあります。
ゼロ葬とは、火葬場に火葬や骨上げを任せて遺族が遺骨を引き取らない方法です。ただし、自治体によっては、遺骨を遺族が持ち帰る決まりになっているところもあり、ゼロ葬ができないこともあります。
焼き切りは、遺灰になるまで焼く方法です。しかし、骨を残さないほど火力を上げることは難しく、対応している火葬場は多くないため、希望する場合は対応している火葬場をあらかじめ調べておくと良いでしょう。
手元供養する
遺骨の全部もしくは一部を骨壷に入れて自宅で保管する「手元供養」という方法もあります。お墓よりも手元に遺骨を置くほうが、故人との繋がりを身近に感じることができるでしょう。大切な人が亡くなった悲しみを和らげられるかも知れません。
遺骨は、仏壇や飾り台に置くことが一般的ですが、仏壇がないご家庭も多いでしょう。最近では、遺骨ペンダントやキーホルダーなどもあり、ライフスタイルや好みに合わせたものを選ぶことができます。
永代供養してもらう
永代供養とは、お寺や霊園が遺族に代わって故人を供養する方法です。永代供養では、ロッカーのような形式や仏壇形式で納骨堂に遺骨が保管されます。
宗教や宗派を問わず利用できる施設が多く、駅の近くにあるなど、利便性が良い施設もあります。そのため、お墓の継承者がいない場合に限らず、今あるお墓が遠い場合や遺族が高齢の場合などにも選ばれています。
なお、永代供養の方法は大きく分けて、個別墓・集団墓・合祀墓の3種類があります。個別墓は個別の墓石があり、骨壷も1人1つあります。
集団墓は遺骨を個別に保管したうえで、1つのお墓を複数人で共有します。合祀墓は遺骨を骨壺から取り出し、他の遺骨と一緒にまとめて埋葬します。集合墓の場合、3回忌や13回忌など一定の期間が経つと、合祀墓にまとめられることが一般的です。
散骨する
火葬した後、粉末状に砕いた骨を海や山に撒いて自然に返す「散骨」を選ぶ方もいらっしゃいます。故人の思い入れのある場所などで行うことが多いでしょう。
ただし、自治体によっては散骨が禁止されていることもあるうえ、散骨可能な場合も条例で定められています。さらに、遺骨はそのまま撒くと遺棄罪になってしまうため、2mm以下の粉末状にする必要もあります。
ほかにも、自然・住民への配慮として、献花は花びらだけを撒くといったルールもあります。散骨は取り決めが多く、個人で行うとトラブルになりかねないため、専門の業者に依頼するのが安心です。
葬儀しない・お墓を持たないメリット
ここでは、葬儀をしない場合やお墓を持たない場合のメリットについて解説します。
費用が抑えられる
火葬の費用相場、公営の火葬場で無料〜5万円程度、民営の火葬場で3〜5万円程度です。骨上げなどの儀式を行なったとしても、全体の費用は20~50万円に抑えられることが多いでしょう。
葬儀費用の相場は約119万円(特定サービス産業動態統計調査(経済産業省)を元に算出)が一般的であるため、葬儀を行わない場合は大幅に費用を抑えられます。
また、お墓を建てる費用は100〜200万円ほどかかるといわれていますが、手元供養や永代供養(合祀墓)の場合、遺骨の保管方法によっては5〜30万円程度に抑えられます。
ただし、海への散骨は散骨費用に加えて、船のチャーター費も必要です。場合によっては、お墓を建てるより費用がかかることもあるため事前に金額を調べておくと良いでしょう。
以下の記事では、直葬・火葬式を検討している方に向けて費用相場を詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。
あわせて読みたい!

葬儀の費用相場
直葬(火葬式)の費用相場は?内訳や賢く費用を抑える方法を解説
体力的な負担が抑えられる
葬儀をせず、お墓も持たない場合、時間と体力的な負担を抑えられるでしょう。
通常の葬儀は、準備や一連の儀式などやるべきことがたくさんあります。遺族がご高齢の場合や葬儀の規模が大きい場合、体力的な負担が心配という方も少なくありません。
また、お墓があると定期的にお墓に通って手入れをする必要があります。お墓が遠方にある場合などや遺族の足腰が悪い場合、通うだけで大変でしょう。
手元供養なら体力的な負担が少ないだけでなく、命日やお盆に限らず故人を日常的に供養できるというメリットもあります。
参列者の対応や親族の集まりなどの心理的な負担が抑えられる
親族付き合いが苦手な人にとっては、葬儀・お墓がないことで心理的な負担を軽減できる点もメリットです。
葬儀を行わない場合、弔問に対応することはありますが、一度に多くの参列者と会うことはありません。また、故人が亡くなってからある程度時間が経っているため、弔問は心の整理がついた状態で落ち着いて対応できるでしょう。
お墓がない場合も、お盆やお彼岸に親族で集まってお墓参りをする機会が減るので、心理的な負担は軽減しやすいといえます。
葬儀しない・お墓を持たないデメリット
葬儀をしないことやお墓を持たないことは、メリットばかりではありません。事前にデメリットも知って十分検討することが重要です。
親族からの理解を得にくい
親族の理解を得られず、トラブルを引き起こしやすいことがデメリットのひとつです。
核家族化や生活様式の変化により、葬儀をしない方やお墓を建てないという方も少しずつ増えてはいますが、葬儀やお墓という形式を重んじる方もいらっしゃいます。
親族のなかには、「葬儀をしないと故人がうかばれない」「お墓がないと供養できない」と考える方もいらっしゃるかもしれません。葬儀しない場合やお墓を持たない場合は、親族にしっかりと理由を説明し、理解を得られるように努めましょう。
供養の方法を選ぶのが大変
葬儀で読経などの宗教的な儀礼を行っていない場合、お寺によっては納骨が認められないこともあります。葬儀はしないものの納骨するお墓が決まっている人は、菩提寺に事前に確認をしておきましょう。
また、遺骨を持ち帰らなかった場合はもちろん、合祀墓で永代供養する場合も、後から遺骨は取り出せません。
後でお墓を建てたい、手元で供養したいと思っても叶わないこともあります。故人とお別れしてから「やっぱり葬儀をしておけば良かった」「お墓を建てれば良かった」と後悔することのないように、よく考えて決めることが大切です。
葬儀をしない・お墓を建てない場合の注意点
ここでは、葬儀をしない場合やお墓を建てない場合に注意しておくと良いことを解説します。
役所の手続きが必要
葬儀をしない場合やお墓を持たない場合でも、法律的な問題はありませんが、死亡届を提出するなどの手続きは必要です。
死亡届の提出は、故人が亡くなってから7日以内に行うことが義務づけられています。火葬を行う際に死亡届の提出が必要になるため、実際には亡くなってから1〜2日程度で提出することが多いでしょう。
医師が発行した死亡診断書の左側が死亡届です。基本的に記入や押印は遺族が行いますが、提出などは葬儀社が代行してくれる場合もあります。
弔問対応が必要
葬儀をしない場合、お見送りができなかった知人やご友人が故人を供養したいと弔問に来られる可能性があります。
葬儀を執り行う場合は、関係者が一度に参列しますが、後日の弔問ではそれぞれ個別の対応が求められます。弔問のためのスケジュールの調整や、返礼品の準備などが必要になる点に留意しましょう。
とくに故人の交流関係が広い場合は、弔問に来る人が多くなる可能性があります。葬儀を行わなかったことを残念に思った人から説明を求められる可能性があることも覚えておきましょう。
墓じまいが必要になることがある
お墓はいらないと判断した際、すでに今ある先祖のお墓を管理する人がいなくなることも少なくありません。
そのような状況では、今あるお墓を撤去したあと更地にして使用権を返還する「墓じまい」を行うこともあります。墓じまいには50〜150万円近く費用がかかることを覚えておきましょう。
墓じまいの手順
墓じまいを決めたら、お墓を管理している寺院や霊園に墓じまいの意向を伝え、お墓に納骨されていることを証明する「埋蔵証明書(埋葬証明書)」を発行してもらいましょう。
新しい納骨先を決めたら、「受入証明書」の発行を依頼し、お墓のある自治体の窓口に「埋蔵証明書」「受入証明書」「改葬許可申請書」を提出します。
次に、石材店や専門業者など、墓じまいを行う業者とお墓を撤去する日取りを決めます。当日は、お墓から遺骨を取り出して墓域を更地にし、管理者に土地を返還します。
なお、墓じまいの手続き方法は各自治体によって異なるため、窓口やホームページで確認をしましょう。
葬儀の方法に悩んだら葬儀社に相談を
葬儀をしない、お墓を持たないという選択肢には、費用や心理的な負担が抑えられるなどのメリットがあります。
その一方で検討しておかなければならないこともあるため、葬儀・お墓の有無は遺族や関係者でよく考えて決めるようにしましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックで火葬のみ(直葬)も承っております。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。