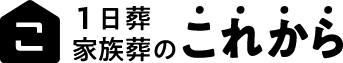家族が亡くなったら、主治医が書いた死亡診断書を受け取り、遺体を安置して葬儀の準備となるのが一般的な手順です。しかし、事故に合ったり突然死で死亡理由がわからなかったりするケースもあります。
こうした場合、警察による「検視」が行われますが、具体的に何が行われるか知らない方は多いでしょう。また、「警察」「検視」といった言葉に不安を感じる方もいらっしゃるかもしれません。
本記事では、検視の意味や内容、社会的意義、費用や時間などをまとめました。身近な人の死に必要以上の不安を抱えなくていいように、参考にしていただければ幸いです。
この記事を要約すると
- 検視とは人が亡くなった際、犯罪が絡んでいないかを調べる刑事的な措置です。この時に行なわれる調査は遺体の外表だけで、解剖は含まれません。
- 検視が行われるのは、主に病院とは別の場所で死亡した場合です。原因不明の突然死や事件の可能性がゼロではないとみなされると、検視となります。
- 検視の費用は3〜10万円と自治体や個々の状況などによっても異なります。所要時間は、早くて半日、事件性があり解剖も実施する場合は数ヶ月となるケースもあります。
検視とは
検視(けんし)とは、人が亡くなった状況を調査し、犯罪が絡んでいないかを明らかにする措置です。遺体の状態や死亡時の状況を詳しく観察し、いつ・どこで・どのように死亡したのかを究明します。
刑事訴訟法229条に則って行われる刑事的な処置で、検視官または警察官によって行われます。調査対象は、遺体の外表面をはじめ、着ていた衣類や所持品、周囲の状況など広範囲にわたります。
警察が行う措置ではありますが、必ずしも犯罪が関わっているわけではありません。例えば災害死や事故死、独居高齢者の孤独死などのケースでも検視の措置が取られます。
自宅で死亡して検視となった場合にかかる日数は、以下の記事でも解説しています。気になる方はご確認ください。
あわせて読みたい!

葬儀の流れ
自宅で死亡した際の検視にかかる日数は?|検視の流れや費用を解説
「検視」と「検死」の違い
「検視」と近い言葉で紛らわしいのが「検死」という言葉ですが、それぞれの意味は以下のとおりです。
| 検視 | 犯罪が絡んでいないかを調べる刑事的措置。刑事訴訟法に従って行われる。法律用語 |
| 検死 | 死因を取り調べること。検視・検案・解剖をまとめて指すこともある。一般用語のため、厳密な定義付けはされていない |
「検視」と「検死」の違いは、法律的な手続きなのか、一般的な概念なのかによって使い分けが異なるといえるでしょう。
検視が行われる割合
年間の死亡者数のうち、検視の措置が取られるのは約1割程度です。
例えば2023年の死亡者数157万5936人(2023年人口動態統計月報年計 概数)のうち、警察取り扱い遺体数は19万8664。そのうち検視官の臨場数は15万7,826で、臨場率は79.4%です(警察庁の報道発表資料より)。
死亡を届け出た後、警察官の調査で2割の死因が判明し、8割は検視官が調査を行うことになります。
| 死亡者数 | 157万5936人 |
| 警察取り扱い遺体数 | 19万8664体 |
| 検視官の臨場数 | 15万7826回 |
検視=解剖ではない
一人きりの状況で亡くなった場合や死因がわからないなどの場合、検視となりますが、このうちすべてが解剖となるわけではありません。
遺体発見現場の状況確認や遺体外表面の調査、体液の採取など、解剖までにはいくつかの段階があります。状況調査や体液採取などで死因が判明すれば解剖は実施しません。
2023年に警察が取り扱った遺体19万8,664体のうち、解剖となったのは1万3,215(司法解剖:1万99、調査法解剖:3,116)です(参考:警察庁報道発表資料)。
なお日本の法解剖率は約10%で、英国・豪州で40~50%、北欧の70~80%と比較すると低いといわれています。
検視で調べる項目・内容
検視で具体的に調べる内容については以下の通りです。
警察庁の国家公安委員会規則「検視規則 第六条」によって、以下の内容を綿密に調査するよう定められています。
一 変死体の氏名、年齢、住居及び性別
二 変死体の位置、姿勢並びに創傷その他の変異及び特徴
三 着衣、携帯品及び遺留品
四 周囲の地形及び事物の状況
五 死亡の推定年月日時及び場所
六 死因(特に犯罪行為に基因するか否か。)
七 凶器その他犯罪行為に供した疑のある物件
八 自殺の疑がある死体については、自殺の原因及び方法、教唆者、ほう助者等の有無並びに遺書があるときはその真偽
九 中毒死の疑があるときは、症状、毒物の種類及び中毒するに至った経緯
例えば一人暮らしの高齢者がベッドで死亡しているのを発見した場合、どんなに自然に見えても自然死と断定はできません。重大な伝染病の可能性や事件性が必ずしも否定できないからです。
このような場合に上記の項目を調査することで、死因を確かめ、犯罪が絡んでいないかを明らかにします。
検視はどのような場合に行われるか
検視は、主に病院以外で亡くなったケースで実施されます。具体的には、死因が特定できない場合や突然死、事件性が疑われる場合です。自殺・事故死・孤独死などの場合も行われます。
例えば自宅で療養中の家族が亡くなり、主治医が持病が死因と判断した場合、死亡診断書が発行され、そのまま葬儀が行われるのが通常の流れです。一方、死因が持病ではないと見られ事件性が疑われる場合は、警察に連絡され、検視が実施されます。
またお出かけ先などで亡くなり、事件性が認められ死因が不明な場合、遺体は警察へ引き渡され検視の措置が取られます。これに対して事件性がなく死因が明確であれば、死体見分にとどまります。
検視が必要と判断される具体的事例
病院以外で亡くなるケース全てが検視となるわけではありません。ここでは検視となる具体例を紹介します。
- 一人暮らしの高齢者が自宅で亡くなっているのが発見された
- 病気の兆候などはなかったが施設で突然亡くなった
- 高所から落ちて亡くなった
- 外出中、事故に遭い亡くなった
- 海・川・プールなどで亡くなった
- 火災で亡くなった
- 地震・落雷・水害など自然災害によって亡くなった
- 仕事の作業中に亡くなった
- 薬物などを摂取したと見られる状態で亡くなった
- 自殺と思われる状況で死亡しているのが発見された
- 他殺と思われる状況で発見された
検視は拒否できない
検視が必要と判断された場合、遺族はそれに応じる義務があります。人が亡くなった際には、個人の尊厳や社会の安全を守ること、事故の再発防止、伝染病の拡大を防ぐなどのため、死因の究明が求められます。
検視は刑事訴訟法第229条に基づき実施される重要な措置です。社会的にも大きな意義を持つため、調査に協力しなければなりません。
また検視の過程では、自宅への立ち入り調査や関係者への聞き取り、指紋の採取などが行われることもあり、これらにも協力する必要があります。警察からの聞き取りでは、故人の病歴や生前の様子のほか、収入、生命保険の加入状況など、幅広い内容が確認されます。
検視の費用
費用は、「検視」だけではなく、遺体の保管・搬送、死体検案書の発行を合算することが多いようです。死体検案書とは、死亡診断書にあたるもので、役所に死亡届を提出する際必ず必要になるものです。
金額の目安は3万~10万円ですが、自治体によって大きな開きがあり、通常の死亡診断書よりは出費は大きくなる傾向があります。金銭面の不安がある場合は、検視が行われると決まった時点で警察に費用や支払い方法を確認しましょう。
なお、解剖費用は通常25~30万円ほどかかります。犯罪性があるために解剖となった場合は、解剖費用は公費から支払われます。
検視を行う場合の逝去から遺体搬送・安置までの流れ
検視となった場合の具体的な流れは以下の通りです。
- 遺体を発見
- 警察に届け出
- 遺体を警察署へ搬送
- 遺体の外表面を調査・遺体発見場所の調査・関係者への聞き取りなど
- 死因の特定
- 死体検案書の発行
- 遺族への遺体引き渡し
- 遺体を安置場所へ搬送
(参考:厚生労働省:異状死の届出と検案・解剖等との関係について)
人が亡くなった際の一般的な手順として、最初に行うのが警察への連絡です。警察の許可が下りるまでは遺体・現場はそのままにしなければなりません。遺体の周囲の状況を変えないよう、亡くなった人にもその周りにも、手を触れないよう注意しましょう。
検視にかかる時間
検視にかかる時間は状況に応じて異なります。早ければ半日、長ければ解剖作業に移り、数ヶ月かかるケースもあります。期間の大まかな目安としては以下の通りです。
- 事件性なし・解剖なし:半日~1日
- 事件性なし・解剖あり:1日~1日半
- 事件性あり・解剖あり:数日~数ヶ月
死因が判明すると死体検案書が発行されます。葬儀や火葬には死亡診断書または死体検案書が必要です。この時点でようやく、死亡届を提出したり葬儀の日時を決めたり、死亡に伴う社会的な手続きを進められることになります。
検視中・検視後にやるべきこと
検視がいつ終わるかはケースバイケースです。いつ警察から引き取りの連絡を受けても対応できるよう、葬儀社を探しておきましょう。
検視が済み、ご遺体が戻ってくるとようやく葬儀を行えます。検視後スムーズに葬儀が行えるよう、葬儀の準備も進めておきましょう。具体的な段取りは以下の通りです。
- 葬儀社に見積もりを取る
- 葬儀社を決定する
- 葬儀の大まかな内容(規模・予算・内容など)を決めておく
なお遺体を引き取る際、引き取り人と故人、両方の身分証明書・印鑑が必要です。検視・死体検案書の発行などの費用の支払いもあります。具体的な金額や支払い方法を確認し、現金が必要であればその用意もしておきましょう。
検視は社会にも遺族にも重要な手続きです
検視(けんし)とは、人が亡くなりその死因がわからない時に、犯罪が絡んでいないかを確認する刑事的な手続きです。検視で確認するのは、遺体の表面だけで、解剖は行われません。検視で調べるのは、身に付けていた衣類・所持品などのほか、遺体の状態・状況など、多岐にわたります。
検視は社会的な意義もあるため、従う義務があります。検視関連で必要となる費用は、死体検案書の発行や遺体搬送費などです。検視にかかる時間は、早ければ半日、状況によっては数ヶ月要することもあります。検視中は、いつ警察から遺体の引き取り要請があってもすぐ対応できるよう、葬儀社を探しておきましょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。