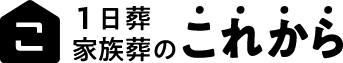身内が施設で亡くなると、気持ちの整理がつかないままさまざまな手続きに追われることになります。「死亡診断書の受け取りは?」「警察の検視って必要?」「葬儀の準備は何から始めれば良いの?」など、不安や戸惑いを感じる方も多いのではないでしょうか。
本記事では、施設での死亡から葬儀までの10ステップと、警察対応が必要なケースについて詳しく解説します。死亡診断書の受け取りから葬儀の打ち合わせまで、必要な手続きを紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。
この記事を要約すると
- 危篤の連絡を受けたら速やかに病院へ向かい、死亡確認後は死亡診断書の受け取り・死亡届の提出・葬儀の手配と施設への挨拶まで順序よく進めましょう。
- 突然死や事故の場合は、警察による検視が必要です。検視費用は5万円前後で、遺体搬送や保管・死体検案書発行にも費用が発生します。
- 葬儀は施設内で行うことも可能ですが、ほかの入居者への配慮と施設の設備状況を確認しましょう。
身内が施設で亡くなった場合における葬儀までの流れ
施設での死亡から葬儀までには、いくつかの重要なステップがあります。ここでは、葬儀までの流れを10のステップに分けて解説します。
- 危篤の連絡
- 医師による死亡確認
- 死亡診断書の受け取り
- エンゼルケアの実施
- 葬儀社への連絡と遺体搬送
- 親族への訃報連絡
- 死亡届の提出
- 火葬許可証の申請
- 葬儀の打ち合わせと実施
- 施設への挨拶
それぞれの手続きについて、詳しく見ていきましょう。
1. 危篤の連絡
危篤の知らせは、施設や病院から電話で知らされます。
たとえば「〇〇様の容態が急変し、意識レベルが低下しています。できるだけ早くお越しください」というような連絡を受けることになるでしょう。
この連絡を受け取ったら、できる限り早く施設や病院に駆けつける必要があります。家族や親族に状況を伝え、現場に向かいましょう。
身内が危篤になったときの対応方法について詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください。
あわせて読みたい!

葬儀の基礎知識
危篤・臨終とは?身内が危篤になったときにするべきことと連絡方法について解説!
2. 医師による死亡確認
医師から死亡宣告を受ける瞬間は、どれだけ心の準備をしていても辛い時間です。死亡宣告の流れは、以下のとおりです。
- 心配や呼吸の停止を確認す
- 脳機能の停止を確認
- 死亡時刻の確認
- ご家族に臨終した旨を伝える(死亡宣告)
死亡宣告を受けたあとは、死亡診断書が発行されます。
3. 死亡診断書の受け取り
死亡診断書は、死亡届とセットで医師から発行されます。死亡診断書と死亡届は一体となっており、A3用紙の右半分が死亡診断書、左半分が死亡届という形式です。
発行手数料は、公的医療機関で3,000~5,000円、私立病院では5,000~10,000円程度です。死亡診断書を受け取ったら、死亡届を役所に提出できます。
4. エンゼルケアの実施
エンゼルケアは、故人の尊厳を保つ最後の身支度です。施設の看護師や介護士が、故人の体を清潔なタオルで拭き、服装を整えます。
具体的には、医療器具を丁寧に外して髪を整え、男性なら髭を剃り女性なら化粧を施します。この時間は、故人との最後の時間となるため、家族で静かに過ごすことも大切です。
5. 葬儀社への連絡と遺体搬送
葬儀社に連絡して、遺体を搬送します。基本的には24時間365日受け付けてもらえます。
連絡する際は、以下の内容を伝えましょう。
- 故人の氏名・住所
- 施設名の住所・詳細(病棟、階数、号室など)
- 連絡者の氏名・電話番号
- 故人との続柄
- 搬送先 など
葬儀社のスタッフは施設に到着後、ストレッチャーで霊安室まで移動し、寝台車で搬送します。搬送費用は距離によって決まり、10kmまでは1.2~2万円ほどかかるのが一般的です。
搬送先は、自宅以外にも斎場や民営の安置施設など、複数の選択肢があります。
なお、弊社「1日葬・家族葬のこれから」で家族葬を執り行う場合、50kmまではセットプランの料金内に含まれておりますので、ご安心くださいませ。
6. 親族への訃報連絡
近親者から順番に、電話やメールで訃報を伝えます。たとえば「父が本日午後2時に〇〇病院で心不全のため永眠しました。葬儀は明後日の予定です」と具体的に説明しましょう。
遠方の親族は、交通手段の確保や宿泊先の手配が必要なため、できるだけ早く連絡することが大切です。故人と親しかった友人や知人にも、状況に応じて連絡を入れます。訃報連絡は、人間関係に配慮しながら、漏れがないよう慎重に進めましょう。
家族葬に招待する人の範囲については、以下の記事を参考にしてみてください。
あわせて読みたい!

葬儀の準備
家族葬はどこまで参列すべき?選定基準とマナーを徹底解説
7. 死亡届の提出
次に、死亡届を提出します。死亡届には、主に以下の内容を記入します。
- 個人の氏名
- 生年月日
- 本籍地
- 死亡日時
- 死亡場所 など
提出先は、以下のとおりです。
- 死亡地である東京都の市区町村役場
- 本籍地の市区町村役場
- 届出人の居住地の市区町村役場
死亡届の提出期限は、死亡の事実を知った日から7日以内と法律で定められていますが、実際は火葬や葬儀のため1~2日以内に提出する必要があるでしょう。
死亡診断書と死亡届の提出を済ませると、故人の死亡が法的に認められるため、火葬や埋葬の手続きを進められます。
8. 火葬許可証の申請
火葬許可証は、火葬する際に必要な法的書類です。通常、死亡届の提出時に同時に発行されます。
申請時には、志望届と死亡診断書の提示と手数料の支払いが必要です。火葬許可証がなければ火葬場の予約確定ができないため、早めに対応しましょう。
火葬の詳細な流れについては、以下の記事を参考にしてみてください。
なお弊社「1日葬・家族葬のこれから」では、手続きの代行がプラン料金に含まれているため、手続きのご心配は不要です。
9. 葬儀の打ち合わせと実施
葬儀社との打ち合わせで、式の規模や日時・場所・形式を決定します。たとえば、家族葬なら20人程度の参列者に向けた小規模な式場を選び、一日で執り行う形式を検討しましょう。
打ち合わせでは、祭壇の花の色や配置・遺影写真の選定・会葬礼状の文面を決めます。読経を依頼する寺院と戒名や当日の進行について調整することも必要です。なお、打ち合わせには通常1〜2時間ほどかかるのが一般的です。
葬儀社との打ち合わせを終えたら決めた流れに沿って、葬儀から火葬まで一連の儀式を執り行って故人を弔いましょう。
葬儀の打ち合わせで気を付けるべきことについて詳しく知りたい方は、以下の記事もご覧ください。
10. 施設への挨拶
お世話になった施設にお礼の挨拶に行くことも忘れてはいけません。葬儀後1週間以内を目安に、施設へ挨拶に伺います。
たとえば「父が3年間お世話になり、最後まで手厚い看護をしていただき、ありがとうございました」と具体的な感謝の言葉を伝えましょう。
施設スタッフへのお礼は、小分けできる菓子折りがあると理想ですが、マストではありません。菓子折りを持参する場合は、白黒の結び切りで「志」と書かれた熨斗を使うのが適切です。
また、施設に訪問するときは、遺品の整理と入所費用の精算も同時に行います。たとえば「父の着替えや日用品をまとめて持ち帰りたいのですが、いつがよろしいでしょうか」と具体的に相談しましょう。
施設との最後の関わりとなるため、感謝の気持ちを丁寧に伝えることが重要です。訪問前に必ず連絡を入れ、都合の良い日時を確認しましょう。
身内が施設で亡くなったときに警察が来るのは検死が必要な場合のみ
ここでは、施設での死亡に関する警察の関与について、検視が必要なケースとその流れを解説します。ぜひ参考にしてみてください。
1. 検視が必要なケース
施設での死亡を医師が確認する方法は、死亡時期によって異なります。たとえば、最後の診察から24時間以内の死亡であれば、医師は改めて診察せずに死亡診断書を発行できます。
24時間を超えた場合でも、かかりつけ医が治療中の病気による死亡と判断できれば、死亡診断書の作成が可能です。しかし、以下のケースでは警察による検視が必要です。
- 治療していない病気による突然死
- 指定感染症による死亡
- 中毒症状後の死亡
- 施設内での転倒事故
検視にかかる時間は状況によって大きく異なります。たとえば、事件性がない単純な検視なら半日から数日で終わるでしょう。一方、検案が必要な場合は3日程度、解剖となると2ヵ月程度かかることもあります。
このため、葬儀の日程は検視の結果が出てから決める必要があるでしょう。検視について詳しく知りたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。
あわせて読みたい!

葬儀の流れ
自宅で死亡した際の検視にかかる日数は?|検視の流れや費用を解説
2. 検視の流れ
検視とは、犯罪の嫌疑の有無を明らかにするための刑事手続きです。
遺体は、警察署の霊安室へ搬送されたあと、検察官や警察員による検視が行われます。また、医師が立ち会って検案を実施し、遺体の外表面を調べて死因を特定する流れです。
事件性がないと判断された場合は、死体検案書が作成されます。
検視費用は5万円前後で、遺体搬送や保管・死体検案書発行には費用が発生することも留意しておきましょう。
| 死体検案書作成費用 | 2~3万円 |
| 死体検案書発行料 | 5,000~1万円 |
※自治体によって条件は異なる
なお、検視は死因の究明と事件性の有無を確認するための法的手続きであり、拒否できません。
身内が施設で亡くなった場合に葬儀を準備する際の注意点
施設での葬儀準備には、いくつかの重要な注意点があります。以下の項目について詳しく説明します。
- ほかの入居者への気遣いを忘れない
- 安置場所を事前に確認する
- 遺影写真を早めに準備する
- 葬儀会場を確保する
ひとつずつ見ていきましょう。
1. ほかの入居者への気遣いを忘れない
施設内での死亡は、ほかの入居者へ心理的な影響を与えるため、細やかな配慮が必要です。たとえば、遺体の搬送時は人どおりの少ない時間帯を選び、人目につかない経路で行います。
施設内では大きな声での会話や慌ただしい動きを控え、静かに過ごしましょう。
2. 安置場所を事前に確認する
遺体の安置場所は、葬儀場へ搬送するまでの一時的な場所です。専用の安置室がない施設では、自宅や葬儀社の安置施設の利用を検討しましょう。
事前に安置場所を確認することで、その後の葬儀準備をスムーズに進められます。遺体を安置する際は、最低1日以上期間を取ることが法的に定められている点も留意しておきましょう。
ご遺体の安置については、以下の記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてみてください。
あわせて読みたい!

葬儀の基礎知識
ご遺体安置とは?費用相場や安置場所の決め方を解説
3. 遺影写真を早めに準備する
遺影写真は故人の人柄が最もよく表れた一枚を選ぶことが重要です。たとえば、施設の行事中に笑っている写真や、家族との面会時の穏やかな表情の写真を使用しましょう。
長期入所の場合、最近の写真が少ないことを想定し、入所時から定期的に写真を撮っておくことをおすすめします。具体的には、以下のような写真を選びましょう。
- 亡くなる1年以内から5年以内の写真
- 故人の特徴がよく表れている写真
- 背景やほかの人が写っていない写真
- 自然な表情で正面を向いている写真
写真が見つからない場合は、施設スタッフに日常生活での写真がないか確認してみましょう。遺影写真の準備は、故人を偲ぶ大切な要素として、慎重に選定する必要があります。
4. 葬儀会場を確保する
葬儀会場は、参列予定人数に応じた適切な規模を選ぶことが大切です。会場の規模が大きくなると、費用もかさむため、参加者に合わせて会場のグレードを選びましょう。
たとえば、家族葬規模の葬儀を執り行う場合は、20人ほどを受け入れられる会場を確保すれば十分です。また、電車やバスからのアクセスの良さも考慮しましょう。
自宅や火葬場からの距離も考慮し、遺族の負担が少ない場所を選定することが重要です。
身内がなくなった施設で葬儀を挙げられるケースもある
最後に、施設での葬儀について施設葬の特徴やメリット・注意点を詳しく解説します。施設葬を考えている方は、ぜひ参考にしてみてください。
1. 施設葬とは
施設葬は老人ホームや介護施設内で行う葬儀形式です。たとえば、施設内の安置所で遺体を安置し、僧侶を招いて通夜から告別式、出棺まで一連の流れを執り行います。
近年は施設内に医師が常駐することも増え、看取りから葬儀までをスムーズに進められるケースが増えています。一日葬や家族葬など小規模な形式が一般的で、施設の設備に応じて柔軟に対応してもらえるでしょう。
死亡から葬儀までを同じ場所で行えることは、遺族の負担軽減につながります。
2. 施設葬のメリット
施設葬には、故人が最後まで暮らしていた場所で葬儀を執り行えるというメリットがあります。故人と親しくしてくれたスタッフや入居者の方が参列しやすいのが、魅力的なポイントです。
また、遺族は会場探しや遺体搬送の手間が省けるのも助かるポイントといえます。人生の最後を過ごした場所での葬儀は、故人と遺族双方にとって心の通った送り方を実現できるでしょう。
3. 施設葬の注意点
施設葬を執り行う際は、ほかの入居者への配慮が最も重要です。たとえば、大部屋で生活している場合、遺体の移動はほかの入居者の目に触れないように行う必要があります。
また、専用の葬儀スペースがない施設では実施が難しく、一般の葬儀場を使用することになるでしょう。火葬場は別施設への移動が必要となるため、交通手段の手配が欠かせません。
施設葬は多くの利点がある一方で、実施にはさまざまな制約があることを留意しておきましょう。
施設で身内がなくなった場合は葬儀社に相談しましょう
施設での身内の死は心の準備ができていても大きな心理的負担となるものです。このようなときこそ、経験豊富な葬儀社のサポートを積極的に活用すると良いでしょう。
葬儀社は24時間365日対応しており、遺体搬送から葬儀の段取り・各種手続きまでトータルでサポートしてくれます。とくに施設での死亡の場合、ほかの入居者への配慮や施設との調整など、特有の対応が必要となるため、プロのアドバイスは心強い味方となるでしょう。
弊社では、価格を抑えたプランパックでの葬儀をご用意しています。参列人数に応じた広さの式場で、現代に合わせたシンプルな葬儀を行えます。依頼・相談は24時間365日受け付けているので、興味をお持ちの方はぜひお気軽にご相談ください。